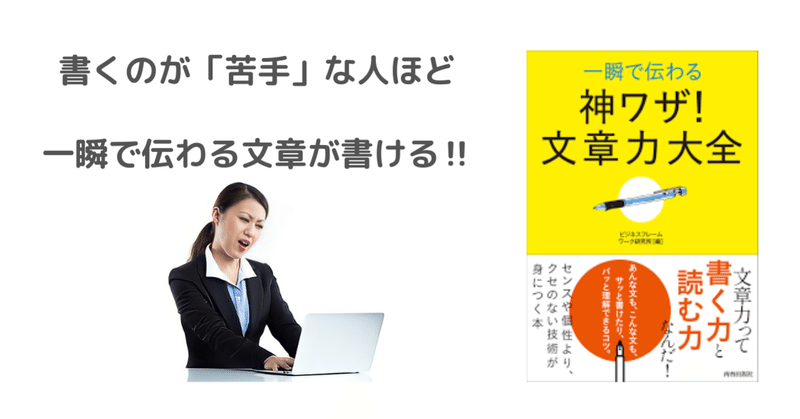
noter必見!センスや個性より、クセのない文章を書くためのライティング164テク|【読書日記】一瞬で伝わる 神ワザ! 文章力大全|
結論。「読解力」も大切だが、「わかりやすい文章を書く力」も大切です。
どうも、あなたのキャリアを失敗させないコンサルタントのタルイです。
週イチでnote更新しています。
いきなりですがクイズです。
「兄と友人の結婚式に出席する」
この文の意味は次の3つのどれでしょうか?
A:(私)と兄の二人で、友人の結婚式に出席する
B:(私)が兄の結婚式、そして友人の結婚式に出席する
C:兄と友人(女性)が結婚し、その結婚式に(私)が出席する
いかがでしょうか?
気になる正解は...
3つとも正解です。
確かに3つとも意味が通ってますよね🤔
しかし、逆に意味が通ってしまうということは
とてもややこしい文章ともいえるということです。
つまり
これは読解力の問題ではなく
この文章自体が問題です。
▼この本から教わりました。
これは前回ご紹介した「大人の読解力 ”読み解くこと”は最強の武器である」と同じ著者と出版者です。
私がnote執筆に関して参考にしている本は2冊
以前ご紹介した「言葉にできるか」は武器になる。では
自分の内なる言葉を磨くことが大切と書きました。
そして本書:一瞬で伝わる神ワザ!文章力大全は
具体的なライティング術の参考書として活用してます。
▼ご覧ください。レイアウトも参考書並みにわかりやすいです。


※画像はAmazonさんよりお借りしました。
この中に1ページに1テクニックで
実に164個ものライティングテクニックが書かれてます!
スゴい量です!まさに「大全」です。
それから...
本書を活用するメリットは、
ただ文章が読みやすくなるだけではありません。
これについては一番最後にお話します。
それでは解説にいってみましょう!
◆書くのが苦手な人でも今日から書ける「猫・メロス式文章術」
まず「猫・メロス式文章術」ってナニ?
これから説明します。
夏目漱石「吾輩は猫である」の書き出しは
「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」
太宰治の「走れメロス」は
「メロスは激怒した。」
この文章の共通点は
・主語は文頭
・8〜9字の短文
で構成されているところです。
これが本書が提唱する「猫・メロス式文章術」です。
本書が定義するわかりやすい文章とは
●主語を文頭に置くのが一番意味がとりやすい
●短文の積み重ねが最も意味を伝えやすい
書き手は書きたいことがシンプルで簡潔に伝えられます
読み手は一読で意味が読み取れます。
私もnoteでこの2つのシンプルなルールを使って書いてます。
ここからは
私もnoteで駆使してる3つのポイント
●「主語」
●「短文」
●8つの表現技法
を順に紹介します。
◆『主語』と『主語回り』のテクニック集
●主語を文頭におく
前回の記事でも書きましたが
「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように」
この5W1Hがはっきりとしている文章はわかりやすいです。
よって「主語」である「誰が」は文頭にあるほうが
望ましいのです。
▼こちらは主語の前に、あれこれ書いてある文章例です。
数日間あれこれ悩み、困り果てていた彼は、ついに上司に相談することにした。
▼文頭に主語を持ってくると…
彼は数日間あれこれ悩み、困り果てたのち、ついに上司に相談することにした。
「誰が」+「いつ」+「何して」+「どうした」が
はっきりとわかります。
●主語は一つの文に一つが読みやすい
▼こちらは主語が2つあります。
私たちが仲間を信頼せず、自らの利益を優先しようとすれば、敵対組織は私たちを分析するだろう。
「私たち」と「敵対組織」が主語ですね。
▼このように主語を一つにします。
私たちが仲間を信頼せず、自らの利益を優先しようとすれば、敵対組織に分断されるだろう。
ちょっとしたことですが
読みやすく変わってますね。
●「主語」の次は「助詞」の使い方についてです。
私が苦手な「てにをは」も含みます。
▼悪文の見本として「が・が文」が紹介されてます。
日本経済が危機に瀕していると、多くの経済学者が延べているが、日本経済が真価を発揮する時代がこれから来ると予想がなされている報告もある。
う〜ん
「が〜が〜」うるさくて読みづらいです!
▼そこで、このように変えると...
日本経済は危機に瀕していると、多くの経済学者が延べている。その一方で、日本経済はこれから真価を発揮すると予想する報告もある。
ホントだ!
「が・が・が」と書いてないとスッキリ読めますね🤔
▼「の・の文」も紹介されてました。
韓国の首都のソウル在住の2分の1近くの人は、自分の子供の名前の漢字を間違えて書いたという。それほどに、近年の韓国での漢字の識字率の低下は、著しい。
おっとこれは
私もうっかりやっちゃう文章です😅
▼「の」を減らしてみます。
韓国の首都・ソウルに住む半分近くの人が、自分の子供の名前を誤った漢字で書いたという。それほどに、韓国では近年、漢字の識字率が低下している。
おぉ!読みやすい。
ちなみに本書の基準では、
一つの文で助詞の「の」が3回以上使われた場合
「の・の文」認定だそうです。
●主語のそばに述語を置くと読みやすい
「誰(何)が」+「どうした」と
「主語」と「述語」は対となって文を構成します。
そこで
主語と述語のつながりをはっきりさせることで
意味のとりやすい文章になります。
▼この文は主語と述語が離れすぎています。
中国は大きな人口と広大な国土を有し、その長期にわたる経済成長に加えて、軍事力の増強によって、東アジア世界にとって大きな脅威となりつつある。
▼この場合は文を二つに分けるのが得策でした。
中国は、東アジア世界にとって大きな脅威となりつつある。
大きな人口と広大な国土を有するうえ、長期にわたって経済成長し、軍事力を増強させているからだ。
ここまではいかがですか?
私のnote記事もこの主語テクを使って
「私は」から始まります。
最近になって
日常会話において主語を省略したくなる理由がわかりました。
リアルな会話ですと
「私は〇〇です」「私は△△だから□□です」
このように
すべての会話の文頭に「私」をつけると…
まるで承認欲求が満たされていない人の話し方のようにしつこいですね😅
◆『短文』にするテクニック
一文を短くするのは読み手が読みやすく伝わりやすい文章になります。
もう一つ
書き手も書いているうちに
混乱して変な文章を書く原因を取り除けると思います。
●一文は50字以内におさえる
▼これは一文80文字です。
本籍地を現住所にしなければならないという法律はなく、実際には住めない土地でも本籍地にでき、 人気なのは東京都千代田区千代田 1番だが、それは皇居の住所だ。
(法律はない...住めなくてもOK...人気...)
この人は何が伝えたいのだろうと思いませんか🤔
▼解決策は4つの文に分けます。
本籍地を現住所にしなければならないという法律はない。
実際には住めない土地でも、 本籍地にできる。
本籍地として人気なのは、 東京都千代田区千代田1番。
それは、皇居の住所だ。
こうすると
最初の「本籍地を現住所にしなければならないという法律はない」が強く印象に残ります。
最後の「皇居の住所だ。」も活きてきますね。
●「一文一内容」だけ書くと伝わりやすい
「一文一内容」のすると、とたんに読みやすくなります。
▼この文は一文に2つの内容が入ってます。
我々の時代の学生の旅行といえば、貧乏旅行と相場が決まっていたが、最近の若者は汚い宿に泊まるのを敬遠する傾向にあるようで、そもそも海外旅行自体に興味を示さない者も多いと聞く。
「自分の学生時代の話」と「最近の若者の傾向」が入ってますね。
行間ゆとり世代の私には、これは長すぎる文です。
▼こちらが「一文一内容」バージョン
我々の時代の学生の海外旅行といえば、貧乏旅行と相場が決まっていた。
ところが最近の若者には、汚い宿に泊まるのを敬遠する傾向があるようだ。
そもそも、海外旅行自体に興味を示さない者も多いと聞く。
このように分けると「一文が短文」になってスッキリしますね🤔
●書き出しこそ「短文」で始める
読み手に興味をもって読んでもらうには
書き出しを工夫する必要があります。
たとえば
▼この文章はその書き出しに難があります。
グローバル資本主義とは、国家間の障壁を取り除き、グローバル化、自由化を推し進めた資本主義のことだ。グローバル資本主義は、 ソ連の崩壊後、1990年代に進行した。国境を越えた企業買収が盛んになり、金融グローバリゼーションが進んだ。その結果、グローバル資本主義は、バブルを発生させ、 さらには通貨危機をもたらした。
グローバル資本主義を説明するのに「3文」で、しかも「長文」です。
しつこいようですが
「行間ゆとり世代」の私は
この書き出しの文章は読みたくありません😅
▼伝えたいことを短文でスパッとした文がこちら
20世紀末、世界に怪物が現われた。グローバル資本主義という名の怪物だ。
おぉ!これはそそられる書き出しになりましたね。
このあとに
しかし、コロナ禍により社会・経済システムが抜本的に見直され、幸せやウェルビーイングを中心とした新たな秩序を模索されている....
なんて文章が続いたら読んでみたくなりますよね🤔
ちなみに
私のnote記事の書き出しは
「結論」から書き出すパターンが多いです。
ほかには
「印象的なワンフレーズ」から書き出したりと
ちょっと工夫してます。
では次に
その印象的なワンフレーズをつくるコツとして
8つの表現技法を解説します。
◆読み手の興味を惹きつける8つの表現技法
さてここまでは「主語」と「短文」でシンプルに書くことに
力点を置きました。
ですが、シンプルにすることだけにこだわりすぎると
文書の面白みが犠牲にされちゃうのも事実です。
そこで本書では
だいたい1000文字以上書くときは
一箇所ぐらいは8つのテクニックをつかって
読み手の興味をつなぐことを提案してます。
●テク①「倒置法」でハッとさせる
倒置法とは言葉の順序を通常とは逆にする手法です。
▼通常バーション
「ルコビン川を渡ったからには、二度と戻れない」
▼倒置法バーション
「二度と戻れない、ルコビン川を渡ったからには」
映画ポスターに出てきそうなキャッチコピーになりました。
キャッチコピーは印象的なワンフレーズといっていいでしょう。
「二度と戻れない」までを読み
なぜ?と思ったところに
「ルコビン川を渡ったからには」と最後に持ってきた言葉が強調されました。
順序を変えるだけで、カエサルの不退転の決意が伝わりますね。
●テク②「体言止め」でテンポを生み出す
「体現」とは名詞です。
名詞で文を終わらせる方法です。
▼通常バーション
「満天の空に星がきらめく」
これは日常会話でもありえる表現ですね。
▼体言止めバージョン
「満天の空にきらめく星」
どうでしょう!
このように体言止めを使うと
キャッチコピーができあがります。
テンポもよくなります。
ですが、使いすぎも良くない。
▼悪い例
イベント会場には、 予想以上に大勢の人が来ています。 どのブースも、長蛇の列。さばききれないスタッフ。苛立ちはじめる客。このままでは、お客の不満が爆発。至急、ヘルプ。
このように体言止めを5つも使い過ぎると
アタマが悪い文章になっちゃいます😅
▼体言止めはポイントのみ使用
イベント会場には、予想以上に大勢の人が来ています。どのブースも、長蛇の列。スタッフはさばききれず、お客は苛立ちはじめています。このままでは、 お客の不満が爆発しかねません。 至急、 ヘルプの人員をお願いします。
体言止めを効果的に使い、緊急性を演出してます。
すごく優秀なスタッフさんに思えて
助けてあげたくなっちゃいます。
●テク③「押韻」で耳に残るフレーズを
ラッパーのように「韻(いん)」をふみます。
「行きは極楽、帰りは地獄」
「来た、見た、勝った」
発音しやすく耳に残るキャッチコピーを作ることができます。
●テク④「反復法」で感情を揺さぶる
「同じもしくは似た言葉を繰り返す技法」のことです。
カッコよくいうと「リフレイン」です。
「入った!入った!ホームラーーン!」
野球中継のように同じ言葉を繰り返すパターンが一般的ですが
「ついに、その日がやってきた。もっとも恐れてきた日がやってきたのだ」
「その日」と「もっとも恐れてきた日」と変えて
「やってきた」とするだけで印象が高まります。
●テク⑤呼びかけ法で感情に訴える
「ここからが本番です」⇒「さあ、ここからが本番です」
私がよく使うのは「あなた」です。
「あなた」という二人称を多用することで
当事者意識が芽生えます。
読み手に「あなたは○○ですか?」
と疑問を投げかける
設疑法もあります。
このあとの後半3つは
特に印象に残るフレーズとしては
重要度が高いです。
「逆説」「対句」「比喩」です。
テク⑥「逆説」で魅力的にする
私もよく使う「逆説フレーズ」です。
最近ですと、You Tubeで「○○やってみた!」なら
私はnoteで「○○やめてみた!」と逆説を唱えてます。
もう私の生き方そのものが逆説といってもいいでしょう。
高い山こそ、ゆっくり登れ
こう書いてあると、理由が気になってしまいますよね。
逆説は2パターンありました。
・「〇〇であり、△△ではない」パターン
省益あって、国益無し
拡大あって、撤収なし
高級官僚(キャリア)の行動様式を揶揄する言葉です😅
解説ついでに皮肉を書きました。
・「〇〇ではなく、△△」パターン
▼哲学者ニーチェの名言
「事実などは存在しない、ただ解釈だけが存在する」
▼キューバ革命の指導者カストロが、同志ゲバラの死に際して贈った言葉
「戦士は死ぬ。だが、思想は死なない」
これは両パターンともかっこいいですね。
逆説は記憶に残りやすいです。
テク⑦「対句法」でギャップをつくり強い印象を
対句とは、
形は似ているが
意味は違うフレーズを並べる手法です。
▼対照的な2つの言葉をならべて調子を高めます。
「上に政策あれば、下に対策あり」
「谷深ければ、山高し」
上と下、谷と山 形の似た反対語ですね。
▼これが対句の王道パターンです。
イチローは誰の真似もしなかった。そして、誰もイチローの真似をできなかった。
「誰の真似もしなかった」と「誰も真似をしなかった」と同じ主語と同じ述語で対句になってます。
▼ヘレン・ケラーの名言
障害は不便である。しかし、不幸ではない。
「不便」と「不幸」と似た言葉の対句です。
ちなみに英訳だと対句になっていません。
It's inconvenient to have a disability, but I'm not unhappy.
ですから
厳密にいうとヘレン・ケラーの名言というより
日本語訳した人が作り出した名言ですね。
●テク⑧「比喩」:モノに喩えて印象を強くする
▼直喩:「〜のような」「〜のように」で喩える
地球は、宇宙の中では芥子粒のような存在だ
▼隠喩:「〜のような」「〜のように」で喩えない喩え
地球は、宇宙の芥子粒だ
▼擬人法:人間でないものを人間に喩える
大地が怒り、海が泣いている
本書いわく「比喩」は、文章表現の華だそうです。
しかし、言い古された陳腐な比喩を使うと、
文章全体も陳腐になってしまい残念な結果に。
そこで
比較的失敗の少ない比喩の作り方を解説。
「地形」「気象」「有名なモノ」に喩えるのがベターでした。
ご覧ください。
▼地形にたとえる
「浮島のように残っている部分」
▼気象現象にたとえる
霧が晴れるような思い
▼有名なモノにたとえる
坂本龍馬のような働き
◆(まとめ)文章が苦手な人ほどわかりやすい文章が書ける!
この文章が苦手な人とは、「私のこと」です。
つまり
「一文50文字」以上の長い文書が書けないということです。
自分でも長い文章を書くと
何書いているのかわからなくなってしまうのです。
しかし、ここで逆転の発想です。
長い文章を書けないことが
「猫メロス式」とは相性が良かったのです。
もう一度
本書ので解説されている3つの方法をまとめます。
●主語は文頭に置く
●「短文」で一文一内容
●8つの表現技法
いよいよ最後です。序文でお知らせした
これらを駆使して得られるメリットとは
「説得力」です。
主語を文頭に置くことで「自己の主張」がはっきりします。
一文を短文にすることで論旨がわかりやすくなります。
表現技法を使うことでインパクトが生まれます。
noteのおかげで文章を書くことが好きになりました。
以前ブログを書いたりしていたときは
よくわからない義務感しかありませんでしたが
いまは楽しさを覚えました。
多くの本を読むことで「読解力」が磨かれ
多くの読書日記を書くことで「説得力」が身につきました。
この本には感謝です。
最後の最後に
いつも私の記事を取り上げていただき
「説得力」を褒めていただいたchiyoさんにも
感謝を伝えたいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
記事の感想は「スキ」と「コメント」でお知らせいただけると嬉しいです。
記事がお役に立てたら100円サポート願います。 noteで頂いたサポートとAmazonアフィリエイトは児童養護施設を退所する子どもたちの就労支援団体ブリジッフォースマイルさんに毎月寄付させていただきます。https://www.b4s.jp/action/contribution

