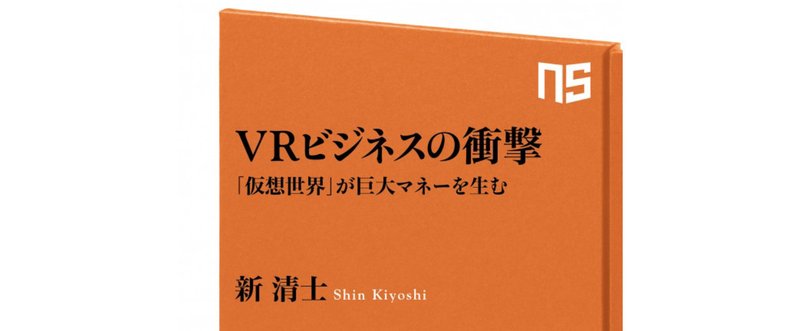
『VRビジネスの衝撃 「仮想世界」が巨大マネーを生む』──空に浮かぶ鋼鉄の城を目指して──
『VRビジネスの衝撃 「仮想世界」が巨大マネーを生む』
新清士著・NHK出版新書刊
VR元年とも呼ばれる、2016年。
急速に立ち上がったVRビジネスが、今まさに世界中で始まろうとしています。
VR元年と呼ばれる所以は、「Oculus Rift」「HTC Vive」「Playstation VR」といった主要なゴーグル型VR端末が、今年中に出そろうからです。
本書は全四章の構成になっており、バーチャル・リアリティの歴史から未来までを、最前線で取材を続けているVRジャーナリストの新清士氏が分かりやすく解説しています。
主な内容は以下のとおり。
序章「VRビジネスの大潮流──熱狂はなぜ生まれたのか?」
VRとは何か、VRビジネスの概観。VRにあまり詳しくないけど興味はある……という方も、この導入で分かりやすい説明があるので安心です。
特に用語の説明だけでなく、現在知られているVR機器やそれを取り巻く状況など、知っているという方も復習に最適です。
第一章「VRの現在──映画とゲームをつなぐものは何か?」
映画産業とVR、普及への課題、モバイルVRの可能性。VRが今どのように発展してきていて、どのような市場や広がり方が考えられるかが述べられています。
特に、高性能PCで用いるハイエンドVR機器に対し、スマホだけで動作するモバイルVRは、そのチープさを差し引いてもVRの普及において大きな役割を果たすであろうことは、意外な側面でした。
第二章「ハイエンドVRの夜明け──オキュラスはなぜ生まれたのか?」
Oculus創業ストーリー、そのビジョン、他勢力の概説。なかなか知ることのできないOculus最初期のエピソードが面白かったです。
Oculus創業者・パルマーの魅力には僕も惹かれていましたが、彼を支えた強力な仲間たちの活躍もまた感嘆させられるものでした。
それにしても、VR機器を買い漁って「微妙だから自分で作ろう」と言えるパルマーはやはりすごいですね。見習いたいところです。
第三章「日本のVRビジネス──独自のビジネスモデルは生まれるのか?」
日本独自の熱気、欧米と日本のVR観の違い。今度は日本に焦点をおき、日本ならではのVRコンテンツについて話が展開します。
日本といえばミクミク握手やHashilusなど、独自のVR機器を用いて五感から現実感を引き上げるコンテンツが多い印象でしたが、日本で作られているVR機器「FOVE」の話題や、戦艦大和のVR復元など、実に多様なVRビジネスが広がっているのだと知ることができました。
第四章「VRからAR・MRの時代へ──これから登場するビジネスとは?」
VRの未来、AR(拡張現実)やMR(複合現実)についての概説と展望。VRは仮想空間の実在感を演出するのに対し、ARは現実にあたかも存在するかのような仮想物を重ね合わせる技術で、それらを融合し、現実と仮想の区別がつかなくなったものをMRと呼びます。
本章ではVRの未来にはAR、その次にMRと、次々と技術が進歩していくであろう未来が描かれています。全てがこの通りに進むとも思いませんが、しかし実際訪れるであろう未来を考えると、ワクワクが止まりません。
総じて客観的に各内容が述べられており、読みやすくためになる内容でした。
バーチャル・リアリティはもちろん今この瞬間に始まった技術ではありませんが、しかし一般に浸透し始めるのはまさしく今年に違いありません。
とくに日本にも馴染み深いPS4の周辺機器として発売されるPlaystation VRは、安価であることもあり一番世間に広まる機器になると思います。
僕も未だにしっかりとしたVR機器を買い揃えられていませんが、自分でもコンテンツを開発していきたいとずっと思っているので、乗り遅れないうちにこの大潮流に飛び込みたいと思います。
僕がVRに興味を持ったのは例に漏れず『ソードアート・オンライン』の影響で、作中では難しい立ち位置でありながらも、真の仮想世界を実現しようとした茅場晶彦の理念には共感できるところがあります。
もちろん彼のようにとはいきませんが、しかし僕も、最終的にはVR異世界を目指して、様々な技術を勉強していきたいと思っています。
『SAO』についてはその文庫版第一巻もまた作品としての完成度が高いので、いずれI/Oで取り上げたいと思います。
それでは、またの機会に。
※この記事は、2016/7/14に掲載した記事の再録です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

