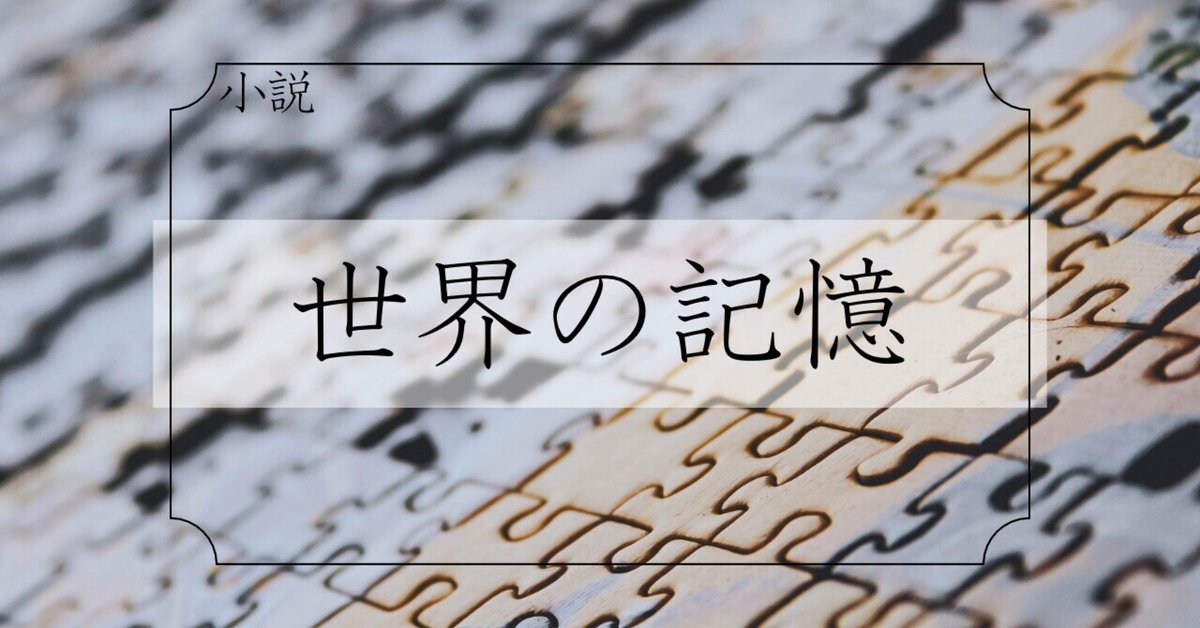
小説|世界の記憶
眼を閉じれば、すべてのことが頭の中で処理することができた。あらゆることが、僕の頭の中で綺麗に並べられ、必要な情報だけが抽出されていく。そうすることによって余分なものは排除され、洗練されていくのだ。その時感じるのは、とてつもなくゆっくり流れる時間と、自分の中の頭の中の世界の大きさのみ。まるで自分が自分じゃないような感覚に陥る。けれどこういうことがあった時は大抵、少し時間が経ってからとんでもない頭痛に襲われるのが決まりだった。これだけ脳味噌を使っているらしいのだ。そればかりはしょうがないだろう。けれど薬をつかっても少しも改善されないのだからたちが悪い。その痛みさえも僕の頭の中で処理できないかと試みてみるが、どうにもできないのだった。もともと自分の内部に存在しているものは、それ以上動かすことはできない。
僕は公園のベンチに座って、空一面に広がる星を眺めていた。都会と自称しているわりには空気がきれいなのだ。お陰で遠くの、微かな星の光まではっきりと肉眼で見ることができる。だからここから見る星空は、黒い画用紙に様々な色のビーズを大量に撒いたような、無秩序さと煩雑さがあった。けれどそれは不快に感じられるどころか、とても心地が良い。完全に決められたものをよりも、こうやって不規則になっているものの方が見ていて安心するのだ。あぁ、ここは人間の世界なのだと、再認識することができる。
昔の人間は神を人間として見ていなかったようだった。もちろんそうだろう。神様というのは人間の形をしたまったく次元の違う存在なのだ。人間として扱うこと自体が失礼にあたると考えられてきたのだろうが、時間が経つにつれて、それらは大きく変わることになる。いつからか、神様を自分たちの力で表すようになったのだ。それは絵の形態であったり、文章の形態であったり。何かしらの彫刻だったりもするのだろう。いずれにせよ、人間というものが神様という遠くの存在のものに手を出したのだった。
それからは人間と神の境界線も曖昧になってきた。神というものが、数学や、科学によって証明されるものなのならば、それらを見つけ出した自分たち人間のほうが、神よりも優れているのではないかと。当時は様々な意見があったのだろう。褒め称える人もいれば、馬鹿なことだと貶す人間もいるだろう。どんな意見があったとしてもそれは別にいいことなのだが、そういう考えにいたってしまうということに、僕は問題意識を感じているのだった。
たとえば自分には到達できないほど高くに立っているものがあるとして、もちろん自分はそれに向かって行動はするけれど、もちろんそれにたどり着いてはいけない。目標はいつまでも高く、遠くなくてはいけないのだ。けれど、それらを手に入れようと考えてはいけない。それらを自分と同じものとして考えてはいけない。そんなことをしてしまったら、それこそ失礼にあたる。相手に対してもそうだし、自分に対してもだ。その人物に対する侮辱である。だからこそ、僕たちは同一化ということをしてはいけないのだ。
「まーたこんなところにいて。風邪ひくよ?」
ふと、少し離れたところから声が聞こえた。快活な少女の声。彼女のことを少女だなんて呼んだ日には、彼女の顔は林檎よりも赤くなってしまうのだろう。大学生にもなって少女と呼ばれているだなんて、若さゆえの言葉ならいいが、幼さからくる言葉だとしたら、恥ずかしいものでしかないだろうから。最初は学校に来られなくなるほどのダメージを受けていたようだったが、その小ささが気に入られたようで、皆のマスコットキャラクターとして一躍人気者となってしまったのだった。
彼女は何かを投げてくる。僕は慌てて顔を持ち上げて、それをキャッチした。熱い。
「……ねぇ、僕が甘いもの苦手だって知ってたでしょ。なんで買ってきたの?」
僕の問いに、彼女は開けたばかりのコーンポタージュに息を吹きかけながら答えた。
「だって、それしかなかったんだもん」
「コーヒーは?」
「なかった」
「ココアは?」
「ココアって甘くなかったっけ?」
「いいんだよ。ほかにはあったかいものは?」
「なかったかな……」
白い湯気が上がるコーンポタージュを口に含む。熱かったのか、口を開けて息を吹きだしていた。まるでどこかの怪獣であるかのように、息の塊を吐き出している。
僕は小さく舌打ちをして、おしるこの缶を手に挟んだ。飲むことはできないけれど、暖かい。持っていて損はしないだろう。良いことだ。けれど、温かいものを手にして初めて気が付いた。今日はとても寒い。暦上は冬であることは知っていたが、それでも特に不便は感じていなかったから、いつも通りの、シャツにパーカーを羽織るだけの格好でいたのだ。まったく気にもならなかった寒さが、一気に僕の身体に襲い掛かる。がたがたと、みっともなく震えてしまった。
「これ使う?」
彼女は自分の持っているコートをつまんで示す。けれども僕は、首を横に振って応答した。女子から衣類を借りるだなんて、男子として恥ずかしい。それに、彼女のサイズが僕に納まるはずもない。
「そう」
残念そうにつぶやく彼女は、誤魔化すようにコーンポタージュに口をつけた。今度はちょうどいい温度になっていたのか、おいしそうに飲みこんでいる。
僕も何度か手の中でおしるこを転がしてみたが、ほとんどの熱が僕の身体へと吸収されてしまっていた。味気ないじんわりとした冷たさが皮膚越しに伝わってくる。
「そういえば、なんでこんなところに来たの? こんな時間に、僕を探しに来るなんて。なにかあったのか?」
僕の素朴な疑問に、彼女は訳が分からないといった様子で首を傾げた。
「特に理由はなかったかなぁ。いつもアルバイトから帰るときこの公園のそばを通るんだけど、その時に限っていつもあなたがベンチに座ってぼーっと空を眺めてるからさ。ちょっかい出しにこようかと思って」
そういって公園の入り口へと視線を向ける。そこには彼女の赤い自転車が止められていた。
特に用事はなかったのか。だとしたら、僕の星を見るゆっくりとした時間は彼女の気まぐれによって粉々に破壊されてしまったわけだな。
「はぁ……」
「なんでため息をつくのさー」
彼女は自分がしたことを全く意識していないようだった。悪いとすら考えていないのだろう。まぁ、彼女の中では、僕は公園でぼーっとしているつまらない人間なのだろうから。つまらない人間は何も考えていないだろうという等式が、彼女の中にはあるのだろう。はた迷惑な話だが、彼女のその気遣いも人気の一つなのかもしれないなと、くだらないことを考えてしまった。
けれど、僕には彼女の言葉の裏には何かあるようだと感じ取ることができた。あまりにも彼女の言葉は軽すぎた。薄っぺらいとでもいうのだろうか。少し風が吹けば、その中に何が入っていいたのかもそれとなく見ることができてしまう。
ほとんど空っぽになったコーンポタージュの缶を手のひらで転がしながら、彼女は遠くの何かを見ているようだった。しかしその視線の先を追ってみても、ただの木しかなかった。何か面白いものがあったわけでもない。
「ねぇ、本当は別の理由があったんでしょ。僕に聞きたいことでもあったんじゃないの?」
僕の言葉に彼女の動きが一瞬だけ止まった。そして、観念したかのように大きくため息をつく。
「となり、座っていい?」
彼女の言葉に僕は了承の意を伝えた。彼女もそれをきちんと認識したのか、ゆっくりと僕の隣へ腰かける。彼女はまるで雪だるまのようだった。白一色に統一されたコートやマフラーが、厚着をした彼女のもこもことした身体を覆っている所為で、余計にそう見えてしまう。なんだか可愛らしいが、詳しく眺める隙間も与えないで、彼女は話し始めた。
「私のバイトのこと言ったっけ? ちょっと特殊な仕事なんだけどさ。仕事量も少ないし給料もそれなりに高いから続けちゃってるんだけど、それに君が少しだけ関係してるんだよね」
「僕? 僕がなにかしたか?」
彼女は小さく首を振る。
「なんていうかね、知っているのか知らないのかはわからないけれど、あなたは普通じゃないことをやってるみたいなの。こんなこと言ったらあなたは私のことを馬鹿な人間として笑い飛ばすかもしれないけれど、いい機会だからはっきりと言わせてもらうね。
あなた、世界の記憶の管理になにか手を出してない?」
世界の、記憶の、管理?
まったく思い当たる節がない。ないわけでもないが、それは全く別のことだろう。僕の頭の中で起きている、ただの自己満足な妄想だ。それが世界の何かに影響しているとは思えないし、僕の頭の中を彼女が知っているとも思えない。ほかのなにかの要因があるのだろう。僕には全く考えつくものがない。
僕は首を横に振ったが、彼女は悲しそうに肩を落とすだけだった。
「……とりあえず説明しておくけれど、この世界はね、生きているの。私たち人間と同じように、長い長い寿命というものがあって、私たちと同じように外側と内側という、物質と精神の境界線みたいなものがあって。私たちと同じように経験をして、記憶を蓄積していくの。その中のプロセスに、記憶の管理というものがあってね。私たちの経験っていうのは、個人によって主観化された限定的な情報でしかないじゃない? だからその記憶を抽出して、綺麗に並べて、必要なものだけを記録として取り出すの。そうすることによって内側には本当に必要なものだけが蓄積されて、より純度が高くなっていくわ。それと同じことが、この世界でも起きているの。この世界が経験したことを、この世界が見たものを、神様たちが記憶の調節と管理をしているのだけれどね。
なぜだか知らないけれど、それがいっつも邪魔されるの。とっても小さなものに、いつも阻害される。やろうとしても、いつの間にか整頓が終わってしまっているのね。仕事がなくなればそれは嬉しいけれど、何もないのに消失してしまったんじゃびっくりしてしまうでしょう? だから私がここに派遣されたの。私たちが知ってる中で一番怪しい、あなたのところにね」
長々と話す彼女は、とても悲しそうだった。何をそんなに苦しそうに語る必要があるのだろう。いつもの元気な彼女はどこにに行ってしまったのだろうか。こんなのでは調子がくるってしまう。うっかり自分かも知れないと口にしてしまうそうだった。けれど、これも彼女の戦略のうちかもしれないと考えると、余計に身が引き締まるのだった。うかつなことは言えない。余計なことも言ってはいけない。彼女に僕がやっているかもしれないということを告げたところでどんなことが起こるかは全く想像ができないけれど、少なくともいいことは起こらなそうだった。そんな予感がする。
「……僕は知らないな」
少しだけ声におちつきがなくなってしまったが、彼女に対する答えを提示することはできた。あとは彼女がどのような反応をするかだけである。
彼女は黙っていた。風がベンチの下を吹き抜ける。ズボンの裾からするりと冷気が入り込んできて、思わず震えてしまった。遠くのほうで車が走り抜ける音がする。いくら人が少ないからって、そんなに急がなくてももいいだろうに。どこかで猫が鳴いた。呼応するようにまた別のところから猫の声がする。それ以外はとても静かだった。夜の公園は、驚くほどに人の気配がしない。それはあたりまえなのだが、昼間までいたであろう子供たちの残留した温かさというか、そういったものがきれいさっぱりなくなってしまっているのだ。なんだかそれが寂しいというか、怖いというか。僕には言葉にして表すことができない。
ふと、彼女が立ち上がった、数歩進んで、僕の方へと向き直る。
「別に、あなたがやっていたからと言って何か特別なことをするわけでもないよ。邪魔な人間だからと殺したりなんかはしない。特別な人間だからと取り込むこともしないと思う。けれど、少なくとも忠告はすると思うの。これはあなたの仕事ではないから、余計なことはしないでね、って。あなたが犯人だということは、もうわかった。あなたって、嘘をつくのが下手ね。すぐわかっちゃんだもの。私と同じ」
そういって彼女は缶の奥底にへばりついたコーンの粒を食べようと缶をひっくり返して揺らす。けれども、一つも出てこない。
ばれているのか。けれどもそれは不思議なことではないのかもしれない。彼女がいったいどんな本性を持っているのかはわからないけれど、普通の人間ではないことは確かなのだ。彼女自身も言っていた。僕と同じだと。そうすれば、逆説的に、僕も普通の人間じゃないということになる。
「なんだかなぁ……」
僕はいたたまれなくなって、手の中に納まっていた冷たいおしるこの缶のプルタブを引っ張った。からん、と間の抜けた音がする。口につけて、勢いよく半分ほど飲んだ。
「……不味い」
僕の声は冬の寒さに呑まれて消えた。
この小さな呟きも、世界には記憶されないのだろうな。
だとしたら、つまらない記憶なんてすべて消してしまえばいい。
僕は、すべてを見通す目なのだから。
【情報】
お題:とてつもない感覚(制限時間:1時間)
2012.11.08 02:01 作成
2023.12.22 13:59 修正
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
