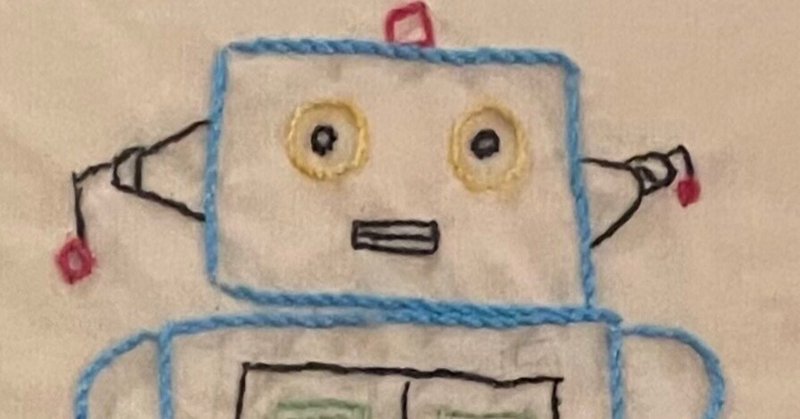
おれと人生とパニック症
初めて発作を起こしたのは小学2年生の夏休みだった。その日は学校の隣にある公民館で小学生対象の「マフィン教室」が開かれていて、おれはそのマフィン教室の参加メンバーだった。朝早く起きて、エプロンと三角巾をリュックに、ドキドキとワクワクを胸にしまって家を出る。トボトボ、テクテク、ウィーン。小学校にはない自動ドアが開いて中へと入る。しかしなぜか、公民館の調理室に入るとすぐにイヤな感じがした。どんどん自分の脈が早くなるのがわかる。興奮や期待からくるドキドキとはまた違う。しばらくすると、急に足がすくんで立っていられなくなった。目眩がする。それに強い吐き気と悪寒がある。訳もわからなくなって、そのまま調理室の床に足を抱きかかえるようにしてしゃがみ込んだ。環境音が耳をつんざくほど大きく聞こえる。呼吸が荒くなる。世界に一人取り残されたような絶望的な気分だった。冷や汗と震えが止まらなくて、このまま死んでしまうんじゃないかとも思った。生まれて初めて味わう感覚だった。
✱ ✱ ✱
これが所謂パニック発作の症状であり、自分にとって初めてのパニックだった。そのときのことは、昨日の出来事のように覚えている。昨日の出来事のようには少し言い過ぎたけど、数ヶ月前に起きたことのように覚えている。分かりやすくいえば、Twitterの固定ツイートのような形で、パニックの体験が脳の先頭にくくりつけられている。何をしていても、何を考えていても、そのときの記憶が頭の隅でチラつく。
その後はというと、様子のおかしくなったおれを見かねた職員さんが自宅に電話をかけ、母親に迎えに来てもらった。おれは半ば引きずられるようにして公民館を後にする。このマフィン教室に参加しているのは面識のない上級生ばかりだったから、全員おれを見てキョトンとしていたのを覚えている。何がなんだか分からなかったのだろう。おれにも何がなんだか分からなかった。結局その日、マフィンは作らずに家に帰ることになった。おれはマフィン教室に行って、マフィンではなくパニックを持ち帰ってきたのである。
家に着いてからは強烈な虚脱感に襲われて、そこから1ヶ月ほど魂が抜けたように寝込んだ。自分がおかしくなってしまったと思ってショックだったのだ。しかも、実際おかしくなっている。可哀想に。幸い、マフィン教室事変が起きたのは7月の最終週のことだったから、その後8月の1ヶ月間は学校に通う必要がなかった。そのときのパニックがずっと続くわけではないけど、その置き土産としておれの人生には恒常的な「吐き気」と「不安感(予期不安)」がインストールされた。
そしてここから、おれと吐き気とパニックとの長い戦いの日々が始まる。まず近くの病院に行って検査をしてもらった。しかし、身体にはなにも悪いところはみつからない。今思えば、パニックを起こしてるのは自分の脳みそなのだから当たり前である。パニックマッチポンプというわけだ。それでも、そのときは原因がわからないということでさらに袋小路に追い込まれた。原因が掴めないのなら、対策もしようがない。どうしたらいいんだろう。
医者は気のせいだと言った。たしかにそれも一理ある。気のせいなのだ。またパニックが起きるかもしれないという「気のせい」で脳が混乱し、それが吐き気や動悸、震え、過呼吸といった身体反応として体に降りてくる。ここに精神的な恐怖感、絶望感が加わって立派なパニックが完成する。刑事さん、これがパニック発作の正体ですよ。ベテランパニック探偵となった今ではこんな風に冷静に分析できるが、当時は冷静ではいられなかった。そもそも、この頃はパニック発作自体を知らなかったから、「それ」は自分だけに起きる特別な体験だと思っていた。ただただ恐かった。
何度か通院を重ねる中で、おれの吐き気は“自律神経失調症”からくるものではないかと医師に告げられた。また、度々起こる「それ」は“パニック発作”という名前がついていることを知った。体に異常が見つからず、原因の分からない不定愁訴は、自律神経失調症、あるいは不安神経症などと診断されることが多い。それにしてもピンとこなかった。かけ算を覚えたばかりの小学生に、「自律神経失調症」なんて七文字は画数が多すぎるのだ。
少年期から薬を飲むのはよくないということで、服薬はせずに、治療は行動療法のような形をとった。学校に通い続けていれば、また自然と元のように戻れるだろうという見立てだった。自分でもそれが一番健全だと思った。クラスにはマフィン教室で起きたことの詳細を知る人はいないから、このことは内緒にしておくことにした。9月に入って新学期が始まると、おれはこれまでどおりに登校を続けた。すぐに元に戻るだろうと信じていた。
✱ ✱ ✱
戻らなかった。3年生になって、4年生になって、5年生になっても、治らない。おれは気づくとそのまま6年生になっていた。特に辛かったのが3、4年生の頃で、この頃はほとんど毎日学校で授業中にプチパニックを起こしていた。発作を起こしても、失神したり大きな声を出したりしない限りは中々気づかれにくい。それに、パニックを起こしている時は呼吸が乱れて助けを求めようにも声を出すのが難しい。おれは友達に「それ」がバれるのが怖くて、こういう時は教科書で顔を隠してその場をやり過ごすか、ただ机に突っ伏すしかなかった。授業が終わるまで耐えられない時には、症状が収まったのを見計らって体調不良を申し出た。次第に、教室という閉鎖空間に対する恐怖が大きくなっていった。
保健室に行くと、おばあちゃん先生がよく飴と紙コップに注いだポカリスエットをくれた。水を飲んだり、飴を舐めたりすると吐き気は少し落ち着いた。パニックもそう長くは続かない。そもそも、保健室に着くまでには発作はすでに治まっていることが多い。パニックに慣れてくると、辛いのはそれよりも常態化した吐き気の方だった。パニック同様、授業中に吐き気が強くなって我慢できそうにない時は、お腹が痛いのでトイレに行かせてくださいといって教室に一番近い男子トイレに駆け込んだ。
トイレに入るとおれは大便器に篭ってよく吐いていた。吐くといっても、心因性の嘔気からくる「えずき」であってブツが出ることは少ない。からえずきであっても、何度も繰り返していると胃液が混み上がってくる。咳をしても一人と言ったのは尾崎放哉だが、おれはえずいてもえずいても一人だった。胃液を通した喉が焼けるように熱い。痛い。加えて、嘔吐やえずきを断続的に繰り返すと、舌が痙攣してつることがある。さらに、トイレの臭気がおれの嘔吐中枢を刺激する。これが引き金となってまたオエッとなる。吐き気をエネルギーとした永久機関の完成である。もちろん、永久機関が成り立たないように、えずきが永遠に続くわけではない。それでもその時間は文字通り永久のように感じられた。生きた心地がしない。この頃には嘔吐に対する強い恐怖感も生まれていた。
4年生の頃、保健室に行き過ぎて一度保健室を出禁にされたことがある。保健室を出禁にされたというよりは、担任が保健室に行かせてくれなくなったという方が正しい。それにしたってふざけるんじゃない。小学生のおれは本当に体調が悪くて保健室に行きたいと訴えていたのに、先生の目にはただ授業をサボりたいだけの生意気な子どもに映っていたようだ。大人は判ってくれない。もう誰にも本当のことを言うのはやめようと誓った。
気持ち悪い、吐きそう、苦しい、分からない、治らない、死んでしまいたい、そういった考えが頭の中を占めるようになった。不眠や拒食を経験したのもこの頃だ。それでも学校に行くのをやめなかったのは、不登校になってクラスメイトから愛想を尽かされるのがパニック発作よりも何よりも恐かったからだ。一度そうなったら、もうここには戻れないとも思った。大人たちは「学校くらい」というが、小学生のおれにとっての学校は世界そのものだった。
①体調が悪くなっても保健室に行かせてもらえないときがある。②発作が起きた時や吐き気が強く出たときに、飴やラムネを口にすると症状が落ち着くことがある。①、②を受けて、小学生のおれが導き出した答えはミント系タブレットを携帯することだった。ただし、公然と校内にお菓子を持ち込むわけにはいかない。授業をサボる(サボっているように見える)上に、学校にお菓子を持ってきているとなったら列記とした不良少年である。ここでおれはある作戦を思いついた。それは、中のタブレットだけをティッシュにくるんでポケットに忍ばせるというものだ。時が来たら、ポケットの中でティッシュを引き裂き、取り出したタブレットを口に運ぶ。持ち前の手先の器用さを生かしたトリッキーな作戦だ。
案外これがうまくいった。懐に忍ばせたこのお守りで、ある程度吐き気をコントロールできるという安心感もあった。それにミンティアは錠剤に似た形をしているから、プラセボのような効果もあったかもしれない。これで残りの小学校生活はなんとか乗り切った。しかし、こんなのは所詮その場しのぎの弥縫策であって、根本的な解決には程遠い。校内お菓子無許可携帯罪にも抵触している。コナンが小さな探偵さんなら、おれはちびっ子犯罪者だ。いつしかクラスメイトにトリックを見破られるのも恐ろしい。罪悪感が積み重っていく。おれは弱い。吐き気だけが強い。
✱ ✱ ✱
中学に入ると症状はだいぶ落ち着いた。不安感や吐き気こそあるものの、実際にパニックが起きるのは1ヶ月に2、3回程度になっていた。部活が始まって、運動が習慣づけられたのが効いたのかもしれない。一番社交的だったのも中学生の頃だと思う。教室でパニックを起こすことが少なくなった代わりに、おれのパニックは深夜に根城を構えるようになった。眠れないという恐怖がパニックを誘発する。そんな時はよく深夜ラジオを聴いていた。ラジオから流れる声に意識を向けて、呼吸が整うのをじっと待つ。
更にパソコンとインターネットが身近になって、自分と同じような症状を抱えている人がたくさんいることも知った。一人じゃない、そう思うだけで心強かった。また、ネットにはパニックを回避するための方法として、ミント系タブレットを携帯することがよく挙げられていた。衝撃だった。おれと同じだ。それに、自分と全く違う場所で育った全く知らない人間が同じ結論にたどり着いているというのが、生物の収斂進化のようで少し可笑しかった。
高校は、県西部に位置する公立の男子校に進学した。変わった高校で、制服と校則がない。変わり者も多かった。しかも駅から高校まで徒歩で約30分もかかる。数ある高校の中から、駅徒歩30分で私服登校の男子校を選ぶ人間なんておかしいに決まっている。それでも、自分にとっては小さい頃から憧れの高校だったから、入学が決まった時は素直に嬉しかった。
部活は「古典ギター部」に入った。演奏にクラシックギターを使う珍しい部活だ。新入生歓迎会での演奏に惹かれて入部を決めた。この頃には症状がだいぶ改善されていて、新しいことに挑戦してみたいという気持ちもあったと思う。念願であった第一志望にも合格して、今ならなんでもできるような気がしていたのだ。しかし、それから数ヶ月して、これが甚だしい自惚れであったことがわかる。
春の定期演奏会が終わると3年生は引退となって、いよいよコンクールに向けた本格的な練習が始まる。先輩に基礎を教えてもらったら、パート練習、全体練習を繰り返して完成度を上げていく。度々外部コーチにも演奏を聞いてもらって、フィードバック、調整を重ねる。夏休みに入るとすぐに合宿があった。部員全員で士気を高めていく。おれが再びパニック発作を起こしたのはそんなときだった。
✱ ✱ ✱
あまり正確には覚えていないけど、「それ」が起きたのは4日間の合宿のうちの2日目の夜のことだったと思う。全体練習が終わって、夜のパート練習に入った頃。手が震えて急にギターが弾けなくなった。吐き気と動悸が激しくなり、呼吸が不安定になる。冷や汗が止まらず今にも死にそうだ。コンクールが迫っているという緊張感からだろうか。山の上の合宿所という閉鎖空間で過ごすことへのストレスもあったかもしれない。とにかく、「またか」と思った。そこから、パートメンバーにことわりをいれて自分だけ部屋に戻らせてもらった。悔しい。情けない。おれはまた振り出しに戻る。
同じパートの同級生は、明らかに様子のおかしいおれをみても深入りせずに、そっとしておいてくれた。こんな異常者と残りの日数同じ部屋で過ごすというのに、嫌な顔一つしないで受け止めてくれたのだ。なんて優しい人たちだろうと思った。同時に、これ以上自分がこの人たちの演奏の邪魔をしてはいけないとも思った。おれは練習にも参加出来ないから、ギターよりも重い文字通りのお荷物である。山を降りたら退部を申し出よう、そう決心した。
合宿から帰ってきて少ししたら、パートのメンバー、部長、顧問の先生に最後の挨拶をして部活を辞めさせてもらった。この時も、同級生にはハッキリとした理由を伝えられなかった。説明責任を果たせずに辞めていったことを今でも申し訳なく思う。顧問には自分の症状のことを丁寧に説明してみたけど、能天気な先生なのもあってあまりピンと来ていないようだった。それがどこかありがたくもあった。それと、今読んでくれているか分からないけど、部活をやめた後も変わらずおれと仲良くしてくれた古ギタのみんな、本当にありがとう。
✱ ✱ ✱
久しぶりに発作が出てからは自律神経の調子が狂ったようで、一ヶ月ほど37℃〜37.5℃台の微熱が続いた。それがよくなると、他クラスの友人に斡旋をしてもらって美術部に入った。というのも、全能感に包まれて入学したおれは、文化祭の実行委員にも所属していたのだ。そこで仲良くなった友人の一人に美術部の部員がいた。これも後出しになるが、おれは絵を描くのが好きだった。目の前の紙に向かって全集中している間は、吐き気や不安を忘れることができたからだ。
美術部の活動はあくまで個人作業で、自分におあつらえ向きのように思えた。作品が思うように進まなくても、他の誰にも迷惑がかからない。また、美術部には他にも転部を経験した部員が多かった。いつも異臭・悪臭がする美術室は衛生的には最悪だったけど、いつしかおれにとっては最高に居心地のいい場所になった。制作は絵画、彫刻、金属加工、アニメーションの中から絵画を選んで、静物画を始めた。
静物画は孤独だ。キャンバスとモチーフ、そして自分の内面とひたすら向き合い続ける必要がある。それでもこの没入感が好きで、受験勉強と並行しつつも作品制作は高3の秋まで続けた。美術大学に進学したい気持ちもあったけど、自分は絵が得意なわけじゃなくてただ手先が器用なだけであること、真似ごとがうまいだけで独創性や創造力はないことが分かっていたから、その道はキッパリ諦めることにした。中々冷静である。
✱ ✱ ✱
高校卒業後は都内のとある大学に進学した。といっても、学部1、2年の間は横浜に近い別のキャンパスまで通う必要がある。自宅から通うのか、大学近くに家を借りるのか悩んだ末、電車での長距離通学を決めた。片道2時間半と長旅ではあるものの、実家から通えない距離ではない。それに、一人暮らしで別途発生する家賃や光熱費はバカにならない。
最初の二週間、おれは何も問題なく大学まで通えていた。往復5時間あれば、軽い新書や短めの小説は読み切れるし、端末にダウンロードした映画も2本は観れる。あまり苦には感じなかった。しかし、三週間が経った頃、おれは初めて電車の中でパニック発作を起こした。
朝の満員電車に耐えられなかったのだ。何がトリガーになったのかは分からないが、電車の中という閉鎖空間が急に恐ろしく思えた。しかも周りは人に囲まれて逃げ場がない。足が震えて力が入らない。冷や汗が頬や背中をつたうのがわかる。吐き気が込み上げてきて、えずきが止まらない。通勤特急も止まらない。気持ちが悪くて、苦しくて、うまく呼吸ができない。次の停車駅につくまでの数分が、数十分、数時間のように感じられた。意識が薄れる。
気がつくとおれは数駅先のホームのベンチに座っていて、時計を見ると1時間半が経過していた。意味がわからなかったけど、自分の中で何かが終わったんだということだけが分かった。そこから10分間は、ただ遠くのビルを眺めてぼーっとしていた。ホームに入る電車の音、構内アナウンス、人の足音、学生たちの声。水中から陸上の音を聞くように、全ての音が曖昧にぼやけて遠くに聞こえる。いつまでもこうしていても仕方ない。今日はもう家に帰ろう。そう思った。
✱ ✱ ✱
パニックの典型的な症状に広場恐怖というのがあるのは知っていたけど、高校には3年間電車で通学できていたし、みんなと同じように修学旅行にも行けたから、勝手に自分はその限りではないと思っていた。大学以外に寄る辺のないおれにとって、通学手段の電車を封じられるのはかなりの痛手だ。休学するという手もあった。しかし、ただでさえ知り合いの少ない大学で同級生と学年がズレていけば、卒業が難しくなることも確かだ。どうにかここにしがみつくしかない。だから、病院に行ってきちんと薬を飲むことに決めた。
小学生の頃と同じ病院だけど、先生が変わっていたから、自分の症状のこと、大学のこと、今までのことを最初から事細かに説明した。親身になって話を聞いてくれる大人がいる。それだけでも少し救われたような気がした。8歳の頃は、子どもの言うことだと思って誰もまともに取り合ってくれなかったからだ。その後は、内服(常服)と頓服の薬をそれぞれ処方してもらって、次の週から元のように大学に通うことを約束した。急行や快速にはまだ乗れないから、各駅停車でじっと堪えて学校の最寄り駅に着くのを待つ。
それから、朝のラッシュを避けるために、一限の講義がある日はいつも始発に乗って大学に向かった。特に冬場の始発は寒い。寒い上に暗い。電車に揺られて少しすると、宵の空が白み始める。東雲色に染まったガラス窓から、柔らかい朝の日差しが車内に差し込む。夜から朝にシームレスに切り替わるこの瞬間がおれは好きだった。また、始発の電車に乗っている人間は、身支度をしているか、寝ているか、いびきをかいているかの3パターンで、人の視線を気にする必要がなかった。朝から働く大人がこんなにたくさんいることも知った。お疲れ様です。今日も一日頑張りましょう。俯いて顔こそ見合わせないものの、そんな連帯感が朝イチの電車にはある。
✱ ✱ ✱
薬を飲んで大学に行く生活が1年近く続いた時、ふと死にたいなと思った。死にたいというより、死んだ方がいいかもなと思った。薬を飲んでいれば、発作は未然にふせげるけど、不安感と吐き気の方はどうにもならなかった。むしろパニックを薬で無理に抑え込んでいるような形だったから、発作が出る寸前の気持ち悪さ、居心地の悪さが発散されずに自分の中に溜め込まれて行くような感覚だった。これがずっと続くというなら小学生の頃と変わりないし、だったらどこかで見切りをつけた方がいいと思ったのだ。
21歳を迎える前に死のう。そう決めたのが19歳の頃だったから、タイムリミットは一年半。その間にできるだけのことをやろう。現実での関わりを大切にしようと思って、まずTwitterをやめた(今思えば、現実での関わりとかネット上での関わりとか分けて考えてるのがくだらないけど)。おれのTwitterアカウントが「2018年3月からTwitterを利用しています」となっているのに、2018年と2019年のツイートがほとんどないのはそのためである。心配して連絡をくれた人ごめんなさい。
大学2年の夏休みは、しばらく会えていなかった小学校の同級生、中学校の同級生、高校の同級生、いろんな人を遊びやご飯に誘った。そのためにアルバイトも掛け持ちした。薬で常に頭がふわふわしていたからこその決断力や行動力でもある。「死ぬ気になればなんでもできる」とはよくいったもので、死ぬことを決めてからは全てがどうでも良くなって、その分足枷が外れたように自由に動き回ることができたのだ。
そうしている内に、社会では未曾有のウイルスが蔓延、あれよあれよと言う間に世界中で流行。死んでる場合じゃないぞ、と思っておれは死ぬのをやめた。子供の頃から漠然と死にたい死にたいとは思いつつも、自分の人生史の中でこれほどまでに自死に近づいたことはない。冷戦で言うところのキューバ危機である。そしてその危機は謎のウイルスの登場によってあっけなく解消された。でも本当は、死ななくてもいい適当な理由をどこか自分の外側に求めていただけだと思う。なんでそんなに死ぬことに必死だったのかはわからないけど、人が死にたい理由も、死なない理由も、そんなものなのかもしれない。
✱ ✱ ✱
ところで、こんな文章を書いているおれが今どうなっているかというと、特にどうにもなっていない。症状はひどくはなっていないけど、別によくもなっていない。大学4年の10月だというのに、就職先も決まってない。来年からどうしたらいいのかも分からない。とんだ大うつけものである。それでもこのnoteを書こうと決めたのは、自分の体調のこと、これまでのことを打ち明けられるタイミングが今しかないと思ったから。中学校を卒業するとき、高校を卒業するとき、いつか言おう、いつか、いつかと思いながら今日までずるずるときてしまった。
昨日、10月1日は、多くの企業で内定式が執り行われて、新しい一歩を踏み出した同級生も多い。心からおめでとうございます。反対に、家の学習机でこんな恥ずかしい文章をしたためているおれは、見事に新しい一歩を踏み外したことになる。お決まりの言い方をすれば、社会のレールを外れたわけである。もっとも、小学2年生のあの日からおれはとうに脱線していて、その隣を自転車で息せき切って並走しているようなものだった。当然、自転車ではいつか電車に追いつけなくなる。そしてそのいつかが、昨日だったんだと思う。
今まで、正確には8歳から22歳までの14年間、友人や同級生を騙し続けているような後ろ暗い気持ち、罪の意識が心の中に大きなしこりとして常にあった。それを隠すために、生返事ではぐらかしたり、冗談を言って誤魔化したり。長らく使っているこの「finto」というハンドルネームも、ニセモノや偽善者といった意味である。誰かに分かってほしいと願いながら、勝手に一人達観した気になって、みんなとの間に境界線を引いているのは自分の方だった。だから、レールを外れたとはいっても、胸襟を開いて話せた今はむしろ、肩の荷が下りて清々しい晴れやかな気分でいられる。
✱ ✱ ✱
こういうエッセイは、僕/私はこんなハンデを抱えていながらそれを乗り越えて立派に育ちました、そしてこんな企画を、こんな会社を立ち上げました、努力最高!、みなさんも努力をされてみては?といった内容のものが多い。別にそれに異議を唱えるわけじゃないけど、世の中の大半の人間は努力を重ねてもそっち側にはいけない。症状を抱えながら、誰にも打ち明けられず、更にはそんなサクセスストーリーに日々打ちのめされて、打ちひしがれる人の方がずっと多いはずだ。成功譚、成功談は目についても、失敗談はなかなか見つからない。
だからこそ、烏滸がましいけれど、こういう形で自分の弱い部分、恥ずかしい部分を含めた全部を書き留めておくことに意味があるんじゃないかと思った。もしかしたら、同じような悩みを抱えている人もいるかもしれない。「絶対に治る」とか「必ずよくなる」とか、そういう強い言葉は送り出せない。明確な対処法も示せない。おれは「死にたい」と言う人に死なないでとも言えない。言えないけど、これを読んで、こんなにみっともなく生きてる人間がいるんだったら まあ自分も死ななくていっかくらいに考えてくれる人が本当に一人でもいたら、自分の14年間も少し報われたような気持ちになる。
最後までありがとうございます。
