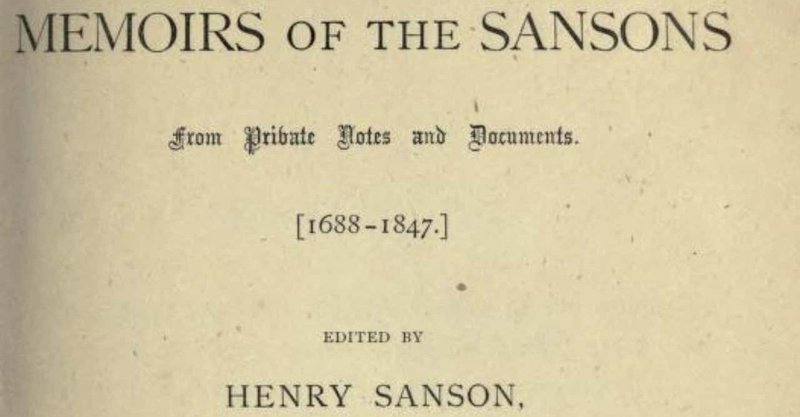
第16章 ゴマール神父
我々の家族の3人目の友人について話そうと思う。その愛情はジャン=バティスト・サンソンからわが祖父の時代まで非常に長く続いた。その友人とはレコルト修道会[17世紀に創設されたフランシスコ派の流れを汲む一派]のピクピュス[現パリの南東部にある地域]の神父であるアンジュモデスト・ゴマールである。
ルイ14世の治世の末期と摂政時代において、処刑台まで罪人に同行することを認められるのはソルボンヌの神学博士のみであった。しかし、ルイ15世とルイ16世の時代になると、そうした慣習は破棄され、その目的に応じてあらゆる宗派から適切な聖職者が選ばれるようになった。ゴマール神父は罪人に同行するという困難な責務を割り当てられていた。わが祖父の職歴の大部分の間、ゴマール神父はそうした責務を忠実に果たしていた。そのような職務にふさわしい者はほかにいなかった。神父の顔は優しく、話し方が穏やかで説得力に富んでいた。いかなる強張った心であっても親父の言葉に動かされないことはなかった。強い義務感のみでゴマール神父は多大な労力を必要とする責務を果たしていた。罪人の近くにとどまってその額から流れ落ちる汗を拭い去ることをずっと強いられることになる緩慢で残虐な責め苦のせいで彼が力を失うこともあった。高等法院によって濫用された刑車による刑罰が執行される際にそうしたことがいつも起きた。わが曽祖父と祖父は哀れな聖職者の苦悩を見てしばしば助けに入った。あまりに神父が弱ってしまったために住んでいる修道院に帰れなくなったことがあった。そこで神父は、我々の家で数時間休んだからどうかという申し出を受け入れざるを得なかった。愛情深い気遣いを受けた神父は、これまで家の主人の職業のせいで感じていた恐怖を克服できたようであり、それ以後、苦痛に満ちた責務を共有する我々に対して本当の愛情を示すようになった。神父はしばしばわが祖父を訪問して毎週金曜日に我々の家で夕食をともにした。
ゴマール神父は嵐のような激動の人生を送ったと言われていた。彼の穏やかな表情は、情念によって強く試されていた魂を隠していた。大きな悲しみを経験した後、彼は修道会に入ったという。わが祖父もわが父も神父の素性を確かめようとしなかった。彼の若い頃のロマンスは誇張されて噂されているだけだと彼らは納得していた。神父はとても話好きであり、我々とテーブルを囲んだ時、パリに住む若い姪の身の上を心配していると言った。姪の軽薄で遊蕩な生活は彼にとって絶えず不安の種になっていた。彼は「彼女は原罪の子です。彼女がその生まれによる影響を受けているのではないかと私は恐れています[ 父親がはっきり誰かわからない子供だということ]」と言った。
この少女の名前はマリー=ジャンヌ・ド・ヴォーベルニエである。彼女は、代父のビラール・ド・モンソーの庇護の下、サン・アン修道院[パリにあった修道院]で教育を受けていた。しかし、本当に庇護を与えていたのは尊敬すべき神父であった。神父は何らかの理由で彼女に対する愛情を社会から隠していた。教育は彼女の心にまったく恩恵を与えなかった。彼女の思考は完全に世俗のことに向けられていた。そして、熱心な懇願したおかげで彼女はラビーユという名前の有名な仕立て屋で修行することになった。こうした変化は彼女の堕落の原因となった。毎日、宮廷や町の華美な物を見られるようになった彼女はすぐにあだっぽくなり、いつも見ているすばらしい者たちを真似たいという思いで心がいっぱいになった。ジャンヌの美しさは並外れたものであり、もしその魅力が価値を持つ舞台に上がることさえできれば、彼女が大きな成功を修めることは間違いなかった。少女は野望の餌食になった。邪魔な叔父の干渉を受けなくなった彼女は、罪深く遊蕩な生活を送り始めた。
ジャン=バティスト・サンソンは毎日、ゴマール神父の嘆きを聞いた。神父は公然と彼女の自堕落な生活について話すことはなかったが、彼女についてそれとなく苦言を呈した。神父は、堕落の主な原因となった彼女の際立った美しさの特権を絶えず嘆いた[以下、ゴマールの姪に関する部分をこの章の終わりまで仏原文から翻訳する]。
その当時、わが祖父のシャルル=アンリ・サンソンは若さの血気と情熱に満ち溢れていた。神父の話によって彼の想像力に火がついた。彼はその美しい少女を知りたくてたまらなくなって、大きな危険に身をさらすことになった。高潔で立派な心構えは本心の吐露や秘かな欲望の兆しと常に混じり合うものだ。シャルル=アンリ・サンソンの心の中では、その堕落した魂を正道に戻して父のような愛情を持つ年老いた叔父の言うことを彼女が聞くようにしたいという微かな希望と、ゴマールがあまりにも得意になりすぎたせいで描写を止められなかった美女を知りたくてたまらないという熱望が混じり合っていた。
神父の口からうかつに漏れた言葉からシャルル=アンリは、少女がバク通りに住んでいることを知って、さらに家の番地も覚えた。その瞬間から彼は監視人となって、自分が作り上げたゴマール神父の姪の理想像とぴったり合う人を見つけるまでその家を出入りする人をすべて見張った。それほど長く待たずにすんだ。そうした観察を始めた最初の日から彼は、夕食後に若い娘が姿を現すのを見た。その娘のまばゆいばかりの瑞々しさ、清く澄んだ瞳、珊瑚のような唇、真珠貝のような歯、そしてみごとな淡い豊かな金髪は、優れた古代の彫像を作った者でも生み出せないような優美さと明るさを現代のヴィーナスに与えていた。この若い娘は1人の侍女を連れていた。彼女は悪意を抱いてその者と話しているようだった。というのは、若者が秘密を隠す時にするような大げさな笑いで何度も会話を中断させていたからだ。2人はテュイルリー庭園[パリ中心部セーヌ川沿いにあったテュイルリー宮殿に付属する庭園]に入った。わが祖父は少し距離を置いて2人の後をつけた。2人を見失いたくなかったが、自分の姿をあまりさらしたくもなかったからだ。

こうした慎重な行動は望んだような成功を収めなかった。娘と侍女は同じような手管の対象になることに明らかに慣れていて、つけられていることに気づいていたので、庭園の通路を3、4周しかしなかった。ところが彼女たちは気分を害したようには見えず、何度も頭をぐるりと回すと、怒りではなく挑発的な視線を不思議な追跡者に投げかけた。
すでに言ったようにシャルル=アンリ・サンソンは容貌優れた紳士であり、ごく自然な感じで優美かつ目立つ服を着て、剣を帯び、飾り紐のついた帽子をかぶっていたので、完全な貴人の雰囲気を漂わせていた。この好ましいよそ者は、ジャンヌ嬢と侍女をこれ以上怯えさせないほうがよいだろうと思ったようだった。そこで彼は、彼女たちがテュイルリー庭園を散策して公園を出て家に戻るまで後をつけるのを止めた。
翌日、彼はできる限りうまくやろうとしたが、前日と同じく彼女たちに声をかけられず、試みようとしている改心をほとんど進められなかった。彼は、彼女たちの姿がバク通りにある家の小さな扉の中に消えるのを見ていた。そして、根を生やしたように舗装に立ち尽くして天を仰ぐと、人間の言葉の無力さと神による救済の難しさについて悲しい物思いに耽った。2階の窓のカーテンが少しだけ引き上げられたように見えた。するとジャンヌ嬢の魅惑的な顔がガラスの後ろにもの珍しそうな様子で現れた。それを見た彼は怯むどころか、沈黙の会話を終わらせて思わせぶりを言葉に変えてほしいという願望を強い眼差しで示そうとした。
訴えかけが理解されたにせよ、それとも若い娘が不思議な追跡者の目的から何が期待できるのか知りたくなったにせよ、もう二度と彼女の姿を見られないかのようにじっと窓に目を向けていたシャルル=アンリ・サンソンは優しく侍女に腕を引かれた。侍女は彼に深々と挨拶した。
侍女は「騎士さま、私の女主人のランソン嬢は、あなたがお近づきになって何かを伝えようとこの2日間にわたって後をつけていることにお気づきです。この点に関して疑惑を解いて、あなたが何をお求めになっているのかうかがうように私はおおせつかりました」と勝手に称号をつけて話しかけた。
わが祖父はいつも断固たる決意を持っていた。彼は引き下がろうとせず、ためらうことなく答えた。
「私があなたの女主人とお近づきになりたいと真摯に思っていたことは本当です。しかし、彼女に私の気持ちを伝えることができなくてお近づきになる栄誉を得られないでいました」
侍女は「お嬢さまは目が見えないわけではありません。お嬢さまは独身でどなたでも自由にお招きになれます。私はどのようなお名前の騎士さまがお嬢様とお話ししたいと伝えればよろしいのですか」と強い語気で続けた。
「私の名前はたいしたものではありません。繰り返しになりますが、あなたの女主人に光栄にもお伝えできるような名前ではないのです。彼女はまったくご存知ないでしょう。しかし、隠す必要はありません。ロンヴァル騎士とお伝えください」
そうした称号は侍女の洞察力を裏付けるようなものだったので彼女をとても喜ばせたようだった。彼女は矢のようにその場を離れると同じようにすぐに戻って来て、満面の笑みを浮かべながら、お嬢さまが騎士さまをお待ちですと言った。
決定的な瞬間が訪れた。シャルル=アンリ・サンソンははやる心を抑えきれずに階段を上って部屋に案内された。その部屋には太陽の光が差し込んでいたが、カーテンによって明るさが和らげられていた。香水の芳香が充満していた。壁[仏原文はtrumeau de la cheminée et les dessus de portes、18世紀フランスの炉棚上に絵画や鏡板で組み込んだ装飾壁のこと]にはヴァトー、ランクレ、ナトワール[いずれも18世紀に活躍した画家]の模作が飾られていた。ジャンヌ嬢は、当時流行していた「その日のお楽しみ[仏原文はbonheur du jour、18世紀半ばに流行した女性用の装飾が施された小型の書き物机、恋文のような女性の「その日のお楽しみ」を隠すための収納が設けられていたことがその名前の由来だという]」というかわいらしい名前が与えられた小さな家具の一つにしどけなく座っていた。わが祖父を見ると彼女は親しげな微笑みを浮かべて、どうにか1人しか座れないような小さな家具に座るように身ぶりで示した。
わが祖父が座った後、彼女は「騎士さま、どうしてあなたは私をご訪問くださったのですか」と言った。
それはなかなか厄介な状況だった。哀れなわが祖父はプティ=ジャンの親父[17世紀半ばにJean Racineによって書かれた喜劇『Les Plaideurs』に登場する人物]と同じような困惑を感じた。ただ彼はまだ始まりを知っただけだった。本当になんと言えばよいのか。このかわいらしい罪深い者が笑うと、地上の楽園のあらゆるリンゴ[禁断の果実のこと、すなわちジャンヌがあらゆる欲望に耽っていることを示唆している]を噛み砕く32本の歯が見えた。シャルル=アンリはサタンの爪から彼女をもぎ取って神の救済に至る道に戻すためにやって来た。守護天使にして改心を促す者の役目を果たすには彼はあまりに若かった。ジャンヌ嬢を見つめている間に天国の仕事よりも地獄の仕事をしたほうがましだという考えが彼の心に浮かんだことを認めなければならない。
しかしながら、なんとか仕事を終えなければならなかった。だから彼は、たとえ抵抗に遭って打ち負かされることになっても、前置きをすべてすませて、すぐに問題に取り掛かろうと決意した。
彼は重々しくため息をつくと「お嬢さま、ゴマール神父をご存知ですか」と言った。
この名前を聞くと、彼女は唐突に立ち上がった。楽しそうに紅潮していた彼女の顔は急に青ざめた。彼女の瞳には怒りがさっと閃いた。彼女は震えをなんとか隠そうとしながら言った。
「なんということをおっしゃるのでしょう。いったいあなたはどのような権利があってゴマール神父のことを私にお話しにいらっしゃったのでしょうか。あなたは神父が私のもとに送り込んだ密偵に違いありませんわ。そんなにお若いのにあなたが女を追い詰めるような仕事にもうすでに関わっておいでなら残念に思います」
わが祖父は「お嬢さま、そのような疑惑をあなたは抱いておられるのですか。私がゴマール神父を知っているのは本当のことです。しかし、私は自らここに来ました。私は神父が姪であるあなたのことについて話しているのを何度も聞きました。あなたを心から愛している神父は、不信心者があなたを堕落させていると嘆いていました。私はあなたを見つけに出てようやくあなたのもとにたどり着きました。そしてあなたの足元に身を投げ出して、昔のあなたに戻って、あなたの現世の幸福と来世の永遠の祝福を願って、教会と親族という二つの権威をもってあなたに話しかけている立派な聖職者の声に耳を傾けてほしいと懇願するつもりです」と哀れみを込めて言った。
このように話すと、シャルル=アンリ・サンソンは言葉を行動に移して、ジャンヌの足元に身を投げた。こうした熱弁が始まってゴマール神父の自分に対する愛情を聞いた時、若い娘は感動したように見えた。涙が彼女の目蓋を湿らせた。しかし、このすばらしい説得が終わると、彼女は誤りを犯した説教師の耳に響いたことがないような高笑いをして、半ば引き上げられた仕切りに隠れて視界の隅から推移を見守っていた侍女に声をかけた。
彼女は「とんでもなく愚かな人ね」とまったく遠慮もなく言った。
自分の説得がほとんど成功を収めなかったのを見てシャルル=アンリ・サンソンがどれほど困惑して驚愕したのか判断するのは止めておこう。おそらく咄嗟に状況を判断できる力がなくてそのまま長い間、馬鹿げた姿勢を保ったのだろう。彼は立ち上がって膝の埃を払いながら、説教を聞き入れないような生意気な女を相手にしていると納得して、悔悛による救済よりも破滅に目を向けさせて怯えさせる手法は成功しそうにないとすべての希望を捨てた。
彼は「確かにあなたの言うとおりです。神父の嘆きをすっかり信じるとは私は愚か者です。立派な方には勝手に嘆いていただき、人生は甘美なものだと納得していただきましょう。あなたのカーテン越しに見ると、人生は決して薔薇色に見えませんけどね」と言った。
今度はジャンヌが言い返す番だった。
彼女は「ゴマール神父についてもっと敬意を払ってお話しください。粗忽な若者の口を通すと、神父の説教が馬鹿げたものに思えるかもしれませんが、神父自身の口を通せば立派に思えます。それは年齢と品性のなせるわざです。それにあなたは私が心から尊敬する親族について言及していることを忘れないでください」と言った。
そうした非難はシャルル=アンリ・サンソンの心に響いた。確かにそれはそのとおりであったからだ。彼は旧友を軽々しく扱ったことで良心の呵責を秘かに感じた。
彼は「お嬢さま、私よりもゴマール神父を尊敬してる者はいないと請け合います。ただ私がここに入った時に浮かんだ考えがあまりに心を乱すものだったので、どうすればよいかわからなかったのです。私は同時に笑って泣きたかったくらいです。私はあなたのように若く陽気で美しい方と会えて幸せです。私は心から嬉しかったのです。それから私はあなたの尊敬すべき叔父が言っていたことをすべて思い出したので、強い悲しみで心が沈んだのです」と続けた。
少女は「いろいろとほめたりけなしたりしていただいてありがとうございます」といたずらっぽく答えた。「ただ我々の知識は近日のものに限られています。叔父はあなたがおっしゃったお名前の家との関係を私に話したことがありません。ここでこのすばらしい会話をお開きにしてまた良い機会に続きをやりませんか」
わが先祖は「ああ、ランソン嬢、私のやり方が間違っていました」と苦しげに答えた。「しかし、それはあなたの叔父さまへの敬意と私があなたにお目にかかる前に感じていた不思議な気持ちから生じたものなのです。あなたにお会いしてからそうした感情がより強くなって絶対的な支配力によって動かされているとお伝えしたほうがよろしいでしょうか。私を拒絶しないでください。私をあなたの友人にしてください。いつか私の貢献がきっとあなたのお役に立つ時が来るでしょう」
若い娘は再び笑って「そうなると、私が叔父の密偵と思った者が今度は私の密偵になろうと言うのですね」と言った。
彼女に対する親族の思いやりを伝え続けるという手法を秘かに喜ばしく思ったのか、それともわが祖父の率直さと善意がジャンヌの繊細な心を動かしたのかわからないが、彼女は最初に示した意思を完全に改めることはなかったにせよ、奇妙な方法で関係を始めた哀れな追跡者と再会を約束して友人になった。
この時からシャルル=アンリ・サンソンは、しばしばジャンヌ・ヴォーベニエルと会った。もしこの本が醜聞を追求すれば、その当時の娘は浪費を示すことが愛嬌なのだという考えを彼女が共有していたと私は指摘できる。私が知っていると断言できることは、わが祖父はこの若い友人、すなわち後のデュ・バリー夫人について思いやりと敬意を示して話すことがなかったということだ。
わが祖父は彼女を愛していたと否定しなかったし、無感動な王の関心を引くことになるこのやっかいな美女に対して熱烈な情熱を抱いたことも否定しなかった。しかし、彼は、愛が報いられたと言ったことは決してなかった。したがって、こうした家族の告白において私は、王の愛妾になる運命を持ち、その人生の黎明期において王冠と処刑台の間[王冠は王、処刑台はサンソンのこと]で板挟みになる彼女とわが祖父の恋とヴァラン夫人とジャン=ジャック・ルソーの恋[ルソーは富裕な愛人のヴァラン夫人の後援によって身を立てたことをその著作で赤裸々に綴っている]を、生じた結果がまったく違うとはいえ、わざわざ比べようとは思わない[この一文は非常に難解であり、原文に忠実に沿って訳すと意味が通らないのでかなり意訳している]。死者の記憶を侵すようなことをするべきではない。
こうした慎みは不幸なことに誰にとっても当たり前のことではない。なぜならシャルル=アンリ・サンソンとデュ・バリー夫人の関係はしばしば言及され、出どころの怪しい回顧録の作者たちや逸話の収集家たちによってまったく信じられない話がでっち上げられているからだ。彼らはわが祖父を奇妙で宿命的な若者として描き、ジャンヌ・ヴォーベニエルの人生における成功と没落の預言者として扱うだけではなく厳しい警句と結びつけているが、私は彼女がフランスの王妃になれた場合に恩寵を与えてほしいと彼が求めたという話をまったく知らない。彼らは伯爵夫人の人生の記憶に残る状況で彼を2回登場させている。そして、もし彼女が3度目に彼と会うことになったらそれは神のもとへ行くことになるという神秘的な言葉を紹介している。この3回目の邂逅は処刑台で起きた。この不幸な女は予言の成就という奇跡を経験したという。
若い頃の友人が革命の餌食になった時にわが祖父にどのような恐ろしい試練が待ち受けていたのか私が述べる必要があるとは思わない。しかし、紹介したばかりの馬鹿げた話をここで否定する機会を私は逃したくない。そうした馬鹿げた話は、たとえ聖エドム[13世紀イングランドの聖職者、王権と対立してローマ教皇に助けを求めたが受け入れられなかった]の信条よりも正確な信条の中であろうとも居場所を見つける。こうした荒唐無稽な捏造は十分に馬鹿らしさを露呈しているし、私の家族の誰かが将来、それらを読む恩恵を受けられるかどうかわからない。

シャルル・アンリ=サンソンとジャンヌ・ヴォーベルニエの関係は私が話したとおりであり、彼が彼女に対して予言を告げたという話が生まれた背景は明らかである。ルイ15世の愛人であった彼女は敵によってフランス王政の崩壊の原因の一つとされているが、少なくとも王政の崩壊の傍観者であり犠牲者であった。不思議な一致であるが、彼女は、王を戴冠させて国を救った英雄的な乙女であるジャンヌ・ダルクを生んだことで永遠の栄誉を得た小さな村のヴォクラール[フランス北東部にある村、ジャンヌ・ダルクゆかりの地として知られる]で生まれた。快活な精神、品性、礼儀作法を持っていてもヴォーベルニエ嬢は15世紀の英雄と自分の関係を誇らずにいられなかった。その誇り高い人生と受難にもかかわらず、ジャンヌ・ダルクは聖人の列に加えられなかったが[ジャンヌ・ダルクが列聖されたのは20世紀のことである]、ヴォーベルニエ嬢は、しばしばジャンヌ・ダルクに加護を祈っただけではなくジャンヌ・ダルクが守護聖人だと主張した。
ある日、彼女が「私の守護聖人である聖ジャンヌ・ダルクにかけて」という使い慣れた表現をシャルル=アンリ・サンソンの前で使ったことがあった。彼女がいつもそのように言っていたかは私にはわからない。
彼女と親しくなっていたわが祖父は「ああ、ジャンヌ。あなたはジャンヌ・ダルクとほとんど似ていません。もし神があなたをもう1人のシャルル7世[ジャンヌ・ダルクが活躍した時代の王]の前に置いたとしても、あなたが果たす役割はジャンヌ・ダルクの役割ではないでしょう。むしろあなたが果たす役割はアニエス・ソレル[シャルル7世の愛人、奢侈を好み、宮廷内で内紛の種を作った]でしょう」と優しく言った。
まさに予言である。未来は2人が思うよりもすぐに到来した。
ジャンヌはべキュ、通称カンティニーという名前のお針子の娘であった。彼女は後にランソン・ド・ヴォーベルニエと呼ばれる門番と結婚して子供を自分の子供として認知した。彼が彼女の父親ではないことは間違いなかった。実父はゴマール神父であると信じるに足る十分な根拠がある。聖職衣を着ていることからゴマール神父が実父だということはまともに取り上げられなかった。ゴマール神父が若い頃に不道徳な生活を送っていたと考えられることがこの秘密の親子関係の唯一の根拠である。
確かなことはゴマール神父が姪と呼んでいる娘に父のような優しさを抱いていたことである。長い間にわたってゴマール神父は、そのような愛情を強く示して彼女のことについて話していた。さらに彼はそれを隠そうとしなかった。そのせいでシャルル=アンリ・サンソンは強い情熱を抱いてこの心が奪われるほど蠱惑的な女と恋に落ちた。我々は彼がその時に抱いた感情について知ることができる。金曜日の夜、彼はゴマール神父がジャンヌについて話すのを聞いた。日中、彼は彼女のことを数時間も見つめていた。そのせいで燃え上がった恋の炎に彼は飲み込まれてしまった。
彼は老人から色々と聞き出していつも秘密を暴こうとした。しかし、ある考えからそれを止めることにした。ランソン嬢は、ランソン・ド・ヴォーベルニエの娘と言われている。ただ出自を隠す必要があると考えられたのか、彼女の名前の頭文字が変更されていた[仏原文ではランソン・ド・ヴォーベルニエはRançon de Vaubernier、ランソン嬢はMademoiselle Lançonと表記されている]。パリの処刑人は彼女のそうした変名を暴露しないように注意していた。彼は、若く容貌優れた貴人のロンヴァル騎士であり、正体の露顕を恐れずにゴマール神父の友人だと主張できた。というのは彼は叔父と姪、実は父と娘が顔を合わせていないと知っていたからだ。謎のヴェールを取り除こうとすれば完全に引き裂くしかない。シャルル=アンリ・サンソンはそのような危険を冒したくなかった。なぜなら彼はこの美しい娘との関係に完全に心を奪われていたからだ。
ジャンヌは美しいだけではなかった。彼女はごく自然で快活な何とも言えない最高の魅力を持っていた。彼女には狡猾な貴婦人となる素質があり、後にフランスのロクセラーナ[16世紀オスマン帝国のスレイマン1世の皇后、奸計を用いて愛人から皇后の座に上り詰めたとされる]となった[以下、デュ・バリ-夫人のその後の経歴に関する話が続くだけなので省略]。
第17章に続く
目次に戻る
ここから先は
¥ 100
サポートありがとうございます!サポートはさらなる内容の充実によって読者に100パーセント還元されます。
