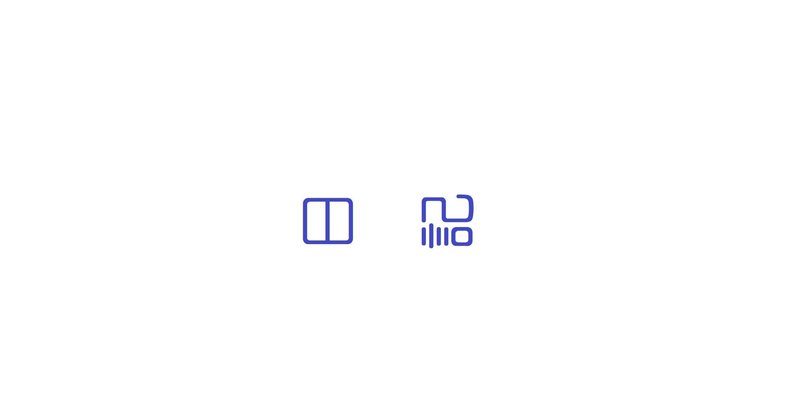
【2020.04.19】痛みは避けられない。けれど、それを苦しむかどうかは自分次第である。
1週間ぶりにランニング。ネックウォーマーで鼻の上まで覆って12km。
皇居のような景色の良いランニングスポットを走れれば最高なのだけれど、外とはいえ人が密集する場所は避けたい。聞いた話によれば、同じくランニングスポットである駒沢公園はランナーでいっぱいらしい。今回の事態を機に走ることを始めたランナーも多い気がする。
そういう場所を避けていつもの退屈な大通り沿いを走ったけれど、それでもそれなりに人がいる。信号待ちのときなどは、意識して離れないとソーシャルディスタンスを保てない。ランナーのなかでマスク着用などのなんらかの配慮をしている人は、ざっと見たところ1/3もいない。
走って乱れた呼気はけっこう大きい。今日みたいに風が強ければ、ソーシャルディタンスの2メートルでも足りないのではないかという気がする。「気にしすぎ」なのだろうか。
とはいえ、運動はやはり気持ち良い。走り始める前は鬱々としていたけれど、汗をかいて風呂に入り、すっきりした心身で味わう美味しいクラフトビールのテイクアウトは最高。
お気に入りのお店は、こちらから持ち込んだ容器でのテイクアウトも始めてくれた。このためにわざわざ酒類小売業免許を取得したらしい(同じことを考えるお店が多く、いま申請がわんさか集まっているとか)。ビール用の水筒は「グラウラー」というらしい。初めて知った。このお店のクラフトビールは入れれば2日はもつというから、土曜日にテイクアウトすれば連休楽しめるじゃないか。
欲しい...欲しいぞ......グラウラー......。
美味しい燻製料理のランチテイクアウトも500円~で始めてくれていて、ぜひ試したい。が、お店まで行ったら昼からビールも付けてしまいそう......抗える自信がない。
オンラインショップも作り、クラフトビールと燻製おつまみのギフトセットの販売も開始。もうすぐデリバリーも始めるらしい。どんどん対応が広がっていて頭が下がる。
オーナーいわく(僕と似ていると言われる例のオーナー)、この状態が短くとも今年いっぱいは続くことを想定して、新しいこの営業形態を充実させていくそう。
冷静に状況を見極め、臆せず新しいチャレンジをし、お客さんとのコミュニケーションも良好。
大丈夫。このお店は絶対大丈夫だ。
今日は、過去に読了したけれど書き忘れていたレビュー執筆を何件が済ませた。そのうちの一冊がこれ。
2014年に読んだ本で、9月の208kmマラソン挑戦に向けて今年もう一度読んだ。
村上春樹作品はどれも、読後に身体がズシンと重くなるほど疲れる。想像の中で旅しているのではなく、現実の身体が本当に旅をしているような感覚になる。
これだけフィジカルな影響を与えられる文章をなぜ書くことができるのか?
それは、村上春樹さん自身が身体との対話を丁寧に繰り返しているからなのだと思う。そのことがこの本を読むとよくわかる。身体を単なる「物質」として見ていない。擬人化し、言い聞かせたり駆け引きをしながら付き合っている。
この感覚は、いちランナーとしてよくわかる。
面白いことに、この本を読んでいると「走ること」と「書くこと」の類似点が見えてくる。たとえば、ゴールすること以上に、そのプロセスにおける進歩──自身の限界値を少しずつ上げていくこと自体を重要視することなど。
申し込んでいたマラソン大会がどんどんと中止になっていくなかで凹んでいたけれど、もうそろそろ「走ること以外の別の目標」を見つけなければならないと思っている。
ウルトラマラソンの準備には、数カ月にわたる多大な準備が必要だ。お金も、時間も、労力もかかる。短い人生のなかで大きな負担を強いて挑むためには、機を外さないことが大事。ここまで外部状況が悪いのだから、そろそろこの目標を一度手放す覚悟を持たなければならないと思っている。
そんなときに、村上春樹さんのようにアナロジーによって類似点を見つけ、同じような醍醐味を味わえる他の領域への移行ができればいいのかもしれない。
それがいったいなんなのか。それを見つけ出すためには、僕が「走ること」に何を求め、どこに喜びを感じていたのかをひとつひとつ言語化していかなければならないのだと思う。大好きなことができなくなったときに、それに代わる新しい何かと出会うためのアナロジーを見つけるために。
Pain is inevitable. Suffering is optional.
──同書、p.3
痛みは避けられない。けれど、それを苦しむかどうかは自分次第である。アナロジーは、苦しみを回避するひとつの有力な手段なのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
