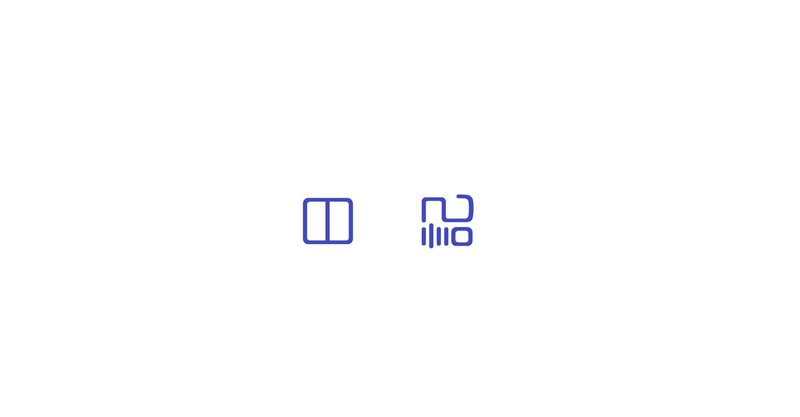
【2020.05.29】バトンを渡すことを前提に進める。そこには、自分一人で取り組めてしまうこと以上に謙虚な気持ちが生まれそうな気がする。
「21:00の『キングダム』放送までに1,500字書き終えなければならない」という大いなるプレシャーにさらされている。もしも最後のところが「ああああああ」とかになっていたらごめんなさい。そういうことです。
「毎日水を2リットル飲みなさい」と、あちこちで聞く。
「そんな、ビールじゃないんだから飲めるわけないでしょ」と思っていた(ビールなら飲める)。
が、最近飲んでいるのである。水を、2リットル、毎日。スーパーで汲んできている2リットルペットボトルが毎日1本カラになるのだから、間違いない。
なぜ飲めるようになったのか。「ビールでもなければ」と思っていたはずなのに、なぜか。
それは、水を注ぐグラスをビールのパイントグラスに変えたからだ。朝っぱらからパイントグラスである。会議中も、オンラインイベント中も、気まずさのかけらも持たずにパイントグラスである。
おそらく、脳はビールだと思い込んで飲んでいるのだろう。手に馴染むこの形状が、脳をうまく騙しているのだろう。
これだけ飲んでいると、やはりトイレが近くなる(なんの話を)。身体の中身がどんどん循環しているような気持ちになり、なんだか気分が良い。
そんな良い気分に乗っかって、今日は準備していたものをなんとか入稿することができた。「入稿、迫る」というと、とても怖い響きだ。間に合ってよかった。
仕事で本棚を漁っていて、買ったのに読まずに置きっぱなしだったこの本を再発見した。
中世ラテン語辞書。これをつくるのに100年以上かかったらしい。
もう口語として使われなくなった言語の辞書をつくる。つまり、せっかく苦労してつくっても、需要も儲けも見込めない。加えて、100年かかるとなれば、制作開始当初から携わる人たちは生きているうちに完成を目にすることはできない。
それなのに、なぜ情熱を傾けて取り組むことができたのだろう。
よっぽどその言語が好きで、取り組んでいるプロセス自体に喜びを感じられる人たちだったのだろうか。
リーダーが素晴らしい人格者で、「この人のためなら」と、事業内容以上に人柄に惹かれて仲間が集まったのだろうか(でもそのリーダーは100年以内に変わるはずだから、これで感性までつなぐのは難しそう)。
あるいは逆に、事情があって逆らえないような人たちが泣く泣く取り組んできたのか(それだったらこんなに素敵な装丁の本にはならなさそう)。
政府や財団からすごい額の助成金が出ていて、実は裕福になれる仕事だったのか。
いろいろな妄想をしていると、読み始める前から楽しい。本は開かれる前から喜びを与えてくれる。
ラテン語辞書づくりに限らず、こうやって自分の人生ひとつよりもずっと大きい目的をイメージするのは、けっこう大事なんじゃないかと思っている。バトンを渡すことを前提に進める。そこには、自分一人で取り組めてしまうこと以上に謙虚な気持ちが生まれそうな気がする。
「自分がいなくなっても残るものをつくる」、それに対しての取り組みはイメージがわきやすい。誠意ある本づくりは、まさにそういうスパンで見ている仕事だと思う。
「自分がいる間に完結しないものをつくる」、これはやっぱりレベルがだいぶ違う。いまそんなものを、自分は持てているだろうか。
今週1週間はけっこう慌ただしかった。これくらいの時間になってくると猛烈に眠くなるのに、なぜか布団に入ると眠れない。季節の変わり目はだいたいこうなってしまう。早く慣れないと。
明日はゆっくりしたいところだけど、ボランティアで受け持っている冊子編集のお手伝いや溜まっている選書作業を進めなければ。それが終わったら身体を動かしたい。そろそろある程度長い距離を走る感覚も取り戻していかないと。
21:00の10分前。なんとか間に合った~
それでは、『キングダム』!!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
