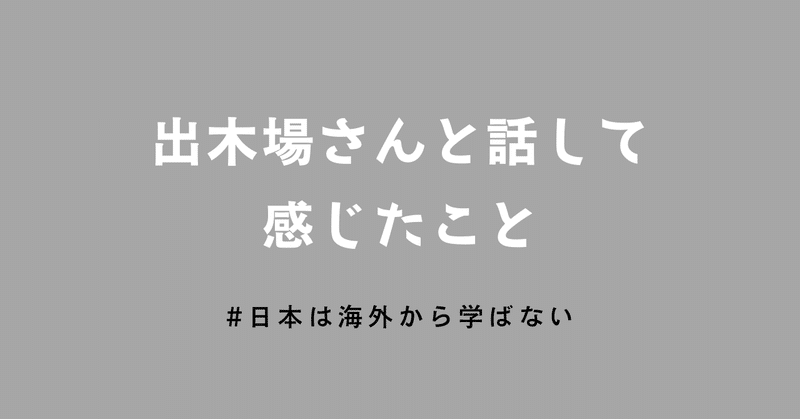
リクルートCEO出木場さんと話して感じたこと
出木場さんと話して学んだことを、自分のためにテキストでまとめながら、これはもっと広く伝わった方がいいことだなと思ったので、今回ブログとして書いてみます。
初めてリクルートの出木場さんとお話させていただいた。改めて自分のスケールの小ささを感じたし、ずっと口開いてたと思う。w
— Ichiro Shoda | HERP (@fabichirox) March 10, 2022
内容はともかく、世界から見た日本についてずっしり学んだ。
<対象としている読者>
- 起業家と、スタートアップで働く皆様
- 日本のスタートアップエコシステムを進化させようとしている全ての方々
本エントリーの私のスタンスとして、起業家の目的は人それぞれで、何が正しいという立場の議論ではないということをまずここに書いておきたい。上場をすること、売却をすること、調達をすること、それぞれとても意義深いことで否定されることでは絶対にないし、何より会社経営は個人の意思と個人の価値観で進むものであり、それは絶対に否定されるものではない。本エントリーも何が正しいということを論じたいのではなく、あくまでも出木場さんのお言葉をうけて僕が解釈したこと、感じたことを書いていると認識していただきたい。
日本全体に対しての危機感
まず僕が感じたことは、強い危機感でした。それを全身で感じる時間だった。Indeed買収からアメリカに拠点を持ち、アメリカの第一線の起業家・VCの方々と日々接している彼だからこその視点・視座からくる危機感は私にとって新鮮でかつ痛烈なものでした。シンプルにいうと、日本の起業家の目線の低さ、そしてその状況が劇的に変わっていく兆しもないということ。
日本の起業家の意識
年間100人以上の起業家と話をしている彼の視点から彼らに対して抱いている印象は、1回目の起業がほとんどであり、時間軸への意識や、最終的に成し遂げたい目標の高さに対しての意識が低いレベルで共通化しているということ。
具体的には、マザーズに上場することを過度に意識していたり、創業時に最終的なゴールのあるべき形(売却なのか、長期目線での経営を意識して上場を考えるのか)に対しての意識が薄い。言葉を変えると、とりあえず数百億でマザーズに上場すればいいのではと思っている人、それを目標にしている人が多すぎるということだった。
彼の指摘は、その先に待ち受けていることへの覚悟と意識はあるのか?上場がゴール化して、リビングデッドのようになることへの危機感はないのかというもの。話を聞いていて非常に耳が痛く、自分にも大きく当てはまるものだと思った。本当に高い山を目指せているのか、どこまでいけると思っているのか、それを創業期にしっかりと考え、売却を通じてミッションを達成するつもりで経営するのか、それとも産業を作る当事者になるのかをはっきりさせること。これこそ起業家が自分に問い続ける必要がある問いなのではないかと。
それを作り上げているもの
では、そういった日本の状況を作っているものは何なのか。ここには個人的な見解も交えて書いてみようと思う。
<日本は世界から学ばなくなった>
出木場さんのお言葉を借りると、「明治時代より海外の事例に学ばなくなってしまった」「タイムマシン対応できることをしようとしない」。おっしゃる通りだなと思った。SaaSビジネスはアメリカからおよそ15年遅れ。
もちろんマーケットの性質に大きな差分はあるものの、複数回日本と同じサイクルを回しているアメリカの起業家たちから学ぶべきことは計り知れないと思う。言語の壁や、国内にベンチマークがあること、そして国内の起業家やVCとしか交流をしないという状況があり、海外から常に何かを学ぼうとしている人が圧倒的に少ない。非常に耳が痛い。
<シリアルが少ない、マーケットを押し上げることにつながっていない>
それに加え、日本にはまだまだ複数回の起業を通じて大きな山を登っているという人が少なく、アメリカの数十年前の状況そのものになったままの状態がある。特定の領域がホットになり、その領域で1回目の起業をする人が増えていく様子はさまざまな領域で見られるようになったが、そのトレンドを繰り返すだけ。以下の記事にもあるように、マーケットサイズからするともっといろんな領域で特大ホームランがあってもいいし、ホームランを打った人たちが新たな産業を作り出す動きがあってもいい。それが日本では創業者の退職に対してまだまだネガティブなイメージが残っていたり、マザーズに上場し、非常に特殊な市場環境での経営に苦戦・奔走する状態の人たちが多い状況が生まれている。
また、上記の記事にも言及があるが、複数回の起業・売却を経てベンチャーキャピタリストとして活躍している方々が多いアメリカに比べ、日本のVCは金融系出身の方々や、VCが初めてのインターネット産業との接点だという人も少なくないからこそ、この状況を良い方向に強い力で導くに至っていないという点もある。
<コミュニティがない、意識が上がるきっかけがない>
私は幸いなことに出木場さんとお話をする中で大きく意識が変わるきっかけになったが、そんな機会がなければ、同じようなステージで、同じマーケットに対峙している人たちとの会話の機会しかない状況になっている。「数千億の上場を目指してその先はどうするの?」という出木場さんのお言葉がいまも印象に残っている。
<日本人的な家族観>
これは良い悪いという議論をするものではないし、ある意味日本人らしい良いところでもあると思うが、やっぱり日本においては会社や仲間へのつながりの意識が強いと言える。事業上のミッションを達成することに対しての合理性の追求よりも、つながりが優先されては元も子もない。こういった意識が事業売却などのEXITにおける意思決定の歯止めになっていることもあるのではないかと思う。 ただ出木場さんも、「仲間だけは絶対に大事にしないといけない」とおっしゃられており、ここは僕も共感するところでもある。おそらくバランスの問題なのかなとも思う。ただ、この仲間たちと何かをやること、一緒に成功することを必要条件にスタートしていては、登るべき山にたどり着くのに時間がかかりすぎる。世の中をどう変えるのか、が大前提あった上で、仲間を大事にできることが素晴らしいスタートアップ経営なのだと思う。大きな論点ではないかもしれないが、起業家の中にも自分自身のエゴとしての大成功したいとか、成功した人だと思われたいみたいな気持ちも、本質的なゴールに向かうことを邪魔をしている部分もあるのかもしれない。
アメリカの状況
上記のような状況に対し、アメリカはどういう状況か。これも何となくは理解していたつもりだったが改めて現地にいる出木場さんに話を聞くことでリアリティを持って感じられた。インターネット産業のエコシステムが全く異なるとシンプルに感じた。 スタートアップの起業家は、創業時から大きなプラットフォームに乗るのか、それともプラットフォームになるのかを意思決定した上で会社をスタートする。前者の場合は、起業してすぐからGAFAMを筆頭とする大きなプラットフォームに対して売却の相談を持ちかける。そして、上場後の経営とスタートアップの経営というものが別のものという認識が揃っており、最適なタイミングで交代をすることを称賛する文化まで存在する。作ること・育てること・そしてより大きな山を登ることの役割分担がはっきりしているという印象だ。
起業家の意識
その中でも印象的だったのは、複数回の起業家だからこそブートストラップ(外部からの資金調達をせずにスタートアップを経営すること)を意図的に選択する人が多いという話。我々に近い例でいうと、BambooHRもその一つ。資金調達をしないのは、そもそも資金があるからそういった選択ができるというのはもちろん、最終的に上場するとしても、売却をするとしても、創業者の株式保有比率が高い状態を維持することがとても大切であると創業期から理解しているということである。「上場するときに80%は持ってたいよね、その先ずっと(経営を)やるなら」という出木場さんの言葉もこちらで共有しておきたい。これだけでも日本との差分がすごいことはよくわかると思う。その前提にあるのは、売却自体をとてもいいことだと捉えている共通認識がある。その起業家が新しい山を登れるようになるという意味でもそうだし、ミッション達成のために巨人と組むことが戦略としても正しいということ、そして大きな組織の経営は大きな組織の経営に対して専門性を持っている人たちがやるべき(交代をよしとする)という意識がある。事例として出木場さんに教えてもらったものは、直近上場をしたStitch Fixの創業者は、現在ボードには名前があるもののCEOからは退いており、新たなCEOの紹介文にも以下のような記載がある。
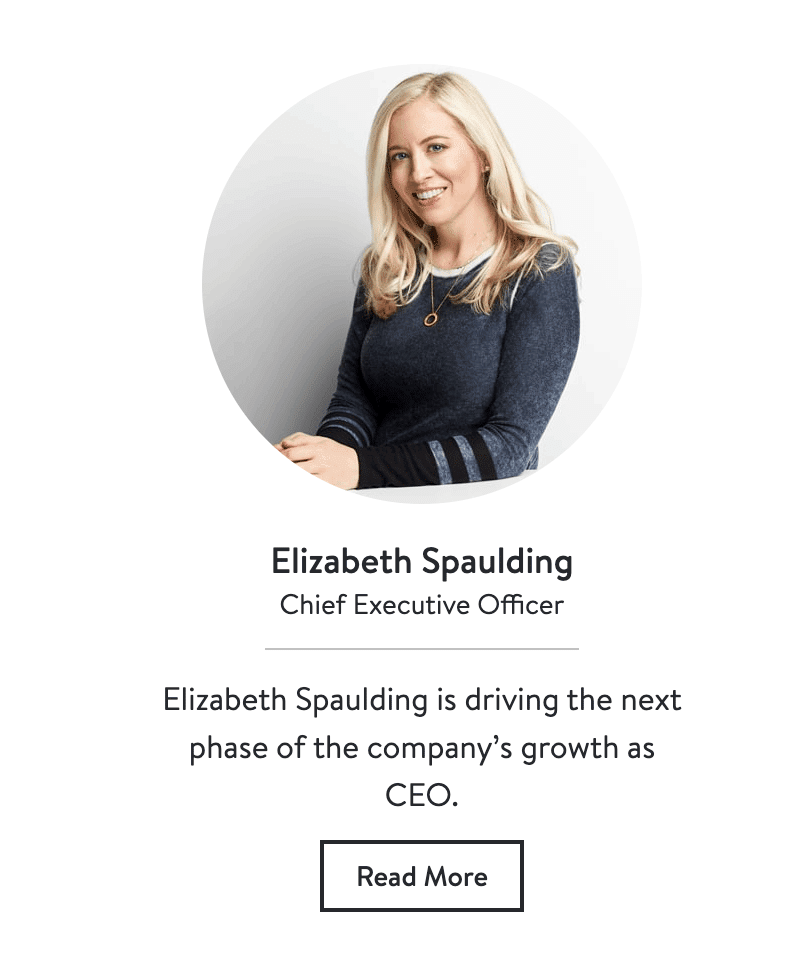
この事例においてアメリカでは素晴らしい交代だったと称賛の声が大きいとのこと。そんなことまだ日本ではあまり見たことがない。SmartHRの宮田さんの代表交代が記憶に新しく、素晴らしい事例だと思うが、もっと増えていく必要がある。
そして全ては「世界を変える」という思い、それに尽きる。会社の成長戦略・生存戦略ではなく、どこまで世界を変えられるか、その一点から合理的な意思決定を行っていく。本来そうあるべきなのは頭ではわかっているつもりなのだが、上記の通り、日本人的な感覚なのか、やっぱり会社や仲間への帰属意識・当事者意識が強くなる傾向があるように思う。
それを高めるもの
こういった状況を作っているのはもちろんこれまでの歴史が生み出してきたエコシステムである。多くの経験をした起業家がVCとなり新興産業を作る起業家を支援する。そして、起業家自身も、自分の登る山を見極め、自分の役割を果たそうとする。すべてが綺麗に整った状態で進んでいるわけではもちろんないと思うが、少なくともそれが理想であるという共通認識はあるように感じた。
そして、出木場さんが拠点をずっとアメリカにおいている意味がとても理解できた。
個人的な感想・気持ち
出木場さんとお話をしてから、2週間。自分の中でいろいろなことを噛み砕き、今回こちらにめちゃくちゃ簡潔にまとめてみたが、何かしらエッセンスが少しでも伝わったら嬉しいなと思う。出木場さんのお考えについてこちらにもよくまとまっているのでご一読を。
そして個人的な感想も戒めとして最後に記載しておきたい。まず私が感じたのは、悔しさと虚しさだった。出木場さんに言われていることに対して本当にぐうの音も出ないという状況だった。そして同時に、「僕がこれまでやってきたことはなんだったんだ?」というような何とも言えない感情も生まれた。でも後者の感情はすぐに変わって、今からやれることをやるしかないなという気持ちになった。
2週間ほど経って今の気持ちとしては、より高い視座を獲得するための機会を得ようと努力しつつ、改めてどうやって世界を変えるのかを突き詰めること、そしてそこにフォーカスすることが結局は大事なことなんだなという気持ちになっている。結論我々もEXITを目指す上で、上場するのか売却をするのかみたいな話は本質の部分ではなくて、いかに会社としての目標を達成するかにフォーカスしたいなという気持ちだ。
そして、この悔しいという感情は、彼の言っていることが全て当てはまると思ったからにすぎなくて、自分自身は目線をさらに上げるきっかけを自分から取りに行く努力を疎かにしていたところがあると思うし、ある意味コンフォートゾーンに留まってしまっていると思う。そういう意味で今回の機会は本当に貴重でありがたいものだった。
出木場さんの話が私にとても刺さったのは、上記の総論の話だけではなく彼がHRTechマーケットにおける巨大サービスを作ってきた経験があり、欧米のマーケットにも詳しいというところがある。具体的な例でいうと、僕自身は解像度の低かったアメリカのATSマーケット事情について、LeverやGreenhouseという有名サービスも、とても厳しい状況に置かれているということ。マーケットサイズとバリュエーションを考えた時に選択肢が少なくなってきているということ。我々と同じ年に創業したHRTechのスタートアップが、4000億円以上のバリュエーションをつけながら売却をしようとしていること、そもそもHRマーケットのSaaSはバーティカルな領域に比べ成長速度が遅く(これは実体験からも理解があった)Workdayクラスのサイズになれるポテンシャルがないと上場しても意味がないという彼の言葉は僕にとても刺さった。
そして些末な話ではあるが、英語力にめちゃくちゃ自信があるという状態では全くないので、英語学校に通うことにした。w 昨日レベルチェックテストを受けてきたところ。何か意味がありそうなことをしたくてすぐに申し込んだ。NCC綜合英語学院というところに通うので、もし一緒に勉強してくれる人がいたらご連絡を。w
以上、少し過激な内容も含まれていると思うが、自分にとってはとても貴重な機会で、多くの人に知って欲しいという思いで綴ってみた。いろいろな方々の感想やご意見をお待ちしております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
