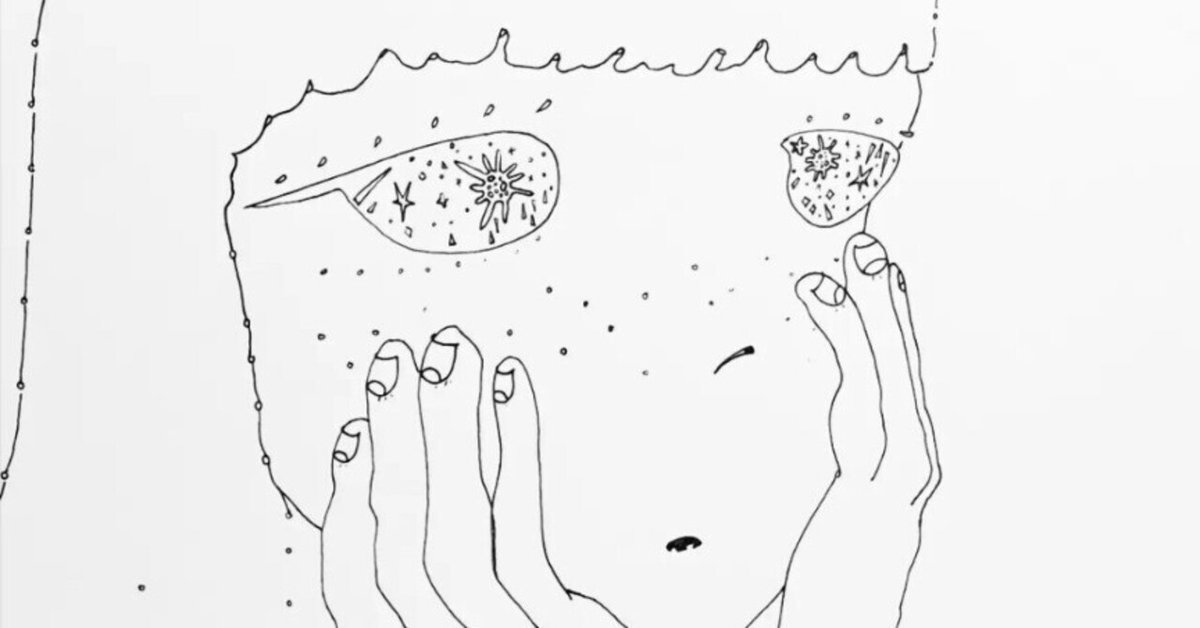
「やり方」がまちがってたときのこと 2O24.O5.31 essay
今日からこのnoteのアプリに日記を書いてみようと思う。
日記を書くのは16、17歳の頃からの習慣で、いつもはスマホの日記アプリにポツポツ打ち込むか、Rollbarnのノートに手書きで書いている。なんでnoteに書こうと思ったのかというと、それは今これを読んでくれている方のように、他者の目に映る文章を書いてみようと思ったから。いや、違う、他者向けの文章を作るのではなく、自分の素の文章が他者の目に映ることを望んでいるんだと思う。とか書きながら、「今これを読んでいる方」のところを「読んでくれている方」に打ち直してしまった。カメラが回ったら素ではいられないのと同じで、文章もきっと他者の目を意識した瞬間に純粋なものからは遠ざかってしまうんだろうな。けれどそうであるにせよ、なるべく自分が心の底から思っていることを書き出し、いや、吐き出してみたい。そう、吐き出すことがこのnoteでやりたいことでもあるし、なかなか素直になれないわたしの人生における一つの目標でもあります。
それに好奇心として、自分がどんなテーマなら書き続けられるのかを知りたいというのもある。わたしが敬愛する坂口恭平さんは、いわゆる起承転結があり筋の通った小説は書けないけど、自分のことならいくらでもするすると書けるそう。文庫本化もされている『躁鬱大学』はそうして書かれたもの。さらに何も何も書けなくなる鬱の時でも、自己否定の言葉ならとめどなく出てくるそう。そもそも文章が書けない人間なのではなく、書きたいスタイルの文章が書けないっていう事実があるだけで、別の蓋を開ければそこから言葉は流れ出してくるんだ、と。理想とは違う文章になるかもだけど、書けないってことは、きっとない。
わたしは読書は好きだけど、読書を始めたのも中学生くらいと個人的には遅めのスタートかなと思っており、なので今も活字に対して苦手意識はゼロじゃないと感じる。それよりも辛いのは、論文やレポートなどの、論理立ててわかりやすく文章を書くというのが非常に苦手なこと。大学時代はそのせいでかなり苦しかった。今日はそのことを書こうと思う。
レポートも冗談抜きで泣きながら必死にやっていた。難しいからわからない、といってしまえばそれまでなのだが、それ以上にその難解な文章を前にしたときの身体面での強張りが尋常じゃなかったのだ。学習サポート課ではなく、病院に行って診てもらいたい、助けてもらいたいと切に思っていたけど、誰にも話せなかった。身体症状としては、まず首から肩がガチガチに凝る。とにかく動悸が止まらないし、呼吸が深く吸えない。汗を握った手にマーカーペンを持ち、落ち着いて一文目を読む。読むだけだとただ文字を目で追っただけで意味が頭に入ってこないので、声に出して読んだり、書き写したり、脳内で誰かの声に置き換えて読んでみたりと色々工夫する。一文終えてホッとしたのも束の間、左手をそっとずらすとその下には隠れていたさらに何十行もの文がぞろりと待ち構えてこちらを凝視する。その瞬間に今しがた読んだ文の意味が飛ぶ、そもそもの問いがゲシュタルト崩壊する、なんでこんなレポートやらなくちゃいけないんだろう、なんで大学に通ってるんだっけ、なんでなんで、と今最優先で解くべき問いがずれてゆく……。
というふうに、とにかくレポートが出る度にひいひい汗をかいていた。ゼミの先生から三浦綾子の『塩狩峠』を貸してもらったので感想を送らねば、というときも酷だった。他者のためにする読書はなんと大変なことか、この時も一文目から「感想をかかなきゃいけないからちゃんと理解しなきゃ」という緊張で、意味が頭に入ってこないため、最初から書き写していた。分厚い本なので書き写すだけじゃ次に開いたときに前回までの内容を忘れてしまう。なので、読みながら思ったことや疑問など、些細な気づきをできる限り詳細にわたって書き込みまくった。もちろん、こんなの全然楽しいわけなかった。先生、わたし読めません、と言えなかった。この時はまだ自分の頭や体がおかしいんだと思い込んでいた。わたしは小説が読めないんだ、文章が苦手なんだ、この先もずっとそうだ。そう思っていた。
でもうちに帰ると、その日の日記はいくらでも書けたのだ。書けない辛さや身体症状の苦しみも言葉にあらわせた。文章や言葉が嫌いじゃないことは知っていた、むしろ好きなのだということもわかっていた。大学を卒業しても、楽しく自由に文章を書く機会を持ち続けたいとも思っていた。でも、そのあと始まった卒論ももちろんひいひいで動悸ばくばく焦りまくりの日々。書きたいのに書けない。怖い。もっと読みたいのにちゃんと理解できない。自分がいやだ。気持ちは灰色から黒色へとどんどん変わっていっていて、最終的には先生の前で泣いた。「書けないんです、読めないんです」と伝えたけれど、先生とは最後まで通じ合えず、「もう今日限りで研究室にはくるな」といわれ、わたしのぼろぼろの卒論は先生の加筆によって完成されたのだと思う。無事卒業することができたから。
要するに全然素直じゃない日々だったのだ。言いたいことが言えない、思ってることができない、やりたくないことをやり続けている、という状態だったからうまくいかないだけだったのだ。そのことに気づいたわたしの人生大転換は大学3回生、大好きで通いまくっていた阿倍野の「スタンダードブックストア」に、ある本が平積みにされていたことからはじまる。
『躁鬱大学〜気分の波で悩んでいるのはあなただけではありません〜』
水色の表紙にシュールな学生猫。ふと手に取りめくって読んでみた。ふむ、ふむ、次のページ、次のページ……あれ、読める。買って駅へ。駅のホームでも読む。電車の中でも読む。読める、読める!っていうか、読んでる感覚がない。いや、読んでる。
そして唐突に聞かれる。
「今これ読めてるでしょ?」と恭平さん。
「それは、興味があるからだよ」
久しぶりなのか初めてなのかわからない脱力感を感じた。深く息が吸えた。そして吐けた。
ずっと努力でどうにかなると思って頑張ってきたレポートや論文。周りのみんなもそもそもテーマに興味なんてなかったはず。それでも、だるいだるいと言いながらも結局はできてしまう彼らに劣等感を感じながら図書館で一人ひいひいやってたわたしが一番聞きたかったことばは「大学卒業するためだから頑張って乗り越えて」という社会的な励ましではなく、恭平さんのことばだった。
どこから読んでも読めたし、どこから読んでもいいのが本だ、それが読書だと思えたこと。どこまで読めたかページ数を確認する、なんてことしなくても読んでるだけで嬉しくて楽しくて面白くて、読了の達成感なんてどうでも良いと思えたこと。この本の音声版があるのに気づいた時、読書っていうのは言葉と出会うことが本質であって、その言葉は必ずしも紙面にくっついてないといけないわけではないんだ、音に乗っていたっていいんだと気づいたこと。
こんな読書体験は初めてだった。とにかく言葉を吸収するたびに体や心がやわらかくなっていくようだった。素に戻れる。夢中になれる。
ここまでで2,695文字。これがレポートだったら何日かかってるだろうと思う。好きなことならどんどん書ける。何を書くか全く決めてなかったけど、ちゃんと着地できた。書けなかった時のことが吐露できたので、すっきりして寝れそう。そうだ、これは「エッセイ」という名の「吐露」だ。おやすみなさい。読んでくれてありがとう。明日も素直でいられますように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
