
【開催レポート】10月30日に10名のゲストが登壇する「esse-senseフォーラム vol.0」を開催しました!(8183文字)
10月30日(土)に、NPO法人ミラツクが新たに設立した株式会社エッセンスによる先端研究メディア「esse-sense.com」のローンチ記念イベント「esse-senseフォーラム vol.0」を開催しました。
「esse-sense.com」は、独自アルゴリズムによる視野を拓く推薦システムを備えたWEBメディアとして、2021年9月16日にスタートしました。「esse-sense.com」は、研究者が持つ、専門分野としての深みと、独自のものの見方・捉え方の2面を伝えるためのインタビュー記事を、オリジナルのインタビュー記事として制作し配信するインターネット上で読めるWEBメディアです。
今回のフォーラムは3つのセッションで構成され、esse-senseに関連しつつ、異なる立場の10名の登壇者にお越しいただきました。
当日のスピード感あるパネルセッションと魅力的なプレゼンテーションのレポートを動画アーカイブとともにお届けします。
開催概要
■日時 2021年10月30日(土)13:30-17:30(13:15開場)
■場所 オンライン
■セッション1登壇者
・Forbes JAPAN Web編集長 谷本有香さん
・エール株式会社 取締役 篠田真貴子さん
・JT 取締役副会長 岩井睦雄さん
・慶應義塾大学大学院 SDM研究科 教授 白坂成功さん
■セッション2登壇者
・東京工業大学 地球生命研究所 教授 中村龍平さん
・東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構 特任助教 大黒達也さん
■セッション3登壇者
・大阪大学 高等共創研究院 准教授 丸山美帆子さん
・株式会社ALE 代表取締役社長 / CEO 岡島礼奈さん
・京都大学総合博物館 准教授 塩瀬隆之さん
・北海道大学大学院理学研究院 講師 渡邉剛さん
■進行 / 全体コーディネート
株式会社エッセンス 代表取締役 西村勇哉
セッション1:「Future in esse-sense -なぜ今esse-senseなのかへの多角的視点-」
■ゲストのご紹介
◯谷本 有香さん / Forbes JAPAN Web編集長
証券会社、Bloomberg TVで金融経済アンカーを務めた後、2004年に米国でMBAを取得。その後、日経CNBCキャスター、同社初の女性コメンテーターとして従事。3000人を超える世界のVIPにインタビューした実績があり、国内においては多数の報道番組に出演。現在、経済系シンポジウムのモデレーター、政府系スタートアップコンテストやオープンイノベーション大賞の審査員、企業役員・アドバイザーとしても活動。2016年2月より『フォーブスジャパン』に参画。2020年6月1日より現職。「アクティブリスニング なぜかうまくいく人の「聞く」技術」(ダイヤモンド社)、「世界のトップリーダーに学ぶ一流の『偏愛』力」(ディスカヴァー・トゥエンティワン)などの著書がある。ロイヤルハウジンググループ株式会社上席執行役員、株式会社ワープスペース顧問
関連記事 :
◯篠田真貴子さん / エール株式会社 取締役
慶應義塾大学経済学部卒、米ペンシルバニア大ウォートン校MBA、ジョンズ・ホプキンス大国際関係論修士。日本長期信用銀行、マッキンゼー、ノバルティス、ネスレを経て、2008年10月にほぼ日(旧・東京糸井重里事務所)に入社。同年 12 月から 2018 年 11 月まで同社取締役CFO。1年間のジョブレス期間を経てエール株式会社の取締役に就任。社外人材によるオンライン 1on 1を通じて、組織改革を進める企業を支援。「聴き合う組織」が増えること、「聴くこと」によって一人ひとりがより自分らしくあれる社会に近づくことを目指して経営にあたっている。
「LISTEN――知性豊かで創造力がある人になれる」(日経BP)、「ALLIANCE アライアンス —— 人と企業が信頼で結ばれる新しい雇用」監訳。
関連記事:
◯岩井睦雄さん / JT 取締役副会長
1983年日本専売公社(現日本たばこ産業)入社。経営企画部、2003年経営企画部長、2005年執行役員食品事業部長を経て、2006年取締役食品事業本部長。JT International S. A. Executive Vice Presidentを 経て、2013年専務執行役員企画責任者、2016年専務執行役員たばこ事業本部長、2016年代表取締役副社長たばこ事業本部長、2020年3月より現職。株式会社ベネッセホールディング社外取締役、日本アスペン研究所 理事、日本経済同友会 幹事 アフリカ開発支援戦略PT委員長
◯白坂成功さん / 慶應義塾大学大学院 SDM研究科 教授
1994年東京大学大学院修士課程修了、2012年慶應義塾大学後期博士課程修了。博士(システムエンジニアリング学)。大学院修了後、三菱電機にて、「こうのとり」、「みちびき」などの開発に参画。専門分野は、システムアーキテクチャ、大規模複雑・高信頼性システム構築方法論、イノベーション創出方法論。2010 年より慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科准教授。2017年より同教授。2015年12月より2019年3月まで内閣府革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)プログラムマネージャ。株式会社Synspective取締役/創業者
◆セッションハイライト
セッション1は、esse-senseの構想段階からいろいろと相談にのってくれた4名の方とのパネルセッション。「Future in esse-sense -なぜ今esse-senseなのかへの多角的視点-」をテーマに、なぜ今このメディアが必要なのか、バックグラウンドの異なる方々で紐解いていきました。

谷本さん:これまでのような資本主義的な評価軸ではなく、わくわくするような共同幻想をつくっていくのがこれからのメディアとして大事です。真実性とわくわく性を担保できるのは、esse-senseのようなサイエンスをテーマにしたメディアだと思います。
篠田さん:esse-senseの記事は、研究の話をしているというより、その人の話をしている、という設計になっていますよね。だから、同じ記事を読んでも自分と違う感じ方をしている人がいるということになる。バライティ豊かなテーマがフラットに並んでいて、一人ひとりに読み方を委ねられているところが読み手にとって心地よいメディアになっていると感じます。
岩井さん:記事を読むことで、自分自身を振り返えることができるし、走っている方向が違う人とつながりができるという期待感があります。ただ、単純に知識をダウンロードするわけではない、なにか考えさせられるメディアですね。元々「Education」という言葉は、「その人の中から引き出す」という意味ですが、esse-senseはまさにそれができるのではないでしょうか。
白坂さん:イノベーションの観点から見たときのesse-senseの価値は、ある目的を達成するための手段の選択肢が広がることだと思います。課題が複雑化している社会だから、アイデアを実装していこうとすると必ず他の分野とも絡んでいきます。ただ、専門以外の分野について応用しようと思うと、いったん抽象化して考えることが必要なんです。esse-senseは専門家以外の人がインタビュアーのインタビュー記事なので抽象化しやすい。そこが良さ。
多角的視点でesse-senseの面白さと可能性についてパネルディスカッションが展開されたセッション1。記事を読んで触発された読者の方が、実際に行動する、行動を変えるようなメディアを目指していきたいという話でクローズしました。
セッション2「essence of esse-sense -その中心軸にある価値-」
セッション2はお二人の研究者のプレゼンテーションとQ&Aの形式で実施しました。
■2-1:登壇者のご紹介
◯大黒達也さん / 東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構 特任助教
音楽や言語がどのように学習されるのかについて、 神経科学と計算論的手法を用いて、領域横断的に研究している。また、神経生理データから脳の「創造性」をモデル化し、創造性の起源とその発達的過 程を探る。さらに、それを基に新たな音楽理論を 構築し、現代音楽の制作にも取り組んでいる。オッ クスフォード大学、マックスプランク研究所(ドイツ)、ケンブリッジ大学等を経て2020年4月より現職 。
セッション2-1は、「脳とAIの創造性と音楽~未来音楽の生成に向けて~」について大黒さんにプレゼンテーションしていただきました。時代毎に音楽をモデル化して未来の音楽をつくることを目指されています。

大黒さんは研究する意義を次のように語ってくださいました。
大黒さん:音楽は脳がつくっているので脳の研究を始めました。役に立つのかと聞かれると耳が痛いです。でも、人類の進化全体を見た時に研究のリターンはお金だけなのでしょうか。それはあまり興味はありません。究極の目標としては、我々が予測もできない音楽を創ることです。将来的にホールで未来の音楽を演奏したいと思います。
私たちも大黒さんが導き出した未来の音楽を少し聞くことができました。なぜか懐かしい、でも新しい調べに心が満たされたセッションでした。
■2-2:登壇者のご紹介
◯中村龍平さん / 東京工業大学 地球生命研究所 教授
東京工業大学 地球生命研究所 教授 理化学研究所 環境資源科学研究センター チームリーダー 1976年北海道生まれ。2000年東京理科大学卒業、2002年北海道大学修士課程修了、2005年大阪大学博士後期課程修了。ローレンス・バークレー国立研究所(Lawrence Berkeley National Laboratory)博士研究員、東京大学大学院工学系研究科 助教を経て現職。2016年、「深海生命圏を支える生体電子移動論の開拓に関する研究」が科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞。
関連記事:
セッション2-2のプレゼンターは、深海底に眠るエネルギーについて研究されている中村さんです。中村さんは科学者という仕事について、「謎を解き、新たな疑問を作り出す仕事」と語ります。
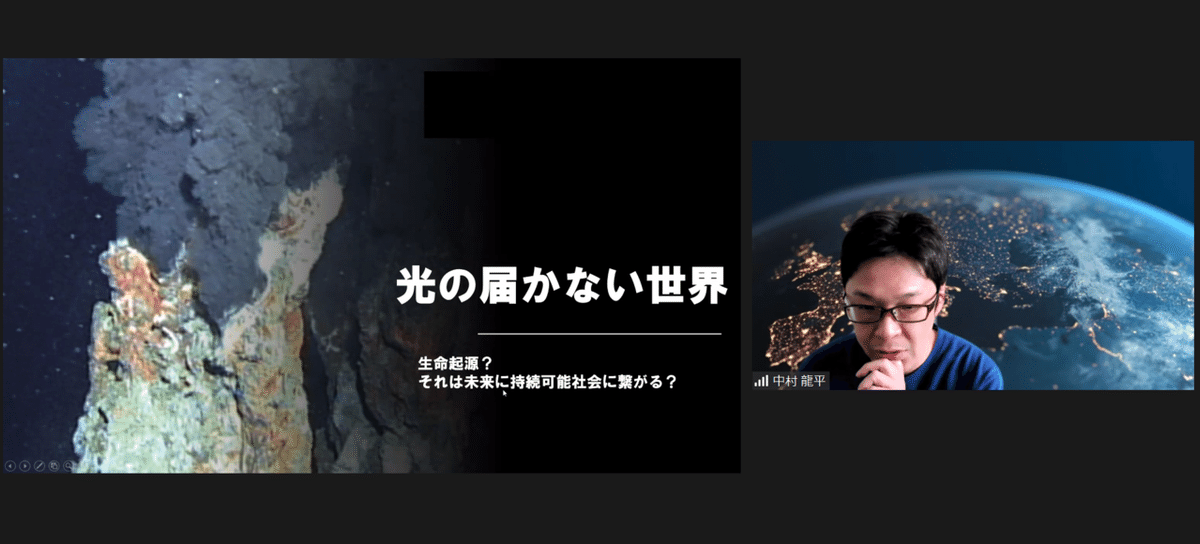
中村さん:社会で人々が電気を使って生活をしているように、海底では電気を使って生きている生物がいます。海底発電が見つかったのは10年前ですが、実は40億年も前からありました。もしかしたら、種の誕生にも電気が関わっているのではという仮説があるんです。あのダーウィンも生物がどうやって生まれたかについては答えられていません。生命と非生命の繋がりはどこにあるのか。全く異なるものから共通点を見つけるというのが私が考える科学の面白さです。
中村さんはesse-senseの記事の中で地球を「巨大電池」と例えられていました。もしその電力が活用できたなら、私たちが抱えるエネルギー問題を解決につながるかもしれませんね。参加者からも生命と非生命の境界線についてたくさん質問が出たセッションとなりました。
セッション3「Future in esse-sense 2 -領域を超えた交流が生み出す価値- 」
■ゲストのご紹介
◯丸山美帆子さん / 大阪大学 高等共創研究院 准教授
栃木県出身。東北大学院理学研究科 地学専攻博士課程修了。東北大学 大学院理学研究科 日本学術振興会特別研究員、大阪大学工学研究科 特任研究員・特任助教、北海道大学 低温科学研究所研究員、大阪大学レーザー科学研究所 特任研究員、日本学術振興会特別研究員、京都府立大学生命科学研究科 特任講師を経て2020年4月から現職。専門は結晶成長学。
バイオミネラル、タンパク質の結晶化、医薬品化合物の結晶化技術開発など様々な物質を対象に分野横断的な研究を行い、近年は、「隕石と尿路結石は似ている」という着眼から尿路結石症の新予防法・治療法開発を目指すMETEOR PROJECTを立ち上げる。大阪サクヤヒメ表彰の人脈を活かした女性の異業種交流も推進。科学者そして母として、ライフイベントと研究のインテグレートを目指し“ママ研究者”の目線でSNSを活用した発信も着手。女性躍進、科学啓蒙活動も精力的に行っている。
関連記事:
◯岡島礼奈さん / 株式会社ALE 代表取締役社長 / CEO
鳥取県出身。東京大学大学院理学系研究科天文学専攻にて博士号(理学)を取得。卒業後、ゴールドマン・サックス証券へ入社。2009年から人工流れ星の研究をスタートさせ、2011年9月に株式会社ALEを設立。現在、代表取締役社長/ CEO。「科学を社会につなぎ 宇宙を文化圏にする」を会社のMissionに掲げる。宇宙エンターテインメント事業と中層大気データ活用を通じ、科学と人類の持続的発展への貢献を目指す。
関連記事:
◯塩瀬隆之さん / 京都大学総合博物館 准教授
1973年生まれ。京都大学工学部卒業、同大学院工学研究科修了。博士(工学)。専門はシステム工学。2012年7月より経済産業省産業技術政策課にて技術戦略担当の課長補佐に従事。2014年7月より復職。小中高校におけるキャリア教育、企業におけるイノベーター育成研修など、ワークショップ多数。平成29年度文部科学大臣賞(科学技術分野の理解増進)受賞。著書に『問いのデザイン 創造的対話のファシリテーション』、『インクルーシブデザイン:社会の課題を解決する参加型デザイン』(いずれも共著、学芸出版社)など。
関連記事:
◯渡邉剛さん / 北海道大学大学院理学研究院 講師
横浜市生まれ。1994年、北海道大学理学部地質学鉱物学科卒業。同大学大学院地球環境科学院修士・博士課程終了後、サンゴ礁に記録される地球環境変動をテーマに、オーストラリア国立大学、フランス国立気候環境研究所、ドイツ・アーヘン工科大学地質研究所、ハワイ大学などで研究に従事。2014年より鹿児島県喜界島にNPO法人喜界島サンゴ礁科学研究所を立ち上げ、理事長に就任。
関連記事:
◆セッションハイライト

セッション3は、「Future in esse-sense 2 -領域を超えた交流が生み出す価値- 」をテーマに、全く異なる専門分野の方々で、議論が展開されました。
バックグラウンドが専門で「結晶成長」という分野で博士号を取得し、今は隕石を調査する方法を応用して尿路結石について研究をおこなっている丸山さん。
科学を社会に繋ぎ宇宙を文化にする、というミッションを掲げている「エール」というスタートアップの創業者岡島さん。
コミュニケーションをどうデザインしていくかを追究し、京都大学総合博物館で、研究を伝えていく活動をしている塩瀬さん。
北海道大学の理学部でサンゴ礁を研究しながら、地域でさまざまな人と融合するために演劇をつくっている渡邊さん。
自己紹介を聞いただけだと、今後の話の流れはどうなっていくのだろうと疑問に思われるかもしれませんが、お互いの専門性と相手の領域との共通点を見つけ出し、流れるように展開されたパネルディスカッションでした。
まずは丸山先生の尿路結石と隕石がどう繋がっているかのお話。そこから分野を超える意味についてお聞きしました。
西村:分野を超える意味って何でしょうか。尿路結石の研究に隕石の考え方を持ってきたことで見方が変わったことありますか。
丸山さん:今まで交わることのなかった臨床医者と鉱物学者、研磨技術者が同じ場所で議論するようになりました。全然違う視点でものを見るので、新しい発想が出てきます。
以前は、患者の体から尿路結石を出すためにとにかく石を割って体内から取り出すことに主眼が置かれていました。でも今は尿路結石から患者さんの体内のイベント記録を分析するために、どういう割り方をすると一番効率がいいのかという議論をしています。最終的には患者さんに還元されます。とにかく面白いです。
そこから隕石といえば、人口流れ星をつくっている岡島さんですよね。と繋がっていきました。岡島さんは流れ星をつくっている理由の一つに「サイエンスコミュニケーション」があるといいます。
西村:なぜ、人口流れ星を流すことがサイエンスコミュニケーションなんですか。
岡島さん:出前授業だと興味をもってくれない層がいるので、一般の人に受け入れやすいエンターテイメントとしてやっています。200キロ圏内で肉眼で見られるので、多くの人になぜ人口流れ星ができるのだろうと思ってほしいんです。もしかしたらがっかりする人がいるかもしれないが、できる過程に興味を持ってくれる人が出てきてくれたら嬉しいですね。
異分野が交わるにはまず「知ること」が大切だということがこのお話からも分かります。塩瀬さんからも異分野融合の設計についての言及がありました。
塩瀬さん:人は専門家になればなるほど、難しいことを理解するほど伝えることが難しくなります。専門用語が前に出てしまうんです。博物館の役割は言葉の粒度を揃えて伝わりやすくすることだと思っています。例えば、以前X線の企画展をおこなったのですが、自分もよく分からなかったので、タイトル自体を『X線ってなんだろう?』にしました。同じX線だけど研究者が見ているスケールを翻訳装置として博物館展示をしたんです。共通言語をつくると融合しやすくなります。
演劇も解像度を揃える手段ですね、とバトンは渡邊さんに。領域を超えるという観点から、研究者であるご自身が演劇をつくられている背景を伺いました。
渡邊さん:私がいる喜界島には研究者だけでなく、アーティストの方もいるので表現するのが上手なんです。演劇は人と人を繋いでくれます。可能性を感じたのは、フィクションの世界をつくる力です。未来のことはまだ誰も知らないのでフィクションですよね。でもそこから学べることは多いと思いました。また、研究の発信について論文だけに頼ると地域に残していくことは難しい。子どもたちと一緒にやることでそれも可能になります。演劇を通じて色々な研究者と本当の意味での融合ができると感じました。
研究者同士の議論の融合がまさにおこっているのをリアルに見聞きすることができたセッションでした。
クロージング
イベントの最後には、esse-senseの役員紹介をおこない、それぞれからコメントをもらってクローズしました。
役員一覧
・西村勇哉 / 代表取締役(NPO法人ミラツク代表理事)
・井上有紀 / 取締役(非常勤)(一般社団法人イノラボ・インターナショナル 共同代表)
・白石智哉 / 取締役(非常勤)(ソーシャル・インベストメント・パートナーズ 理事)
・田崎有城 / 取締役(非常勤)(KANDO Founder&CEO、リアルテックホールディングス株式会社 エンビジョンマネージャー)
・篠田真貴子 /創業メンバー(エール株式会社 取締役)
・大関真之 / 技術顧問(東北大学大学院情報科学研究科情報基礎科学専攻・教授、株式会社シグマアイ代表取締役CEO)
・依田真美 / 社外監査役(相模女子大学 学芸学部/大学院社会起業研究科 准教授)
・樋口哲朗 / 社外監査役(公認会計士 /樋口公認会計士事務所所長)
今後のセッションのご案内
セッションのご案内は、esse-senseのWEBサイトでユーザー登録いただくと届くニュースレターにてお知らせしています。
esse-senseでは、今後も記事と連動した研究者をお招きするセッションを開催していきます。登録は、下記WEBサイトから右上の「ログイン」ボタンよりご記載ください。
これからも進化し続けるesse-senseをお楽しみください!
──────────────────────────────────
「未来は、知識と精神の出会いによって生まれる」
esse-sense.com
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
