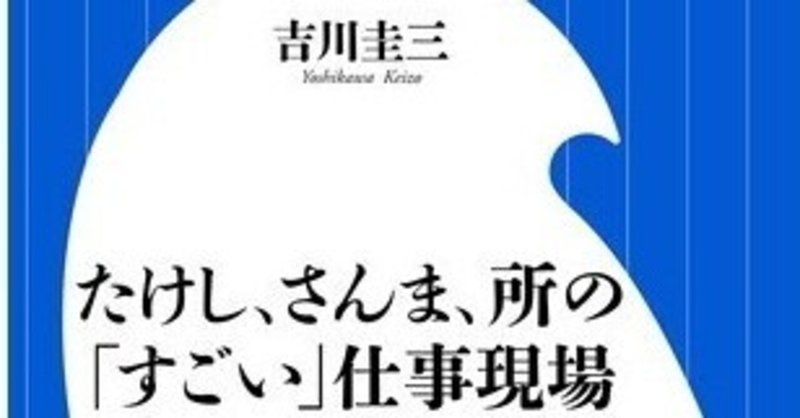
「たけし、さんま、所の『すごい』仕事現場」吉川圭三
「平成の茶の間の時間を作り続けた男」
「平成の茶の間の時間を作り続けた男」、と呼んでも過言ではない。それがこの本の著者、吉川圭三さんである。その代表作を見れば「世界まる見え!テレビ特捜部」「特命リサーチ200X」「恋のから騒ぎ」「踊る!さんま御殿」「笑って!コラえて!」とテレビ界における王者・日本テレビの立役者の一人とも言えるだろう。
その吉川さんは現在、ドワンゴにおいてエグゼクティブプロデューサーを務めていると聞く。この事実は、テレビ業界を知り尽くしながら、現在の趨勢であるネットから発信するコンテンツ事情にも精通していることを意味する。それだけに、吉川さんの語る言葉には重みがあり、説得力が桁違いにあると言っていいだろう。
私自身、吉川さんの下で直接、仕事をする機会には恵まれなかったが、作家の師匠であり、本書にも「お笑いウルトラクイズ」の発案者として登場するそーたにさんからはこう言われていた。「島津!まる見えのナレーションはすごいからな、盗んでおけよ!」と。当時、「出動!ミニスカポリス」でデビューしたばかりの私は、テリー伊藤さんが代表を務める制作会社ロコモーションで、駆け出しの放送作家として動いていた。伊藤さんが作るある種のハチャメチャな番組とは違う、吉川さんの番組は大きな刺激だった。当時の私はそーたにさんの書いたナレーション原稿を日本テレビにFAXしていたが、やはり見るだけではダメだと思い、時間を作っては、「まる見え」のVTRの文字起こしを何度も繰り返していた。そこで見えてきたのは、VTR構成の仕方や絶妙なナレーションであった。
短いセンテンスでまとめられ、文章にはリズムがあった。そして形容詞、副詞の使い方が秀逸だった。また、結論をスパっと言いながら細部を語るやり口など、私の文章に大いなる影響を与えた。と書いている文章がまさに体現しているであろう。ではそんな影響を受けた文体で吉川さんの本の魅力を「まる見え風」に書くとこうなる。
「狂気」を大事にする男
「元日本テレビプロデューサー、吉川圭三。
この男、只者ではない。
彼が作りだす番組は軒並みヒットするばかりではなく、かつ長寿番組になっているのだ。驚くべきは『世界まる見え!テレビ特捜部』『笑って!コラえて』など、吉川が日本テレビを離れた令和の時代になっても今尚、そのDNAは残り、影響力を与えている。
その番組をじっくり見てみれば、
『時に知性が溢れ、時に衝撃的映像が盛り込まれている。』と言えるだろう。
テレビ界に革命を起こした「元気が出るテレビ」の後の「特命!リサーチ200X」では、大胆にも日曜日の夜8時にあえて「笑い」を捨てた。当時の日本のテレビでは見たこともない、謎をひも解き、かつバラエティーだった。導入部を架空のリサーチ会社という設定を持ち込みドラマ仕立てにした。キャスティングには佐野史郎、稲垣吾郎、高島礼子を配置し、ストーリーテーラーとした。私に言わせれば、どう逆立ちしても発想出来ない番組を目撃し「これを作った人は天才だ!」と度肝を抜かされた。後に、フジテレビの『奇跡体験!アンビリーバボー』など多数の類似番組が生まれたが、その原点は紛れもなく「特命」だ。そんな知性溢れる番組を作り上げる吉川だが、この本を読むと、そのエンターテイメント作りの正体が見えてくる。
それは・・・「狂気」だ。
意外にも私の師匠であるテリー伊藤を絶賛している箇所が何度も出てくるのだ。しかし、よく考えてみれば、知性溢れる番組を生み出す一方で「世界の衝撃映像」「たけし・さんまの超偉人伝」なども手掛けてきた吉川にも紛れもなく、クレイジーなエンターテイメントを生み出してきたことに気付く。その吉川圭三が、『ビートたけし、明石家さんま、所ジョージ』という紛れもない天才を間近で見たことを伝えている。
本人によれば、この本は「テレビ戦記」であり、シンゴジラならぬ「シンテレビ」を生み出すヒントになればとの思いが込められている。ではそこから放送作家である島津が、読み解こうではないかーーー。」
読み手によって楽しみ方は変わる多彩な仕掛け
本書の味わい方にはいくつかある。それは読み手によって変わるとも言える。テレビマンやクリエイターにはその仕事に対する姿勢が大いなる学びとなる。また、一視聴者の立場で見れば、たけしさん、さんまさん、所さんの意外な一面を垣間見ることも出来る。もちろん、「仕事人」として参考になる部分、刺激になる部分が散りばめられている。
その中でも、学びたいポイントがいくつかあった。
まず、一つ目は「天才と仕事をする。」である。あの明石家さんまさんがたけしさんと仕事する時には緊張するという逸話や吉川さん自身が、「明石家さんま」さんと仕事するまでの経緯。どうやったら「信頼」を得ることが出来るのか?というエピソードは並々ならぬ気苦労や奮闘ぶりを窺い知れる。また、「元気が出るテレビ」においてビートたけしとテリー伊藤という二人の天才が、ぶつかり合う話は実にしびれる話だ。しかし、「俺の周りには天才なんかいないよ。」と自分にとって遠い話と思うの早計だ。大事なポイントは「あの人に恥ずかしい所は見せられない」「あの人につまらないものは出せない」というプレッシャーの中に身を持って行くことが、仕事人としての成長をもたらすことを暗に伝えてくれている。
これは私自身、痛感している。テリー伊藤さんの下で働いてきた私には何度もそんな経験がある。数年前、テレビ東京の特番で爆笑問題をMCに起用した「現状打破TV」というスペシャル番組があった。そのメイン企画となったのはiPS細胞の初の実現化で一躍、注目を浴びながらそれが嘘の情報であったために、袋叩きにあった森口尚史氏だった。伊藤さんは言った。「森口さんにさあ、iPS細胞で胸毛を生やせてもらおうぜ!どうだーーー!」とのアイディアが生まれた。森口さんが出演をしてくれるのか?どうやったら捕まるのか?胸毛を生やせてくれるのか?問題は山積みである。プロデューサーの尽力で森口さんは捕まった。食事の席に臨むのだが、いきなりの初対面で「胸毛を生やしませんか?」とも言えない。しかし、手ぶらで伊藤さんの下に帰るわけにはいかない!「何が何でも!!」である。結果として胸毛が生やす!了承を得ることは出来なかったが、森口さんがTMネットワークの「Get Wild」が好きで意外にも歌が上手い、という収穫を得た。これには伊藤さんも満足をし、最終的には木根尚登さんをゲストに招いた上で、プロデュースをするかどうか?という企画として成立した。ちなみに蛇足ではあるがこの時のVTRは放送日、前日にテレビ東京の社長の目に触れて、撃沈。OAが吹っ飛ぶという大惨事になっているのだが。。。このように踏ん張りながら代替案を探るというのも仕事人としてあり方だと常々、思うし「無理だよ」と嘆きつつ、突破口を探すのが仕事だと思う。
「狂気と公序良俗に反することが面白い」
二つ目は「狂気と公序良俗に反することが面白い」である。かつてたけしさんが、さんまさんの「レンジローバー」事件、NHKの大河ドラマ「おしん」における差別問題をオブラートに包みながら表現するという例を出しながら、本当に面白いことは何かを説いていく。今のテレビ業界、さらにはYouTubeのコンテンツにしてもどこか、半径5mの世界に留まっているのではやはり、メガヒットにはなりえないだろう。狂気という点においてはある種の予定調和をぶっ壊すという側面や現場の空気次第という側面もあるだろう。テリー伊藤さんの例で一番分かりやすいのは、40代以上の方は分かるだろうがかつて、「元気が出るテレビ」においてエンペラー吉田さんというおじいちゃんがいた。町内会に参加していた一人のおじいちゃんが、入れ歯をフガフガして怪しい動きをしていたことに目を付けた。その時、それまで考えていた台本の筋書きを捨て、吉田さんをフューチャーすることになる。その後、浪越徳次郎さんと一緒に、起震車で対面させたり、ジェットコースターに乗せたりと、今では「老人虐待」のそしりを受けるだろうが、間違いなく爆笑映像ではあった。公序良俗と言われればそれまでかもしれない。コンプライアンスの厳しい時代には許されないだろうが、時として現場を最優先して、台本をかなぐり捨てる、いわば「頭で考えたこと」より「現場の面白さ」を大事にする姿勢は持っていたいものだ。
未知の世界に挑んだ時に開ける道
三つ目は「未知の世界に挑む」ことである。吉川さんは「海外ロケで鍛えられた。」「ダーツの旅は、(企画の形が)見えなかった」という。この言葉が非常に重いし、本当に新しいことを生むにはここしかないのでは?とも思う。海外ロケにつきまとうトラブルの数々、瞬発力、ずぶとさ、対応力が否応なく試される。また、「ダーツの旅」では多くの人に反対されながらも、まずはやってみようと挑戦したことで道が開ける話は、「やはり!そうか!」と物凄い説得力がある。ややもすると、「ダーツの旅」は「村人の話って面白いよね。」と素人目線ではそう映るかもしれないが、プロは知っている。あのシーンを撮るためにどれだけの時間と人にインタビューをしたのか。時間と労力と編集技術の上に成り立っていると。今のテレビ東京の「家についていっていいですか?」も同じパターンのロケ手法であるのは言うまでもない。
やはり、歴史を学べ!
四つ目は「歴史に学べ!」ということである。クリエイター足るもの過去に学ぶことは多いことを説いている。吉川さん自身、映画の造詣が深く、また「まる見え」のような世界の番組を見続けたがゆえに圧倒的なインプット量があるだろう。そこから抽出されるアイディアも数々あったことは明白だろう。
これもまた、テリー伊藤さんの話だ。ハチャメチャな一面が強いが、企画のプレゼンの際は、過去の人の作品を引用することが多い。ある時は映画の黒澤明監督。ある時は、西武の堤義明さん。また、ある時はクリント・イーストウッドだったりする。確か、2000年に巨人が優勝した時のことである。突然、テリー伊藤さんは言いだした。「よーし、長嶋さんの家から、読売新聞まで神輿を担いでパレードするぞ!!」アイディアだけを聞くと「何のこっちゃ?」と思うかもしれない。「また、テリー伊藤が変なこと言ってるよ。」と思うかもしれない。しかし、私は知っている。このアイディアの素になっているのは、ヒトラーだ。ベルリンオリンピックの際に、聖火ランナーをアテネからベルリンまで走らせ。大々的にPRをし、成功を収めたことを。これはひとえに町の人を巻き込む演出として伊藤さんは捉えていた。(もちろん、ヒトラーの人種差別に賛同しているわけではない。)アイディアとして「聖火ランナーにおけるトーチ」のアイディアのエッセンスを抽出し「神輿」に変えながら。新たなアイディアを生み出していたのだ。(私の推測だが。)吉川さんの本を読みながら、私はそんなエピソードを思い出していた。「歴史を知ることもまた、新たなものを生むのだ。」と。
ちなみに私はテリー伊藤さんが今、「から揚げの天才」をやっているがあれはカーネルサンダースになろうとしていると勝手に睨んでいる。
吉川さんは、日本テレビの出身者であるために「シンテレビ」とは何か?「テレビ屋」の立場から次のクリエイターへのヒントとなる言葉を数々、紹介しているのだが、私自身が受け取った一番のメッセージは、「マーケティングなんかクソくらえ!」そんな認識でいる。「予定調和を崩す」「未知の世界に挑む」「歴史に学ぶ」全てはデータではない。テレビだろうがネット配信だろうが、YouTubeだろうが、共通しているのはそこじゃないのか。「今、〇〇が流行ってます!」みたいなクソみたいなプレゼンや企画には何の面白みもないと。私もこの本を読み、勉強し、まだまだ無謀でいたいと強く感じている。
皆さんもぜひ、本を読み、力をもらって欲しい。
私も世界の主婦3人と柴犬による食にまつわるトークショーをやってます!ターゲットは「食を愛する世界の人々」です。コロナ禍で生んだエンターテイメントでもあります。ぜひ、見てください。
動画制作、執筆、キャッチコピーなど、お悩みの方は気軽にどうぞ!
執筆者:島津秀泰(放送作家)
Twitter:@shimazujaoriya
Instagram:hideyasushimazu
是非、フォローをお願いします。
コメント、ツイート、シェアはぜひ!あなたの行為で生きていけます!
宜しければサポートをお願いします。あなたの応援を、私のエンジンにさせてください。
