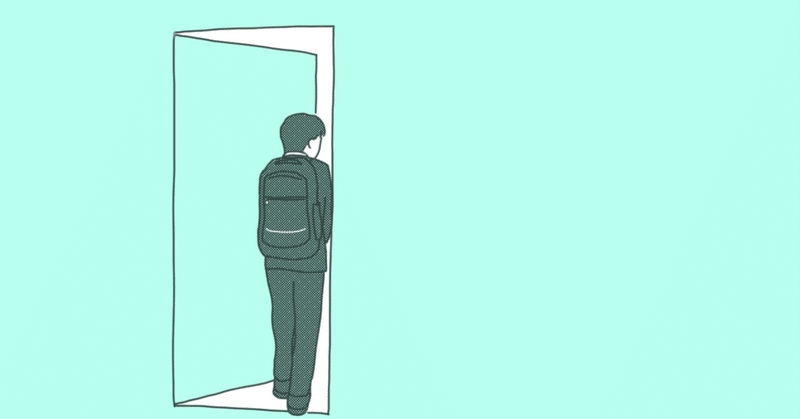
今日を生きるために、引きこもる。
職員室の机の上には、様々な回覧書類が来ます。自分に直接関わるような書類以外は流作業の確認で済ませてしまっているのが現状です。
ある日、何の資料かは記録していないのですが、
「フリースペースたまりば」理事長の西野博之さん
の言葉が私のメモには残っています。
34年間、不登校の子どもと関わってきた人間の言葉は、お役所から届いて回覧される様々な教育政策のお知らせやガイドライン、確認事項より、
すっと自分の中に入ってくる感覚がありました。
(その時の読書メモも再度まとめてみました。自分なりの解釈も踏まえて書き足しているので、その点はご了承ください。)
朝起きられない子ども。
理由は、夜遅くまでYouTubeやゲームをしていて朝起きられない。
「生活リズムを整えなさい。」
この言葉に間違いはない。しかしそんな心配もいらない様な真面目な子どもの中にも、昼夜が逆転してしまうことが起きている。
生きるために、引きこもる。
全ての学校の準備も整えた。
「よし。」
あとは玄関を出るだけ。
「あれ・・・。」
(足が鉛のように動かない。)
「・・・。」
「どうして私はみんなと同じようにできないんだ」
「・・・生きてる意味ないのか。」
と自分を追い詰め、追い詰め続け、心の壊れる寸前・・・まで来た時に、"朝起きられない体"を作り出してしまうようだ。
①体のせいにしてしまうことで諦めがつき、現実を受け止められる。
②そして精神的に自分自身を追い詰めるところから逃れることができる。
③結果、メンタルに大きく関わる病気の発症危機を回避している。
「生きるために、引きこもる。」
こんなメカニズムがあるのでは、と思うように。
担任に出来ること
不登校に限らず、学校現場で見られる問題行動の裏には、その子自身がなんとか生きていくための必要なプロセスが、潜んでたりする。
生きるために引きこもる子どもに対して、
(本人が学校=安全とは思えない状況の中で)
「〇〇、学校に戻っておいで。」
なんて声はかけられない。
「給食だけ食べおいでよ。」
の声かけでもし学校に来れたなら、
食べたら必ず帰らせる。
「調子良さそうだから、このまま5校時行ける!」
なんて言ったら、きっと無理してしまう。
「よく頑張った。」なんて言っても
その一度の無理が、きっかけで
積み上げてたものが、崩れることも。
生きるために引きこもって人間が
一歩を踏み出した。
だから決して、無理はさせなくていい。
無理矢理5校時に出させる必要はない。
その子自身もそんなつもりはない。
生きるために引きこもる子どもには、
担任は安心できる存在になること。
安心できる居場所を作ること。
全ての行動には何かしらの理由がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
