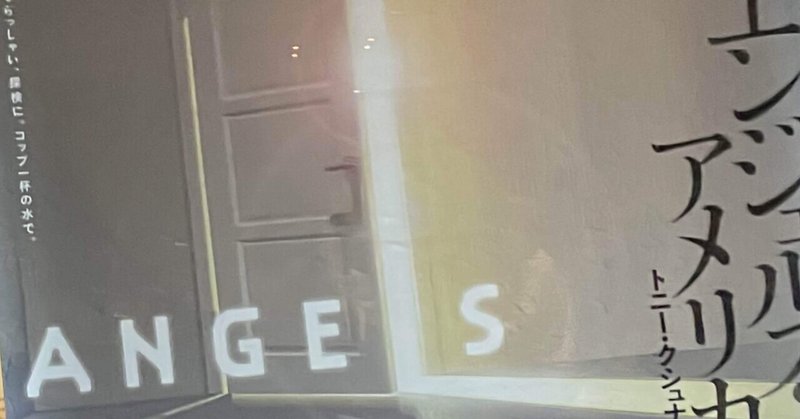
エンジェルス・イン・アメリカ 舞台感想
エンジェルスインアメリカ
5.13新国立劇場 小劇場
観劇直後に友人と話したことや帰りの電車で思ったこと等々の吐き出しです。
いいなと思った所5割、うーんと思った所5割なので批判苦手な方は注意!あとネタバレいっぱい!!
体力勝負の観劇
舞台上手よりのブロック。やや遠いので舞台前方に出てきて貰わないと役者の微細な表情は読み取れない。オペラグラスで一部補完をした。
キャパは400ちょっと。一部はほぼ満席、二部は8.9割くらい埋まってたかな。二部は前の座席2つが空いていたので視界が明瞭で助かった。
今回は一部二部通しだったので狂気の7時間半観劇でした。一日中演劇で幸せだった。
一部13:00~15:30 休憩2回あり。
一場:まだ元気だった。登場人物の把握に一所懸命になってたら終わった。
二場:それぞれの関係に葛藤が生まれるシーンが多かったので長く感じた。やや眠気、がんばる。
三場:天使のインパクトに爆笑した。体感時間は瞬き一回分くらい。
二部 17:30~21:30 休憩2回あり
一場:ここだけ90分あるからそろそろ終わる?あ、まだ終わらない、を繰り返してた。そっと座り直す。
二場:肩と首の凝りがやばくなる。ロビーでストレッチしている人が多くて面白かった、疲れるよね。
三場:身体は痛い、そろそろ彫刻になりそう。終わった瞬間に謎の達成感に襲われた。やったぜやりきったぜ!
ここから本編
舞台概要
<第一部>
1985年ニューヨーク。
青年ルイスは同棲中の恋人プライアーからエイズ感染を告白され、自身も感染することへの怯えからプライアーを一人残して逃げてしまう。モルモン教徒で裁判所書記官のジョーは、情緒不安定で薬物依存の妻ハーパーと暮らしている。彼は、師と仰ぐ大物弁護士のロイ・コーンから司法省への栄転を持ちかけられる。やがてハーパーは幻覚の中で夫がゲイであることを告げられ、ロイ・コーンは医者からエイズであると診断されてしまう。
職場で出会ったルイスとジョーが交流を深めていく一方で、ルイスに捨てられたプライアーは天使から自分が預言者だと告げられ......
<第二部>
ジョーの母ハンナは、幻覚症状の悪化が著しいハーパーをモルモン教ビジターセンターに招く。一方、入院を余儀なくされたロイ・コーンは、元ドラァグクイーンの看護師ベリーズと出会う。友人としてプライアーの世話をするベリーズは、「プライアーの助けが必要だ」という天使の訪れの顛末を聞かされる。そんな中、進展したかに思えたルイスとジョーの関係にも変化の兆しが見え始める。
好きな台詞
ニュアンス
「あなた分からないでしょ、私の考えてること。」
「想像してごらん!」
「赦しは最も難しい行為。」
想像と寛容の話。
宗教と性愛と倫理、どこまで寛容になれるか。寛容は不寛容に寛容になれない。
物語構成について
二部構成であるが故に、一部ごとの纏まりの良さには欠けてしまうかな。ただ一部ラストのインパクトは絶大だったので、日を空けても観に行きたくなるお客さんは多いと思う。
ラストシーンの後日談は必要だったのかという疑問。後日談があることでハッピーエンドの物語であるという印象は確固たるものになるが、登場人物にこの物語の総括を話させることで蛇足であるという感触が消えない。
シーンの変わりに暗転が多くて、ぶつ切り感が強いなと思った。演劇的なシーンの区切りというより、ドラマのワンカットを連続しているような印象を受けた。一方で、二場面を同時に演じさせることであえて声をぶつけて緊張を高めたり、ストップモーションを用いた場面の転換など演劇でしか使えない手法に挑戦しているなという印象は受けた。第四の壁を壊す取り組みが2回ほど行われていたが成功しているのか、で考えると後日談のシーンは成功していると思う。ただ、非常に雄弁に観客に語りかけるので、この物語の正解を教えられているようでうーん好みが分かれるかな、、
美術と演出について
近景、中景、遠景の使い分けによって物語の同時展開や、転換を上手く使ったなと思った。上手と下手にキービジュアルを想像させる扉があって、場面によって開いたり閉じたりしていたのでその意図が気になった。額縁のような枠が舞台の四面を囲っていた。西洋絵画のような空間が生まれ、登場人物に共感を覚えながらも、枠のせいで何処か俯瞰的な目で見つめる自分がいた。1985年を古典化させたかった?演出についても、同様の印象を受けた。裏方のスタッフが舞台上に出てきて割と堂々とセッティングをする。天使のハーネスを外すスタッフは明転中、しかも彼女が話している最中に作業を行う。この物語は作り物である、というメッセージ性を強く感じた。没入したいのに演出のせいで没入しきれない、ノイズのような感覚が私を理性を与えた。ただのエンターテインメントで消費させないぞ、考えろよ。そんなことを演劇を通して言われた気がした。
会話、または翻訳について。
前項目から続くが、会話については言葉遊びやギャグが多く、テンポの良い流れとは言えない。一方で、アメリカ精神を感じる翻訳は聞き心地が良く単純に面白い。まさに日本語吹き替えを演じている感覚。ハーパーを筆頭に各登場人物が己の考えについて激しく語るシーンがあるが、それぞれの考えに若干の共通点(想像、赦し、生きる)があるので、一つ一つのスピーチについて一度で全てを覚えるのは難しいだろうが、全体で見渡した時にふんわりとメッセージが伝わってくる、一定の効果はあったと考えられる。
観客の反応と台詞についても関わってくる。笑いが多くない?今まで観てきた中で一番客席の反応が敏感だった。今笑うシーンではないなと思う場面でさえ笑いが起きて動揺した、という友人の話に共感した。(二部一場冒頭の共産党代表スピーチのシーン。おじいさんの小刻みな揺れは面白いかもしれないが、あれは弱りきったように見える老人が、理想を語り人々を扇動することで巨大な力を持つこと、への恐ろしさを語る場面だと思った、笑えない。)というか、そもそもコメディシーンが多い。先述したように元々がテレビドラマであるせいもあるだろうが、話の流れを遮ってまで言うギャグか?という疑問がある。これは7時間半に縮めたゆえの感想である可能性が高いです。
印象に残った登場人物
天使
天井から降りてきた時のインパクトは抜群だった。舞台後方で蠢いている羽根の異生物感は畏怖さえ覚える。
だが、物語中の天使の扱い方に疑問を感じた。というのも、圧倒的な力を持つ存在として物語中で説明されながらも、何処か人間くさい動揺や面倒くさそうな動作が見られた。人間くさくしたのことで、同情を買う展開になるかと思えばそんなことはなく、天国での聖書の変換手続きは極めて事務的なものだった。(主人公は確かに一方的な主張をしていたが、天使がそのスピーチに感動した描写はなかったように感じる。)人間の挙動と結びつけることで、物語独自の異生物に親しみを湧かせようとするのは安易だし、どっちつかずに感じてモヤモヤした。
ロイ・コーン
憎みきれない悪役。悪に自覚的である悪役なので、寧ろ彼の生き方には潔さすら感じた。最期の言葉が「待って……」だったのは、何に対する待ってなのか気になった。幽霊後のジョーとの対話で、私の中で彼に対する解釈が揺らいだ。彼は擬似的な家族を望んでいる人物だと思っていた。擬似的な父親を演じ、ジョーに擬似的な息子を演じさせることで自分の「愛されない」寂しさを埋めようとしているのかと思った。ジョーがロイにカミングアウトした時、彼は酷く取り乱しそれから2人が会うことはなかった。しかし、幽霊後の再会を観ると、彼は実はジョーに性愛感情を抱いていたのではないかと思う。彼が取り乱したのは、自分の部下が自分と同じ同性愛者であり、自分の性的指向がバレることを恐れたのではなく、心の底で愛していたジョーに恋人がいたことに対し、ショックを受けたのではないか。
ジョー
無意識の悪は人を心底苛立たせる。人の話を聞け、会話を遮るな、自分の話をするな、論点をすり替えるな。コミュニケーションのできない男、キスで全部黙らせればいいと思っている。わーー嫌いだーーー!!最後の方でハーパーに平手打ちをされて心底スッキリした。その痛みを忘れないで。ジョーはルイスから置いていかれ、ロイからも置いていかれ、ハーパーからも置いていかれた。何故彼は置いていかれたのか、何故彼だけは成長できなかったのか。ジョーを赦すことは難しいかもしれない。彼が今後の人生で自分に欠けているものを見つけ、想像をすることができるようになりますように。
プライアー
全編に渡って株が上がり続けた男。役者さんの演技が良かったな。苦しみに喘ぎながらも生きたいという意思、病気に犯されてもコミカルさを失わないバランスが良かった。ただ、一幕ラストシーンの預言者として掲示を受けてからのプライアーは、物語の記号的存在に変化していったと感じる。自由になりたい、生きたい、という彼の主張は印象に残ったものの、彼自身の微細な感情の揺れであったり、人間くささが失われていった。ある意味、物語の役割からしても、人ならざる者に変化していったなと感じる。
ルイス
臆病さを尊大な物言いと上辺の知識で誤魔化しているのが、印象に残った。病床に伏せているプライアーを見捨てて別の男に即物的な愛を求めてしまったり、ジョーと付き合ったりもしたが、結局プライアーに戻ってきてしまう所に、嫌いになりきれない人情を感じた。でも倫理的に浮気はよくないと思う。イデオロギーSMゲイバーという単語が気に入ったので今後も使いたい。(どこに?)
ハーパー
想像の住民。彼女にように苦しんでいる人はこの世界にたくさんいる。「想像なしに生きていけないこの世界で、あなたといる時だけは想像しなくていいと思ってた。でも違ってた、それはそういう想像。」といったニュアンスの台詞が気に入った。結局は気の持ちよう、想像から逃れることは出来ないし、想像なしに人間と関わることは出来ないなと感じた。彼女のラストシーンが好き、飛行機に乗って、生きることをやめられない、想像をやめられない、冒険の旅に出るというのが力強くて美しい。
考えるのをやめるな、想像をやめるな。この演劇の感想、結論はまだ全然出ないけど今のところそんな気持ち。
小田島さんの訳が良かったので戯曲も読みたいな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
