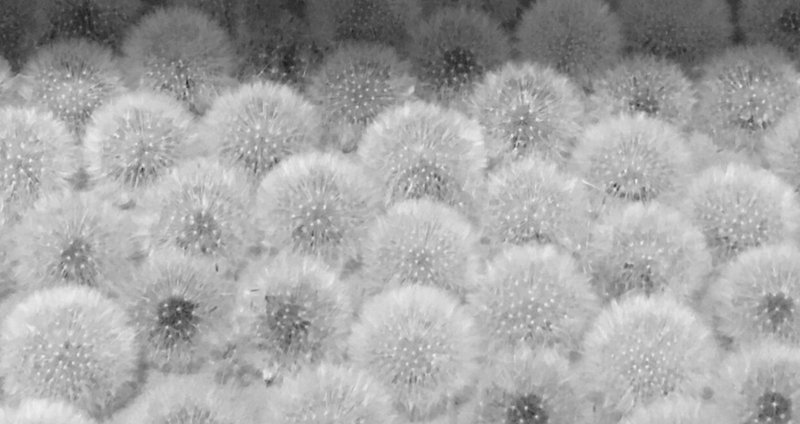#紺野登

特別オンラインセッション「イノベーション創出のカギ ダイナモ人を呼び起こせ」第2回「ダイナモを活かす経営に変わるために」紺野登 動画公開! PART2
多摩大学大学院MBA特別公開セミナーとして、第二回の特別オンラインセッションを開催致しました。 登壇者は前回(5月27日開催)に引き続き「ダイナモ人を呼び起こせ」の共著者の3人が務めました。 二回目のテーマ「ダイナモを活かす経営にかわるために」です。 紺野登教授による『知識創造のプリンシプル』についてのオープニングトークをお聴きください。 いまや、どこの企業/組織もイノベーションの重要性を認識し、若手主体の新規事業開発プログラム、場づくりに取り組んでいます。しかし、古い経営システムのうえに無理に接ぎ木をしているような状況です。 ※「企業変革をリードする新世代リーダー ダイナモ人を呼び起こせ」(2021)日経BP社 https://www.amazon.co.jp/dp/4296109065/ ※多摩大学大学院MBA特別公開セミナー〔第二回 開催:2021年6月28日より〕

【京都流議定書】Day2Program3:知識資本
第13回 京都流議定書 2020年9月9日(水) 一日だけの経営大学院 全体コーディネーター:桜井肖典氏(一般社団法人リリース 共同代表) プログラム3 知識資本 ▶︎紺野登氏(多摩大学大学院 教授)[事前収録] 人類はどのように共存していくのか? ニューノーマルという言葉が出てくるなど今目まぐるしく変化している時代に、私たちはどのようにその変化に向き合って共に生きていくかを考える2日間です。 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、オンライン開催することとなりました。 イベントの実現に向け、衛生面での対策準備等を進めておりましたが、参加者、関係者のみなさまの健康や安全面などを第一に考え、本方針を決定しました。 ●京都流議定書とは 数値化されない価値の重要性を唱えて、京都から日本全国、そして世界をじっくり考える2日間。 目的は日本の縮図ともいえる京都を研究し、その資産を分析し、強みを再認識すること。 偶発的な出会いから生まれる価値、内省と対話で考える組織にしませんか。 https://kyotostyle.jp/kyotoryu/ https://www.facebook.com/kyotostyle.jp

【DX時代のデザイン経営とは?】テクノロジーとデザインの関係性を解説!
【Schoo / できる!デザイン経営塾】 第9回:「DX時代のデザイン経営とは?」 ゲスト:紺野 登氏(多摩大学大学院 経営情報学研究科 教授) 大人たちがずっと学び続ける生放送学習コミュニティ「Schoo(スクー)」と「エイトブランディングデザイン」の共同企画のオンラインセミナー「できる!デザイン経営塾」その第9回目の授業を公開!※2020年10月28日放送分 【第9回 授業内容】 ゲストは、多摩大学大学院 経営情報学研究科 教授の紺野登さん。なぜ ”形をつくるデザイン” が100年かけて ”デザイン思考” に変化したのか、人や企業はどう対応しデザイン思考を取り入れていくべきなのか、などデザインの歴史を振り返りながらテクノロジーとデザインの関係性についてお話いただきます。 できる!デザイン経営塾とは: 最近流行りの「デザイン経営」や「デザイン思考」。近年、ビジネスキーワードに「デザイン」がよく登場しますが、何からはじめたら良いか分からない、勉強のしかたが分からない。そんな悩みをお持ちのビジネスパーソンやデザイナーにオススメ。 ブランディングデザインの第一人者、エイトブランディングデザイン代表 西澤明洋による経営に効くデザインの実践方法を、レクチャーします。 Schoo webサイト : https://schoo.jp/