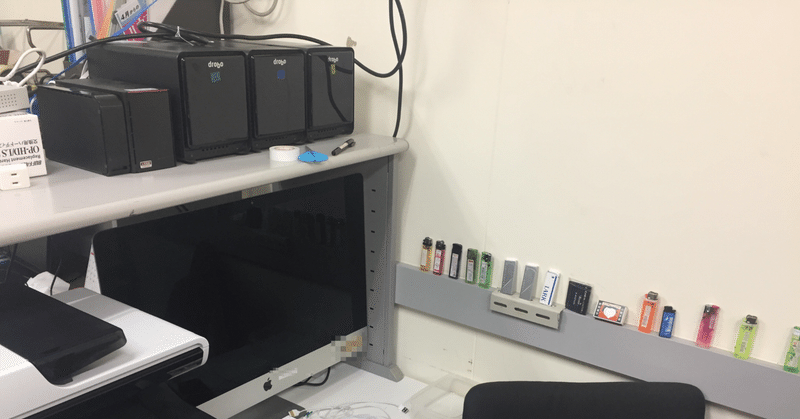
大学院失敗記録
大学院を除籍になったことを思い出が鮮明なうちにちょっとずつ整理しておきます。
なんだかとても長い夢を見ていたような気分だ。
大学院に通ってよかったこと
多少なりとも研究調査の遂行能力を身につけ、論文や文献を探る習慣を得て、アカデミックな空気に触れられたことは間違いなくプラスです。
自分の研究テーマが生き物の行動ログの取得システムの構築と数理的な解析手法の提案と確立に関わるものであったため、Linuxを始め、webに関するプログラミングの技術の習得を実践的に行えたのは良かったです。
また、Webプログラミングの技術は自分の世界を広げてくれて、学生のうちにこれに出会えたことはとても幸運だったんじゃないかなと思います。
困ったこと
大学院を辞めた大きな理由としては金銭的な不安定さがあります。
日本学生支援機構の奨学金は、コレのおかげで大学や大学院に通えている人が多くいるであろう一方で、実質は無金利(あるいは低金利)のローンであることが揶揄されます。
給付型の奨学金もたびたび募集があるのですが、出身地や将来の就業地が限定されていたり、工学部の情報系や機械・電気系じゃないと申し込めなかったり...
と辛い限定要因が多く、また、募集はあっても狭き門であり、私が大学〜大学院の間、申し込もうと奨学金の窓口に行っても、「実際に申し込んで通ったケースはほぼないので...」と門前払いを食らったり、と特に私学では全く充実しているとは言い難いです。
それに加えて私の場合はそもそも学費を滞納しがちだったことに加えて洪水で祖父母の家が流されてしまうというアクシデントがあって金銭的な圧迫が大きくなったりしたのもあり、リカバリーが効きにくかったのも追い打ちでした。(同居の家族ではなかったので学内外の災害見舞金の対象にならなかった)
もう一つは研究内容や研究室とのマッチングミスというのもあります。
私が所属していたのは研究室は主に生き物の神経や電気生理的な活性の探求を大きなテーマとしたラボでしたが、コンピュータに関する技術習得や技術に関するキャッチアップを優先せざるを得ず、自身の行動生態への興味関心、知識の不足がいろんな問題の引き金になっていたように感じます。
自身の整理も兼ねて時系列で振り返ってみると、
■1年目春〜夏
ボスの昇進に伴い研究室が移動となり、実験室レベルで装置の再組み立てや後輩への指導、先生方の方針の間で板挟みになるストレスで6月にはもう辞めようという気分になっていました。このときは大学が用意している心理カウンセラーの先生に予約をとって相談していたのですが、毎回「辞めよう!」という決心を固めるものの、なかなか行動に移すことができずにズルズルと2年も過ごしてしまいました。
もちろん、私が所属していたラボの先生方に限らず、学部生への指導は教員の役目であることは先生方も認識されていますが、現実的に自分が指導しないと研究が前に進まない、という場面もままあることなんじゃないでしょうか。
ちなみに身近な家族にも相談しましたが、「なぜ初志貫徹できないのか」といった話で感情論で責められ相談にはならず、他人に相談すること自体が間違っていたんだな、ということになかなか気づけませんでした。
不謹慎な話題ではありますが、もういっそ研究棟に火を着けようかと毎日悩んでいたところ、アニメーションスタジオが放火され死傷者がでるという大きなニュースが報道され、思いとどまったのを記憶しています。

■1年目秋〜冬
この頃は前年度に共同研究案件としてデザインした実験のデータ分析を行っていたのですが、ようやくデータの解析が終わりかけてきたところで、そもそもデータ量が不足していることと、実験デザインに不備があることをみつけ、これをどう報告したものかと延々と悩んでいたと思います。(今思えば報連相が適切にできる心理的安全性がラボに存在していなかったし、そもそも実験デザインをした先生が大御所だったのもあって「できない」と言いにくかった。)
先生としては鼓舞するために叱咤されていたのでしょうが、進捗の報告のときに、「学年がひとつ下の卒論生はうまく実験できているのになぜ君(たち)はできないんだ」と呆れられ本質的な議論ができなかったことが印象に残っています。
この件に関してはWeb系の企業が就活シーズンに入り情報が多く降りてくるようになったことをきっかけに、なにも研究にこだわる必要はなくて辞めて既卒で就活する選択肢もあるんだと気が付き、
「かくかくしかじかでもう無理」
とメールを出してラボに行かなくなったところ研究方針の変更提案がされ、卒論の内容の拡張にテーマ変更をしました。
本来ならば自分の方からテーマ変更を申し出るのが良かったのでしょうが、追い詰められてそのことを考えられなかったのだと思います。
研究テーマの変更というか揺り戻しを行ってからは参考研究の掘り出しなどが思いの外うまくいき次年度のデータの取得などの計画を練り始めました。
プレスリリースされた研究がとても面白かったので詳細を伺ったところ、その研究者の先生がAuther版のコピーを送ってくださったりして更に研究が加速し、このころが一番研究がノッていたのではと思います。(朝8時から夜10時で毎日いても苦じゃなかった)
■2年目春〜夏
1年目があまりにもゴタゴタしすぎていてほぼ学会や論文誌への投稿がこなせなかったので挽回しようと発表の計画を練っていました。
立て続けに学会発表を企画していたのでよく時間を作って指導を受けていた時期ではあるのですが、今思えば内容に関するツッコミはほとんどなくパワポをいかに作るかに心血を注がざるを得なくなっていたように思います。
もちろん、主張を聞き手に理解してもらうためにデータをいかに綺麗に見せるか、ということに重要性は理解しているつもりなのですが、それは本質ではないわけです。
毎度「パワポ職人になりに大学院に来たわけでは...」と暗い気持ちになっていました。
もちろん生物学的な面白さがどういうところにあるのか、というのをいかにまとめるかといった指導はしてもらえたのですが、なかなかクリティカルな指摘をもらうことは少なかったです。
学会の準備や発表の際に毎回思っていたのですが、指導教官の先生の専門とする領域から、数理・コンピュータに関する領域へと内容がどんどんはなれていってしまい、適切なフィードバックを受けにくくなっていたのを感じました。
研究グループに共同研究者として情報工学の先生も関わっておられましたが、毎日疑問を訊ねるわけにも行かず、自身の目指す方向性があっているのかを確かめる術がありませんでした。そのうえで、所属している研究科的に、理学的な観点を以って研究をまとめなければならず、研究内容の面白さを評価してもらえなかったように思います。
さらに、予定していた学会は新型コロナウイルスの影響で中止や出展見込み処置となり、誘ってもらった外部の研究グループでの共同研究などにも精を出していたところで続けざまに出鼻をくじかれた感じでした。
加えて指導教官ともトラブルがあり、再びしばらく大学に行かなくなりました。(コロナ対応で大学が閉鎖されたりしたせいで有耶無耶になったが...)
上半期はコロナ対応で学部生の講義もほぼ行えない中でTAとして講義支援のシステムを作ったり、実験動画の撮影を行ったり、リモートでも後輩たちが研究室のデータが使えるようにインフラを整えたりしつつ、自身のデータ解析を回していました。
書けるうちに修論を仕上げようと意気込んでデータのまとめを行い始めましたが、祖父母宅が洪水によって流されて以降は一月ほど大学から離れざるを得なくなりました。
なんとか修了単位に含まれる中間発表を終え、専攻内の他の先生からの指摘や質問などを整理して研究を前に進ませはじめたのですが...
■2年目秋〜冬
元から指導教官の先生は文面では明らかにハラスメントレベルのチャットやメールを投下してくる傾向にありましたが、自分たちの学年の修了が目前に迫る中でその苛烈さが増し、とうとう僕は最寄り駅の改札前で悲鳴を上げてうずくまってしまいました。
それ以降はメールなどが見れなくなってしまって「もう今年度は修論は書けません」と先生にお伝えするのが精一杯でした。
SNSなどで得たエンジニアの知り合い各位が、気分転換にとたびたび外に連れ出してくれてとてもありがたかったのですが、結局春が終わるまで大学に顔を出すことができませんでした。
学生支援機構の推薦枠では減免が貰えたりするんですが、かなり研究成果を挙げなくてはいけなくて、それを無理に狙おうとしたくない、と先生に伝えるべきだったとも思います。
熱心な先生ですのでそこまで狙っていろいろ指導してくれましたが、そこまでの熱い気持ちについていけず、なんというかもっと無理なく興味を深堀りできる環境を選ぶべきだったのでしょう。
指導教官の先生始め、大学院の先生方は基本的には学生思いで、特に自分の先生は平常時は学生とも密にコミュニケーションを取っておられ、イノベーションに対してのキャッチアップが上手で、学生の身分からみても研究者としての能力がかなり高いことを伺えました。
それでも自分のようにラボに馴染めない学生もでてしまうのはある種、内包されうる事故であるのかもしれません。
(当事者としてはたまったもんじゃないけど)
大学院生活を振り返って、なんだかずっと細い細い道をたどっていて、転ぶべくして道踏み外したような感じですね。
他の院生がみている景色はどんな景色だったんだろうか、というのは今でも気にまります。
僕の肩には学部生の頃から蓄積した500万前後の無利子の借金だけが残ってしまった...(というと悲観的ですのでやはり身についた手札は認識していくべきでもあると思います。)
出来の悪い院生であったため、双方のリソースを無駄に消費してしまったという罪悪感と、半ばわかっている地雷を踏み抜いてしまったことでもっとベターな選択肢を選べたのではないかという後悔はありますが、まあ今後の人生はオマケだと思ってのんびり自身の興味を探求できればと思います。
とりあえず定職が見つかれば嬉しいです。
追記 :
自分の所属のラボにはDの先輩や大学院の先輩がいて、色々アドバイスを貰える機会に恵まれている方でしたが、そもそもの院生の絶対数が専攻全体でも10人にも満たず、院生同士の活発なディスカッションなどが計れる環境ではありませんでした。それはまあ仕方ないと割り切って、そのため隣の研究科とブチ抜きで文献紹介ゼミなどを企画したりしていました。
しかし、自分が在籍している2年間の間に院生が少なくとも5人辞めたり大学に来れなくなっているのは環境として実際どうなんだろうという気持ちがあります。
また、書くべきか悩んだんですが、自分と同じラボに所属していた同級の院生が、ラボでゆっくり実況を延々とみていたり、研究に関するディスカッションができる人じゃなかったり、話題がソーシャルゲームとライトノベルしかなかったり、なにより彼の研究のスクリプトなどを自分が書かざるを得ない環境だったのは精神的に苦痛でした。ゆるさん。
呪詛→https://note.com/stnk/n/nda63c795ff8b
ほな...また...
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
