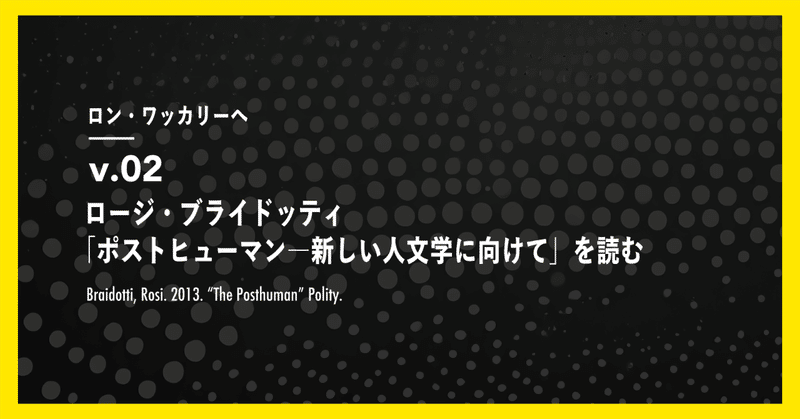
ロージ・ブライドッティ「ポストヒューマン―新しい人文学に向けて」を読む
Ron Wakkaryの「Things we could design」の翻訳に携わるなかで、森が関連図書を読み漁るコーナーです。今回はロージ・ブライドッティの「ポストヒューマン」(原著:Braidotti, R. (2013). The Posthuman. Polity)を読みます。
ブライドッティは著名なフェミニズム理論家で、特にノマドや生成変化といった、ドゥルーズを介して身体的な主体概念(「主体」という語がわかりにくければ「わたし」)を検討してきた論者です。彼女は新唯物論(new materialism)のさきがけとしても知られており、本書「ポストヒューマン」ではその思想がはっきりと語られています。
本書は極めて僕には読みづらい一冊で、正直彼女の言わんとするところの3割程度しか受け取れていないように思われます。しかし、本書がワッカリーの「Things We Could Design」に与えた影響は決定的で、ワッカリーはとりわけ、ポストヒューマンという語のまわりの議論の多くをブライドッティの議論によっています。本書の論旨を追っておくことは、新唯物論、生気的唯物論、ポストヒューマニズム論といった議論を追う上で非常に重要なものだと言えるでしょう。
ブライドッティの「アンチヒューマニズム」
まず、ブライドッティはポストヒューマニズムを提出するうえで、彼女が「アンチヒューマニスト(反人文主義)」であることを繰り返し強調しています。このことについて簡単に振り返ってみたいと思います。
ブライドティは、既存のヒューマニズムが前提とする人間(=Man、あるいはThe Human)とは「特権的白人男性」のことであり、その意味で、「ヒューマニズムの人間とは、理想でも客観的な統計的平均値でも中間値でもない(p.26)」ことを喝破します。つまり既存のヒューマニズムは、より直接的に言えば、とある「正しき人間」、ブライドッティの言葉を使えば「超越的」なものとしての人間を前提しているというわけです。
こうした超越論的な人間を前提とするヒューマニズムは、同質的かつ理想的な〈人間〉の基準を示し、強制しようとします。ひいては、それは「正しくない」、異なった、理想的ではない「他の人間」や「人間以外のものたち」を、別のものとして生み出す。普遍的基準としての正しき人間に対して、特殊で、異なった、他者的なものたちを生み出してしまうのです。
ブライドッティフェミニズム的な議論を引き受けてこれに応答しており、ここに彼女のなかで前提とされているのは彼女自身の女性としての位置づけられた立ち位置ですが、これには「性別化・人種化・自然化」された他者―例えば女性、先住民、周縁的な主体―が続くことになります(さらにいえば本来的に、女性や先住民や周縁的な主体という発想すら、本来内部に多様性や差異、それぞれの内部分裂をはらんだ、曖昧で部分的で流動的なものだと理解される必要があるでしょう)。
そして、こうして「正しき超越的人間」像は、異質で「人間以下」に押し出された他者("他の"人間や、非人間たち)を生み出します。ブライドッティは、このヒューマニズム的構造に対して「アンチヒューマニスト」を自称しているのです(その意味で、ブライドッティのアンチヒューマニストは、当然、人間嫌いなどといった意味ではありません)。
当然、このように押し出された他者には、"他の"人間のみならず、動物や多くのモノたちも含まれます。それゆえ、ヒューマニズムを乗り越えようとする挑戦は、当然のことながら、〈正しき人間〉と〈"他の"人間〉の地位を並列させようとする運動を超えて、動物やモノといった非人間たちをも含んだすべてのものたちと中心を共有しようとするうねりへと展開することになります。
ポストヒューマニズムとは?
そして、このヒューマニズムとアンチヒューマニズムの対立を乗り越えようとブライドッティが提案するのがポストヒューマニズムです。ここでのポストヒューマニズムは、人間を技術によって拡張しようとするトランスヒューマニズムとは明らかに異なるものであることには注意しなければなりません。つまりポストヒューマニズムとは、既存のヒューマニズムがもつ人間の超越論的な立場を拒否し、中心性を「正しき超越的人間」のみならず、他の人間や非人間たちと共有することを目指しています。こうしたポストヒューマンは、身体を持ち、状況に埋め込まれ、他の種と共生する存在です。そしてこうしたポストヒューマンは、超越的で独立した立場に立っているわけではなく、常に他との関係のなかでのみ存在しうる関係的で相互連結的(interconnected)な存在であるといえます。
ここでひとつ重要なことは、ブライドッティが「一元論的哲学」を提唱していることです。これはブライドッティが「人間-非人間」をはじめとする二元論的立場をあまねく否定することから見出される立場ですが、この一元論については我々にとってはややどきっとするような言葉遣いであることもあり、説明が必要なように思われます。
この一元論的哲学は、スピノザの一元論的宇宙を展開したもの(としてのドゥルーズなどの議論を引き受けたもの)です。基本的にスピノザの議論は、ごくごく簡潔に言うならば、神だけが唯一の実体であり、私もあなたも、その神の無数の様態にすぎないという「汎神論」として知られています。より雑に総括するならば、私もあなたも何もかも神である、というわけです。二元論を否定することで、このように一元論的な議論が生まれます。しかし、ここでの一元論はこうした、単純に私=あなた=神という図式よりも(当然のことながら)複雑化されていることに目を向ける必要があるでしょう。
ポストヒューマニズムは、あらゆる超越を否定し、徹底した内在性に依拠しているのだとブライドッティは言います。当然、一元論のうちには二項対立はありませんから、なんらかの超越もうまれません。そして内在性という意味においては(僕の解釈があっていれば…)、その一元論の"うち"でしか関係性は生じません。内在性というのはこのように、〈わたし〉はこの一元的なものとしての関係性のなかでのみ立ち現れるのだというものだと理解できます。
この、ポストヒューマンの主体性(ポストヒューマンであるような「私」)は「諸関係の内在性に依拠している(p.125)」という語は、マヌエル・デランダ(「社会の新たな哲学」)の表現と比較すると非常に顕著に対立構造にあることがわかります。デランダは、彼も同様にドゥルーズ=ガタリの議論を広く受け取りながらも、ブライドッティの真逆をいく徹底した実在論的立場をとり、「外在性の諸関係」を主張しました。つまりデランダの立場は、まずもって独立した個別の実在が存在するのであり、それが〈わたし〉の外側で関係しあうのだ、という立場です。
ブライドッティはまさにこれとは逆に「徹底した内在性」に依拠します。つまり、まず関係性が存在し、その全体としての関係性の「内側」でしか私は存在しない。つまり、独立した個別の実在は存在しないのであり、関係性のうちでしか主体、私を考えることはできない、と主張したのです。たぶん。
ブライドッティの議論はドゥルーズの議論に基盤を据えているところが多いのですが、そのドゥルーズはスピノザの汎神論的一元論に大きな影響を受けました。宇野邦一は、そのドゥルーズのスピノザ的解釈を、一元論的な存在のしかたのなかにあらゆる神の様態が存在しているのであり、その無数の様態たちが「どこまでも流動的にめまぐるしく変化し、たがいに作用を及ぼし合い、触発しあっている(宇野, 2020, p.78)」のだ、と説明しています。
そして、このように内在的に位置づけられる謙虚な主体としての、部分的で、状況付けられた、流動的で、差異的で、関係的で相互連結的なポストヒューマンを措定することでこそ、ブライドッティは(そのポストヒューマニズムが持つ「ヒューマニズムを乗りこえられるはずだ」という極めてヒューマニズム的かつ進歩主義的な自己矛盾に葛藤を抱えながらも)ヒューマニズムの誤謬から抜け出す可能性を見出そうとしたのでした。
バイタルマテリアリズム(生気的唯物論)へ
このような一元論はさらに、生/死という対立を乗り越えることにも繋がります。つまり、いきいきとした生/不活性で沈黙した死という二項対立を、です。
ポストヒューマニズムにおいては、人間と非人間の区切りがずれてきている、それどころか、人間や動物やモノたちといったものはともに中心を共有していました。さらに一元論的哲学においては、〈わたし〉はあらゆるものたちとの関係性のなかで定置される、部分的で状況付けられた主体となるのでした。そうであるならば、例えばそこにある一本のペンですら、〈わたし〉という主体を構成するうえでもはやなくてはならない存在であり、そしてこのように〈わたし〉を駆動する意味においてきわめて「いきいきとした」非人間です。
ブライドッティの論じるところによれば、このとき死は、「いきいきとした生」から「沈黙した死」へ、という二項対立的な転換を拒否することになります。つまり、死は「非人間への」生成変化になるわけですが、ポストヒューマニズムの議論においては人間と非人間はおなじ中心を共有しているがゆえ、生から死への変化もまた、単なる一元論的な生気的生成変化の一幕でしかない。ポストヒューマニズムの図式を挿入することで、これまでの生きていることと死んでいることのあいだにあった二項対立をも乗り越えることが可能になるのです。
こうしたバイタルマテリアリズム(生気的唯物論)的観点は、追ってジェーン・ベネット「Vibrant Matter」(まもなく「震える物質」として刊行が予定されていますが)でまた詳細に見ていくことになると思います。
ワッカリーへのひろがり
ワッカリーは、このブライドッティのポストヒューマニズムを極めて真剣に受け取っています。つまり、いかに人間と非人間とが中心となる舞台を共有するさまを表現し探索できるかという問いを掲げて、ブライドッティの抽象的な議論をより経験論的に引き寄せようとしたのがワッカリーのThings We Could Designだと言えるように思います。なによりこの本は「本書はデザインをポストヒューマニズムの観点から探索しようとするものである This book is a posthumanist exploration of design」という書き出しから始まります。ワッカリーの出版関連動画においても、彼は「人間例外主義 human exceptionalism」を乗り越えることが重要な課題のひとつだと繰り返し発言しています。
ここでのポストヒューマニズムの観点は、当然幅広い議論を引き受けていることは承知のうえで、ブライドッティの議論にかなりを負っているものと思われます。
例えば冒頭で彼はこんなふうに述べています。
ここで人間の啓蒙、つまり「人間性(ヒューマニティ)」は、人間ではないものをケアするという理想的な状態に至ることができるはずだと信じている人がいるかもしれない。端的に言えばそれは、私たちが人間と呼ぶもののなかに一切「その他」を作らないということであり、動物の虐待と絶滅を終わらせることであり、そして豊かな生物圏と積極的に共存しようとすることを意味する。あるいは、人間は他の種とは区別されるものの、あらゆる非人間や物質と同一の運命に巻き込まれているのだ、という現在広まっているひとつの理解のしかたからはじめることで、未来を欲望することからデザインを再考することへ転換していけるのでは、と信じている人がいるかもしれない。
これはいずれも反語形式の(つまり、どちらも実現はできないと言っている)文章なのですが、上記の二つの形式とも、ブライドッティが「ポストヒューマン」のなかで否定/批判したやりかたです。
つまり、ヒューマニティが非人間をケアできるという考えは、「正しき人間」という不変的基準を目指すまさに「ヒューマニズム」であり、かつそれは動物や生物圏に対する「人間例外主義的」としての「ヒューマニズム」でもあるという意味で、すでにこの記事でも述べた通りの実現不可能な路線であるわけです。
さらには後者の「人間は非人間らとおなじ運命に巻き込まれている」という理解―「私たちは、同じ地球の危機に瀕しているのだ!」的言説―も、ブラドッティがポストヒューマニズム的ではないと退けている考え方です。というのも、本来、"人間"とひとくくりにされるもののなかにも多様性があり、実際には地球を危機に陥れるような行動を積極的に取り入れてしまっている"人間"もいれば、それどころかカーボンポジティブなしかたで生活している"人間"もいるわけで、このような「おなじ運命」的なネガティブな紐帯は、その人間のなかにある多様な差異を退け、結局のところひとつの基準でくくられるものとしての人間的ヒューマニズムの考え方を保持してしまっています。さらにいえば、当然「地球の危機」を生み出しそれを憂いているのは人間なわけで、その非人間から見れば理解不能な憂いは、まさに人間中心主義的に他のモノたちを紐帯に巻き込もうとするものだといえます。その意味でこれもまた、極めてヒューマニズム的で、人間中心主義的で、人間例外主義的な立場だと言えるのです。
こうしたかたちで、ワッカリーは明に暗にブライドッティを下敷きに議論を展開しています。しかし改めていうように、ブライドッティの議論は正直かなり追うのが難しく、私自身ほとんど受け取れていないのが正直なところ。むしろ、ワッカリーの経験論的な議論のほうが、もしかするとよほど読みやすいのかも?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
