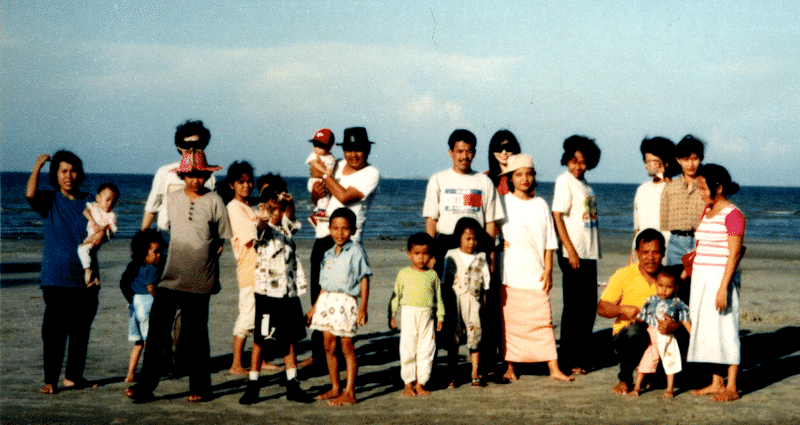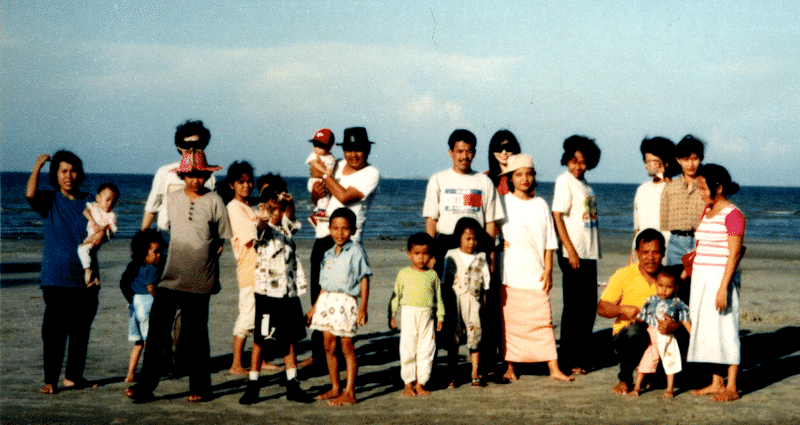III-1 すべての人が信仰によって死のからだからの救いを得て生きる
ローマ 5:12-8:39
ローマ人への手紙第三部の最初の議論は、ユダヤ人もギリシャ人も、すべての人がかかわる「罪のからだ、死のからだ」からの救いについてです。
こころ・霊とからだ霊は生きても、からだが死んだままでは、神の栄光をあらわす本来の人間としての働きはできない、とパウロは看過しているようです。人が神に生きるためには、「罪のからだ」(6:6)、「死のからだ」(7:24)から救われることがまず必要になるのです。
聖書が示す人間像は、魂と体が一体の存在です。それが、人