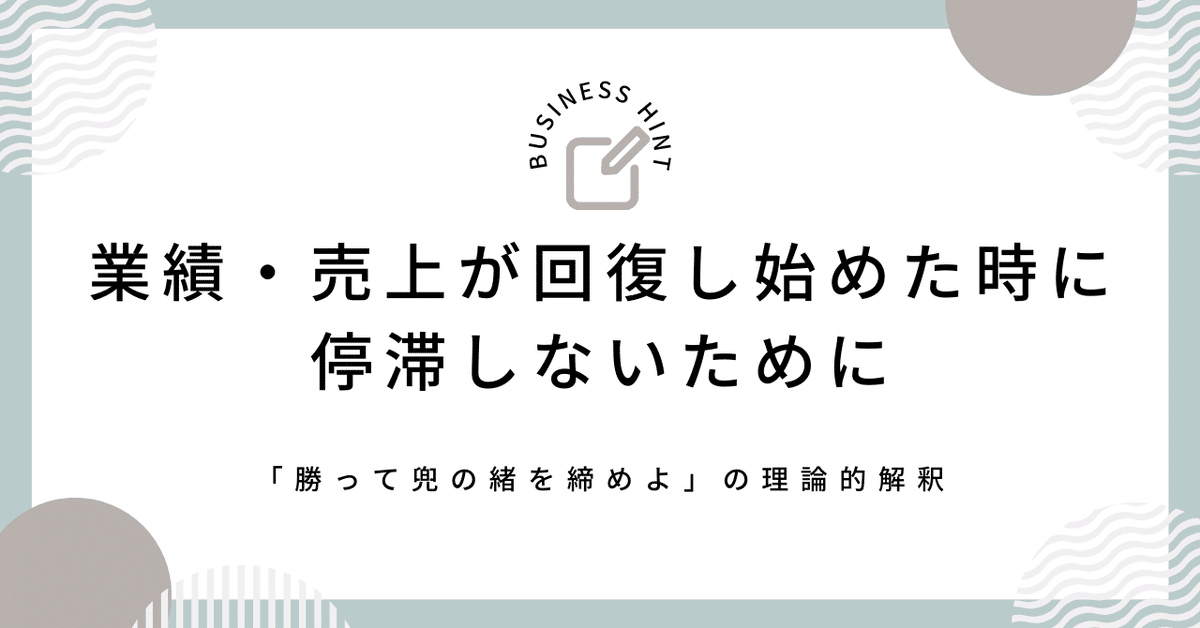
業績・売上が回復し始めた時に停滞しないために―「勝って兜の緒を締めよ」の理論的解釈
業績が伸び始めるといつも停滞してしまう・・・
いつも苦しんでいる会社というのは存在する。業績が悪化してきて「これはヤバい」と社内一同が無理をしながら猛烈に頑張り、何とか倒産廃業は免れる。しかし大きく伸びて事業拡大ということはなく、しばらく経つとまた何かの理由で業績が悪化し「これはヤバい」と四苦八苦するわけである。
平均的に損益分岐点の下側(左側)にいて、本当に危なくなるギリギリのところで、ほんの少しだけ上側(右側)に浮上してくるようなイメージだ。潰れそうで潰れない。潰れないからには実力があるのは間違いなさそうなのだが、しかし大きく成長する兆しも見えてこない。そんな会社について書いてみたい。
そういった会社をよく見てみると、「業績が伸び始めると停滞してしまう」傾向があることに気がつく。マイナスからゼロに戻すことはできるのに、ゼロからプラスに転じることができないのだ。
そうやって停滞している間に、世の中に変化が起きる。消費税増税、原材料価格の高騰、円安、取引先の倒産、人気商品の廃盤、トレンドの変化・・・・。その時々で理由は異なるが、とにかく不利なイベントが発生すると、もれなくそのあおりを受けて業績が悪くなり、また「マイナスからゼロ」に戻す作業を始めるのである。
カミュの『シーシュポスの神話』でも薦めてみようかと思われるような状況だが、それで終わっては実務家とはいえない。ぜひとも「ゼロからプラス」の試みを成功せしめる必要がある。
上昇と下降の裂け目:成功か失敗かで世界が違って見える
「なぜ業績が伸び始めると停滞してしまうのか?」という問題にアプローチする手がかりを得るには、「上昇局面」と「下降局面」との間に明確な裂け目を見出すことが有効である。
「業績が上がっている時期」と「業績が下がっている時期」とで、何かが異なっているのではないかと構えるのである。言い換えれば、「成功」と「失敗」を区別するということだ。
業績が下がっている時期は、たいていの場合「失敗」として認識されている。そして「失敗」は「否定」の思考ないしコミュニケーションを活性化する。この「否定」が果たす機能こそが重要なのだ。
「あの施策が間違っていたからだ」「データの分析が不十分か間違っていたのではないか」「会社に〇〇という構造的な問題があるせいだ」といったように、原因を組織内に求める議論もあれば、組織外に原因を帰属する議論もある。つまり、「強力なライバルが現れたせいだ」「景気悪化のあおりを受けている」「マーケットのトレンドが変わってきている」等の議論である。
事の真相はともかく、何らかの確からしい原因が突き止められることで「否定されるべき要素」が見えてくる。現状の否定は、通常の場合「改善」として認識される。失敗した施策の反省を活かしてやり方を変えてみたり、新しいデータ分析を可能にするツールを導入してみたり、新しいトレンドを意識した新商品を展開してみたり、「今までとは違うこと」が試みられる。改善とは、自分自身への抵抗なのである。
「失敗」が「否定」を活性化する反対側で、「成功」が「肯定」と結びつくことは容易に想像がつくだろう。ただ、「失敗」の概念が生々しい内容を伴っているのに対して、「成功」は「失敗していない」ということによって、すなわち「失敗の不存在」によって、概念化されることが多いという点には注目すべきである。レジリエンス・エンジニアリング研究で有名なエリック・ホルナゲルの言を借りれば、「成功」は欠性語なのである。
私たちは異常事態や危機として知覚される「失敗」には敏感に反応する一方で、「失敗の不存在」たる「成功」には鈍感になる思考のクセを持っている。「失敗」が現状を「否定」するきっかけとなり、それが「改善」行動を動機づけるというメカニズムは、「成功」局面においては機能しなくなる可能性が高くなる。失敗が存在しないのだから、わざわざリソースを割いてまで積極的に改善を行うことが不合理に見えやすいのである。
成功局面においては改善行動が動機づけられない。少なくとも、改善行動を動機づけるメカニズムの1つは機能しなくなる。したがって、業績が落ちていたところ(失敗局面)では必死になって改善が模索されるのだが、業績が上がりはじめて成功局面に切り替わるタイミングで業績を持ち直すことを可能にせしめたメカニズムが失われ、停滞してしまうのである。
多くの実務家は賛成してくれると確信しているが、事業において文字通りの「停滞」はありえない。「停滞」は「衰退」のバリエーションの1つである。
改善を動機づける概念装置としての目標
では、成功局面に入ってもなお改善行動を動機づけるために、私たちに何ができるのだろうか。
ここまでの議論を踏まえることで、私たちの体験を加工する概念装置としての「目標」が見いだされることになる。目標は、失敗の機能的等価物として利用することができるのだ。
目指す業績、あるべき姿が目標として定まることで、業績の上昇局面においても「目標未達」が認識できるようになる。目標がなければ「成功(=失敗の不存在)」として体験されていたであろう現状が、目標という概念装置によって再び「失敗」として体験される可能性が高くなる。「目標達成のために、何かできることがあるはずだ」という形で現状の否定が議論されるようになり、改善行動が動機づけられる。
成功局面においてこそ、機能する目標が求められるわけだが、これはそんなに簡単なことではない。少なくとも、(こういって良ければ)環境の方から否定の契機を与えてくれる失敗局面のように、自動的なメカニズムを期待することはできない。
現状を「否定すべきもの」「改善が必要なもの」として体験せしむるような目標とは、関与するメンバーにとってリアリティのある目標でなければならない。目標にリアリティを付与するためには根拠が、説明が、物語が必要であり、そういった目標を策定するためには相応のリソースを割かなければならない。また、定めた目標のリアリティが損なわれないように随時監視・評価する必要がある。場合によっては改定する必要もあるだろう。
ここまで努力してようやく得られるのは「改善の動機づけ」である。では具体的に何を試みるのか、そのための段取りはどうするのかといった議論が、また別途必要になってくる。
このように、失敗の機能的等価物として目標を機能させることは、能動的な努力を必要とする。だからこそ、「業績が伸び始めるといつも停滞してしまう」という現象がひろく観察されるのだろう。「失敗から立ち直る」ことよりも「成功し続ける」ことの方が難しいという状況が、社会には存在している。
そしてこのことは昔から知られていたものと思われる。「勝って兜の緒を締めよ」という言葉は、戦国時代、関東に勇名を馳せた北条氏(後北条氏)の2代目当主である北条氏綱が嫡男に残した遺言が由来であるそうだ。
この遺言を受けた嫡男こそ、後に北条氏の全盛期を築くことになる北条氏康その人であった。私たちもまた、故事に習いたいものである。
参考文献
二クラス・ルーマン(馬場靖雄、赤堀三郎、菅原謙、高橋徹訳)(2009).社会の社会 1. 法政大学出版局
本稿の洞察は大部分がルーマンによってもたらされたものである。詳しい読者は本稿の用語法に違和感を覚えると思われるが、その原因の一部はできるだけ平易な言葉で論ずるための妥協であり、一部は筆者のルーマン読解の至らなさによるものである。
ちなみに、ルーマンの理論に興味が湧いた読者がいきなり上記の文献を読むことはおすすめしない。非常に大部な書物であるうえに、入手性も劣悪である。せっかくの好奇心を伸ばしていただくため、まずは入門書から入って頂きたい。いずれ、読書案内も書きたいと思う。
エリック・ホルナゲル(北村正晴、小松原明哲監訳)(2019). Safety-IIの実践 レジリエンスポテンシャルを強化する. 海文堂
ホルナゲルは、本稿の用語で言えば「失敗から学ぶだけでなく、成功からも学べ」といったスタンスであり、本稿の「目標という概念装置を使って、成功局面でも失敗を見出す」というアプローチの先を行っている。いずれホルナゲルのアプローチも紹介したい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
