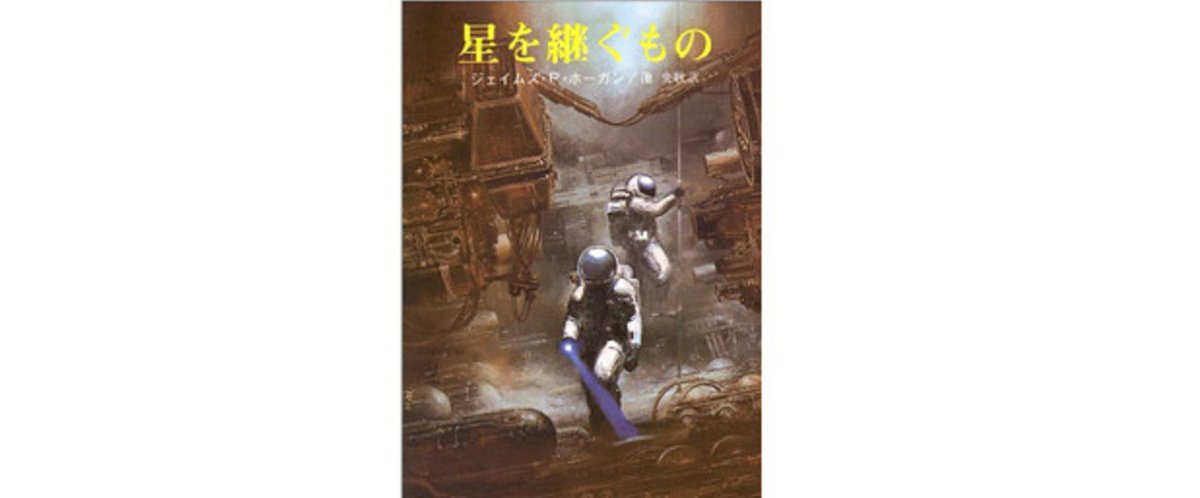
『星を継ぐもの』J・P・ホーガン ◆SF100冊ノック#03◆
『星を継ぐもの』J・P・ホーガン 創元SF文庫 1977
◆1 あらすじ (ネタバレなし)
21世紀。CTスキャンの最強版、みたいなマシン、「トライマグニスコープ」を作っていたハント博士は、国連宇宙軍から呼び出しを受ける。極秘と言われて見せられたのが、一つのひからびた死体―月で発見された、宇宙服を着た死体だった。年代測定の結果は「五万年前」。にも関わらず、彼の姿は、現在の人類―クロマニョン人から進化した地球人と完全に同じだった。
これは大いなる矛盾だった。もしこの死体が地球人だとしたら、五万年前、地球に高度な文明が存在していたことになる。だとすれば、現在その文明の遺跡が見つからないことは考えられない。一方、もし彼が他の星から来たのだとすれば、地球人と同じ姿をしていることの説明がつかない。
ハント博士に依頼されたのは、「トライマグニスコープ」で死体の身体や、彼の持っていた手帳を解析することだった。国連に集まってくる科学者たちは、この大いなる謎を解き明かすために奮闘を始める。
表紙のイラストに騙されて読んでなかった……ほら、宇宙服着て、なんか別の星を探検するみたいなイメージじゃないですか。ところが、ページをめくってみたら、舞台は研究所。出てくるのは探検家じゃなくて科学者ばっかり。そして、
「SFにして本格ミステリ。謎は大きいほど面白いに決まっている。」(小野不由美)
この言葉の通り、本書の構造は「ミステリ」そのものだと思う。「50000年前」という密室に閉じ込められた一つの死体の謎を、「科学」による証拠と推理で解き明かしていく。ご丁寧に「プロローグ」に仕掛けがあるのも、ミステリ仕立てに思える。
あらすじを見てもらえば分かる通り、この死体の矛盾はほとんど解けそうに無い。それが、(科学的見地はともあれ)しっかりと説明出来る結末が用意されてるのは素晴らしい。手帳はじめ、様々な解読が進み、新しい証拠を発見しながら、読者も科学者たちと一緒に「謎解き」に参加しているような気持ちにさせられるのが最高の魅力だろう。
こうした、「冒険」も、大きな「事件」も起きないSFというのは珍しいと思う……というか、ほかに思い当たらない。「古典」とされるけれど、同時に非常に特徴的な一冊。そんなに長くもないので、ぜひおすすめ。科学的ものの見方、という点から、中高生におすすめもされるらしい。僕としては、頑迷な博士ダンチェッカー教授との確執、友情、人間性……みたいなところにも惹かれていた。

◆2 結末
この本は「ミステリ」なので、謎のネタバレはほかの小説に比べて重要度が高いです。ここから先を読むと面白さの8-9割が損なわれるので、「今のところ読む気が無い」人ともう読んだ人だけどうぞ。
とはいえ、このトリックは見事で面白いので、紹介したい気持ちも大きい。そんなわけで、時系列順に見て行きましょう。
●2500万年前以前:太陽系には、もう一つの惑星「ミネルヴァ」があった(火星の外のアステロイド・ベルトはその残骸)そこには、高度な巨人の文明が栄えていた。
●2500万年前:ミネルヴァで二酸化炭素濃度が上昇する。巨人は(二酸化炭素を酸素にするため)地球の植物・動物を移入する。しかし、結局解決にならず、巨人たちは太陽系を去っていく。
●5万年前以前:ミネルヴァに残された地球の動物が進化し、新たな文明を築いていた。ミネルヴァには月があったが、ここに到達できるほどの科学力を手に入れる。
●5万年前:ミネルヴァで大きな戦争が起き。惑星は、月に据え付けられた強大な兵器で破壊される。(アステロイドにまで分解)月に残っていた数百人のミネルヴァ人は、月ごと宇宙を漂い、太陽に向かって落ち込んでいく。その途中で、地球の引力につかまって、「かつてのミネルヴァの月」は「地球の月」へと変わる。このとき、兵士の一人が月面で死んだのが、小説冒頭で出てくる死体。
そして、生き残ったミネルヴァ人は、宇宙船で地球に降下し、当時ネアンデルタール人に代わって再び文明を築いていく。これが現在「クロマニョン人」と呼ばれる地球人の先祖である。
以上が、トリックの答え。ラストのどんでん返しは圧巻ですね。「彼がぼくらに似ている」のではなく、「僕らが彼に似ていた」という大転回に喝采を上げること間違いなし。
◆3 もう二つの見どころ
最大のみどころといえば、この「ミステリ」の「解決編」なわけだけど、この回答を得るに至る道筋も楽しい。ひとことで言えば、それは科学の実証のプロセスをたどっていく。月についての知識、あるいは人類の生物学的・解剖学的な知識が、時折事細かに述べられる。おそらくそれらは科学的にも正しいもので、そこだけ抜き出せば教科書の記述とも差はないだろう。
物語の主人公ハント教授は、様々なデータを積み重ね、仮説を立て、それを実証し、様々な分野の横断―例えば言語学と数学と生物学―を組み合わせることで、このジグゾーパズルのような研究を進めていく。また、十分に証拠が出そろっていなければ、決して断定を行わない。この「研究」の姿勢が、「サイエンス」の側面を強く印象付ける。
そして最後の一つは、ここまで謎解きと科学の話をしておきながら、「人間」も存分に描いているところ。最初は頑迷で、敵役として登場するダンチェッカー博士が、やがて和解し、最後のどんでん返しを叩きつけるシーンにはしびれる。それを置いても、いくつかのアイディアは、ハント博士が広大な宇宙を見上げ、いつかの「チャーリー」と心を通わせることで得たものだった。コリエルというただ一人の不屈の精神、友情から、人間の性質へジャンプするのも非常に感動的。
プロローグで「巨人」という語が出てくることが大きなミスリードになっている。中盤に登場する「ガニメアン」を想起させるのだが、実際は不屈の精神を持つ人間のことを「巨人」と表現する惑星ミネルヴァの慣例だった、というわけだ。僕はこの小さな叙述トリックに振り回され、それが解けたときの満足感を強く覚えている。
◆キーワード
自然人類学、生物学、進化論、天文学、惑星科学、異星人、NASA、科学者、暗号、言語学、数学
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
