
サーミの投げ掛ける『孤星』へのアンチテーゼ
いよいよやってきた待望のサーミイベント、面白かったですね!

乳の馬鹿でかいサルカズッパリが登場し、そんなナリで弓が引けんのか???とかなったり、インターネット一部界隈で大人気の『皇帝の利刃』さんが良い感じで先行きに暗雲を投げ掛けたり(野生化するな)、ウルサスの持つ拡張主義的立ち位置ってヴィクトリアのそれとは質感が違ってなんか嫌にリアルなところあるよな……とか。
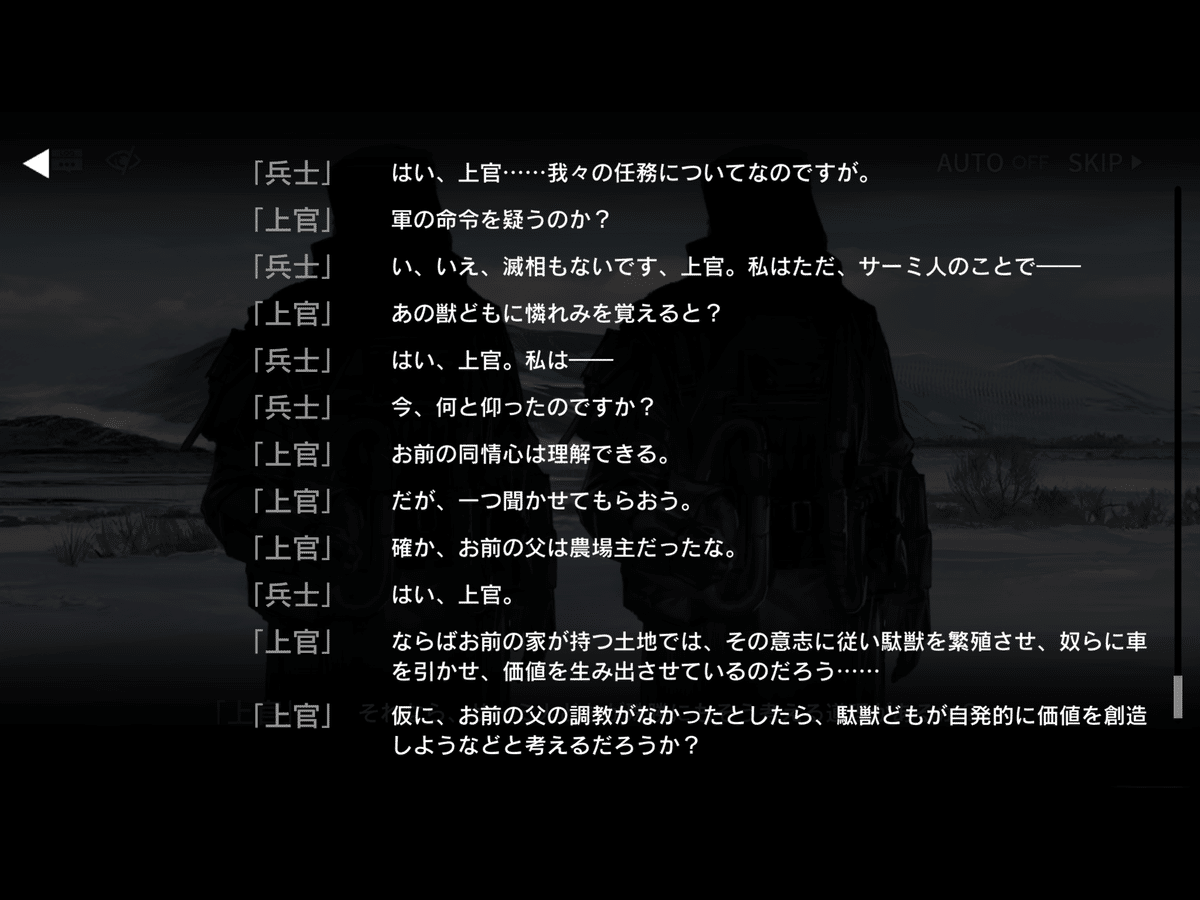
でも自分が一番感心したのが、サーミという大地の物語そのものが『孤星』の、クルビアの、あるいはクリステン=ライトの貫徹した哲学への真正面からのアンチテーゼになっているという点だった。ちょっとそのあたりについてツラツラメモしていこうと思う。
・『孤星』を勝利者の物語にしないために

前提としてなんだけど、クリステンの一連の物語は狂的ともいえる開拓精神の物語であって、“たまたま失敗しなかった身投げ”のようなものだと思う。これはサリアやサイレンスが作中で繰り返し言っている事でもあるし、なんとなればクリステンは“ブレーキ役としてのサリアがいるからこそ自分は全力でアクセルを踏み込める”とまで思っていたフシがある。おやすみ、テラはちょっと人類を信頼しすぎだろ、夜明けとおはようが来るって確信してるんですよ、この女。

“先へ先へ”と逸る心の情熱と、それをアセスメントし抑制する頭脳の冷静の綱引きの中でしか科学は先に進まない。そんなことを長大なテキスト群で表現したのが『孤星』なわけだけど、サーミの大地の物語はそこに新たな視点を加えてきた。すなわち“我々にとっての解明と意味の差異”についてと、先に進むためにもう一つ必要な“生存”という要素について。
・サーミで生きるということ
今回のシナリオは、消息を絶った上司のゆくえを探すためのマゼランの旅行記だ。彼女はシモーネ、ティフォンという心強い味方を得てサーミの大地を南下していく。
その中でマゼランは、彼女自身のフィールドワーカーとしての好奇心から様々な失敗をする。ここで描かれるのはマゼランの、ひいてはクルビアの開拓精神の持つ“解明する”という欲求と、サーミの民の持つ“ありのままに対処する”という精神性の差異だ。

たとえば“ぐつぐつ沸いたお湯”という現象があったとする。解明の精神はこの現象を腑分けしていこうとする。通常の気圧下で、摂氏何度でこの現象は発生するんだろう。H2O以外の液体は同じ現象が起こるのかな……それは別な温度になるのかな……といった感じ。

ところがサーミに属する人々の感覚は違う。彼らは「これで茶が淹れられるし肉を茹でられる」という部分を重視する。目の前で起こる現象が我々にとってどのような意味を持つかが最初にあり、そしてその一助に“サーミ”を観るのが彼らのスタイルだ。どちらが優れているということはない。ただ、北原においては後者が優越する。悪魔がいるからだ。
・わからないまま触れるということ
俺はアークナイツという物語のでっかいテーマの一つは「科学と伝承の結節」にあると思ってる。そして、今のテラ世界は“かつての人類”がくみ上げた何かがその“解明”を失い、現生種族にとっての“意味”だけが残っている世界の物語だと思う。それは古サルカズのアーツであり、黒い王冠であり、サンクタの帰依する“神”であり、シーボーンであり………サーミであるかもしれない。いずれ全ては解明され、確かに科学的説明はつくだろう。ただそれは今を生きる彼ら、特に差し迫った状況で生きている人々にとってはどうでもいい話なのだ。サーミに砦を築き、連峰となって悪魔を食い止める彼らにとって、“解明”とは暇な奴がやればいい話。そう、あの生き急ぎ身投げ女のクリステンですらサーミの人々からすれば“暇な奴”なのだ。これが提示されたのはかなりデカいことだと思う。

テラ世界において未来へ進む力は冷静と情熱の綱引きだと先ほど述べた。そして、それ以外に“喫緊への対処”という当たり前のこと、とりもなおさず生存するということ……そんな当たり前の大事さを改めて提示してくれたのが『樹影にて眠る』の一連の物語だと俺は思った。

だからこそ、マゼランが全く理解の及ばぬ“影”に手を伸ばすのを躊躇したこと、ティフォンがそんな彼女の手を押したこと、未だ数字では測りえぬ何かを目で見て、肌で感じたこと。科学的フィールドワーカーが全身で未知と対峙するこのシーンは、今回のイベントで最も美しいシーンだと俺は感じた。
火曜日からのローグライクも楽しみです。『ミヅキと紺碧の樹』のような骨太なストーリーが提示されるでしょう……!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
