2020年に読んで良かった小説
13.『ミック・エイヴォリーのアンダーパンツ』
乗代雄介

『最高の任務』で第162回芥川賞候補となった現代文学の新星、乗代雄介がデビュー前から15年以上にわたって書き継いできたブログを著者自選・全面改稿のうえ書籍化。総数約600編に及ぶ掌編創作群より67編を精選した『創作』、先人たちの言葉を供に、芸術と文学をめぐる思索の旅路を行く長編エッセイ『ワインディング・ノート』に書き下ろし小説『虫麻呂雑記』(140枚)を併録。
芥川賞候補の乗代雄介が記したブログの書籍化。ぱっと見で厚さに怯むかもしれないが、中身は非常にリーダブルな短編が並んでいる。個人的には「創作」のぶっ飛び加減が大好きだった。少量の短編だと見開き2〜3ページで終わるので、ぜひ書店さんに行ってパラパラ本をめくり、人の目を気にしながらニヤニヤし、意表を突かれて吹き出して、そのままレジに直行してほしい。腹筋を鍛えるために腹パンしてこようとするイカれた音楽教師の話でめちゃくちゃ笑った。
12.『アウグストゥス』
ジョン・ウィリアムズ

養父カエサルを継いで地中海世界を統一し、ローマ帝国初代皇帝となった男。世界史に名を刻む英傑ではなく、苦悩するひとりの人間としてのその生涯と、彼を取り巻いた人々の姿を稠密に描く歴史長篇。『ストーナー』で世界中に静かな熱狂を巻き起こした著者の遺作にして、全米図書賞受賞の最高傑作。
ジョン・ウィリアムズの作品を読むのは『ストーナー』『ブッチャーズ・クロッシング』に続いて3作目。特に『ストーナー』の学問を愛した男の一生を追った静謐な文体に大変魅了されたのを憶えている。『アウグストゥス』は、様々な人物の記録や書簡(そのほとんどは実際の記録をもとにジョン・ウィリアムスが創作した物と思われる)によって成り立つ小説であり、人物造形とドラマの展開が非常に立体的に展開されていく。あまりの面白さに、この作品が史実を脚色したフィクションであることを忘れてしまうほど没入してしまった。史実から人間の生きた様を汲み取ることが出来る良き読者こそが、その史実を最も鮮烈な形で語り直すことが出来るのだということを痛感した。
11.『砂漠が街に入りこんだ日』
グカ・ハン

そこは幻想都市、ルオエス(LUOES)。人々は表情も言葉も失い、亡霊のように漂う。「私」はそれらを遠巻きに眺め、流れに抗うように、移動している。「逃亡」「反抗」「家出」、その先にある「出会い」と「発見」。居場所も手がかりも与えてはくれない世界で、ルールを知らないゲームの中を歩く、8人の「私」の物語。
韓国に生まれ、26歳でフランスに移住した作家グカ・ハンの短編集。夢の中のような抽象性を帯びたLUOESの描写は、小説に独特の浮遊感をもたらしている。韓国でもなくフランスでもないどこかを描いた作品であるのに、どうしようもなく今我々が生きている世界を感じさせるのは何故だろう。2020年、大きな変化に曝された世界の中で、自分たちも気付かぬまま少しづつ変容していった小さな感性を、この作品は思い起こさせてくれるように思う。
10.『ドゥームズデイ・クロック』
ジェフ・ジョーンズ

『ウォッチメン』の世界よりDCユニバースへやってきた神のごとき存在ドクター・マンハッタン。彼が去ったことで『ウォッチメン』の世界は再び核戦争の危機を迎えていた。一方でDCユニバースもまた、ドクター・マンハッタンによる歴史改変の影響で滅亡の危機に瀕することになる。二つの世界を救うため、オジマンディアスやロールシャッハ、そしてDCユニバースのヒーローたちが立ち上がる。しかし、全能に等しい彼を止められるのはただ一人、スーパーマンだけであった……。DCユニバースの過去、現在、未来までもが大きく変化する、歴史的瞬間を刮目せよ!
コミックでありながら、ヒューゴー賞を受賞している『WATCHMEN』の続編。「前作のあまりにも残酷で美しい結末に何を足しても蛇足にしかなり得ないのでは...?」という懸念を、WATCHMEN世界とDCユニバースとの接続という荒技をもって吹き飛ばしてみせた快作。はっきり言ってロールシャッハとバットマンが会話しているだけでも大興奮…!しかしそういったお祭り的要素を脇に置いても、シリーズの魅力であるキャラクターの哲学的思索の深さが引き継がれていることが非常に嬉しかった。各話の間に挿入されている資料篇の充実度も原作へのリスペクトに溢れていて最高。
09.『言語の七番目の機能』
ローラン・ビネ

大統領候補ミッテランとの会食直後、交通事故で死亡した哲学者、記号学者ロラン・バルト。彼の手許からはある文書が消えていた。これは単なる事故ではない! 誰がバルトを殺したのか? 捜査にあたるバイヤール警視と若き記号学者シモン。この二人以外の主要登場人物のほぼすべてが実在の人物たち。フーコー、デリダ、エーコ、クリステヴァ、ソレルス、アルチュセール、ドゥルーズ、ガタリ、ギベール、ミッテラン……という綺羅星のごとき人々。謎の秘密クラブ〈ロゴス・クラブ〉とは? フィクションと真実について、言葉の持つ力への愛を描く傑作!
ロラン・バルトの交通事故死に関する謎をバイヤール警視と記号学者シモンというコンビが追う中で、フランス現代思想界の錚々たる面々が生き生きと喋りまくる様は非常に痛快。現代思想や哲学に通じていればクスリと笑えるようなパロディが満載だが、分かっていなくてもバイヤールの「何わけわかんねぇこと言ってんだコイツら」的な毒づきに共感できて面白い。ローラン・ビネは本作について「エーコ+ファイトクラブを書きたかった」との言葉を残している(作中には”ロゴス・クラブ”という言論版ファイトクラブ的な結社も登場する)。その言葉の通り非常に高いエンターテイメント性をもった作品に仕上がっている。
08.『月の客』
山下澄人

書かれたとおりに読まなくていい。どこから読んでもかまわない。
一気読みできる本のように、一望して見渡せる生など、ない。
「小説の自由」を求める山下澄人による、「通読」の呪いを解く書。
山下澄人の小説を読んでいる間にしか体験できない世界が確実にある。たまたま宿ったこの時代と肉体を抜け出して、世界のあらゆるモノの視点から何かを視る/語ることができたら、どれだけ面白いだろう。いや、そういった経験をもしかしたら自分は既にしているのではないか?と山下澄人の小説は思わせてくれる。小説の語りは、まだ見ぬ地平を拓き続けている途中なのだと確信させてくれる、著者の最高傑作であると思う。
07.『心は孤独な狩人』
カーソン・マッカラーズ
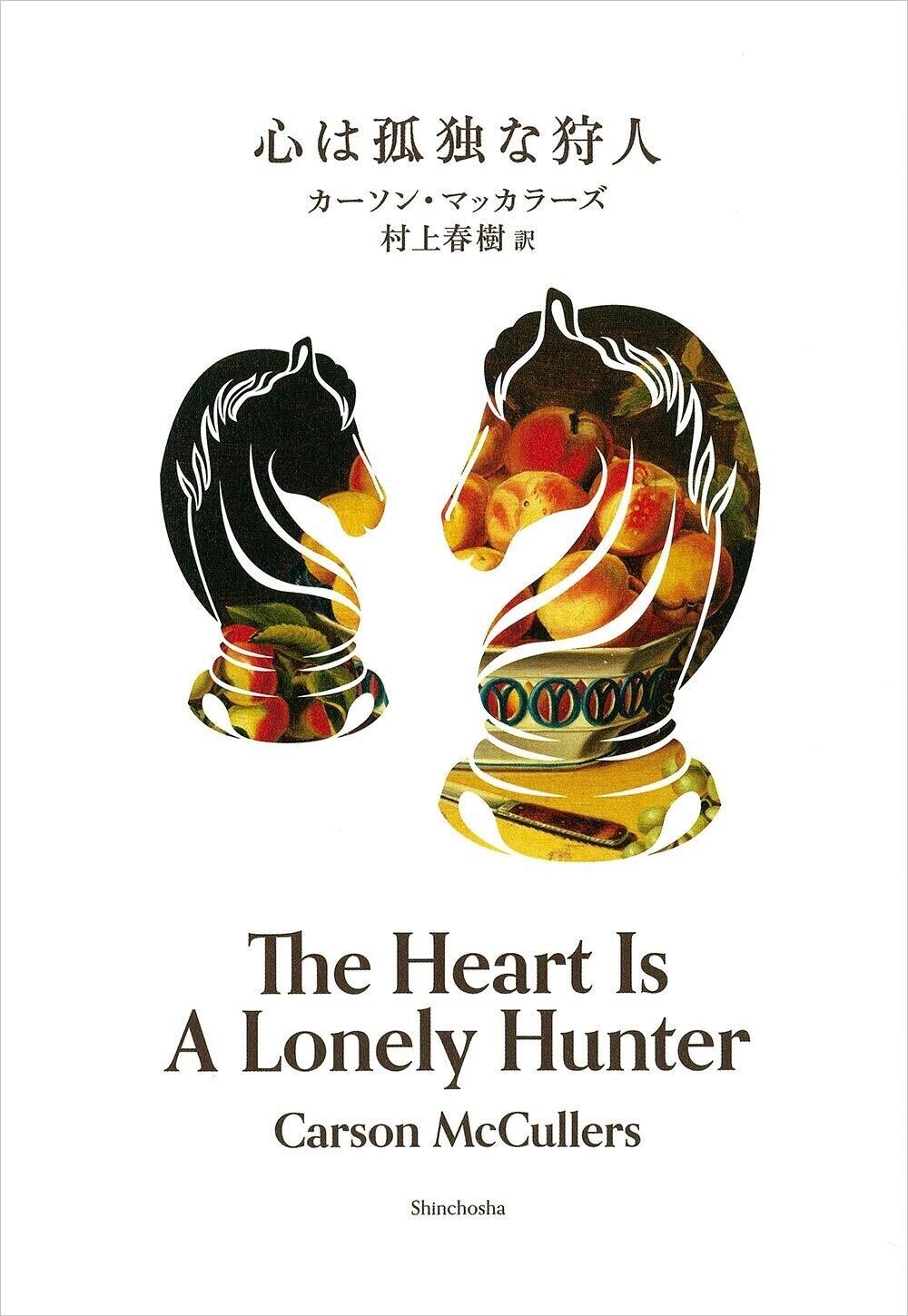
1930年代末、アメリカ南部の町のカフェに聾唖の男が現れた。大不況、経済格差、黒人差別……。店に集う人々の苦しみを男は静かに聞き入れ、多感な少女を優しく包みこむ。だがその心は決して満たされない――。フィッツジェラルドやサリンジャーと並ぶ愛読書として、村上春樹がとっておきにしていた古典的名作、新訳で復活!
女性南部作家カーソン・マッカラーズの代表作。個人的にも非常に思い入れの深い『心は孤独な狩人』が村上春樹訳で刊行されると知った時は、それだけで胸がいっぱいになった。聾唖者であるジョン・シンガーの元に、孤独と鬱屈を抱えたさまざまな人が集う様をフーガの形式で描いている。人々の孤独は、ものも言わず傾聴を続けるシンガーによって慰められるが、当のシンガーの孤独は埋められることがない。人と人との間の理解不可能性を突きつけるような寂しさを残す余韻にも関わらず、この小説には優しさと思いやりが満ちている。
06.『フライデー・ブラック』
ナナ・クワメ・アジェイ=ブレニヤー

欧米有名紙などの各メディアで激賞された規格外の新人、ブレニヤー衝撃のデビュー短編集、初の邦訳! 差別と暴力と欲にまみれた世界をシュールに描く圧倒的な筆力が、ブラック・シュールレアリズムの次世代を告げる!
ケンドリックラマーの引用から始まるこの短編集は怒りに満ちている。それぞれの短編が異彩を放っているが、やはりその中でも「フィンケルスティーン5」は着想の斬新さと世相をチェンソーでぶった斬ったような切れ味を備えた名短編。この短編集の刊行が未発表だった昨年、『MONKEY』サリンジャー特集号のトークイベントに行った際に、柴田元幸さんが朗読してくださったのが「フィンケルスティーン5」だった。黒人らしさ/ブラックネスの数値化(スーツを着るとブラックネスが下がる、パーカーのフードを被るとブラックネスは上がる)という斬新な設定は、彼らが受けている差別と偏見をより明確に可視化するだけではなく、黒人に対する白人の”正当防衛”に対する怒りが炸裂する瞬間のある種のやり切れなさを表現する効果的な手段になっている。人種差別と分断に揺れる社会を、鋭い着想と行き場のない怒りを持って凝視した力作。
05.『ウィトゲンシュタインの愛人』
デイヴィッド・マークソン
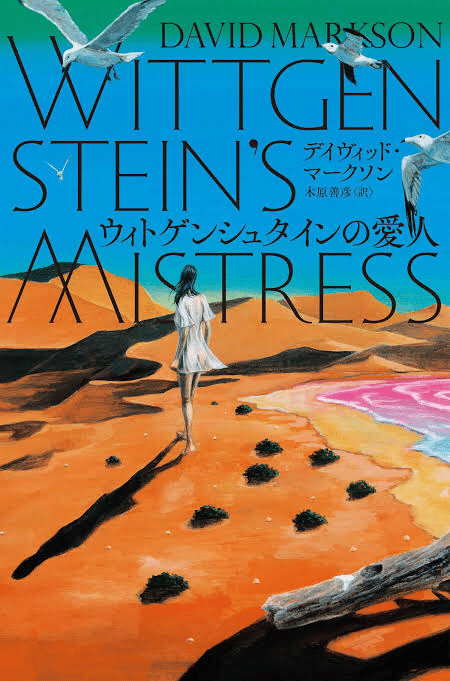
地上から人が消え、最後の一人として生き残ったケイト。彼女はアメリカのとある海辺の家で暮らしながら、終末世界での日常生活のこと、日々考えたとりとめのないこと、家族と暮らした過去のこと、生存者を探しながら放置された自動車を乗り継いで世界中の美術館を旅して訪ねたこと、ギリシアを訪ねて神話世界に思いを巡らせたことなどを、タイプライターで書き続ける。彼女はほぼずっと孤独だった。そして時々、道に伝言を残していた……ジョイスやベケットの系譜に連なる革新的作家デイヴィッド・マークソンの代表作にして、読む人の心を動揺させ、唯一無二のきらめきを放つ、息をのむほど知的で美しい〈アメリカ実験小説の最高到達点〉。
今年読んだ中で最も不思議な気分にさせられた小説。人類滅亡後の世界に一人残された女がタイプライターで残す記録は、まるで詩のような美しさを放つときもあれば、何故かウンコとかパンツの話にめちゃめちゃ執着し続けるときもある、という調子で「あと少しで何か分かりそうな気がする」という状態のまま、いつの間にか作品を読み終わっていた。語り手の女性はおそらく気が触れており、語りを真に受けてよい人物ではないため、作品にはどうしたって謎は残るが、その謎は「人は誰に向かって何のために書き続けるのか」という普遍性を持っているように思われる。人物名/小説名/芸術作品名を問わず固有名詞がバンバン出てきてそれらのワードを調べながら作品を読み進めるのも楽しかった。いつまで経っても、何度読んでもよく分からないでい続けてくれる小説は愛おしい。
04.『チェリー』
ニコ・ウォーカー

スタッカートする荒い文体と会話――戦争とドラッグと犯罪。獄中作家が生々しく描くアメリカ犯罪文学の傑作。
この主人公、バカだろ。あなたはそう思うかもしれない。でもやがて途方もない悲しみが湧きあがり、あなたの心をかき乱す。これはそういう小説です。
銀行強盗の罪で服役中のニコ・ウォーカーが、自身の従軍/薬物中毒/犯罪の経験を綴り、獄中から出版した小説。この小説の魅力は、噛みちぎった痕がそのまま残っているような荒々しい文体に尽きる。それはビートニクの荒さとは異なる、共有すべき思想的背景を持たない荒さ、精神的外傷を覆い隠すための荒さ、とでも言えばいいのか、Breaking Badのジェシーがあの口調のまま小説を書いたらこうなった、みたいな、とにかく一部の層にはたまらない文体なのだ。小説の内容について特筆すべきは、主人公の従軍経験を記した部分で、この経験が若者の言葉で、許し難いイカれた経験として、しかし同時にゲームのように綴られることの複雑なリアルさは、この小説の文体、作者の成し遂げた達成だと感じた。
03.『雲』
エリック・マコーマック

旅先で見つけた一冊の書物。そこには19世紀にスコットランドの村で起きた悲惨な出来事が書かれていた。かつて彼は職を探して、その村を訪れたが、そこで出会った女性との愛とその後の彼女の裏切りは、彼に重くのしかかっていた。書物を読み、自らの魂の奥底に辿り着き、自らの亡霊にめぐり会う。ひとは他者にとって、自分自身にとって、いかに謎に満ちた存在であるかを解き明かす、幻想小説とミステリとゴシック小説の魅力を併せ持つ、著者渾身の一冊。
一人の男がメキシコの古本屋で偶然見つけた本の謎に迫るうち、自分自身の人生の謎に漂着していくというあらすじ自体が放つ圧倒的な魅力、作中に紹介される挿話の数々がそれだけを切り取っても短編小説として成立してしまう圧倒的な完成度。読書の面白さを感じた原初体験を思い出させてくれるような作品であった。このような「作品に没入している時間が何よりも面白い」という類の本を評するのは難しい。とにかくあらすじに何かを感じたら絶対にハマる。
02.『友だち』
ジーグリッド・ヌーネス

誰よりも心許せる初老の男友だちが自殺し、大きな空洞を抱えた女性作家の狭いアパートに、男が飼っていた巨大な老犬が転がり込む。真冬のニューヨーク。次第に衰えゆく犬との残された時間の中で、愛や友情のかたち、老いること、記憶や書くことの意味について、深い思索が丹念に綴られてゆく……。2018年全米図書賞受賞作。
恩師でもあり、誰よりも信頼できる友人でもあった大学教授(作中では「あなた」という二人称で呼ばれ続ける)が自殺した喪失感はどのような言葉によっても慰められることはない。しかし語り手の女性作家は、さまざま文学作品の引用と自分自身の言葉によって、彼がいなくなった世界の意味を洞察し続ける。人間が言葉を用いずに生きていくことはできないが、言葉を用いることは現実に対して嘘をつくことである、だとすれば私たちが語り続けるのは何故なのだろう。そんなことをこの小説は真摯に問い続けている。小説は語りによる芸術であると同時に、騙りによる芸術でもある。この小説の終盤には、“騙り“による鮮やかなトリックが潜んでいるが、自分にはこれが単たる作品上の技巧以上の意味をもって迫ってくるように思われた。
01.『歌え、葬られぬ者たちよ、歌え』
ジェスミン・ウォード

全米図書賞受賞作!
アメリカ南部で困難を生き抜く家族の絆の物語であり、臓腑に響く力強いロードノヴェルでありながら、生者ならぬものが跳梁するマジックリアリズム的手法がちりばめられた、壮大で美しく澄みわたる叙事詩。現代アメリカ文学を代表する、傑作長篇小説。
黒人の少年ジョジョとその母親レオニが、刑務所から出所する白人の父マイケルを迎えにいくまでの旅路を描くロードノベル。その行程を死者を含む三者の語りによる多元内的焦点化を通して描き切る手腕からはフォークナーを想起させられた。母親であること、被差別者であることのアンビバレントな感情を、ポリフォニックな構成によって語りきる手腕は見事... !死者を含む語りというのがこの作品のマジックリアリズム的な側面と思うが、奇想/幻想とは一線を画した説得力が語りの強さから滲み出ていて、これはリアリズムだと言い切りたくなるほどの切実さ。リアルを描くための手法としての死者の語りであって、手段と目的の転倒など微塵も感じない。間違いなくこの作品は本棚のとっておきの一角に位置し続けるだろうという確信が持てる大傑作だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
