
おすすめの「落語」をご紹介
今回の記事では、個人的におすすめな「落語」を紹介しています。具体的には「桂米朝」さんの落語や「英語落語」などを取り上げていますので、よかったら読んでみてください。
はじめに
近年、落語の人気は、幅広い層の方に定着したのではと感じています。落語を題材にした映画やドラマがあったり、テレビ番組でも落語家さんをよく見かけるようになりました。
私が落語に出会ったのは20年ほど前(20代半ば頃)ですが、今ほどポピュラーではなかったという印象です。知っている人は知っていて、固定のファンの方も多かったようですが、若い人にまで落語人気は広がっていなかったと思います。
当時、私自身も、落語のことはほぼ知らないままでした。しかしたまたま見たテレビ番組がきっかけで、はまるようになったのです。それがNHKスペシャルの「桂米朝 最後の大舞台」というドキュメンタリー番組でした。
アーカイブは残っていないようですが、NHKのページを参考として載せておきます。
番組の内容を簡単に説明すると、70代半ばとなった落語家の桂米朝さんが、歌舞伎座での最後の独演会にのぞむ姿を追ったものです。
歌舞伎座の収容人数は二千人!近いのですが、それを話芸だけでひきつけるのには相当なエネルギーがいります。年齢が70代半ばとなり、気力や体力が衰えてきたのを感じていたそうで、こうした大きな舞台での落語は今回(当時)で終わりと決めたとのことでした。
この番組のすごかったのは、米朝さんが演じた落語2席を、カットせずすべて放送していたことです。その時の演目は「一文笛」と「百年目」でしたが、2つを合わせるとそれだけで1時間を超えるものでした。
その前にドキュメンタリーとして、米朝さんの紹介や稽古の風景、弟子とのやり取りなどを見ることができたので、より深く本番の落語を聞くことができたように思います。
これがきっかけで落語に興味を持ち、いろいろと聞くようになったのでした。
落語について

「落語」については多くの方がご存じだと思いますが、「落語芸術協会」のHPを参考に、簡単に紹介してみたいと思います。
落語とは、
噺の最後に「オチ」がつくのが特徴。・・一人で何役をも演じ、演者の技巧と聴き手の想像力で噺の世界が広がっていく、とてもシンプルで身近な芸能です。
と説明されています。
落語には、江戸を中心に栄えた「江戸落語」と、大阪や京都などを中心に栄えた「上方落語」があります。
江戸落語は、舞台に座布団一枚が用意されているだけで、あとは演者が扇子や手ぬぐいを使って、話芸と身振り・手振りだけで演じるのが特徴です。
上方落語では座布団だけでなく、「見台」や「膝隠し」と呼ばれる木の台と、音を出すための「小拍子」を使う点が特徴です。

ちなみに「小拍子」は、手のひらサイズの2本の棒のようなもの。これで「見台」を叩いて音を出し、場面転換の合図にしたりします。また話の演出として、三味線や太鼓、笛などの「ハメモノ」が入るのも特徴です。
江戸落語と上方落語の違いについて、文化庁デジタルライブラリーの記事には次のように紹介されていました。
江戸っ子は華やかさよりも渋めの演出を好む傾向がありましたが、上方の人々は派手で陽気な演出を好むところがあります。
確かに「ハメモノ」が入るのと入らないのでは、雰囲気がだいぶ違うように思います。
おすすめの落語をご紹介
それでは、個人的におすすめな落語を紹介していきます。
まずはじめにおすすめしたいのは、やはり落語を聞くきっかけになった「桂米朝」さんの落語です。その前に少し、ご本人のことを紹介しておきます。
桂米朝さんは1925年(大正14年)の生まれ。「上方落語中興の祖」と言われており、落語界から2人目となる「人間国宝」にも認定された方で、2015年に89歳で亡くなっています。
第二次大戦後、上方の落語家は数えるほどしかいなくなり、「上方落語は滅んだ」とまで言われたそうです。そんななか上方落語の復興に尽力した一人が、桂米朝さんでした。今では上方落語協会に所属する人だけでも、200人を超えるまでになっています。
お弟子さんには有名な方が多く、「桂枝雀」さん、「桂ざこば」さん、「月亭可朝」さんらがおり、ご長男も「桂米團治」さんとして落語家をされています。
それでは、はじめに紹介するのはこちら。
「貧乏花見」

この噺は、花見の時期に同じ長屋に住む面々が、貧乏ながらも家にあるものを持ち寄って花見を楽しもうとする・・・というものです。
それぞれびっくりするくらい貧乏なのですが、とても明るく陽気で、今あるものでなんとか楽しもうという姿が、とても印象に残ります。
この噺を聞くと、私たちは毎日を結構豊かにやっているんだなあと、改めて感じさせてくれます。
かといって「清貧」を良しとする噺ではなく、やっぱり美味いものを食いたい、酒を飲みたいとのことで、最後はハチャメチャになるところも面白いです。
聞くと気持ちが明るくなり、ほっとできる点でもおすすめです。
「はてなの茶碗」

こちらは米朝さんが復活させた噺の一つであり、十八番にしていた噺でもあります。CDにある米朝さん自身の解説によると、「この噺は上方落語の貴重な財産であり、屈指の名作」とのことです。
また私が初めて米朝さんの高座を生で聞いたのも、この噺でした。
噺の内容は、京都の有名な茶道具屋さんのところに、一獲千金を狙って油売りの男がある茶碗を売りに行く・・・というものです。茶道具屋の旦那と油売りの男の対比が面白く、スケールも大きくて、噺にグイグイと引き込まれます。
米朝さんによると、「落語とは、現世肯定の芸である」とのこと。欲張りなところも含めて、登場人物が肯定的にとらえられており、個人的にとても好きな噺のひとつです。
「百年目」
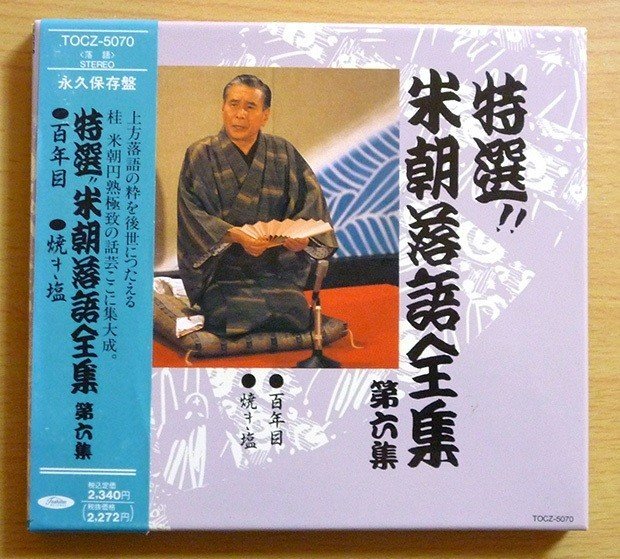
この噺は登場人物が多く、大ネタとして知られています。米朝さんも解説のなかで「どの落語が一番難しいかと聞かれたら、まぁ百年目ですと答える」と書かれています。
落語はだいたい20分前後の噺が多いのですが、「百年目」は40分を超える大作です。
登場人物は、大店(おおだな)の旦那と番頭、丁稚、そして太鼓持ちや芸妓などが出てきます。普段、店をあずかるしっかり者の番頭が、かくれて遊びに出た先でばったりと旦那に出会ってしまう・・・という噺です。
番頭が店の者に一通り叱言(こごと)を言うところや、遊びに出たところでガラリと雰囲気が変わるところ、旦那と番頭のやりとりなど、聞きどころがいろいろとあります。
ちなみに「百年目」という言葉は、コトバンクの「精選版 日本国語大辞典」によると、
運命のきわまる時。運のつき。悪いことが露顕した時などにいう。
といった意味があります。
「地獄八景亡者戯」
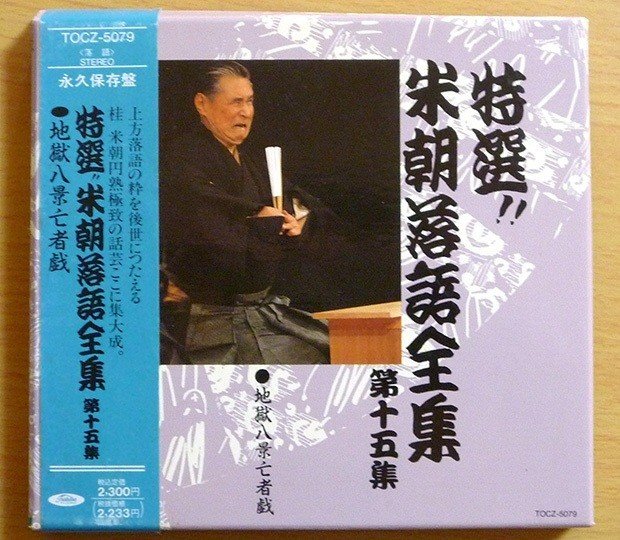
この噺も米朝さんが復活させたもので、終わりまで70分ほどかかる大長編落語です。ちなみに「地獄八景亡者戯」は「じごくばっけいもうじゃのたわむれ」と読みます。
この噺は解説によると、誰もが一度は行く「あの世」への旅を、時事ネタを織り交ぜながら滑稽で陽気な物語にした、「道中ばなし」の一つだそうです。
時事ネタなど演者が工夫できる余地が大きいので、いろいろな落語家さんで聞き分けてみるのも面白いと思います。
また演者の動きが多い噺のため、映像で見るのもおすすめです。
桂枝雀「WHITE LION(ホワイトライオン)」
桂枝雀さんは、米朝さんの3番目のお弟子さんです。米朝さんはいわゆる「正統派」の落語スタイルですが、枝雀さんは「爆笑型」の落語スタイルを特徴としています。
また「まくら」で話す様々な「理論」も有名で、「笑いは緊張の緩和である」というのも、枝雀さんが提唱したものです。
枝雀さんは古典落語も面白いのですが、今回おすすめしたいのは「WHITE LION(ホワイトライオン)」という英語落語です。今では「桂かい枝」さんや「桂三輝(サンシャイン)」さんなど多くの方が英語落語を行っていますが、最初に始めたのが枝雀さんでした。
ちなみに「WHITE LION」というのは、「動物園」というネタを英語にしたものです。お噺は「ハワイ大学ケネディ・シアター」で収録されたもので、アメリカの人にとてもウケています。
最初に「落語とは何か」を、もちろん英語で説明するのですが、子供にも分かるように上手に説明していて、とても感心しました。
英語はとても平易なものを使っているので、理解しやいと思います。また始めに「私の英語は、大阪訛りのジャパニーズイングリッシュなので・・・」と弁解されている通り、むしろ日本人のほうが聞き取りやすいかもしれません。
柳家小三治「トークショー ①②③」

柳家小三治さんは、米朝さんについで人間国宝となった、現役の落語家さんです。80代を迎えられましたが、現在も各地で独演会などを開催されているようです。
小三治さんは、古典はもちろんですが、「まくら」が面白いことでも有名です。
ちなみに「まくら」とは、落語の本題に入る前に、噺に関連するちょっとした小話や世間話などを、つかみとしてしゃべることを指します。
今回おすすめするのは、「まくら」が面白い小三治さんが行った、「トークショー」のシリーズです。①は「めりけん留学奮戦記」、②は「ニューヨークひとりある記」、③は「玉子かけ御飯&駐車場物語」というタイトルになります。
アメリカへ語学留学した時のことや、ニューヨークへ旅した時のこと、バイクの駐車場を占拠された話などを、面白おかしく話しています。
いずれも長尺ですが、飽きずにたっぷり笑えるのでおすすめです。
おすすめの落語のご紹介でした
個人的におすすめな落語を紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
私は米朝さんがきっかけで落語を聞くようになりましたが、他にも多くの面白い落語家さんがいます。
最近の方にはあまり詳しくないのですが、例えば情報番組の司会をされている「立川志らく」さんは、立川談志さんのお弟子さんとして有名です。また同じお弟子さんの「立川志の輔」さんや「立川談春」さんも、とても人気があります。
また笑点の司会をされている「春風亭昇太」さんは、新作落語が有名。NHKの「落語ディーパー」という番組では、「春風亭一之輔」さんがいろいろな落語を披露されています。
もし興味が持てるものがあれば、是非聞いてみてください。それではここまで読んで頂き、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
