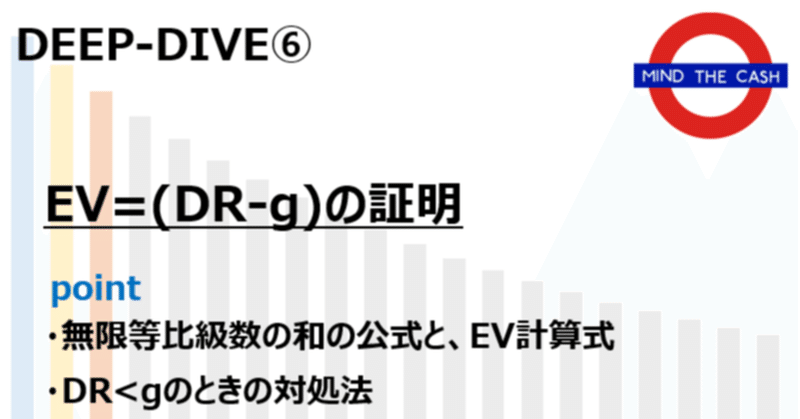
FCF/(DR-g)の証明
等比級数の和の公式
昔ならったこれですが、私も含めて忘れてると思うので公式をおさらい。
初項a, 公比rの無限等比級数の和は、a/(1-r)
ここでDCFにおける計算というのは、数式が以下のような見た目のため

初項はFCF1/(1+DR), 公比は(1+g)/(1+DR)です。2期目以降のFCFを1期目のFCFに(1+g)をかけて表現しているのがポイントです。よって、一定の比率で伸びていくフェーズになってからしかこの公式は使えません。例えば、今後5年間は10%成長で、そこから3%成長を想定する場合、6年目以降の定常状態の評価にしかこの公式は使えません。
公式を使って展開

公式の解釈
解釈というほどの公式ではないのですが、以下のことが分かります。
①DRが大きい=リスクが高い場合、EVは小さくなる
②gが大きい=成長率が高い場合、EVは大きくなる
③DR<gだとEVがマイナスになるため、使えない
DR<gになるケースはあるのでしょうか。短期的にはあります。たとえば、M3のグロースは実績として軽く20%を超えています。通常6-9%程度のDRと比べると明らかに大きく、DCFは使えないようにみえます。しかし、この成長率が永遠に続くと思っている投資家はいません。遠い未来の成長率も、よくて5%といったところでしょう。この段階まで落ち着けばDCFの公式を使うことができます。
定常状態をみつける
つまり、DCFを使うには、どこで定常状態になるのか、ということを意識する必要があります。大企業ですでに定常状態に入っている場合もあれば、若い会社で伸び盛りの場合もあります。後者のような場合には、10年をめどとしてどこまで伸びられるのか、その後は競争力を維持していけるのか、その結果、3%という平均的な会社の成長率を超えていけるかどうかを定性的に判断していくことになります。このフェーズになれば、公式で一気に計算できます。あとは、そこまでの10年間と、今計算した定常状態の価値を足して、EVにすればいいのです。詳しいモデルについては別途解説します。
サポートしてもらえたら週5でアップできるかも!
