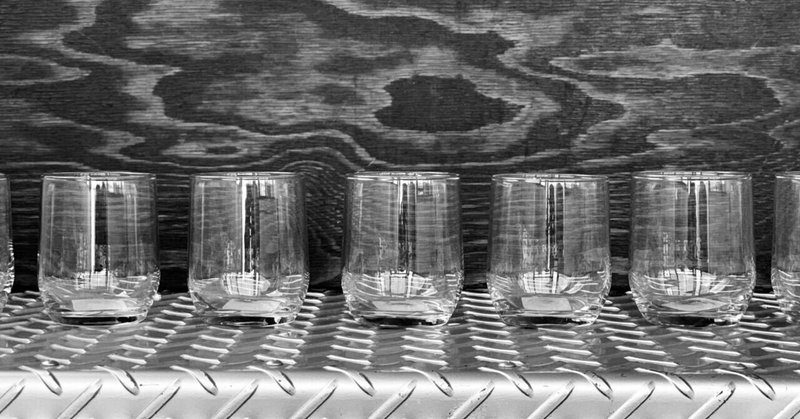
寄稿|「さびしくて透明な」野口卓海氏
今回の展示企画に際し、美術批評 / 詩人の野口氏に寄稿をお願いした。2014年に京都ANEWAL Galleryで行われたhinemos EXHIBITIONで彼の文章に触れ、とても感銘を受けたのを憶えていて、同じくhinemosのデザイナーで本展示のキャプションデザインも担当してくださった前田氏を通してこの度のオファーをさせていただいた。
なかなか言語化しにくい、まさに透明化されていく僕の「とるにたらないもの」への視点をうまく言葉にしていただき感謝しかない。
今回の、いや今後も続くであろうこの「鑑賞」という行為を通してみた透明なものを、ぜひとも読み取っていただけたら幸いである。
「さびしくて透明な」
美術批評 / 詩人 野口卓海
あの厄介な疫病は社会にたくさんの弊害をもたらし続けているが、玄関に積み上がる片付かない段ボールもそのひとつだろうか。物流。文字通り物の流れは日々急になり、勢いを増して私たちの身の回りを擦過する。どれほどその過程が見えづらくなろうとも、物理はノイズキャンセルできない。「物が無事に届けられる」という役目を終えた梱包材や緩衝材は、配達されるや否や私たちの手の中で簡単に息たえてしまう。生活の皮。もしかすると彼らは、もっとも正面から見られる・考えられることのない透明な塊かもしれない。そう思うとどこか、さびしい存在な気もした。
私たちが属する社会はさまざまな事柄を透明化するプロジェクトでもある。誰が・どこで・どんな風に作ったか分からない食事。朝に出したごみは即座に収集され、“キレイ”に失くなっていく。スーパーに整然と並ぶ地球の裏側からはるばる運ばれてきた鶏肉が、国産のそれよりもちょっと安い。なぜ?その問いが浮かぶことは、忙しない生活の中では実はとても少ない。ましてや答えを探し続けることなど。
ただしもちろん、個人にとって煩わしくて・汚く・面倒な事柄を、社会構造によって整理し円滑にしようとしてきた熱意は否定されるわけがない。しかし、それらを知ろうとする動機や、考えようとする想像力までもが、誰かの思惑で透明にされているとしたら、私たちはできればそれを取り戻すべきだと思う。無知であることさえ知らないなんて、あんまり考えたくないような恥ずかしい事態だからだ。
当企画の相談を受けたとき、その透明の一部分を見つめるようなことなのかと思った。梱包材や緩衝材をもう一度見ること・見つめ直すことは、考える行為そのものや想像力につながるだろう。私たちが勢いでポチったその商品は、誰かが詰 め・誰かが運び・玄関にうずたかく積み上がったさびしくて透明な塊のおかげで届いたのだから。知らないだなんて、到底言えない。
透明を希求する近現代の欲望を、大学時代の教授は「脱臭」と呼んでいた。極度な 脱臭の行き着く先は、私たち自身の不在かもしれない。そうならないためには、どうすればいいだろうか?まずは届いた荷物を、次はいつもより少しだけきちんと観察しながら解こう。もしかしたら良いアイデアが浮かぶかもしれないし、思ったよりお気に入りの箱になるかもしれない。私たちが大切なお金で日々購入しているものは、商品だけでなくそれを取り巻くすべてなのだから。
野口卓海|Takumi Noguchi 美術批評/詩人
1983年 京都市生まれ
2007年 近畿大学文芸学部芸術学科造形美術専攻芸術理論コース 卒業
主な展覧会企画として、「有馬温泉路地裏アートプロジェクト」(2013年)、「まよわないために -not to stray-」the tree konohana(2014年)、「松見拓也 写真展 | KASET」hinemos(2015年) 、「METRO WHITE」阪急メンズ大阪(2016年)、「人と絵のあいだ」ALL NIGHT HAPS(2016年)、「みたりのやりとり」マガザンキョウト(2017年)など。
現代美術へのアプローチと平行し、デザイン・ストリートカルチャー・音楽といった同時代的な他領域へ積極的に携る活動としてhinemosにも参加。2015年からは写真家・松見拓也とデザイナー・三重野龍とのサイファーのような月刊紙片「bonna nezze kaartz」の発行を開始、同名義で展覧会や作品制作なども行う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
