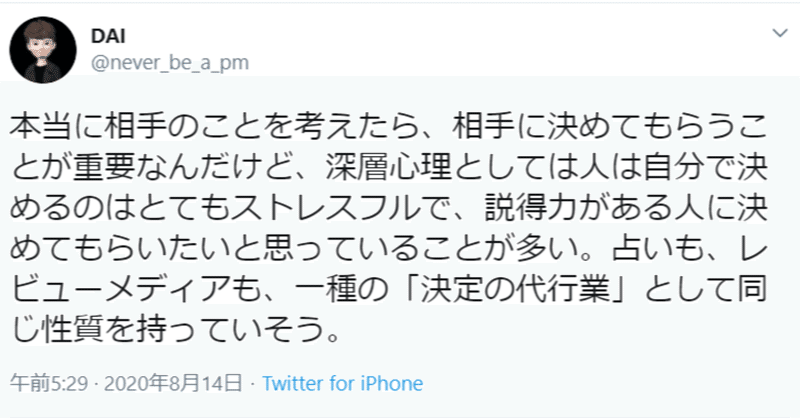
「指図されたくない」けど「決めてほしい」という選択の深層心理
本当に相手のことを考えたら、相手に決めてもらうことが重要なんだけど、深層心理としては人は自分で決めるのはとてもストレスフルで、説得力がある人に決めてもらいたいと思っていることが多い。占いも、レビューメディアも、一種の「決定の代行業」として同じ性質を持っていそう。
— DAI (@never_be_a_pm) August 13, 2020
ライティングのお仕事をしてくれているインターン生と最近話していて、面白いなぁ~と思った会話がありました。
僕:「ん~、この記事って、確かに客観的でファクトが多く書いてあるんだけど、読者の方ってこれでサービス選べるかな?」
インターン生:「私は、客観的な情報があって、そのうえで比較検討して選びたいと思っています!逆にあまり根拠がないことを書いていると、「それってあなたの主観だよね!」と感じてしまいますね」
僕:「確かにねぇ。ところで、自分が子どもを産むとして、産婦人科を選ぶとするじゃん?僕、こういうのって身近な信じられる誰かに、聞くと思うんだよね。よかったかどうかとかで。」
インターン生:「確かに」
-----------------------------------------------------------------------
人って、確かに合理的な根拠に基づいて、比較検討して意思決定するのが、ある意味後悔しない選択だと思うんですよね。
ただ、実際のところこの合理的な選択って、超疲れるんですよ。肌感ですが、合理的な選択をしているのは、生活の中でも5%くらいな気がしています。
あと、実は人間は一日に選択を6000回以上していると言われており、面倒くさいので、選択を自動で処理するような心理的機構もあったりします(詳しくは認知行動療法の自動思考とか面白いです。)
参考)
How Many Decisions Do We Make Each Day?
【専門家が解説】 認知行動療法
ちなみに、24種類と、6種類のジャムの選択肢を与えたときに、どっちの方が売れるか実験して、選択肢の少ない方が売れたという「ジャム実験」からもわかる通り、比較検討というのはとても疲れるんですよね。
参考)マーケティングに使える「ジャムの法則」に惑わされてはいけない選択肢の考察
だからとりあえず
・並んでいる
・友達がいいって言っている
・信頼できる人がおすすめしている
みたいな、比較検討をスキップできるような根拠をもとに、非合理的な選択をしてしまうことがほとんどだと思います。
ポイント:合理的な選択と非合理的な選択
・合理的な選択:様々なメリット・デメリットを考えて、比較検討したうえで出した選択。ストレスが大きい。
・非合理な選択:適当な根拠をもとに、出した選択。ストレスが小さい。
合理的な選択は、意思決定で後悔しなくなりやすい反面、選択に時間がかかり、また決断を下すのがつかれます。
〇ポイント:合理的な選択の特徴
メリット:選択の質が上がる(=選択結果に対して後悔が減る)
デメリット:意思決定に時間がかかり、疲れる
--------------------------------------------
ところで、占いで人生を決めてもらいたいって人、多いと思うんです。
僕自身、占いは怪しいものだと思っていたのですが、実は3-4カ月前に相当メンタル病んでしまって、その時に初めて「占いを使いたい!」と一瞬思いました。
自分って、これからどうしたらいいんだろう....
あらゆる比較検討したけど、決められない....
そんな感じの気持ちです。
あらゆる合理的な比較をしたけど、いまいち決め切れない場合ですかね。
そういう時に、占いみたいな「非合理的な選択」をしたいと思ったんです。
占い師の方に決めてもらえば、あとはやるだけ。迷わなくても済むんですよね。とはいえ、多分それで意思決定して失敗したら、「あの占い師、全然当たらなかった。」ってなるはずです。人のせいにできます。あと、多分占い師はそんなに合理的な決定していません。
あとは、「意思決定の責任を他人になすりつけたい」という深層心理もある気がする。何かを選んで失敗したら、他人のせいにできる。「あのクライアントがこう言ったからうまくいかなかった」みたいな感じ。なので、「意思決定の代行業」と、「責任の保険業」みたいな側面もあるのかな。
— DAI (@never_be_a_pm) August 13, 2020
〇ポイント:非合理な意思決定
メリット:他人に決めてもらえるので、決定に対して力を使わなくて済む。最終的に決められる。
デメリット:意思決定の質が下がる(=後悔する可能性が増える)
占いみたいな非合理な意思決定に頼るときって、要は適当な根拠で「決めてもらいたい」んですよね。
人は人に指図されたくない、勝手に決められたくないと自分では思っているけど、意味不明な根拠で「あなたの手相的に来年結婚します」と言われると、つい信じてしまう。合理的な根拠に基づいて、複数の選択肢を与えられるよりも、適当な根拠で他人に決めてもらう方が嬉しい人の方が実は多かったりする。
— DAI (@never_be_a_pm) August 13, 2020
自分で決めると、
・決めたことの責任を取らなければいけない
・決めることの体力を想像以上に使う
となるからです。
「指図されたくない」けど「決めてほしい」という選択の深層心理
人って一見、誰からも指図されたくない生き物のように見えるんです。
自分のことは、自分で決めたい
そう思っているように思えるんですが、実は
・あまり考えずに、ベストな選択をしたい
というのが深層心理なような気がしています。
実際にこういう思考をスキップするような認知バイアスは人間に多く組み込まれています。(例えば、みんながいい!と言っているものを信じてしまうバンドワゴン効果など)
https://dividable.net/marketing/marketing-cognitive-bias
レビューメディア・オピニオンメディアのゴールはユーザーが「決められること」
僕自身がメディアの方針として、一次情報を仕入れて、なるべく分かりやすく伝えられるようにすることをポリシーにしています。これは合理的な選択を助けるためです。
でも、結局ユーザーにとって一番のメリットは、多分「比較検討できる」ではなくて、「決められる」ことだと思っています。
つまり、合理的な意思決定の判断軸を持ってもらいつつ、最終的には相手の選択の手助けをできることが、ゴールになるんだと思います。
客観的な選択肢だけを提供するのは、多分決められない。
信頼できる誰かの意見を信じて、人は意思決定をします。
だから責任をもって、決めてあげること。これが実は大事なんじゃないかな~と思っています。
サポートでいただいたお金はFanzaの動画を購入するために利用されます。
