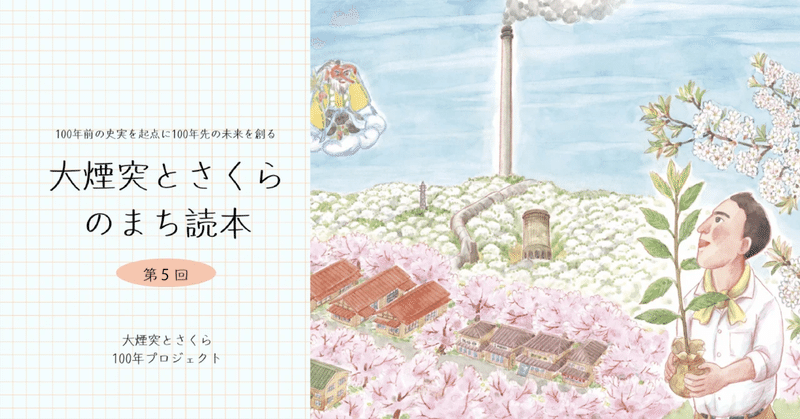
日本最古の地層から宝が出る山
日本最古の地層
日立市は、海と山にはさまれた細長い地域に発達した町です。日立市の6割は、阿武隈山地の南部、多賀山地と呼ばれる低い山地で占められています。
2003年茨城大学名誉教授の田切美智雄氏は、日立市小木津山自然公園入口付近にある花崗岩が5億500万年前のカンブリア紀(※1)の、日本最古の地層であることを放射年代法(※2)により発見しました。その後、研究が進み、2008年には日立市の山に広く連なる赤沢層全体が約5億年前のカンブリア紀のものであることが、2014年には赤沢層の銅鉱石が5億3300年前のものであることがわかりました。
日立市には日本最古のカンブリア紀の地層が日本で唯一広がり、その岩石は小木津山自然公園や神峰公園、御岩山など身近な場所で露出しているのを見ることができます。

なぜ日立にカンブリア紀の地層があるのでしょうか?
日立の地層は、およそ5億年前のカンブリア紀にゴンドワナ超大陸のはずれでプレートの沈み込みによって生じたマグマから形成されました。その後中国大陸の上に乗って赤道付近に移動し、次に北上して現在の中国東北部付近に移動します。2000 万年前頃から日本海ができ始め、日本列島は1450 万年前頃にほぼ現在の位置へと移動しました。
日立のカンブリア紀の地層は、日本列島がユーラシア大陸から分かれる際に、中国東北部にあったカンブリア紀の地層の一部が日立に運ばれてきたものなのです。
日立の山での鉱山開発
中世から戦国時代にかけて、日立の山々は佐竹氏(※3)の領地でした。佐竹氏がこの地域の支配権を確立したのは、源昌義が佐竹郷(※4)に定住した天承元年(1131)の頃からと言われています。以後慶長7年(1602)に徳川氏により、秋田に移されるまで、およそ500年間この地域を支配下に置きました。
佐竹氏は鉱山開発に力を入れ、その鉱山技術は全国屈指でした。八溝金山を始め、領内に多くの金山を抱え、越後、佐渡に次ぐ金の産地でした。
日立の山での鉱山開発も、佐竹氏の時代に始まります。御岩山(※5)の賀畏礼の岩峰の北側直下には、「佐竹坑」呼ばれる採掘坑の跡があり、大久保の金山は佐竹領内でも主要な金山でした。
佐竹氏が秋田に移される際に、佐竹藩の鉱山技術も秋田に移り、日立での鉱山開発は、活力を失います。赤沢銅山も、水戸徳川家や紀伊國屋文左衛門などが採掘を試みるも、鉱毒水の問題や銅鉱石の品位が低く採算が取れないということで開発が進みませんでした。
日立の山での鉱山開発が本格化するのは、明治時代に久原房之助が日立鉱山の開発に着手してからになります。
文=宗形 憲樹
(※1)カンブリア紀
古生代前期で、約5億4100万年前から4億8500年前とされる。カンブリア紀の地層は、日本では日立市と常陸太田市で発見されている。
カンブリア紀には、生物の種類や数が爆発的に増え、現在地球上にいる生物の大グループ(門)がほとんどすべて出揃った。この爆発的な進化は「カンブリア爆発」と呼ばれる。
日立のカンブリア紀の地層から化石が見つかれば、画期的な発見となる。
(※2)放射年代法
物質に含まれる放射性物質の半減期を元に物質の形成年代を調べる方法。
(※3)佐竹氏
平安後期から茨城県北部に拠点を置いて勢力を拡大し、豊臣秀吉の時代に常陸国の大半を支配下に置いた大名。関ヶ原の戦いに参加しなかったため、徳川家康に秋田への国替えを命じられた。
(※4)佐竹郷
現在の常陸太田市。
(※5)御岩山
奈良時代編纂の『常陸国風土記』に出てくる「賀畏礼の高峰」が御岩山の古称という説が有力。縄文時代の祭祀遺跡もあり、古代から中世にかけては修験者の修行の場となっていた。江戸時代には、水戸徳川家が御岩神社を建立し、代々の藩主が参拝する祈願所に。近年では、全国有数のパワースポットとして人気。
御神木である三本杉は、林野庁の全国「森の巨人たち百選」茨城県で唯一選定されている巨樹。この杉の三又のところに昔天狗が住んでいて、人が近づくと、いたずらしたり、脅したりしたという伝説がある。御岩神社は、修験道の修行道場として栄えていたため、修行中の山伏の数が多く、このような天狗伝説となったのだろう。
【主な参考文献】
『茨城県北ジオブック』(茨城県北ジオパーク推進協議会・茨城大学県北ジオパーク委員会/茨城新聞社/ 2022 年)
月刊『地図中心 572 号 特集日立市=最古×最先』(日本地図センター/ 2020年)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
