
人口増加による危機とセレンディピティが産んだ栄養食品チーズ
今回からポール・キンステッド著『チーズと文明』を読む。まずは、第1章チーズの起源古代南西アジアだ。
アペルは羊飼いに、カインは地を耕すものに
私たちの人類は、聖書によると、最初に農耕と牧畜を始めた。神は、アペルの差し出した柔らかい子供の肉と油を受け取った。そのアペルは、カインによってすぐ殺される。牧畜、どうなる!(もう少し旧約聖書を読み進めると、農耕を始めたカインの孫によってまた牧畜が再開された、と。)
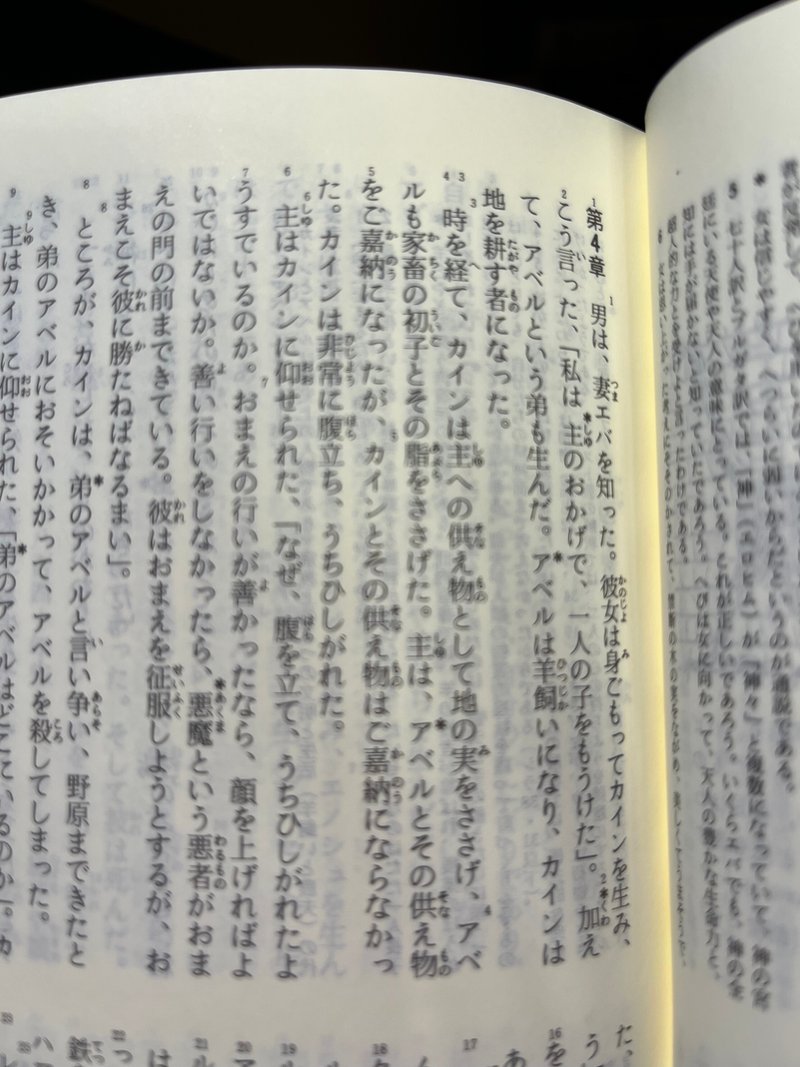
人類に迫る人口爆発による食糧危機を救うのは?
チーズが生まれたのは、新石器時代、人類が農耕と羊やヤギの飼育をベースにした混合農業を始めた頃、肥沃な三日月地帯だった。その頃までには、木の実の収集生活から、定住可能な穀物を選び出し育て、周りの土地で家畜を飼い始めていた。定住によって、技術革新、さらなる穀物の生産性向上によって、人口増加がその土地の規模を上回り、食糧危機が迫る。さらに、周辺の土地の劣化、森林破壊、侵食による環境破壊が進む。未来が危うくなったための打開策が、家畜のミルクの活用だった。
最初に現れたのは、煮て、酸を加えて固めたトルコのCOKELEKに似たチーズ。リコッタチーズの一種だ。たまたまミルクが温められたり、酸が入ったことで、ミルクが固まる。ミルクには、赤ちゃんには分解できるが、大人にはできないラクトースを含む。ミルクを凝固することによって、カートと(ラクトースを含む)ホェイを分離できる。それによって、大人でもお腹が痛くならないミルクの凝固物がチーズとなったわけだ。
この作成に必要な保存するための容器と、塊を濾すための道具も作られた。その当時のチーズは水分が多く、長期保存には向かなかったようだ。そのため、塩や密封容器で工夫した。
人間が世界を改変する可能性を持った時代
チーズの製作も素晴らしいのだが、今回の章で興味深かったのは、人間の環境に対する態度の変化だ。スコットの『反穀物の人類史――国家誕生のディープヒストリー』によると、人類は、木の実や動物を求めて着の身着のまま、危険はあるが自由満載の狩猟生活から、定住生活へ変化したことによって、穀物の世話に追いまくられるようになった、と。つまり、飼い慣らされたのは、我々人類だったのだ。そして、集団で生活することで、ウイルスで病気になったり、安定の代償に得た負の側面もあった。

しかし、定住生活はやはり人類にとって、かけ甲斐のないものだったようだ。道具の革新だけではなく、芸術性や、信仰が開花したのだ。また、定住は、自分の住む場所で暮らすための習慣や文化、歴史を作り出す。そして、雑草や動物を繁殖と飼育によって飼い慣らし、自分の世界を作り上げていった。つまり、環境を人工的に改変し始めたのだ。それによって得た充実感を描き、同時に、自身が生きることを問い始めたのだ。
それに最初から寄り添っているのが、チーズというわけだ。なんのことはない、今も古代も、私たちはチーズを食べながら、自分のしてきた事について、思いを巡らしているのかも・・・しれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
