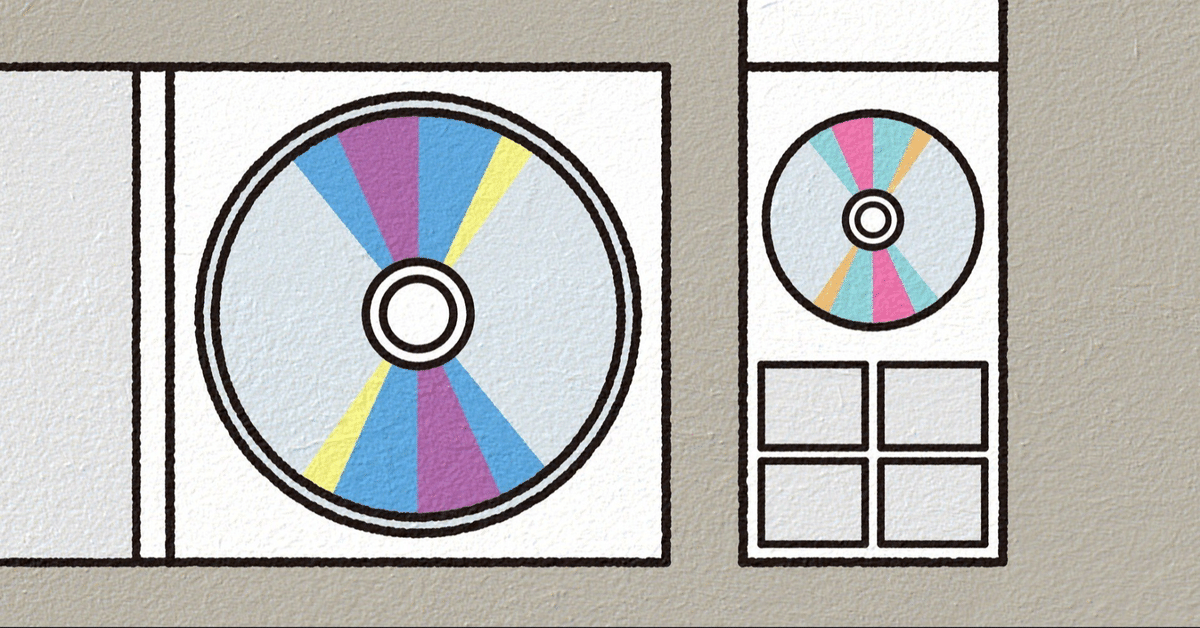
Problem/Issueから始めよう
The most serious mistakes are not being made as a result of wrong answers.
The true dangerous thing is asking the wrong question.
(最も重大な失敗は、間違った答によって発生するのではない。本当に危険なのは誤った問いを発することだ。)
ピーター・ドラッカー Peter Drucker
(20〜21世紀 オーストリアの経営学者 1909〜2005)
こんにちは、システムデザイン研究所(SDL)のともです。
仕事柄、会社を始めようとか、始めたばかりなので話を聞いてくれないか、と言われることがよくあります。
いろいろと面白い話を聞かせてもらうのはいつも楽しいものです。そんな中で、必ずと言っていいほど議論になるのは、
「今考えているソリューションでは(言ってるような問題は)解決しないのではないの?」
っていうところです。
ああだこうだと話をした後、こんな返しが出てくることがあります。
「わかってるよ、まだこのテクノロジーは開発中で、とてもじゃあないけど万人の悩みを解決できない。でもね、今取り組んでいる問題は人類共通の問題なんだよ。エキサイトするに決まってるさ。」
また、ここで議論白熱。そのまま夜更けまで、なんていうこともあったり。
自分でもそれに関係する記憶があります。昔話なのですが巷のインターネット回線スピードが今のような速度にはならないなんて言われていた頃、高画質の映像を利用するには、大容量の記録メディアが必要になる!と言うものでした。そこで注目されたのが光ディスクです。
ビデオカムが登場して、VHSやβなんていうビデオテープに記録・再生していた時代が本格化し、日本の家電メーカーがこぞって様々な光ディスクシステムを開発しました。代表的なデータは映像でしたが、そういえばマルチメディアなんていう言葉も色々なところで耳にしたような覚えがあります。DVDやBlu-rayなんていうのは今でも光ディスクの代名詞のように残っています。
1990年代から2000年初頭にかけて、光ディスクは世の中に映像が溢れるきっかけをつくりました。その当時開発にあたっていた人は皆、このまま光ディスクがあらゆるデータの格納庫になると期待していましたが、インターネットの普及がどんどんと進み、最初はMP3や様々な圧縮形式でデータが送受されるようになり、さらに様々なWebサービスやクラウドシステムの普及により、あっという間に光ディスクの役割が小さくなっていきました。
テクノロジーの進化は止まりません。私は記録消去が可能な光ディスク開発をしていた当時、如何に短波長のレーザー光源で高密度に信号を書き込み消去できるかに集中していました。開発はとても大変でしたが、規格化に成功したものもあり技術者としてはとても誇らしかったのを思い出します。
今の時点での描像になってしまいますが、私が光ディスクの開発をしていた時の様子を振り返り以下のようにまとめてみました。

新しい製品や技術を開発しようとするときに、目の前にある課題にタックルするのはとても大事ですが、開発を取り巻く環境をもシステムと捉えることができたら、もっと俯瞰した形で開発を進められたのだろうなと思います。きっと当時の光ディスク開発を主導した方々には、そんなビッグピクチャーがあったのでしょうが、それが末端の皆にまで行き渡っていたら、なんて思います。どういえばいいでしょうか、ビタースイートな感想です。
何を問題・課題と置くか、でその後の動きが変わります。また、永遠の課題のように見えて、時間と共に変化していくものもあります。
今取り組みたい!と思うことの周りにあることを、こうしてまとめてみることで、未来を予言しつつ、新たな技術開発に取り組んでみてはいかがでしょうか。
というわけで、今日は金曜です。週末何をしてみようかと考えながら音楽を聴いて過ごしたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
