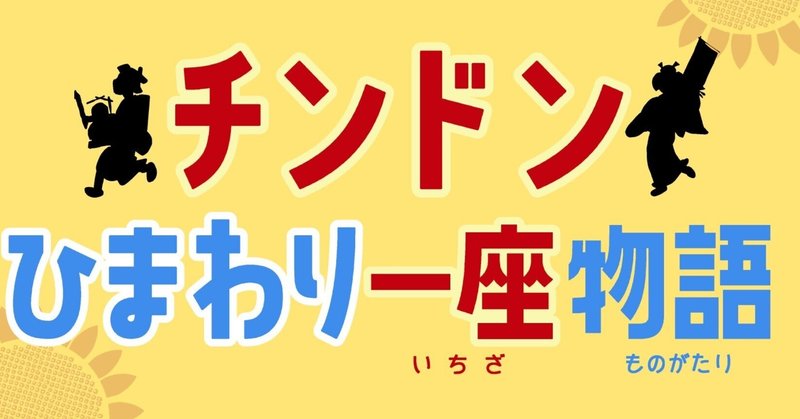
「チンドン平和紙芝居」はこうして誕生した!
【きっかけは『女性たちの原爆』の完成披露試写会】
令和4(2022)年2月以降、テレビのニュースでは連日のようにロシアの侵攻によるウクライナの被害を伝えていた。学校や病院の建物が破壊される映像が映し出され、心を痛めた。
4月14日。
脚本(シナリオ)を担当した国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館の映像シアター『女性たちの原爆』の完成披露試写会へ出席した。そこでイラスト担当の漫画家マルモトイヅミさんと久しぶりに再会。その会場で、高比良則安追悼平和祈念館館長から、私たち2人にひとつの提案があった。

「原爆の展示が怖くて原爆資料館に行けない子どもたちがいる。そんな子どもたちのためにかわち家(河内隆太郎)さんに平和紙芝居の制作をお願いしたので、一緒に協力して作ってくれないか」
私は、未来の世界平和を担っていく子どもたちに向けた平和紙芝居は必要だと思うし、原爆資料館の展示物を怖いと感じる子どもたちにも、マルモトさんの描くイラストを見せながらチンドン屋のかわち家さんが語ることで、受け入れやすくなり、子どもたちの平和を考える入口になれるのではないかと考え、高比良館長の提案に賛同した。マルモトさんも同じような気持ちだったと思う。
【かわち家さんのためらい】
その2日後、さっそくかわち家さんから相談あり、4月26日、3人で昼食をとりながら話し合いをすることになった。
私とマルモトさんはあくまでも協力する立場。制作の決定権は(仕事として)平和紙芝居を実演するかわち家さんにあった。だが、かわち家さんはその時点でまだためらっていた。私たちは彼の胸のうちに平和紙芝居制作への葛藤があることを知った。
かわち家さん曰く、子どものころ原爆の展示を見て恐怖を覚えて以来、これまで「平和」活動には距離を置いてきた。だが、ウクライナの被害を見ていると、何かしなければとの思いもある。今回の高比良館長の提案は、子どものころの自分の恐怖と重なる部分があり、自分が平和紙芝居を演じることで、子どもたちが怖がらずに平和を学び、原爆の実相について知る入口につながればとの思いも出てきた。
【平和紙芝居の制作開始】
このような経緯で、かわち家さんは平和紙芝居の制作を決断する。まずは3人でストーリーの方向性をざっくり打ち合わせし、私が脚本(シナリオ)を書き始めることになった。
しかし、正直、スポンサーはいないし制作にかかる予算背景はゼロだった。そこで、制作費を捻出しようとある平和事業の補助金制度に応募したが、結果は残念ながら落選。この結果を受けて、制作を継続するか中止するかの判断を迫られた。そこで、これまでの経緯も踏まえて、ボランティアでもいいから制作を進めることに舵を切ることになった。
6月14日。
私は8月に開催予定の親子記者事業の編集会議に出席した。この事業は日本非核宣言自治体協議会の主催で、全国から小学生と親(保護者)を長崎に招待し、長崎の平和祈念式典や平和活動を取材してもらい、親子平和新聞『ナガサキ・ピース・タイムズ』を発行するというもの。私が創刊以来15年間編集ボランティアを続けている事業だ。私は会議で、かわち家さんとマルモトさんへ(親子記者による)取材と、その場での平和紙芝居実演を提案した。紙芝居の初披露には絶好の機会だと考えたのだ。
【初稿から第3稿、チンドン屋家族の物語へ】
6月18日。
脚本(シナリオ)の内容を考える段階で、チンドン屋や大道芸人の仕事が戦時中に禁止されたことを知り、平和紙芝居の初稿は、戦前、戦中、戦後のチンドン屋の歴史と、長崎原爆の被害状況をからめた内容に組み立てた。しかし、かわち家さんから実演しづらいとの意見があり、その日の夜の第2稿は、長崎のチンドン屋家族の物語(フィクション)に大きく変更した。子どもの視点を大切にしようと、チンドン屋夫婦の息子(小学生)を主人公にすることにした。19日の第3稿では、かわち家さんが実演しやすいように家族のセリフを追加した。22日、マルモトさんより大ラフも届いた。
【親子記者事業で初お披露目】
その後の制作は、親子記者事業での初披露を目指して進行した。
7月7日。2回目の親子記者編集会議で、かわち家さんとマルモトさんの(親子記者による)取材と平和紙芝居の実演が正式に決まった。
7月29日。平和紙芝居の脚本(シナリオ)とイラストの最終校正。
8月1日。脚本(シナリオ)とイラストが完成。タイトルは『チンドンの音が長崎のまちから消えた チンドンひまわり一座物語』に決まった。

親子記者事業の取材と初実演日が8月8日に決まる。
そこで8月3日、3人で打ち合わせとリハーサルを行なうことに。かわち家さんが実演して見せ、子どもたちに伝わるかどうかの視点で、私とマルモトさんが意見と感想を述べ合った。それを受けて、かわち家さんは実演内容を修正していき、本番に備えた。
8月8日の午後。
初お披露目の日。たまたまNHK秋田放送局が秋田市から参加した親子記者の同行取材に来ていた。その関係で、かわち家さんの平和紙芝居初実演がテレビカメラに収録されることになった。この初実演と(親子記者による)取材の模様は後日、NHK秋田放送局と長崎放送局のニュース番組で紹介され、幸運にも全国放送のNHK「おはよう日本」でも紹介された。



【実演時に配るポケット冊子の制作】
10月7日。読売新聞地方版に平和紙芝居の紹介記事が掲載された。
10月29日。長崎平和推進協会主催の「市民のつどい」で2度目の平和紙芝居実演が行われた。これがかわち家さんの平和紙芝居初仕事となった。この日は高比良館長とマルモトさんと私も見学した。「市民のつどい」の模様は、11月28日の長崎新聞に記事紹介された。

令和5年2月。
かわち家さんが平和紙芝居を実演し、子どもたちに平和や原爆の実相に関心を持ってもらったところで、以後、継続的に平和を考えてもらうために、「なぜ戦争をしてはいけないのか?」「なぜ核兵器を使ってはいけないのか?」などをまとめたポケット冊子の制作を(個人的に)始めた。
マルモトさんのイラストを使った、子どもたちに配布するポケット冊子は、3月1日に完成。その冊子には、国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館の被爆体験記執筆補助の仕事で、私自身が8年間で被爆者や被爆体験者約100名から聞き取った「若い世代へ伝えたいメッセージ」の内容を込めたつもりだ。

このポケット冊子は、かわち家さんとマルモトさんと私で、高比良館長に完成報告した後、かわち家さんが紙芝居の実演で訪れた、長崎市立山里小学校の3年生に配られた。
【今後の抱負】
こうして、4人(高比良館長、かわち家さん、マルモトイヅミさん、私)のそれぞれの平和への思いが、ひとつのカタチになり、チンドン平和紙芝居は完成した。
今後の希望としては、ひとりでも多くの子どもたちに見て聴いてもらいたい。それから、かわち家さんの(仕事としての)実演と並行して、学校の先生や児童・生徒などたくさんの人々に平和紙芝居を実演してもらい、平和について考えてもらいたい。そのための実演ツール(テキストデータ、画像データ、説明書など)も配布していきたい。さらに言えば、原作者として、この物語が将来的にアニメ、ドラマ、映画、舞台などに発展していってくれればと願っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
