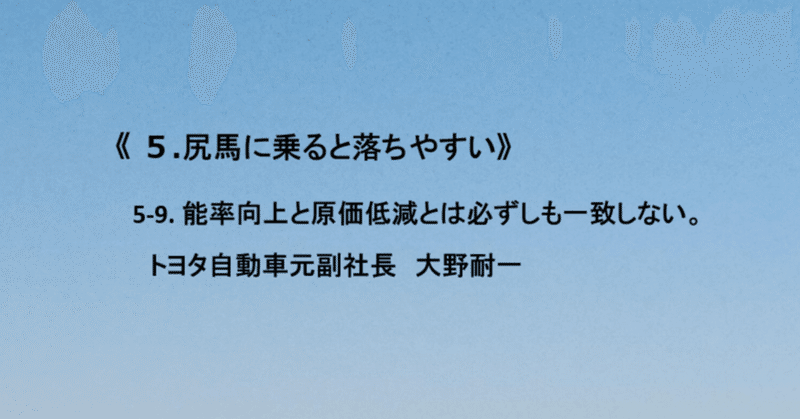
5-9. 能率向上と原価低減とは必ずしも一致しない。
トヨタ自動車元副社長 大野耐一
製造ラインから言えば、「現在1日に100個しか生産できないのを、工程を改善して120個できるようにした」のならば、これは20パーセントの生産性向上である。こうした改善は原価低減につながる有効な手段だ、というのがこれまでの考え方であった。
能率が向上すれば、その分だけ単価が下がるのが普通である。
しかし、大野耐一はそうではないと言う。これが、そもそもカンバン方式とかジャスト・イン・タイム(JIT)と呼ばれるトヨタ生産方式の出発点になった疑問である。
能率が向上しても原価は下がらないのではないか。この疑問に対して、トヨタ生産方式の生みの親である大野耐一は次のように答える。
答えは2つあって、どんな状況でそれが行われたかによる。
一般に、製品の1個当たりの単価は以下の式で計算される。
製品1個の価格 =総コスト/ 生産数
(1) この改善が増産期に行われた場合
1日に100個しかできなかったものを、120個の生産計画を立て、それを人の増員 なしに達成することができれば、人件費の分などの費用が少なく済み、この20パーセントの生産性向上はそのまま原価低減になる。
(2) 改善が減産期である場合
しかし、1日の受注が90個に落ちた中で、120個への増産改善が行われても、製品 は売れ残り毎日30個余ってしまう。これでは材料費や労務費を先払いすることになり、しかも在庫というタチの悪い居候を養うことになる。だからコストアップになってしまう。
では(2)のケースで、改善で原価低減するにはどういう能率向上が必要なのか。大野は言う。
1日の必要数100個を今10人で作っているならば、それを8人でやれるようにすればいい。80個を作るなら7人でやるように改善しなければいけない。こうしないかぎり、能率向上はかえってマイナスになってしまう。
トヨタ生産方式では、必要数が変わらない時や減産している時に生産量を増やしてしまう能率向上を、「見かけの能率」とか「計算上の能率アップ」と呼んでいる。
大量生産時代と多品種少量生産時代のもっとも大きな違いが、この生産性向上の考え方なのである。生産量を増やすというねらいで効率化を図ると、作りすぎのムダが生まれる。その結果、工場には在庫があふれ、コストを計算すると、かえってコストアップになってしまうのである。
これと同じことで、生産時間を短縮するのがいつもいいというわけではないと大野は言う。
「スピードの速い設備が必ずしも生産性が高いわけではない」
工場では一般に、「生産性の高い設備」イコール「スピードの速い設備」と考えがちである。しかし、前述した例と同じように、これも増産時代にしか通じない考え方なのである。
実は、この大量生産時代と多品種少量生産時代の違いが、中国と日本の製造業の質の違いである。世界の工場と豪語しても中国の効率は生産量に支えられたもので、日本と中国の1品1品の作り方の質の差は、いかんともしがたく大きい。
大量生産の時代から多品種少量生産の時代になれば、当然のことながら、生産の仕組みだけでなく販売の仕組みも変わる。新しい販売の考え方が求められるのである。
多くの百貨店が売り上げ減に苦しんでいる1900年代に、一人勝ちといわれるほど業績を伸ばしていた百貨店があった。それが東武百貨店である。山中鏆社長は、東武百貨店のモットーを社員に次のように言う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
