
囲碁棋書と理論書の刊行 中国明代
南宋、金、西夏に分裂していた中国はモンゴル帝国の侵攻により再び統一され元が建国される。元代に囲碁は『玄玄碁経』が刊行されたものの全体的にやや停滞傾向を見せていた。しかし、元の滅亡後の明代になると初代洪武帝、三代永楽帝の活躍により国力は充実し領地も拡大、国内が安定し囲碁は大いに普及していく。
なお、明は一三六八年に建国され一六四四年に滅亡、二七六年続いている。ちなみに日本では室町幕府の三代足利義満が征夷大将軍に就任した年から江戸幕府三代将軍徳川家光の時代までである。
明代初期の洪武帝、永楽帝はいずれも囲碁を愛好し、側近を相手に囲碁を打ったという記録もあるが、囲碁の名手を庇護育成する意思はなく、唐宋時代にあった棋待詔制度の復活はなかった。これに代わり棋士を支えたのは、官僚の好棋家であった。明代の士大夫は囲碁を単なる盤上ゲームとしてではなく、中国文化の一分野として捉えていたようだ。
中国ルールの成立
いわゆる「中国ルール」と呼ばれる囲碁の計算方法が地計算から石数計算へと変化したのは明代である。これを解明したのは、ハーバード大学で中国史を講じた楊聯陞(一九一四~九〇年)の論文「中国圍棋數法變更小考」である。これによって、北宋末に成立した『忘憂清楽集』上巻に収録されている実戦譜が地計算に拠ったものであることが明らかとなった。現代でこそ「中国ルール」は終局後の計算方法が日本や韓国と異なり、地計算でなく石数計算となっているが、昔は中国も日本や韓国と同じ地計算であった。例えば唐の時代、日本では奈良時代になるが吉備真備入唐の対局での逸話でもわかる。吉備真備が入唐したときの対局の記述にアゲハマ一つを飲み込んだというものがあるが、石数計算であれば盤上の石の生存により計算するので、取られた石を数えることはない。これは伝説であるが、そういった伝説が残されているということは、その頃は地計算で行われていたと言える。
囲碁史の成立

囲碁の歴史をまとめたいわゆる囲碁史が初めては成立したのは明代のことである。盛唐の詩、秦漢の文を尊ぶ古典主義を唱えた王世貞(一五二六~九〇年)は、現存する最古の中国囲碁史『弈旨』を著わしている。馮元仲は王世貞にやや遅れて『弈旦評』を著わし、両著によって中国における囲碁史の流れが明らかになった。
囲碁の構造・本質を解明しようとする囲碁論は、明代では後漢・北宋時代の考えの解明について進展を見る。即ち、林應龍は『適情録』第二〇巻で「五音諧律呂局」以下七図を掲載して囲碁と易・五行説、天文暦法等との関係を論じている。『適情録』は一九八〇年には日本で解説書二冊とともに組本社から翻刻刊行、第二〇巻は中国人の易研究家景嘉が解説している。
林應龍に次ぐ論者は、汪廷訥である。多くの戯曲と詩文、囲碁の書を著した汪廷訥の著書『坐隠先生訂譜全集』土巻以下にいくつかの論考が記載されているが、後に言及する。
最接は明末に刊行された徐應橡の『柯枰新印』全一巻である。この中に囲碁の本質に関する原始卦象図、範數図、四聲図、路名図の四図がある。
囲碁を意味する語としては、弈と棊又は囲棊がある。後漢の許慎の著わした辞書『説文解字』によると、弈は本来囲碁を意味する語であったのに対し棊は古代では囲碁を含む盤上ゲームの駒を意味した。その後、盤上ゲームの中で囲碁が最も普及して来ると、棊は碁石を意味する語となり、更に囲碁そのものを意味する語に昇格した。特に唐代になって棊待詔制度が出来、宋代に継承されると、棊は囲碁を意味する語として弈より優位になった。しかし、明代になるとこれが逆転して囲碁を意味する語としては弈が前面に出て、棊が大きく後退している。その理由として、第一に明代になって囲碁の構造、本質に関する考察が盛んに行なわれるようになったことが影響し、 盤上ゲームの駒から囲碁を意味する語に昇格した棊よりも、古来から囲碁を意味する語であった弈の方がより適切と考えられたのであろう。
第二には、明代の囲碁界を牽引していたのは王室ではなく官僚であった。具体的には明代中期以降の官僚・政治家の李東陽(一四四七~一五一六年)と王世貞の影響であろう。前者は『弈説』、後者には『弈旨』があり、両者とも官僚には大きな影響力を持っていた。共に古典主義を唱えていることから、棊よりも弈を使う事が好ましいということになったのかもしれない。
また、明代には長編小説の中に囲碁が登場している。『三国演義』や『西遊記』がそうである。『封神演義』でも殷の紂王が家臣と碁を打つ場面が出てくる。『封神演義』は殷(商)の時代を舞台に仙人や道士、妖怪が住む仙界と人間が住む人界が大戦争を繰り広げるという神話的物語だが、作者の許仲琳は史実かどうかはともかく随分昔から碁が打たれていたと考えていたのであろう。この頃のこうした物語や小説には囲碁の場面を登場させることが当たり前だったといえる。これらは中国の古典小説であるが、日本もこれらを元に、現代でも三国志(『三国演義』が原典)などで多くの作家が描いている。
朱権『爛柯經』
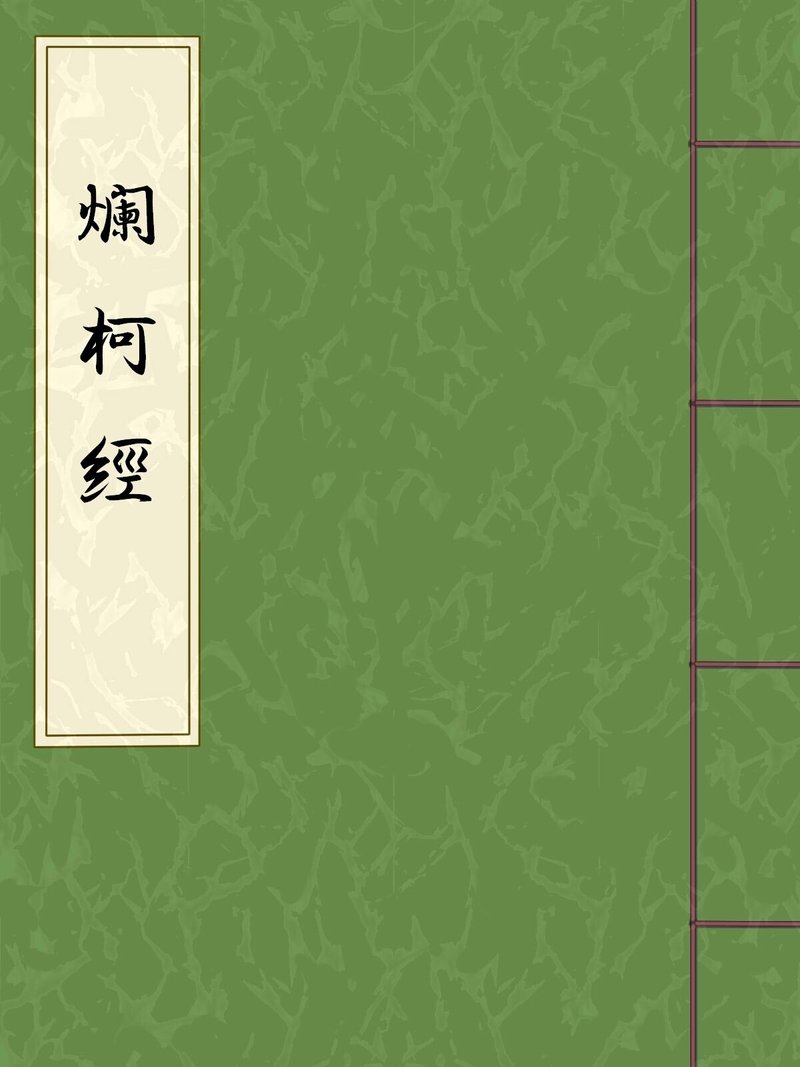
明代には多くの棋書が編まれている。それらについて中国囲碁史に造詣の深い囲碁史研究家香川忠夫氏の解説を元に見ていこう。
『爛柯經』は初代皇帝・洪武帝(朱元璋)の十六子で、明代を代表する文人でもあった朱権が著わした明代初期の棋書である。明代の棋書は多くなく、しかもその大半が萬暦年間(一五七三年~一六二〇年)に集中しており、初期のものは本書以外にはない。本書は元代の棋書『玄玄碁経』の影響を色濃く受けており、以降の明代の棋書は本書の形式を踏襲しているものが少なくない。
まずは建国間もない明の情勢と朱権の置かれた立場について説明しよう。
洪武帝こと朱元璋は貧しい農家の出身で中国を統一した希代の英雄である。洪武帝は明の都を南京に置き、内政に力を入れ官僚機構を整備し、中央集権を強固にした。反面、功臣を殺して皇帝の権力を強化し、二十五人の王子をことごとく地方の要衝に配置、そうして兵権を与え外敵に備えている。その中で最重要の北京には信頼する第四子燕王朱棣(一三六〇~一四二四年)を封じた。洪武帝は皇太子であった長子の朱標が亡くなると、朱棣を後継者にしようとしたが家臣らの反対により断念している。
なお、『明史』巻一一七によると、朱権は洪武二十四年(一三九一年)にモンゴルに近い大寧(遼寧省)へ封ぜられ、寧王と称している。
これらの諸王は父の洪武帝が健在の間は何事もなかったが、洪武三十一年(一三九八年)に洪武帝が没し、皇孫建文帝(朱標の子)が即位すると皇帝と諸王の間に骨肉の争いが起っていく。建文帝は側近の黄子澄等の献策により叔父に当たる有力な諸王を漸次廃していくが、これに反発した叔父の燕王朱棣と戦争が勃発(靖難の変)。四年におよぶ交戦の結果建文帝は敗死し、燕王朱棣が即位して永楽帝となる。いわば日本で起こった壬申の乱の中国版である。幸田露伴の『運命』は靖難の変を描いた名作である。
朱権はこの抗争には直接関係なかったが、永楽元年 (一四〇三年)南昌(江西省南昌)に移封されている。朱権は後年永楽帝から疑われ「精廬」にて隠棲しているが、それでもなお永楽帝在世中は絶えず監視されていたと考えられている。
この時代、諸王の立場は極めて不安定であり、朱権は永楽帝の弟であるから、永楽帝としては自分がそうであったように没後に息子のライバル足り得る存在として、その動向に絶えず目を光らせていたと推定出来る。朱権としては、政治的な識見や軍事的な才能を仄めかすことは危険であり、一度疑惑の目で見られると直ちに隠棲して芸術分野に没頭、政治的野心が無いことを示すことが最善の選択であったのだろう。朱権の諡が「献」であるところから朱権は寧献王と云われている。
朱権は臞仙と号し、博学多才、諸芸に優れ、琴や鼓を得意とし、演劇を愛好した。
青木正児博士の『支那近世戯曲史』 によると、 朱権は雑劇十二編を作ったが、現存するのは『沖漠子独歩大羅天』『卓文君私奔相如』の二編である。これによって朱権は明代初期の劇作家として中国戯曲史にその名をとどめている。
『爛柯經』は『明史』巻九八の芸文四において、林応龍の『連情録』『棋史』とともに明代の棋書として記載されている。なお『棋史』は亡逸している。『爛柯經』は現在中国や台湾の図書館にはなく、日本の内閣文庫の所蔵するものが天下の孤本となっている。ところで、内閣文庫には『囲碁機軸』と題する朱権の棋書も別に存在している。
『囲碁機軸』との相違は『爛柯經』は小型の二冊本であり、欧陽旦の序文があって成立年代が特定出来るのに対し、『囲碁機軸』はB五版の一冊本で、序文がなく成立年代が特定出来ない。序文を除く本文は両者同一であることから『囲碁機軸』は『爛柯經』の普及本として出されたと考えられる。
『爛柯經』の成立時期は欧陽旦の序によると正徳三年(一五〇八年)、朱権没後六〇年になる。この間『爛柯經』稿本は存在すら知られていなかったのであろう。『囲碁機軸』の成立は、この時期以降と考えられる。『適情録』の刊行は嘉靖三年(一五二四年)であるため、恐らく『爛柯經』は明代最初の棋書であろう。
『内閣文庫漢籍分類目録』は、所蔵漢籍の旧蔵者を略字で表示している。これによると『爛柯經』は「江」であり、『囲碁機軸』は「毛」である。「江」は林羅山旧蔵本で、羅山から昌平坂学問所、更に内閣文庫へと移管されたもの。「毛」は毛利家旧蔵本で、毛利家から紅葉山文庫又は昌平坂学問所、更に内閣文庫へと移管されたものである。
『爛柯經』の中で論説については、概ね『玄玄碁経』が踏襲され、若干の順序の変更と加減が行われている。即ち、「原弈」「弈旨」「序棊」「囲棊賦」の順に収録し「棊経十三篇」を「囲棊賦」の次に繰り下げ、更に「棊訣」を置き、最後に『玄玄碁経』にはない「囲棊三十二法」が記載されている。その上で「悟棋歌」「四仙子図序」は削除している。
棋譜中で「棋盤図」以下は『玄玄碁経』に準拠しているが、定石に相当する部分は省略されている。『爛柯經』の中心は勢という詰碁八十四題にある。これも『玄玄碁経』にならって各作品毎に史実や故事に拠った雅趣ある題名が付されている。その詰碁は八十四題中五十四題は『玄玄碁経』からの転載であるが、三十題は新しい詰碁である。
最後に朱権の稿本は刊本『爛柯經』の通りであったのか、言い換えれば「原弈」以下囲碁論説が当初から稿本にあったのだろうか。子孫または欧陽旦が付加した可能性もある。これについては推論になるが、私見では朱権の稿本に最初からあったと考える。その理由は『爛柯經』が構成を『玄玄基経』に準拠しているためで、論説も最初から稿本にあったと考える方が自然であるからだ。
この方式は明代の棋書『秋仙遺譜』『石室仙機』『石室秘伝』等にも踏襲されてゆく。
隠棲した朱権の晩年を推測すると、既に永楽帝が没して久しく、警戒より、むしろ忘れられた状態であったと思われる。朱権も隠遁生活が久しく閑雲孤鶴を友とし、その間に囲碁を愛好し、『玄玄碁経』に親しみその詰碁の玄妙さに魅せられたのであろう。そこで新しい詰碁を集めて『玄玄碁経』から引用したものと合わせて『爛柯經』を作成したのだろう。そして、これを稿本のまま秘蔵し上梓せぬまま死去したと考えられ、朱権の死後六十年を経過し、子孫がこれを発見して欧陽旦の序文を加えて刊行したと思われる。
『萬彙仙機棊譜』
『爛柯經』に続いて『萬彙仙機棊譜』について見てみよう。
明の朱常淓の著わした『萬彙仙機棊譜』は『続修四庫全書』に収録されている。明代の棋書は必ずしも少なくないが、著者の経歴が判明しているケースは稀である。台湾の囲碁史研究家朱銘源氏はその著書『中国囲棋話』及び『中国棋芸』で朱常淓の経歴を解明している。
『明史』巻一○四「諸王世表」には「潞簡王翊鏐穆宗嫡四子、隆慶五年封、萬暦十七年就藩衛輝府、四十二年薨。王常淓簡庶一子、萬暦四十六年就封、後以国亡寓抗州。大清順治二年六月、王師至遂降。」とある。
これによると明の穆宗は第四子朱翊鏐を河南省で潞簡王に封じた。朱常淓はその庶子であり、父の死後潞王を襲封した。然し、明末の動乱では抗州に避難して寓居し、その後清軍の侵攻により投降した。明滅亡後、清朝初期には各地に明の王族を擁立して明朝再興を図る動きがあったが、ことごとく清に討伐された。反面、清は投降した明の王族については迫害することなく好遇している。そのため朱常淓は専ら趣味に生き、穏やかな晩年を送ったと考えられる。尚、生没年は不詳である。
朱常淓は好棋家であるが、多趣味であり諸芸に秀で、敬一道人と号していた。
その点では『爛柯經』の著者朱権を彷彿とさせる。先ほども述べたが、朱権は明の洪武帝朱元璋の第十六子で、兄永楽帝による内戦の間に逼塞して専ら趣味に生きた人である。朱常淓は明の洪武帝十四世の子孫で、明滅亡後、晩年を同じく趣味に生きたという点では多分に共通している。
朱常淓は明末の崇禎七年(一六三四)、『萬彙仙機棊譜』全十巻を著わした。各巻の名称は数字に拠らず、十干で表示している。甲集には序文、跋のほか「原弈」「囲碁賦」「碁経十三篇」「碁訣」「三十二法」「十訣」等の囲碁論説があり、「碁経十三篇」には詳細な註釈が付されている。目次に次いで平上去入四隅格式図、四隅數目格式図及び囲碁三十二方式図等があり、更に『忘憂清楽集』所収の十図を収録している。
乙集から戊集までは布石が集約されており、己集から辛集までは定石、壬集から癸集までは死活が集められており、明代の実戦譜は収録されていない。
この棋書は明代の棋書の標準的な内容と言えるが、漢字の四声を碁盤の四隅に配置した「平上去入四隅格式図」と、碁盤の三六一の地点を全て縦横の数字で表現した「四隅數目格式図」が目新しいものと言える。
『坐隠先生訂譜全集』

もう一つ『坐隠先生訂譜全集』を紹介しよう。
全八巻、一二〇〇頁近くの大作であるが、棋譜部分は二割弱で、残りが編著者汪廷訥(一五七三~一六一九)とその友人の囲碁に関する詩文で構成されている。
汪廷訥は現在の安徽省歙県の西の休寧に生れた。生家は製塩業であったと考えられ、若年より家業に従事し成果を挙げたようである。明代では塩は政府の専売であり、その課税は国家の大きな財源であった。明代では官吏が大きな権限を持ち、経済的に非常に恵まれていた。汪廷訥は持ち前の才覚を発揮して塩運使に昇格したと考えられる。塩運使は塩行政の地方官であり、実務は副使以下が行うので閑職と考えられる。汪廷訥は閑職により時間的余裕があり、また地方官勤務として経済的にも余裕があったことから専ら趣味の世界に没頭し多くの戯曲と詩文、囲碁の書を著している。そして、その過程で多くの文化人と交際した。その大半が士大夫であった。
さて『坐隠先生訂譜全集』についてである。
首巻の題名の裏に「坐隠先生精訂捷奕譜」とあるが。巻数については数字ではなく金・石・竹・絲・匏・土・革・木の文字で表示されている。これは八音と称し、古代中国にあった楽器の材質を示すものである。八音の起源は『書経』にある。
棋譜の部分について述べよう。「訂譜小叙」「坐隠先生碁譜彙粹」と題する二編の文章があり、いずれも囲碁の打ち方の原則を記述したものである。次に「坐隠先生訂碁譜目録」上下があり、金巻には上巻が収録されている。内容は隅の定石であり、二十個が名称と変化図を付して記載されている。「坐隠先生訂碁譜目録」下巻は石巻に収録されている。互先布石、二子から四子までの置碁布石、さらに長生、隅から辺での死活、劫、渡、石の下、征(シチョウ)等の手筋を集めたものになっている。
『坐隠先生訂譜全集』は、汪廷訥の囲碁論説や詩文、そして棋譜さえあれば棋書として成立したはずである。しかし、汪廷訥は多くの士大夫と詩文詞曲を通じて濃密な交際を続け、囲碁も共通の楽しみであったと考えられる。その結果、棋書の刊行にあたってこれら士大夫の寄稿を受け入れたことで、棋書としては類を見ない構成となっている。
汪廷訥は後に官吏に登用されるが、二十六歳の頃には南京で環翠堂書房を開設し出版業に進出していた。ころ頃は戯曲に力を入れていたが、自ら出版業を兼ねていたこともこの刊行を容易にしたものと考えられる。
官吏が囲碁の書を刊行した背景
科挙の試験は官吏登用の方法として隋の文帝が五八七年に創設した制度である。この制度はその後の王朝に継承され、一九〇四年清の末期まで行なわれている。その方法は、郷試という一次試験が三年に一回、全国各地で実施され、合格者に対し会試という二次試験が首都で行なわれ、その合格者が官吏となる資格を持つ。北宋になるとその上に皇帝を試験委員長とする殿試が追加されている。この試験での成績がその後の官吏生活に大きな意味を持っている。殿試の合格者は進士と称して官吏に登用されるが、首席合格者を状元、二位を榜眼、三位を探花と称して待遇がよく、特に状元についてはあらゆる栄光がついて廻った。郷試の合格率は一〇〇人に一人で、会試の合格率は三十人に一人と言われている。
明代では科挙の予備試験の意味で学校が開設され、これも県試・府試・院試の三段階があってそれを通過した者には生員という資格が与えられた。生員は官吏ではないが、その予備軍として処遇され、その中から特に優秀な者を選抜して貢生の資格を得た者が官吏に登用された。一般に郷試から会試合格までは三〇〇〇人に一人という超難関であったため、合格者の知的水準は極めて高かった。中国の学問、文芸、芸術等は士大夫、即ち科挙の試験に合格した官僚がほぼ独占している。ここに紹介したように明代ではこれらの人々が囲碁に関する理論書や歴史書を著しているが、それは囲碁が当時の知的階級に親しまれていたゲームであったからであろう。
『適情録』

最後に、先に触れた『適情録』について述べておこう。
『適情録』は一五二五年に林応龍によって著されたが、そこには日本人僧の協力もあり日本人の囲碁水準がこのときすでに高かったことがわかる書とも言われている。
その日本人僧は虚中という京都東山建仁寺の僧である。虚中上人は明の弘治年間に中国へ渡り、杭州にて仏教を学ぶ傍ら、『忘憂清楽集』『玄玄碁経』などから囲碁の棋譜、定石、詰碁など三八四局を集め『決勝図』二巻にまとめている。そして杭州滞在中に親しくなった林応龍と共に再編に取り組むが、虚中が亡くなったため、林応龍が『玄通集』としてまとめている。
さらに二十年後の一五二五年に、『玄通集』を基に碁経、易経なども加えた『適情録』二十巻が作られ鎮江で刊行される。
「適情」という題は、王安石の詩の中の一節「忘情塞上馬、適志夢中蝶」から取ったと林応龍は述べている。
『適情録』は昭和五十五年に囲碁棋士の呉清源師、中国史学者でもある貝塚茂樹氏(京都大学名誉教授)等が中心となり復刻されている。『適情録』の原典は貝塚茂樹氏の父小川琢治氏が蔵書として大切にしていたものである。小川氏は囲碁の起源の章で何度も登場しているが囲碁史においては「支那に於ける囲棋の起源と発達」という論文を発表されていて、囲碁の起源に関して学術的な見解を初めて行った人物といえる。編纂委員で囲碁史家の林裕氏が中国を訪れてみたが、『適情録』は揃っておらず、当時全てを確認できたのは小川氏の蔵書のみであった。つまり小川氏の尽力がなければ『適情録』の完全な復刻はありえなかったと言える。その小川氏も『適情録』を自身の手で研究する前にこの世を去ることになり、その意志を息子の貝塚氏が継ぐことになった。
内容としては詰碁などの盤上のみの解説だけでなく、易経の解説を入れ、囲碁と数の関わりなども載せられている。囲碁の棋書の中では類を見ないものである。
王思任『弈律』
明の第十三代神宗の治世に王思任という人物がいる。この時期は豊臣秀吉の朝鮮出兵等があり明の国威が衰えてきている時期である。王思任はそんな時代を生き抜いた地方官であった。
王思任には『弈律』という著述がある。『弈律』は対局マナー違反に対する王思任流の罰則規定である。その中には罰金や鞭打ち、重いときには懲役というものまで記されている。罰金を払わなければ一年間対局禁止で観戦のみというものまである。
ではどういうものに罰則があるのか。碁を打つ者は歌を歌ったり、大袈裟な身振りで感情を表したりして相手の気分をかき乱してはならず、自分勝手な振る舞いをしてはならない。現代風にいえば、大きな声でボヤいて相手を間違いに誘導するようなことであろう。心当たりのある方も多いのではないだろうか。現代の大会等では注意されるぐらいかもしれないが、罰金や対局禁止、酷ければ懲役である。勝っている碁を「ダメだ」とボヤいたり、手のあるところを「そんなところ手が無いよ」と相手を安心させて他に打ったところ手をつける等は詐欺行為と判断されていたといえる。さらに観戦者が口出しするのはもっとも重いことだとされていた。
実際にこれが適応されたかはともかく、対局マナーと観戦マナーの厳守を愛棋家たちに徹底的に訴えものである。近代以前、日本でも中国でも碁を打つということに賭けが発生することがあった。それは囲碁史を通して見れば明らかである。賭けが発生する以上、不正があってはならない。『弈律』は厳格な対局マナーというより、不正に対する抑制のため著されたのかもしれない。
過百齢『官子譜』
過百齢という人物について述べよう。
常州府無錫県梁渓の名家に生まれ幼時から聡明で、十一歳のときに人の打っているのを見て碁を覚え、急速に実力をつけている。福清県出身の葉向高という碁に長けた省の教育長官が無錫へ視察に来た際、公用をすませたあとに誰か碁の相手はいないかと訊ね百齢が紹介された。はじめ葉向高は相手が子供だと驚いたが百齢が連勝し、北上に同行を誘ったが、百齢は学業を理由に断った。このとき地元の役人が省の長官にもっと気を使うようにと言うと、「道理を曲げて相手のご機嫌をとるなど私には恥ずかしくてできません。先方は賢明な方であり、このことで子供に対して怒るなどするはずがございません」と答えている。
その後、百齢はますます腕を上げ、その名は江南に響き渡った。何年かして北京の貴族へもその名が伝わり、百齢を北京に招く。当時北京には林符卿という名手がいたが、百齢はこれに勝って第一人者との評価を得たが、その後また無錫に戻っている。晩年には、百齢を凌ぐほどの力をつけた周懶予と対局し「過周十局」として知られている。
著書に『官子譜』『三子譜』『四子譜』がある。林符卿、周懶予、汪漢年、周東侯、汪幼清、盛大有など当時の名手たちの協力で作られ世に広まったもので、特に『官子譜』は幾度もの校訂を経て後々まで囲碁を学ぶために使われている。
『官子譜』について述べておこう。明の時代に過百齢によって著され、清の時代に陶式玉により編注、改訂され現在の形となった。終盤の死活や攻め合いなどの問題を集めたもので、詰碁の二大名著として『玄玄碁経』と並び知られているが、手筋の網羅性は『官子譜』の方が上回っている。死活だけでなく攻め合いやヨセの手筋など一四七八題が収められている。
王世貞『弈旨』『弈問』
宋代や元代には『玄玄碁経』などの囲碁書が編まれ、明代になると囲碁史書が成立している。王世貞(一五二六~九〇年)が著した『弈旨』である。これが現存する最古の囲碁史と考えられている。
王世貞は、二十二歳で科挙の試験に合格している。文才に恵まれ、盛唐の詩、秦漢の文を尊ぶ古典主義を唱えた十六世紀後半の明代で大きな役割を果たしている。
『弈旨』の冒頭では西晋の張華の『博物志』にある堯の囲碁創始伝説に触れている。また、囲碁に関する文献として以前紹介した班固の『弈旨』や『論語』、『孟子』を挙げている。
王世貞の『弈旨』は中国歴代の囲碁の名手の紹介が中心となっている。これまで紹介してきた人物たちである。つまり、堯の囲碁創始伝説から王世貞の活躍した時代までを記述した「囲碁人物史」ともいえる。また、囲碁そのものを論じた文献には言及していない。
王世貞には『弈問』という「囲碁史問答集」もある。『弈問』は客観性の乏しい囲碁史の出来事や伝説を取り上げ自説を述べたものであり、問答式の構成は現代でも珍しい囲碁論説の書である。
例をいくつか紹介する。
Q:王質が仙人の対局を見ているうちに斧の柄がボロボロになったのは本当か?
A:碁を創案したとされる堯の時代から現在まで三六〇〇年に過ぎない。斧の柄がボロボロになるには三〇〇年以上かかるだろう。だとすれば仙人たちは十局ぐらいしか打っていないことになってしまう。
Q:魏の王粲が崩れた盤面を復元したが高水準の棋力の持ち主か?
A:ある程度の能力がある人物なら復元できる。これをもって高水準の棋力とは言えない。
他にもあるが紹介しきれないのでこれぐらいにしておく。このように設問と答えが繰り返されている。伝説に関して理論的な解釈で反論しているものが多い。
王世貞が囲碁界に与えた影響は大きい。明代になると囲碁が広範囲に普及し技量水準も向上していった。名のある打ち手は腕を競い活躍していった。それだけではなく、囲碁史を著す文化人も登場してきた。王世貞がその先駆けとなり、やや遅れて馮元仲が『弈旦評』を著している。『弈旨』を基にしているが『弈旨』にはない囲碁文献も多く収録し、明代に成立した囲碁史として最も充実した内容となっている。
このように明代には様々な囲碁に関する書が出され、囲碁は大いに普及発展していったのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
