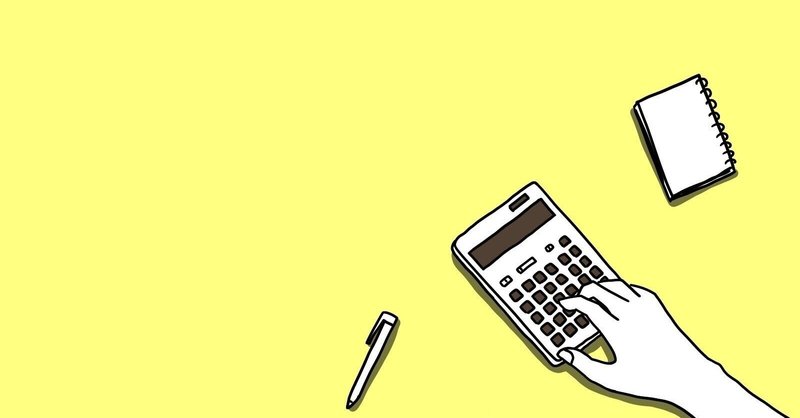
パンデミック下での基本再生産数、感染対策の強化と緩和について(8月2日こびナビspacesまとめ)
※こちらの記事は、2021年8月2日時点での情報を基にされています。※
2021年8月2日(月)
こびナビの医師が解説する世界の最新医療ニュース
本日のモデレーター:木下喬弘
木下喬弘
おはようございます。
岡田玲緒奈
おはようございます。
木下喬弘
どうですか皆さん、月曜の朝ですよ。
岡田玲緒奈
皆さんというほどまだスピーカーにあげられていないじゃないですか。
木下喬弘
今続々招待しております。
眠いですね。
黑川友哉
先生午前2時くらいまで会議だったんですか?
前田陽平先生(Twitterネーム「ひまみみ」先生)
はい、おはようございます。
木下喬弘
おはようございます。
もうね、夜8時から6時間会議するとなかなか疲れますね。
前田陽平先生
6時間の会議だったの?
木下喬弘
そうそう、3つあってですね。
正確に言うと4つだ。
一銭も発生しないです。
前田陽平先生
ああ、なるほど。
お疲れ様でございます。
木下喬弘
ありがとうございます。
前田陽平先生
やはり身を粉にして働いてますな。
木下喬弘
ふふふ、めっちゃ適当感が出ていますよ、コメントに(笑)
相変わらず。
前田陽平先生
いやいや、やはり先生に対する感謝の念を隠しきれないところが出たと思ったんだけど(笑)
おかしいなあ。
【テーマ1】 パンデミック下の基本再生産数の推定について
木下喬弘
もう日本がなかなかやばいですね。
前田陽平先生
あ、やばいですよね。
なんというか、ここまで「気をつけろ」と呼びかけていた人達がみんな全体的にあきらめムードになって、そういう発信をやめてる感というのもあって結構きつい。かなり。
木下喬弘
もうやりようがないんですよね。
前田陽平先生
まあ、みんな分かっている空気感というか。
もうそういう気持ちになるよねっていう気持ちは分かるんだけど。
木下喬弘
どうしたらいいんですかね。
前田陽平先生
うーん、やばいよね本当。
とにかくまあワクチンは打ってもらうことと、やはり密なことを避けてもらうとか。結局同じことを言わざるを得なくって。
もう響く人には響いて、響かない人には響かないというフェーズに入っているという感じを持ってしまっている人が多いのかなという気がしますよね。
木下喬弘
いや、おっしゃる通りでですね、僕ももう「自衛してください」としか言いようがなくて。でも分かっていると思うんですよね、聞いている人は。
前田陽平先生
うーん、そうなんですよね。
例えば、ここ聞きに来てくださっている方って分かっている方なんで、こういうことをここで呼びかけてもあまり意味がないかなって。
もちろん、新しい知識とかその定義とかコロナに関して新しいことを発信していく意義はあるんですけれども。
この聞きに来ていただいている方にそこをめちゃ強調してもなかなか難しいかなという感じがしますよね。
木下喬弘
いやあ、本当にね。
なんかマジでサンクスギビング(感謝祭)前のアメリカみたいな感じですよね。
「コロナってマジやばい」みたいね。
前田陽平先生
ああ、そうですね。
あとデルタ(δ)だとそういうデータがあるのか知らないであれなんですけれど、いわゆる集団免疫を効かせるために必要な接種率がどんどん高くなっている感じだから。
とにかく、もっと、よりたくさんの人に打ってもらわないとダメですよね。
当たり前のことなんですけれど。
木下喬弘
あの、遠ちゃん喋れたらあがって欲しいんだけれど。
CDC がデルタが水疱瘡(水痘)と同じくらいの感染力ということを言い出したんですね。
前田陽平先生
ああ、はいはいはい。
木下喬弘
水痘って基本再生産数が8から10ぐらいあるんですよね。
それがまあ本当なのかどうなのかという。
あっ、遠藤先生来た!
おはようございます。おはようじゃないけど。
遠藤彰
おはようございます。聞こえます?
すみません、今入ったばかりであまり文脈をきちんと聞けていないまま突然呼ばれていましたという感じです。
◆遠藤彰先生
PhD. Faculty of Epidemiology and Population Health, London School of Hygiene & Tropical Medicine. 2021.
MD & BSc. Faculty of Medicine, The University of Tokyo. 2017.
Twitter akiraendo @_akiraendo
https://twitter.com/_akiraendo
木下喬弘
CDC(アメリカ疾病予防管理センター)が「デルタの基本再生産数が水痘並みだ」と言い出したという話があって。これに対して西浦先生がツイッターで「え、ほんま?」みたいなことをおっしゃってたじゃないですか。
デルタって、大体実効再生産数が倍くらいになっているんじゃないか、みたいなデータが結構多くて、90%増とか。90%増ということは1.9倍。
もともとの non-VOC (変異のないウイルス)ですね、変異のないウイルスの基本再生産数が2とか3くらいだったら、倍になったら4とか6とかそれくらいになるんじゃないかと私は思ってたんですけれど。
そしたら、「まさかそんな単純な計算していないよね?」みたいに西浦先生がつぶやかれていて、私は一人で「やべえ」と思ってたんです。
パンデミック時の基本再生産数の計算って、どんなふうにするんですか?
遠藤彰
あ、なるほど。
そもそも基本再生産数の推定ってそんなに簡単にできるものではなくて、いろいろな限界がありながらやるという感じになるんですけれど。
基本的に、パンデミック下で基本再生産数を推定する時に一番よく使われるのは「一番最初に流行が発生した時に人口内にその免疫を持っている人はほぼいない」という条件の下で指数関数的に立ち上がってくるわけなんですけれど、「その立ち上がりの早さ」と、別個に「世代時間(どういうサイクルでその感染が次の世代にどんどん進んでいくのかという時間分布)」の2つの情報を使って推定するというのが一番スタンダードなやり方になりますね。
木下喬弘
平たくいうと「感染が一番最初に始まった時のスピード」と「1人の人から次の人にうつすまでに何日かかるか」ということを使って推定するということですよね?
遠藤彰
そうです。
木下喬弘
それで、いわゆる non-VOC の時は良かったと思うんですけれど、変異ウイルスってそもそも感染対策をしていない状態ではないし、免疫を持っている人が結構いる状態から始まっているわけじゃないですか。
遠藤彰
そうですね、おっしゃる通りですね。
基本的に基本再生産数の推定は、一番最初の時だからこそできる、ということですね。
現在は、 VOC(変異ウイルス)みたいに流行が始まっていて、人口内に免疫が一定数は存在するし、しかもいろいろな対策を取っていて、本来の自然状態じゃない状態で流行が起こっています。その状況でしか流行のデータが得られていないという条件だと、本来の意味での基本再生産数の推定は基本的にはできないですね。
実際に今1.5倍とか2倍とかいう風にいわれているのは、同じ条件下で複数の VOC が流行しています。
例えばオリジナルの株が流行している時に アルファ (α)が入ってきて同時に増えていったと。
あるいはアルファ が増えた後に、さらにデルタが入ってきた。そういう混合状態で、同じ条件下で相対的にどちらがどういう速度で塗り替えていくかという情報を使って、直接再生産数の推定というのはできないんですけれど、複数の変異ウイルス間の相対的な再生産数の比みたいなものを推定するということを、今やっているという感じですね。
木下喬弘
そうですね、そこは非常によく分かります。
私は直接どうやって推定しているかは知らないんですけれど、まあ「従来のウイルスに比べて90%伝播性が上昇しています」とか「アルファに比べて40~50%伝播性が上昇しています」みたいなことをいっているんだと思うんですけれども。
次に知りたいのは「伝播性が従来のウイルスに比べて90%増加なんだったら1.9倍」だと。
ということは基本再生産数は1.9倍になっているって言っちゃだめなんですか?
遠藤彰
基本的にはそれで問題ないと思います。
もちろん、いくつかの仮定は入ってくるわけですけれども。
普通に同じ条件下で Rt (実効再生産数)が2倍であれば、基本再生産数も相対的な比は同じという考え方で、特に問題ないんじゃないかなとは思いますけれども。
木下喬弘
あ、そうなんですね。
繰り返しますけど、アール・ノート(R naught 基本再生産数)の推定には、「感染対策をしていない」とか「免疫を持っている人がいない」という仮定があります。そうすると、既に感染対策をしていたり、免疫がある人がいる集団の中で流行が始まっちゃうと、この推定ができない。つまり、変異ウイルスについては、厳密な推定はできないですよね。
でも、一定の仮定を置けば、「実効再生産数は何倍になっているということは、基本再生産数もそれぐらいでしょう」みたいな推定をしていくのは、めちゃくちゃ的外れなことをやっているわけではないということですね。
遠藤彰
そうですね。
本当に細かいところを突っ込みだしたら、もちろんキリはないというか。
例えば人口内の異質性をどれくらい考えるのかも入ってきますが。そういうのも一旦置いて、とりあえずみんな均一な人口で考えましょうということであれば「ある時の実効再生産数の比が基本再生産数の比でもある」ということを考えても一つの考え方としては特に問題ないと思いますね。
木下喬弘
ありがとうございます。
峰宗太郎
ちょっとすみません、一個だけ突っ込んでもいい?
突っ込むというか聞きたいんですけれど、僕。
遠藤先生、世代時間って変異ウイルスの間で同じと仮定しているのは結構妥当だと思われていますかね?
そこが私は一番気になっているんですけれども。
遠藤彰
それはすごく適切かつ鋭い突っ込みですね。
おっしゃる通りで、世代時間の分布が「とりあえず(異なる変異ウイルスの間で)同じと考えていいだろう」という仮定の下で、相対的な増加率の比をそのまま再生産数の比に引き直して考えているということになります。そこが極端に違う場合には、流行の様子から見る増加率の比が、そのまま再生産数の比につながらないということにはなります。
今お話している1.5倍とか2倍とかいうのも、そこは世代時間分布が同じという想定をした上で出てきている推定値だと思います。
なので、そこが違う場合には推定値に多少の振れが出てくるということになりますね。
実際にデルタ変異ウイルスとオリジナルのもので世代時間とかが違うのか? というと、それは結構難しいと思うんですね。
その潜伏期間、あるいはウイルスが PCR で検出されるようになるまでの時間を考えるとデルタは若干早いという推定が最近出ています。
(検出開始が)早い一方で、感染性期間が伸びていたりすると世代時間の平均値でいうと必ずしも短くなっているとも限らないわけなので。
今細かい時間分布が分からない状況にあるので、とりあえずは現状できるベストの仮定として同じ世代分布時間を使ってやっていると思うんですが。
今後知見がアップデートされて、具体的に世代時間の分布が全然違っているということがもしわかれば、それを使って再度比を計算し直すことになるかもしれないです。
峰宗太郎
ありがとうございます。
すみません、木下先生。
奪っちゃって。
木下喬弘
いえいえ。
峰宗太郎
僕知りたかったの、もう一個あるんだけれども聞いてもいいですか?
ちょっとマニアックな話(?)ですけれども。
木下喬弘
どうぞ、どうぞ。
峰宗太郎
ワクチンを打っていくと indirect effect (間接的効果)が入ってくるじゃないですか、集団には。
そうすると先ほど遠藤先生もちらっとおっしゃってましたけれども、集団の異質性というのも年代ごとに打っている割合が違ったりしますし、周りにいるワクチン接種者率によっても変わってくると思うんですね。
そういう推定って今回モデルの中である程度入れて、デルタの増え方を見たりできるものなんですか?
遠藤彰
ええとですね、今回の具体的な CDC の推定にそれ(集団の異質性)がどのくらい入っているのか確認できていないので、現時点では何ともコメントができないのですけれども、どこまで厳密に基本再生産数を出したいか? という話になってくると思うんですね。
本来の定義通りの基本再生産数ということであれば、全ての人が一切免疫を持っていない条件を仮想的に作って、その中での増え方というのを見ていくということになると思うんですけれども。
例えば、この時点で真のアール・ノートを具体的に計算して比べることにどれくらいの意味があるかというと、もうある意味そういう理想的状態に人口が戻ることはないわけじゃないですか。ワクチン接種も始まっているので。
なので、そういう意味で異質性も全部考慮して、それを初期状態に返した時のアール・ノートを推定するということも、もちろん(理論上は)可能なんですけれども、実用的な意味というのはそんなに高くないかなと思っています。
峰宗太郎
ありがとうございました。
木下喬弘
ありがとうございます。
私もちょっと聞きたいことがあって。
もう一個、ずっといわれていることなんですけれど、オーバーディスパーション(ほとんどの感染者は誰にもうつさないが、極少数の人が多数の二次感染を起こしていく性質)、つまり過分散の問題があると思います。これは流行初期の時から西浦先生がずっとおっしゃっていますよね。
「Middle East Respiratory Syndrome(以降MERS)」のように、スーパー・スプレッダー(多くの人への感染拡大の感染源)がいて、基本再生算数のように平均値だけ見ているとわからないけど、実際には「1人の人が20人とかにうつす」っていう人が時々いるという話です。
クラスターが発生する状況で、一気に多くの人にうつるということで、誰にもうつさない人もたくさんいるけど、再生産数の平均値は上がっていくみたいなイベントがある、ということが去年の3月・4月とかくらいの知見だと思うんですよね。
西浦先生もツイートで、デルタの基本再生産数の議論の中で、オーバーディスパーションについて触れておられました。
私の質問は、デルタは「1人が100人にうつす」みたいなイベントが時々起きているから実効再生産数が上がっているのか。
そうでもなくて、平均的に感染が広がっているみたいなことなのか。
これって、どのぐらいわかってるんですか?
遠藤彰
これですね、知っている限りで「はっきり分かっていない」というのが現状だと思います。
そもそもオーバーディスパーションって個人レベルで感染者数、二次感染者数がどれくらい散らばっているかというのを示す値なので、基本的には毎日の感染者数だけのデータからは推定できないんですね。
実効再生産数の場合は単純に毎日の感染者数だけから、平均値なので推定できちゃうんですけれど、オーバーディスパーションは個人レベルのデータがある程度必要で、例えば接触調査のデータであったりとか、あるいはクラスターレベルのデータだったりとか、そういう個人レベルの精度の高いデータを使わないといけなくて。
そういうデータを使おうとすると、積極的な接触調査をかなり大規模にやっている国のデータをどうしても使わなくてはいけない。
かつウイルスが複数の変異体が混合している状況だとそれを切り分けてデータとして見ることができないということもあります。私自身が最初期のオーバーディスパーションの推定とかを自分の研究でやっていましたが、
その時は一種類しかウイルスがいなかったのでそこにあるクラスターのデータというのは全部まとめて一個の感染として扱うことができました。
今、クラスターが起きてもその中でどれがデルタでどれがアルファかというのが分からない状況なので推定もなかなか難しいです。おそらく元々のオーバーディスパーションの状態と近い形なんだろうと言われてはいますが、
あくまでもそれは推定でしかなくて、具体的に本当のデルタのオーバーディスパーションの数値はありますか? と言われると「今は無い」としか言いようが無い状況ですね。
木下喬弘
なるほど。
これって結構重要な問題のような気がしていて、デルタはすれ違い感染みたいなことも騒がれていたりするじゃないですか。
それがよくあるイベントなのであれば、平均的に多くの2次感染が起こるってことだと思うんですよね。
一方で「過分散が大きいという性質が変わらないのであれば」というのがいい表現なのか分からないんですけれど、原則論として、1人の人が時々多人数にうつすということが問題になると、やはりクラスターを抑えましょうみたいな話が中心にはなると思うんですよね。
すれ違っただけで感染するみたいなことも起こり得ないという話をしているわけでは全然なくて、それがメインの感染経路なのかどうなのかということが結構重要だと思います。常識的に考えて、バンバンそんなことが起こっていたらこの程度じゃ済まないだろうしということもあって。
なんかちょっとどうなのか? とは思っているんですけれど。
この辺ってエキスパートオピニオンとしてどう思われます?
遠藤彰
すごく難しい話だと思います。
今のすれ違い感染に関しても、全体として確かに頻度はそんなに多くないだろうと思うんですけれど、
例えば個人ごとのウイルスの放出量というのがすごくばらついていて、特定の人はすれ違った段階で感染させてしまうような高い感染力を持っていて、ただそういう人は全体の感染者の中でもごく一部ですよ、っていう可能性もあるわけじゃないですか。
その場合だと、すれ違い感染を一部の人が大量に生み出してしまっていることで全体のスーパースプレッディングイベント(平均よりはるかに多い二次感染者がでるような出来事)が発生する可能性もあるわけですし、そうじゃなくて行動様式的にパーティーの場であったりとか多数の人が集まる所での感染がクラスターイベントを生んでいるという可能性もありますし。
ということで、結果的に大量の人に感染させた場合とさせない場合があるところだけは一緒なんですけれど、それを生み出しているメカニズムは違っているということになって。
「じゃあ、それがどっちなの?」といわれると単純なデータの推定値からそこまで知るというのは結構難しいんだろうなと思いますね。
木下喬弘
ありがとうございます。
なかなか難しいですね。
要は、過分散の問題がありそうで、他人にうつすかどうかは人によって全然違うということですよね。めちゃくちゃ人にうつし易い人もいれば、そうじゃない人もいるみたいな感じになっているのは事実だろうと。
そうするとクラスターで大量発生みたいなイメージが湧き易いんですけれど。
実はめちゃくちゃ人にうつし易い人というのが存在すると、すれ違っただけで感染するみたいなことも起こりうる、ということなのかも知れませんね。
デルタがどんなふうにうつしていて、どこを効率的に抑えたら感染の収束に有利なのか? みたいなことって、簡単には分からないということが概ね分かりました。
ありがとうございました。
遠藤彰
ありがとうございました。
特に今感染者数がすごく大きくなってしまったので、特定のイベントの寄与率を出すのがそもそも難しくなっています。分析においては、それがかなり制約になっているといことになりますね。
木下喬弘
ありがとうございます。
どうぞ前田先生。
前田陽平先生
遠藤先生にちょっと質問です。
デルタになってきていわゆるエアロゾル感染(空気中でウイルスと液滴が混じって形成され、吸入すると感染が生じる状態)みたいなやつが増えているということは、可能性としてもちろんあると思うんですけれど、そういったことを調べることはできるのでしょうか。
この件について、遠藤先生はエキスパートオピニオンとしてどう思うのかということをちょっと聞いてみたいなと思うのですが、どうでしょうか?
遠藤彰
ありがとうございます。
具体的なデータとしてはどうこうという話にはまだなっていないし、今後そういう分かり易いデータが出てくるかも正直ちょっと分からないんですけれども。
ただ、いわゆるすれ違い感染みたいなものがあったりとか、例えばホテルの廊下伝いだったりとか、ドアの隙間からの感染なんじゃないかということが疑われた事例が比較的増えているような印象は、実際あります。これまでは、仮にそういう状況下でも、空気中に含まれているウイルスの量がそこまででもなかったので、感染を引き起こすレベルにはなくて、
ただデルタになってきて放出されるウイルス量が増えてきたので、これまでだったら感染しないような低濃度のエアロゾルでも一部の条件下で感染が起こるようになってきたという可能性は、あっても全然おかしくないのかなと思っています。仮説ベースにはなりますけども。
前田陽平先生
ありがとうございました。
それを質問した理由というのが2つあって。
コロナを診ている先生とコミュニケーションしていても、前は「こんな時に会食した」みたいな人が罹っていたけれども、最近はどう考えても何にも感染する心当たりがないような人が感染している、「スーパーとコンビニしか行っていないのに感染している」みたいな話をしていたのでどうなのかな? と思ったのが1つと。
もう1つは、個人的に僕が耳鼻科医なので、どうしてもエアロゾルを発生するような処置を診察上しないといけないので、そのリスクもどんどん上がっているのかな? などと考えていたので、それでちょっと質問させてもらいました。
すみません、ありがとうございます。
木下喬弘
ありがとうございます。
前田先生にとっては生死に関わる問題なんで、気をつけてくださいね!
前田陽平先生
はい、ありがとうございます。
【テーマ2】 感染の流行状況と感染対策の強化と解除のバランスについて
木下喬弘
ちなみに安川先生ね、アメリカってデルタがだいぶ優勢になってきて、ヘルスケアワーカーは接種から時間が経って若干抗体価が下がっていると思うんですよ。
そうすると、院内感染が起きてもおかしくないと思うんですが、これって頻発してるんですか? 特にエアロゾルを発生するような手技において。
安川康介
うーん、まだ報告は少ないですけれども、どこかの医療施設でワクチンを受けていても感染が起きたということはありますよね。
ただ、それが本当にデルタのせいなのか、時間が経って院内での感染予防を少し緩めてきたせいなのか、というのは結構難しいですよね。どこまでがどの効果なのかということを分けて考えていくのはすごく難しいので、何とも言えないんですけれど。
確実に言えることは、ワクチンを受けていてもブレイクスルー感染(新型コロナウイルスのワクチン接種を終えたあと、2週間以上して感染が確認される)というのが一定の割合で起きているというのは認められています。最近のバーンステーブル郡(米国マサチューセッツ州)の論文だとサイクルスレショルド(Ct)に関する報告がありますね。ウイルスの量がワクチンを受けた人とワクチンを受けていない人でも同じだったんじゃないかという、すごく小さな論文なんですけれども。80人と65人くらいを比べた……それしか情報がないんですけれども、ワクチンを受けた人でも気をつけた方がいいよね、という話には確実になってきていると思います。
木下喬弘
ありがとうございます。
実はですね、今日私が選んだニュースはそれだったんですけれど。
せっかくなんでちょっとだけ紹介しますと、皆さん、プロヴィンスタウン(Provincetown)ってご存じですか?
安川康介
知ってますよ。
行ったことあります。
ケープコッド(Cape Cod)の先にある街でゲイのパレードとかで有名なんですよね。
木下喬弘
そうそう、おっしゃる通りで。
そのプロヴィンスタウンという街は、キーワードがいくつかあります。
A community of health-conscious, left-leaning Northeasterners, known as a vacation mecca for gay men って書いてありますね、プロヴィンスタウンの紹介として。
非常に健康志向が高くて、Left-leaning 要するに民主党支持層で、North easterner ということは北東部に住んでいる人ということなんですけれど。ニューヨークとかボストンとか同じですね、いわゆるブルーステイツ(民主党の強い都会型・工業地帯の州)であると。
a vacation mecca for gay men はゲイの男性が特によく来る、行楽地ということですね。
このプロヴィンスタウンという地域は、95%のワクチン接種率を達成していたわけです。そこまで来ていたらいろいろな制限を解除していって、パーティーをしたりとか、バーでマスク無しで喋ったりしていたわけなんですけれど。
そうするとちょっとクラスターが発生し始めて、調べてみたら感染した人のほとんど(75%)がワクチン接種者だったということで、接種していても全然安全ではないということに気づいた、というニュースがあってですね。
このプロヴィンスタウンの周りの人達は非常に理解が良くて、「It’s not nowhere near over.」ということで「全然まだまだこのパンデミックは終わっていない」ということを自覚しているというコメントがいくつかあります。「『マスクをもう1回しましょう!』みたいなところに私たちは戻ります」ということをコメントしていてですね、そういう状況にアメリカ実はちょっとなってきているということで。
これはある程度皆さんご存じだったと思うんですけれど、デルタくらい伝播性の上がったウイルスが出てきてしまうと、ワクチン打った人の中でも感染が広がってしまうということもありますし、ワクチンを打ってから時間が経ってしまうと抗体価が下がってくるので防御力自体が下がってくると。
これは何度も言いますけれども、これはワクチンを打たないより打つ方が圧倒的に有利なんだけれど、特に感染を予防する効果が少し下がってきてしまうという意味です。
一方で、重症化予防効果とかは非常に高い値を保っているので、実際入院した人はごくわずかだったみたいなデータも記事の中に紹介されていたんですね。
そういう状況になっているということですね。
どうせ答えがないんでいいんですけれど、どういうふうにこのパンデミックに落とし前をつけるのかというのが、改めて難しくなってきているというような現状があります。
接種率が高い国、例えばイスラエルとかでも感染が再燃していてみたいなこともありますよね。
そうじゃなくて、アメリカの中で接種率の高い地域でもこういう風なイベント、スーパースプレッディングイベント(平均よりはるかに多い二次感染者がでるような出来事)というか、クラスターが発生していて、少し対策を強化しないといけないところに逆戻りしますよというのがニューヨーク・タイムズのニュースになっているということでご紹介したいと思います。
▼参照
’It’s Nowhere Near Over’: A Beach Town’s Gust of Freedom, Then a U-turn
https://www.nytimes.com/2021/07/31/us/covid-outbreak-provincetown-cape-cod.html
出典:The New York Times 2021/7/31
ということで、こんな感じでですね、しばらくはいろいろな流行が出たり、収まってきたら感染対策を解除していって、完全に元に戻るということを目指しつつも、また流行が出てきたら少し対策を強化してみたいなことを繰り返していかないといけないというのが結論になるんだろうなと思ってます。
2分オーバーしましたけれど何かコメントありますか?
いいですか?
「いや、そんなことはない。ワクチンを8割の人が打ったらマスクを外してもう二度とつけなくていい」とか黑ちゃんが思っているんだったら、コメントをいただいても。
黑川友哉
なんでそういう振り方になるんですか?
木下喬弘
(笑)
黑川友哉
まだまだ変異ウイルスがどれだけ広がってくるかとか、変異ウイルスの性質によって感染対策がまだまだ必要というのは今後も変わり得るかなと思うんで、そういった情報を正確に捉えていくことが重要なのかなと思っていて。
やっぱり安易に「接種して2週間経ったからもう自由だ、わあ!」となるのを避けるというのが重要なのかと今日聞いていて思いました。
木下喬弘
おっしゃる通りだと思います。
ということで本日は「こびナビのスペース」改め「えんちゃんのすぺーちゅ」ということで、遠藤先生に急遽ご登壇いただいていろいろ教えていただいて、ありがとうございました。
また上がってきてくださいね。
遠藤彰
ありがとうございました。
木下喬弘
ありがとうございました。
本日はここまでにさせていただこうと思います。
日本の皆様、よい1日をお過ごしください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
