
THE NEW COOL NOTER賞~小説講座 第5回「視点(人称)について」
THE NEW COOL NOTERコンテストに参加いただいている皆様。
ならびにみこちゃん出版を応援いただいている皆様。
赤星先生の「小説作法(文章作法)」について、第5回「視点(人称)について」をおくらせていただきます。
講座は、今回で最後となります。
人称・視点とは
第5回では「人称」と「視点」について、取り上げさせていただきます。
一奥は過去の講座で、読者の物語における読書を旅にたとえてきました。
この意味において、記号や禁則といったルールは「標識」のようなものであり、読者が快適に道を進んでいくためのものです。
ある意味で、当たり前にできて当然である、歩き方そのものをストレス無く進めさせるためのものとも言えます。
そして、もう一つ、そうした大道具や小道具と合わせて、読者が物語世界を旅していく中で重要な「ガイド」となるもの。
それが「人称」あるいは「視点」という存在です。
「一人称」や「三人称」という言葉を、聞いたことがあると思います。
その小説を書き進める文章が、誰の目から見た書き方で、書き進められているかを表すもので、基本的に使われるのも「一人称」「三人称」の2つとなります。
一人称の例文をあげましょう。
例)
私は急に楽しくなって、ふふんと笑った。機にかないて語る言は銀の彫刻物に金の林檎を嵌めたるが如し、という聖書の箴言を思い出し、こんな優しいお母さまを持っている自分の幸福を、つくづく神さまに感謝した。ゆうべの事は、ゆうべの事。もうくよくよすまい、と思って、私は支那間の硝子戸越しに、朝の伊豆の海を眺め、いつまでもお母さまのうしろに立っていて、おしまいにはお母さまのしずかな呼吸と私の呼吸がぴったり合ってしまった。
朝のお食事を軽くすましてから、私は、焼けた薪の山の整理にとりかかっていると、この村でたった一軒の宿屋のおかみさんであるお咲さんが、
「どうしたのよ? どうしたのよ? いま、私、はじめて聞いて、まあ、ゆうべは、いったい、どうしたのよ?」
と言いながら庭の枝折戸から小走りに走ってやって来られて、そうしてその眼には、涙が光っていた。
「すみません」
と私は小声でわびた。
太宰治『斜陽』より(太字は筆者)
「私は」という言葉を太字で強調させていただきましたが、一人称表現とは、会話文ではない地の文を含めた文章そのものが、登場人物(通常は主人公)が見たもの、感じたもの、なした行動と一致しています。
まるで、日記を書いたり、自分自身を実況・独白しているかのように、状況や情報、物語の展開を読者に示していくこととなります。
このように、その物語の場面に入り込み、旅をする読者にとって、出来事や情景やそれに遭遇した登場人物の心情を、ある意味でスムーズに体感できるのが一人称視点です。
その場面でその視点の人物がどのように感じたのかを、その人物自身が述べているところに一つの特長があります。
これは、読者にその場面の視点の主である人物(主人公など)の考えや感じたこと、心の動きをシンクロさせる効果とも言えます。
必要な情報と、必要でない情報。
言及している情報と言及していない情報。
その人物がその場面で、どんな物事に注目しているのか、もっと言えば、彼彼女(主人公)とは「どういうことに注意し、注意しない者であるか」を、読者に投影する効果を持ちます。
ただし、日々の生活の中では、たとえば、
「一奥はその日、朝寝坊をして全力で駅まで走ったので、気持ちが非常に急いていた」といったように、自分自身を実況するような人間はほとんどいないでしょう。一人称とは、そういう意味でのリアリティを与えるものではありません。
そうではなくて、いうなれば、その視点の人物の呼吸やリズムそのものを、読者に無意識レベルで導いているとも言えるでしょう。
それはそのまま、読者にとって、その一人称のキャラクターの視点を通して物語世界を旅していくことをスムーズにさせるものです。
ただしこれは、そのキャラクターが読者から見て感情移入できる者、望ましい者として造形されているかどうかとは別の問題です。
結果的に、読者から見て好みではないと思えるキャラクターであったとしても、その者の視点を通して物語を読み進める上で、その読み進めるリズムが乱されない――ということが大切です。
過去の講座で「三点リーダ」や「中線」、!(感嘆符)や?(疑問符)の解説を通して、繰り返し述べさせていただいたことと、この点は通底しています。
禁則処理も、様々な作文上の作法も、読み進めること、それ自体をスムーズにして……つまり、読者が内容を味わい、または考えることに集中できるようにするものです。
よく、表現技法や表現技術の文脈から「人称(視点)とはなんぞや」を語る言説がありますが、そういう切り口から入ってしまうと、どうしても表現を過度に装飾してしまう方向に頭が行きがちに思います。
一人称であれば、キャラクターを過度に立たせることだとか、キャラクターを描き分けるために特徴づけることなどに、意識が向いてしまう――しかしそれは、読者に余計な情報を与えることになりかねない。
……観光ガイドさんが、風景の紹介をしながら、いきなりそれらとは全く関係の無い趣味の話ばかりし始めたらいかがでしょうか。
たとえ、そのバスガイドさんが個人として愛らしいキャラクターであるとしても、少なくとも、旅先の文物を知るという当初の目的からはそれてしまうでしょう。
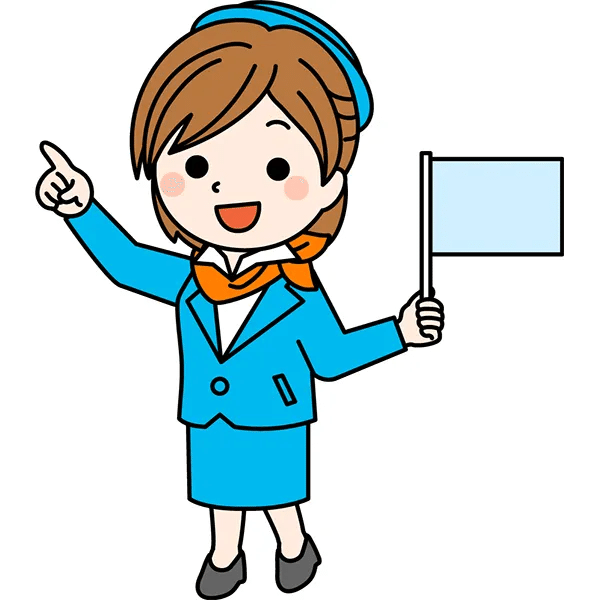
一奥が、赤星先生の文章作法講座の中で、「視点(人称)」を取り上げさせていただいたのは、こういう理由です。
視点や人称というのは、そこまで大層なものではありません。
ただ単に、読者にとって、スムーズに内容を読み進めさせる呼吸を整えるだけのものに過ぎず、表現技法や表現技術とは、切り離すべきものです。
知り得ることと知り得ないこと
それでは、読者にとってスムーズに違和感なく”旅”をしてもらうために「人称(視点)」で気をつけるべきこととは何であるかについて、三人称視点の説明とともに述べさせていただきます。
次の例文を御覧ください。
するとその地獄の底に、カン陀多と云う男が一人、ほかの罪人と一しょに蠢いている姿が、御眼に止まりました。このカン陀多と云う男は、人を殺したり家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥坊でございますが、それでもたった一つ、善い事を致した覚えがございます。と申しますのは、ある時この男が深い林の中を通りますと、小さな蜘蛛が一匹、路ばたを這って行くのが見えました。そこでカン陀多は早速足を挙げて、踏み殺そうと致しましたが、「いや、いや、これも小さいながら、命のあるものに違いない。その命を無暗にとると云う事は、いくら何でも可哀そうだ。」と、こう急に思い返して、とうとうその蜘蛛を殺さずに助けてやったからでございます。
御釈迦様は地獄の容子を御覧になりながら、このカン陀多には蜘蛛を助けた事があるのを御思い出しになりました。そうしてそれだけの善い事をした報には、出来るなら、この男を地獄から救い出してやろうと御考えになりました。幸い、側を見ますと、翡翠のような色をした蓮の葉の上に、極楽の蜘蛛が一匹、美しい銀色の糸をかけて居ります。御釈迦様はその蜘蛛の糸をそっと御手に御取りになって、玉のような白蓮の間から、遥か下にある地獄の底へ、まっすぐにそれを御下しなさいました。
芥川龍之介『蜘蛛の糸』より(太字は筆者)
三人称は「神の視点」とも言われますが、その場面の視点の主となっているキャラクターの心象や思考・行動を描写しているという点では、一人称と代わりはありません。
上の芥川龍之介の例文では、視点の主は「お釈迦様」です。
ただし、お釈迦様が自らの行動を自らの言動や物言い、思考のリズムによって「独白」しているわけではなく――作者、あるいは神の視点の”神”と呼ばれる存在が、一歩引いた位置から物語の展開を述していっています。
ここで、一人称視点で表現することと、三人称視点で表現することの違いにこだわってはいけません。
確かに、読者に与える印象や効果において、どちらを使うかは表現上の違いをもたらしますし、また物語を展開させていく描写についての全体的な統一や方針を大きく左右します。
しかし、その判断はキャラクターや物語舞台の造形、どのようなテーマを乗せるか、どういう表現をしていくか、あるいは書き手としての得意不得意など、様々な要素の中から決まってくるものです。
逆に言えば、それらが決まった時点で、その小説を一人称と三人称のどちらで描くかは、自然に決まっていると言えます。(時にはほとんど直感的に、やりやすいと思った方で書き始めることもあるでしょう)
ここで言いたいことは、描写とは「人称(視点)」から逆算して考えるものではない、ということです。
一人称だからキャラクターの考えをしっかりと――だとか、三人称だからキャラクターの心情描写には距離を置いて――といったような杓子定規で使うと、読者ための文章・描写という本筋を失いかねません。
「人称(視点)」が定まった時に、すべきこと。
それは、その視点の主にとって「知り得ることと知り得ないこと」を、峻別する、というものです。
再び『蜘蛛の糸』から例文を抜き出してみましょう。
ところがある時の事でございます。何気なくカン陀多が頭を挙げて、血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした暗の中を、遠い遠い天上から、銀色の蜘蛛の糸が、まるで人目にかかるのを恐れるように、一すじ細く光りながら、するすると自分の上へ垂れて参るのではございませんか。カン陀多はこれを見ると、思わず手を拍って喜びました。この糸に縋りついて、どこまでものぼって行けば、きっと地獄からぬけ出せるのに相違ございません。いや、うまく行くと、極楽へはいる事さえも出来ましょう。そうすれば、もう針の山へ追い上げられる事もなくなれば、血の池に沈められる事もある筈はございません。
こう思いましたからカン陀多は、早速その蜘蛛の糸を両手でしっかりとつかみながら、一生懸命に上へ上へとたぐりのぼり始めました。元より大泥坊の事でございますから、こう云う事には昔から、慣れ切っているのでございます。
しかし地獄と極楽との間は、何万里となくございますから、いくら焦って見た所で、容易に上へは出られません。ややしばらくのぼる中に、とうとうカン陀多もくたびれて、もう一たぐりも上の方へはのぼれなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで、糸の中途にぶら下りながら、遥かに目の下を見下しました。
芥川龍之介『蜘蛛の糸』より(太字は筆者)
この場面を、芥川龍之介は『カン陀多の一人称視点』で描くこともできたでしょう。
そうしなかったことの是非、文学的な、描写上の意義は置いておくとして、もしこれが一人称視点の場面であった場合、次の箇所に注目してください。
遠い遠い天上から、銀色の蜘蛛の糸が、まるで人目にかかるのを恐れるように、一すじ細く光りながら、
しかし地獄と極楽との間は、何万里となくございますから、いくら焦って見た所で、容易に上へは出られません。
この2箇所は、カン陀多という人物の思考・呼吸とはそぐいません。
1つ目の「まるでひと目にかかるのを恐れるように」という描写は、悪事を重ねてきた大胆不敵なカン陀多という男の人間性からは直接連想しづらく、もしこれをカン陀多の独白・実況による一人称での描写とした場合は、違和感を覚えることになります。
2つ目についても、カン陀多に、地獄と極楽の間の距離について物理的な知識や宗教哲学的な知識がある――とは、これまた直接には連想しづらいはずです。
もちろん、実際にカン陀多が、そういう知識や感性を持ったキャラクターとして芥川龍之介が造形していたかどうかは、ここでは重要ではありません。
あらかじめ冒頭で、お釈迦様の視点(三人称)を通して、
このカン陀多と云う男は、人を殺したり家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥坊でございますが、
このように描写されていることが、意味を持ちます。
この時点で、読者は少なくとも自分自身がそれまで生きてきた人生の中で培った、ある種の人間に対する一般的な見方から連想して、カン陀多という人物がどういう存在であるか、無意識レベルでその人物像が形成されているのです。
――お釈迦様ほどの存在に、客観的にそこまで言わしめ思わしめるほどの悪人であるという前提からは、「蜘蛛の糸が人目をはばかる」ような繊細な表現をしたり「地獄と極楽の間の距離」について哲学的に思考したりしたことのあるような人間であるとは自然には連想しえません。
その流れの中で、後の、群がる亡者達に罵声を浴びせる展開まで、読者はスムーズに読み進めていくことができる。
ここに、人称を書き分けること、そしてその人称でその場面の描写全体を統一することの重要性があります。
「その視点」で読者を導いたならば、その視点から見えるはずの無い景色が見えてしまうのは、物語に風穴をあけて、読者を「内容とは別の技術的な違和感」で足止めさせてしまうこととなるのです。
ある場面を、あるキャラクターの一人称または三人称で描くことを決めたならば、そのキャラクターにとって「知り得ること知り得ないこと」を、読者はそれまでの文脈から、こういうものであるという暗黙にして一定の前提をすでに無意識に抱いています。
これに逆らうような描写をしてはいけません。
あれもこれも、と表現を過度に華美に絢爛に盛り込むのではなく。
「この視点からしたら、この表現はちょっとありえないな」
「この場面で、この人物は、こんなこと知らないだろう」
という風に、むしろ、増殖しようとする表現欲を削り、減じて、最適の描写に切り詰める方位磁針とすること。
それが、物語を旅にたとえて、その旅路を無意識レベルでスムーズに読者に歩ませるための、文章作法、そして描写における「人称(視点)」の役割ではないかと考えます。

まとめ~読者のために書くということについて
第3回THE NEW COOL NOTERコンテスト7月開催分「文芸部門」で、審査委員を引き受けてくださった、赤星香一郎先生が、小説技法や文章作法について、どのようなことを評価されるのか、そのお考えを一奥より最大限概説させていただきました。
その基軸にあるものとは「描写」です。
もちろん、物語が面白いことは大前提です。
ですが、その面白さを、内容とは関係ない部分で損なわないようにするための、様々に工夫されてきたルールがある。
それは守らねばならないルールというよりは、読んでいる最中に違和感を感じさせないようにするための、それなりの根拠があり、文章技術や作法の歴史の中で作り上げられてきたものであるととらえてください。
故に、最後に「人称(視点)」の話をさせていただきました。
この講座が、よりよい小説、読者のための小説を書くための一助とならんことを。
そしてその小説を、コンテストにご応募いただき、お祭りの中でまみえることを心より願うものです。
最後に、ここまでお読みいただき、まことにありがとうございました。
改めて、本講座をご監修いただいた赤星香一郎先生に、この場を借りてお礼を申し上げます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
