古楽の「伝道者」たちの美文を読む
一般に「古楽」とは何?という質問に対して、
ヨーロッパの中世からルネサンスを経て、バロックに至るまでの時代の音楽のこと、と説明されることが多いように思います。
毎日早朝にFMで放映されている、古楽専門のラジオ番組では、おおむねバッハの生きた時代までを、そしてまれにバッハの息子たちの世代(モーツァルトとも重なる)も扱っているようです。
戦後しばらくの時点では、大多数の日本人にとって、バッハよりも前の時代の音楽についての情報など乏しかったはずですが、その偏った状況をいち早く憂い、中世及びルネサンス音楽への深い愛情をもって、日本国内への啓蒙に尽くしたのが、つい最近までご存命であったこちらの方です。

皆川達夫(みながわ・たつお 1927~2020)氏。
昭和期から晩年まで、古楽を紹介するラジオ番組のパーソナリティをされていて、その格調高い語り口ゆえにファンだった方々も多いかと思います。
研究者としては、日本の潜伏キリシタンが伝えていた、かつてのキリスト教の賛歌「オラショ」の研究で特に知られています。
この皆川氏と、私が仕事でご一緒したのはたった一回しかありませんが、とにかく80歳を超えても矍鑠としていたのが印象的でした。
皆川氏には西洋音楽に関する多くの著作があります。絶版となった本も多いものの、以下のように文庫として再販されたものはこの分野の入門書としてはスタンダードなもので、これからもずっと読まれることでしょう。
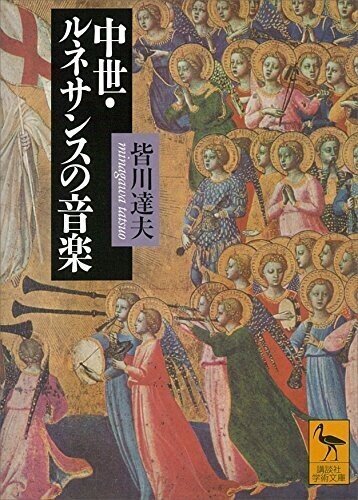
↑ 『中世・ルネサンスの音楽』(講談社学術文庫)
皆川氏の文章は、とにかくその語り口同様に、知性に溢れています。
最近ますます少なくなりつつある、戦前生まれの日本人の教養のさまがうかがい知れるような文章、とでも言えるでしょうか。
音楽という、一瞬のうちに火花のように飛び散り、そして消えてしまう不確定なものを対象とする歴史家は、つねに「とらえがたいもの」ないし「とらえざるもの」を追っているという焦慮ともどかしさから免れることができない。(『中世・ルネサンスの音楽』第一章から)
先ほどの著作の導入部に据えられたこの文章など、過去の音楽と対峙する研究者の「宿命」のありようを、これでもかというほどに的確にとらえていると思います。
このように研究者としての皆川氏の姿勢は、一貫して謙虚です。
かと思えば、ご自身の素直な意見を表明されることもありました。
例えばこのように。
十四世紀イタリアの音楽は、フランスのそれにまさって人間的な情感にみち、フランスに先がけてルネサンスの方向を予告するものであった。
ただし、その反面、その技法や構成はフランスのものに比して稚拙なところがあり、「情あまりて、舌足らず」の嫌いなしとしない。
とくにイタリア人は、旋律の甘美な流れにひたりきって、音楽の構成の重みを忘れがちである。(『中世・ルネサンスの音楽』第四章から)
皆川氏には、バロック音楽に関する入門書もあります。
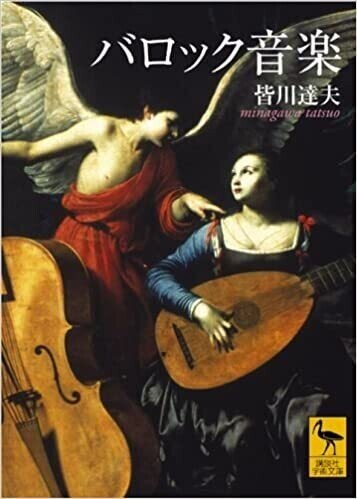
↑ 『バロック音楽』(講談社学術文庫)
ご本人がどちらかというと中世・ルネサンス音楽に軸足を置いた活動をされているということもあるのでしょうけども、ここに出てくるヴィヴァルディ評などは、多少辛辣かも。
率直に言ってわたくしは、ヴィヴァルディの音楽をあまり好まない。なるほど彼の職人芸の見事さに感心はするし、バッハが彼の音楽を一生懸命に取り入れいれようと努力したのもわたくしなりに理解できるのだが、わたくしがいまだかつてヴィヴァルディの音楽に感動したことがないのもまた事実である。(・・)第一、わたくしにはヴィヴァルディの音楽の品のなさが耐えられないのである。(『バロック音楽』第五章から)
こうした、ある意味で「忖度のない文章」というのが、他の部分との対比で心地よいギャップを生んで、それゆえ皆川氏のファンになった方もきっといるはず。
皆川氏が、これらの入門書で紹介した内容の中には、その後研究が進み、現在ではもはや受け入れられなくなった学説なども、たまに見受けられます。豊富な一次資料が、ネット上で入手可能となった時代の到来を前にして、あちらの方へ行かれてしまわれたので、そこは時代ゆえの限界というべきでしょう。
しかし、そうしたこととは別に、私が皆川氏の文章を繰り返し読んでしまうのは、古楽の分野における草分けゆえの、ご本人のにじみ出るような苦労が、その格調高い文章の各所に表れているのが、手に取るように分かるからです。
もう一人、「古楽の伝道者」としての文章に私がほれ込んだ方がいます。

礒山雅(いそやま・ただし、1946~2018)氏。
バッハをはじめとする著作を、たくさん読ませていただきました。
実際に、大学時代にはご本人のバッハに関する講義を受けることができ、そのときの資料やノートは、今も大切に持っています!
礒山氏は、同世代の音楽学者の中では、いち早くSNSを駆使して一般の音楽ファンにも情報を提供してした他、皆川氏と同じようにラジオのパーソナリティとしても活躍し、晩年は大規模な古楽のイベントのプロデューサー業にも精力的に邁進。
自らの集大成と位置付けていたバッハ『ヨハネ受難曲』についての博士論文の受理を前にして、不慮の事故により亡くなられました。
没後にご遺族が代理で、博士号を受け取ったとのことです。
論文の遺稿などをもとに、まとめられたのがこちらの本。

↑ 『ヨハネ受難曲』(筑摩書房)
ご本人が古典ギリシャ語の習得を経て到達した、聖書のテクストに関する深い洞察、そしてバッハの音楽の分析はここでも冴えに冴えています。
たとえば、本編の曲紹介で、最初の文章に接するだけで、冒頭合唱のただならぬ様が見事に形容されていると思います。
《ヨハネ受難曲》は、全153小節、演奏時間10分の大合唱曲によって開始される。受難曲の歴史においてもこれほどの大曲が先置されたことは前例がなく、礼拝の枠組みさえ超える冒険のように思われる。長さばかりではない。その曲想の厳しさ、シリアスな筆致は同時代の受難曲と比較しても際立っており、同時代の聴き手を、さぞ驚かせたことだろう。ライプツィヒにおける最初の受難曲に対するバッハの意気込みはかくもすさまじいが、冒頭楽曲でまず勝負をかける発想は、《マタイ受難曲》にも、《ロ短調ミサ曲》にも受け継がれていった。(『ヨハネ受難曲』第三部第一章から)
実際に『ヨハネ受難曲』を聴いたことのある人なら
「なるほど、うまい!」
と思われるでしょうし、逆にまだ聴いたことのない人には
「なら、聴いてみようか」という気をおこさせてくれる、これぞ「伝道者」に相応しい文章だと思います。
これに先行する『マタイ受難曲』の研究書も、改訂の上、このほど文庫に収められました。私が読んでいたのは、初版の単行本のほうです。

↑ 『マタイ受難曲』(ちくま学芸文庫)
まさに大書というべき著作です。しかし、全体にわたって文章が読みやすいことと、随所に個人的な経験を織り交ぜて書いていることが手伝って、読み通すのは高校時代の私にとっても、まったく苦になりませんでした。
この文章などは、とても微笑ましいですね。
全曲のうちでは、どれよりも、最後の合唱曲が好きだった。もっともその理由は、この曲を歌うある女生徒の姿が、イメージにだぶっていたためかもしれない。あとで気づいたことなのだが、私の高校の音楽部の女声合唱団が、この曲を《嘆きつ奥津城に》という歌詞の編曲でとりあげ、私はそれを、まぶしい思いで眺めていたからである。(『マタイ受難曲』序文から)
さらに、巻末の「マタイ受難曲の音源聴き比べ」では、先ほどの皆川氏によるヴィヴァルディ評に通じるような、個人的な辛辣な批評などもあちこちに出てきて、これまた読者を喜ばせる箇所です。
もっぱらバッハの専門家として紹介されることの多い礒山氏ですが、実はモーツァルトやワーグナーに関する研究もあり、さらに意外なところでは、若い頃に中世・ルネサンス音楽の海外盤LPの解説の執筆なども相当数手掛けておられていて、これが今読んでも、とても素晴らしい内容なのです。
礒山氏のすっきりとした文章には、決して権威主義的な匂いがしません。
それは、古い時代の音楽を現代の私たちが少しでも身近に感じられるように、細心の注意を払って「つむがれた」言葉であるからな気がします。
最初の皆川達夫氏の文章も、礒山氏のそれとはまた違う意味で、「つむいだ」結果出てきたであろうフレーズが、たくさん見いだされます。
ちなみに自分は、「つむぐ」という言葉が、とても好きです。
ひょっとして日本語の動詞の中で、一番好きかも。
「当たり前のこと、あるいは一見自明のことを、当たり前でなく語る」
「理解が難しいと思われる内容でも、本質に切り込み、分かりやすい言葉に置き換えて伝える」
ご両人は、常にそうした「伝え方」を徹底していたのでないでしょうか。
優れた音楽学者は、研究者である前に一流の文筆家でもあるのですね。
実は私は、演奏会のプログラムノートや、CDの曲目解説を執筆させていただく機会がたまにあります。
そして執筆作業中にいつも頭に浮かぶのは、このお二方の文章です。
その際、文章を形だけ似せて書くのではなく、そうした伝え方の姿勢にできるだけ寄り添いたい・・という思いが、このところますます強くなってきています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
