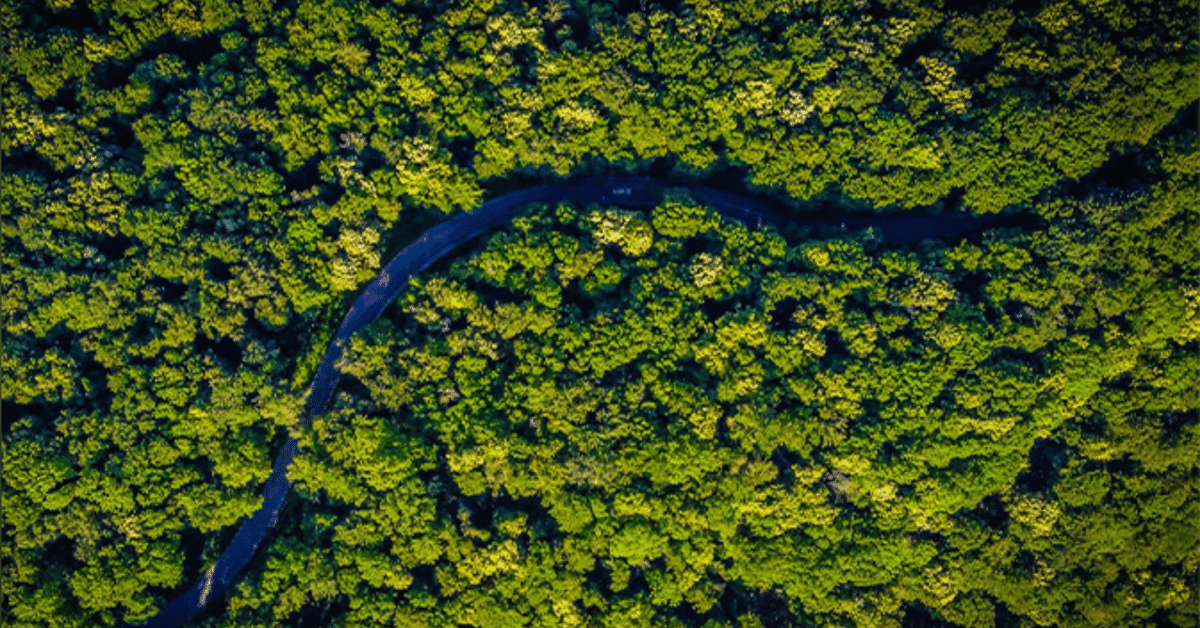
CoPリリースされました
こちらのnoteで、何度もご紹介してきた、CoP(Code of Practice)。
ボランタリークレジットの品質、創り方については、ICVCMによる「Core Carbon Principles:CCP」が4月に公開され、使い方、開示方法については、VCMIによる「Claims Code of Practice:CoP」が共通ルールになるべく、鋭意開発中でした。
5月には、タイムラインが公表されており「6月」となっていたので、7月を目前にして、今か今かと待ち構えていました。
「7月にずれ込むか?」と思いきや、6月28日、滑り込みで公開されました。
今週は、非財務情報開示ルールの大本命と目されていた(?)ISSBによる IFRS S1・S2が予定通り公開され、サス関係者にとっては大フィーバー。目下、皆さん読み込まれていることでしょう。SNSでも、リリース当日(日本時間は深夜)は賑わっていました。
そんなアイドルに隠れて、ひっそりとリリースされた感のある「CoP」ですが、クレジット畑を歩んできた私には、こちらの方が大本命でした。
さて、まだ読み込めてはいないのですが、ざっと見たところで気が付いたところを紹介しておきましょう。
VCMIの主張をするためのステップは4ステップで、ドラフト版からの変更はありません。また、内容についても同等のようです。ただ、第三者検証の必要性については、ドラフト版ではステップ2の説明の中で述べられていたのに対し、正式版では、ステップ名に昇格しています。

この1年で、ウォッシュに対する批判が高まったこともあるのでしょう。「高品質なクレジット」であることを裏付ける情報を適切に開示するよう、具体的な例を示しながら、繰り返し言及されています。

なお、ステップ1の「Foundational Criteria」はこのような説明があります。
このクライテリアは、パリ協定の長期目標に沿うように設計されているもので、現在の企業のベストプラクティスを代表するものだそうです。

ぱっと見ただけで、相当ハードルが高いことが分かりますよね。
算定はもちろん、短期SBT目標の公開やNet-Zeroのコミットも必要。また、目標に対して「on-track」であることを実証していく必要もあります。
削減貢献量を主張するときと同様、VCMIの主張をする際にも、まずは、自社の削減がファーストなのです。
続いて、VCMIクレームのTier、レベルについてです。
ドラフト版では、「GOLD」「SILVER」「BRONZE」となっていました。
それが正式版では、「PLATINUM」「GOLD」「SILVER」となっています。
GOLDが普及しすぎて、各社が続々とプラチナをリリースし始めた、昨今のクレジットカード事情のようですよね(笑)


直近の排出量のうち、何%を「高品質なクレジット」でオフセットしているか、でレベルが分かれていたのですが、その閾値が変わっており、特に「PLATINUM」に至っては、実質カーボンネガティブになっています。

ただ、VCMIの規定する「高品質なクレジット」は、ICVCMのCCPを満たすクレジットとした上で、このように説明しています。
All VCMI Claims require the purchase of carbon credits representing mitigation—either emission reductions or removals—achieved outside the value chain of the company, also defined as ‘beyond-value-chain mitigation’, through which companies contribute both to their climate goals
and to the collective global effort to reach net zero emissions.
「高品質なクレジット」の定義については、ICVCMのルール改訂はもとより、その他状況の変化に応じて、フレキシブルに対応していくそうなので、利用する側も常にキャッチアップしておく必要がありそうです。
さて、これからのロードマップですが、こちらは、5月に公表されたとおり進んでいきそうです。
なお、今後、ステークホルダーとの対話やフォーラム等を通じて様々なフィードバックを受けながら、必要なガイダンス等を開発、理解しやすく、かつ利用しやすいような環境整備を進めていく方針だそうです。
11月の完全版公開まで、目が離せませんね。

非財務情報開示ルールの統一と併せて、高品質なカーボン・クレジットの統一ルールの行方についても、全力でキャッチアップ、ご案内していきます。
継続して、お越し下さいませ。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。
