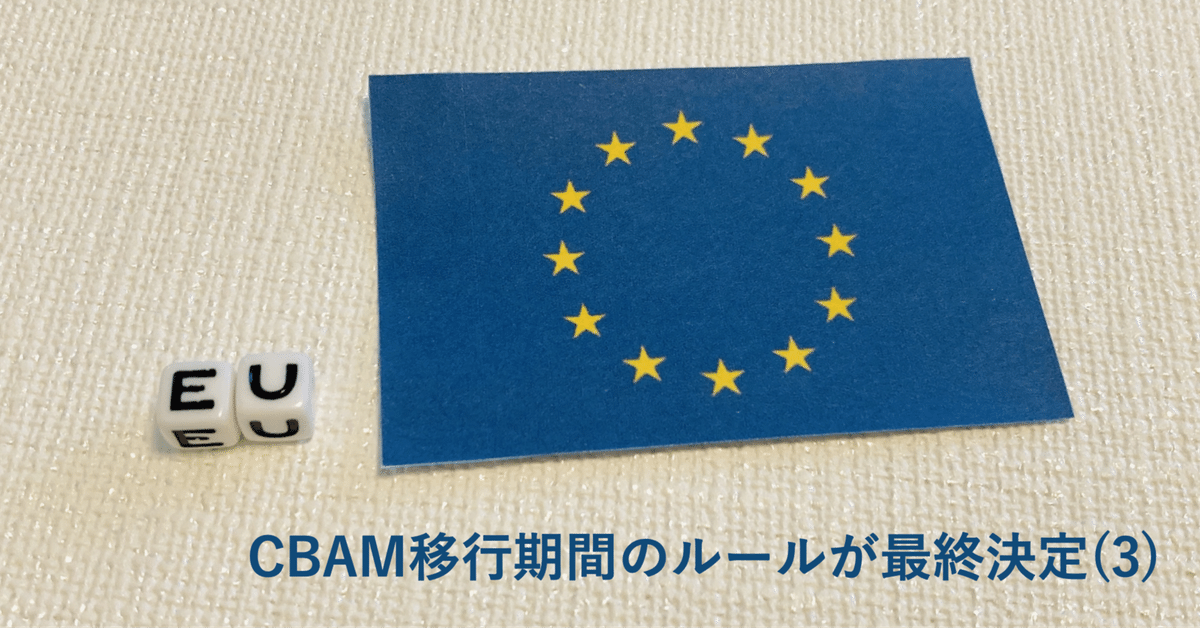
CBAM移行期間のルールが最終決定(3)
CBAMの移行期間に適用される規則及び附属書について、実施されていたコンサルテーションが終了、最終版が公開されたことを受け、2回に亘って、フィードバックの状況及び内容について見てきました。
今回は、フィードバックを受けて、最終版がドラフト版からどのように修正が入ったのかを見ていきたいと思います。
前回ご案内したように、フィードバックの内容は、主に次の5点でした。
1.機密情報の扱い
2.EU-ETSに対する不公平感
3.炭素価格の定義
4.緩和措置や移行措置、算定方法について
5.WTO違反について
「1.機密情報の扱い」は、とにかく報告する内容が細かすぎることに起因するものです。また、「2.EU-ETSに対する不公平感」は、間接排出の報告義務及び四半期毎という報告回数に対するものでした。
なので、最初に、附属書の報告リストを比較してみました。
ドラフト版では、報告する項目が「必須」「任意」「条件付き」と区別されていたものが、最終版ではなくなっていることが大きな変化でしょう。

また、ドラフト版では「CBAMレポートとして提出する情報」として、一つの表にまとまっていたところ、最終版では、「表1 レポートの構成」と「表2 レポートの詳細情報要件」に分かれており、「表2 に記載された詳細情報を記載しなければならない」と必須項目とされています。
Table 1: CBAM report structure
Table 2: Detailed information requirements in the CBAM report
これって、フィードバックに逆行しているのでは?と思い、両者を横並びで比較してみました。赤字は最終版で追加となった項目、青字は削除された項目です。

ドラフト版では「輸入者は報告書レベルで登録」となっていたところ、最終版では、「代表者/輸入者は、報告書レベルまたは輸入された商品レベルで登録」となっていることから、それに併せて項目が追加されています。
「Procedure」に追加されている「Inward processing information」は、「Inward processing(IP)」(再輸出加工制度)を適用した商品についての情報を報告するものです。
「再輸出加工制度」を適用した商品とは、「加工処理のためにEU域外から輸入される非EU商品」のこと。サプライチェーンはグローバルでつながっていますので、当然想定される形態ですね。
この場合は「組込炭素排出量の算出に係る特例」(CBAM規則 6条3、4、5)の適用を受けることができるため、しっかりと記載したい情報。ドラフトには無かったんですね。
「組込炭素排出量の算出に係る特例」は、この他にも「Outward processing(OP)」(再輸入加工制度)と「Returned Goods」(再輸入品)があります。
「再輸入加工制度」を適用した商品とは、「加工や修繕のために一時的にEU域外へ輸出され、再輸入されるEU商品」のことで、「再輸入品」とは、「EU域内から輸出された後、3年以内にEU域内に再輸入された非EU商品」のことです。
最下段の青字で示した「Goods properties parameters」は、最終版では、ごっそり削除されていますが、何故でしょうか。
TARIC(Tarif Intégré de la Communauté)コードは、EUが採用している商品分類、関税、その他の貿易関連措置を識別するためのコード体系で、商品の正確な分類、関税率の決定、貿易統計の収集、貿易政策の実施等を目的としています。
CUS(Customs Procedure)コードは、貨物が通関する際の手続きや目的を識別するためのコード体系で、貨物の通関手続きを明確にし、関税や税金、その他の貿易規制を適切に適用するために用いられるものです。
つまり、これらのコードは貿易を円滑に行うため、また関税やその他の貿易規制を適切に適用するために広く使用されているものであり、これらを含む情報を削除したからと言って、大幅な負担軽減になるとは思えず。
まぁ、輸出入は全くの素人なので、これ以上の詮索は止めておきます。
さて、報告情報のリストは後半分ほど残っていますが長くなってしまいましたので、続きは次回にしたいと思います。
ご意見等ございましたら、お寄せください。
一緒に勉強していきましょう。

もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。
