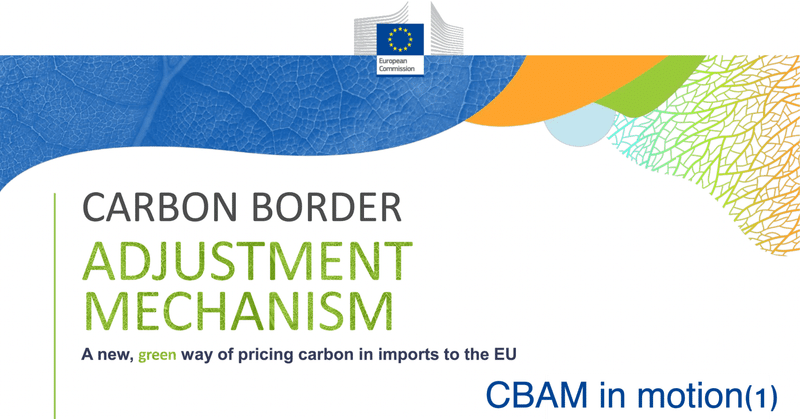
CBAM in motion(1)
EUの炭素国境調整措置(CBAM) が、13日、欧州議会とEU理事会がCBAMの導入について合意に達したことで、事実上導入が決定したことは、既にお伝えしておりました。
あとは、EU各国及び欧州議会において、セレモニー的な「採択(adoption)」が行われて最終決定となります。
詳細はどうなるのかなぁと思っていたところ、EY新日本有限責任監査法人がCBAMとCSRDについてのウェビナーを開催してくれたおかげで、かなり理解が進みました。
ということで、レジュメを使いながら概要を紹介すると共に、個人的なコメントをしたいと思います。
まず、スケジュールです。
移行期間:2023年10月1日〜 報告義務
本格導入:2026年〜 CBAM証書購入義務
ただ、ウェビナー中「26年か27年から」と言及していたのが気になります。
もしかして、確定ではないのか?まぁ、遅くとも27年は確実かと。

以下の6つの素材の「raw material」が対象です。
・セメント
・肥料
・鉄鋼
・アルミニウム
・電力
・水素
特定の「Precursor(前駆体)」つまり、素材の「材料」上流も対象とのこと。まぁこちらはよいとして、注意すべきは、一部の「下流」も対象となることに注意。例として、鉄やアルミ製のねじやボルトが挙げられています。
「ちゃんと分かるようにしてもらわないと、困るじゃないか」
確かにそうですよね。何と言っても「法律」ですから。
ということで、厳密には「CNコード」という、製品の分類コードで対象可否を判断する必要があるようです。
このように、CBAMの対象品目が、暫定ながらも公開されています。


とはいえ、輸入品ひとつひとつについてコードを確認するのは、厳しいのでは?さらに、輸入業者は必ずしも製品に詳しいわけではないでしょう。ましてや、品目の追加が行われるでしょうから、相当の負荷がかかると思います。
続いては、バウンダリーについてです。

対象となる取引は、EU域外からの輸入ですが、EEA(スイス、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン)は除外されています。EU-ETS同等の制度があるためです。同様の地域は順次増えていくようですが、さて、日本のGX-ETSは「EU-ETS同等の取引制度」と認めてもらえるでしょうか。
対象ガスは、CO2、PFCs及びN2O。GHG全体ではありません。
しかし、直接排出に加え間接排出も対象になることに注意。間接排出は、電力だけではありませんよ。
報告は四半期報告と年報告があります。
四半期報告は、下記4点
・事業所毎の商品毎の重量
・商品毎のトンあたりの排出量
・総間接排出量
・原産国で課税されたカーボンプライス
年報告は下記3点
・商品毎の重量
・商品毎のトンあたりの排出量
・原産国で課税されたカーボンプライスを減じた後の排出量に相当するCBAM証書数
「カーボンプライス」が報告内容となっているのは、CBAM証書価格から減じてもらえるからだそうなので、しっかり報告しましょう。
最も重要なのは、報告は法律上の「義務」なので罰則があることと、その法律を担保するために、報告は第三者検証が必須であること。
排出量の算定だけでも大変なのに、検証を受け、さらに対象品目のチェックやら、四半期及び年報告やら。どれだけ、人的資金的リソースが取られるか、空恐ろしいですね。
ということで、まずは、さらっと内容をご案内しました。
次回はCBAMが導入によって何が変わるのか、リスクと機会はどうなるのか、などについて個人的な見解をご紹介したいと思います。
もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。
