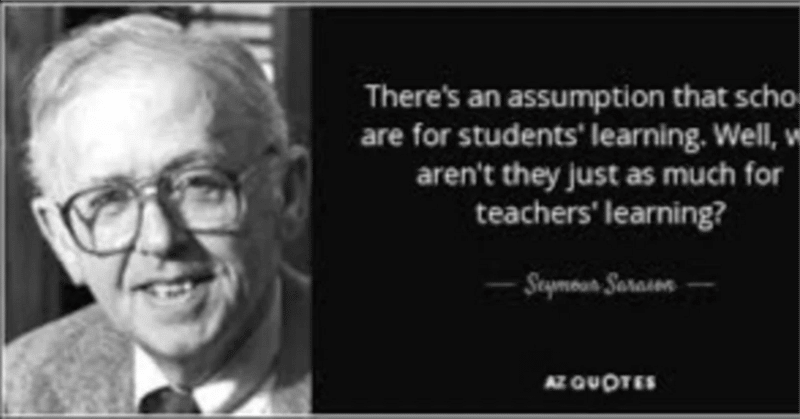
サラソン読書会第2回
コミュニティのチカラで英書を読み通そう!
サラソン読書会の第2回を開催しました!
読書会の目的
「心理的コミュニティ感覚」概念を生み出したサラソンの主著、
『The psychological sense of community』(1974年)の全章を読むことを通じて・・・
1)「心理的コミュニティ感覚」概念への理解を深める
-コミュニティ感覚概念の内容と意義への理解を深める
-当時のアメリカの学会・社会情勢など概念の背景・文脈を理解する
2)コミュニティの意義や可能性について考える
-感想交換を通して、コミュニティの意義や可能性についての考えを深める・広げる
ことを目的としています。
第1回:10月27日(金)20:30-22:00 /第1章
第2回:11月10日(金)20:30-22:00 /第2・3章 ←今日はココ!
第3回:11月24日(金)20:30-22:00 /第4・5章
第4回:12月 8日(金)20:30-22:00 /第6章
第5回:12月22日(金)20:30-22:00 /第7〜9章
第6回: 1月12日(金)20:30-22:00 /第10〜11章
第2章に書かれていたこと
Chapter2. The Societal Origins of Community Psychology
第2章 コミュニティ心理学の社会的起源
コミュニティ心理学が新しい考え方、訓練、実践方法を必要とする特徴的な分野と見なされ始めたのは、60年代初頭のこと。
伝統的な心理学との対立があった(臨床心理学との間の対立もあった)。
歓迎する人たちは、心理学が社会のニーズにより適切に対応できるようになる好機だと考える傾向があり、抵抗する人たちは、心理学が、知ること、理解すること、調査することの必要性よりも、助けたいという願望に基づいて早々とサービス専門職になってしまうという不幸な傾向のもう一つの例だと考える傾向があった。
コミュニティ心理学の成長を促した重要な出来事
・1954年人種差別撤廃判決とその後の公民権運動
・1957年ロシアのスプートニクの成功 米国の教育研究の停滞への危機感
・1963年ケネディ大統領 地域精神保健運動
・ジョンソン大統領の「貧困との戦い」計画
大学人は社会問題に無関心ではいられなくなった。
そのような時代に生まれたコミュニティ心理学は、社会問題に何らかの形で関与し、介入することが必要であると考えられていた。
社会変革に力を注ぐ大学人が認識しなければならない障害
社会問題を解決するのに十分な知識や経験を大学人は持っていない。
新しい役割を担うことに伴う障害。不安と葛藤
新しい問題を知らず知らずのうちに慣れ親しんだ言葉に変えてしまう傾向。私たちの思考には過去の刻印がつきまとう。
上の3つの障害を認識することが困難であること。
心理学と社会学においては、60年代の大学の混乱を予感させるような著作を残しただけでなく、学問と社会との関係、すなわち知識と行動する責任との関係を暗黙的あるいは明示的に提起した著名な人物がいた。
Kurt Lewin クルト・レヴィンの話
・学問的な心理学は社会の問題から無関係ではいられないと考えていた
・アクション・リサーチ
・グループ・ダイナミクス
B. F. Skinner B.F.スキナーの話
・心理学の多くが社会の問題と無関係であることを強く批判
・行動への明確な呼びかけ
・新しい知識を得る方法として、また社会問題を改善する方法として活動主義を提唱
C. Wright Mills C.ライト・ミルズの話
・社会学的理論づけの無意味さと、ほとんどの実証的研究のくだらなさを痛烈に批判
・”社会科学者の多くは直面している課題に取り組むことに不思議なほど消極的であるように思われる”
第二次世界大戦、大学、そして地域社会への貢献
第二次世界大戦は、大学を巻き込んで、しかも進んで、これまでで最も包括的な「地域心理学」プログラムを実施した。
第二次世界大戦=ファシストとの闘い 外部からの脅威 国家をあげて戦う
大学も様々な形で戦争に協力した
普通なら大学教育を受けられなかった人たちが兵役訓練プログラムで大学教育を受けられることとなった
社会が危機に瀕しているときに差別の正当化ができなくなった
危機によって愛国心が引き起こされ、価値観や慣習が急速に変化した
大学にとっての第二次世界大戦の意義=大学と社会は切り離せないこと明らかになった。
戦前、臨床心理学は学術心理学の一部ではなかったが、大戦によって心理学の中で重要な位置を占めるようになった。
↓
援助を必要する人たちが圧倒的に多く、ニーズに応えられない
治療に関する知識や効果のレベルも不十分
パーソナリティ理論やそこから派生した臨床戦術は個人的な問題に焦点を当て、社会的文脈を不十分に扱っていた
↓
社会的文脈の重要性を臨床家は次第に認識するようになった
内的な力と外的な力の相互作用がコミュニティ心理学が生まれる土壌となった。
コミュニティ心理学は特殊な社会的背景のもとで生まれたが、その対象はその時代だけに当てはまる特殊なものではない。
“コミュニティ心理学は、現代の出来事への反応として発展したという意味では「現代的」であるが、これらの出来事は、知的、社会的、経済的基盤がはるか昔に構築された社会で起こったものであり、それらの基盤には、解決されていない対立や論争が埋め込まれていた。
コミュニティ心理学というレッテルは、その使用を正当化しようとする人はほとんどいなかったが、偶然に選ばれたわけではない。おそらく、このレッテルが主要な問題を突き止めると同時に、その問題にアプローチすべき包括的な基準を示していることは、誰の目にも明らかだっただろう。
つまり、主要な問題とは、地域社会におけるさらなる社会的崩壊や劣化をいかにして防ぐかということであり、それは、個人、家族、社会的環境、年齢、人種、民族といった集団の問題ではなく、それらの実際の、あるいは潜在的な相互関連性の問題だった。
その判断基準は、市民が心理的コミュ二ティ感覚をどの程度経験できるかということであった。すなわち、人がより大きな集団に属しており、その一部であるという感覚、個人と集団、あるいは集団の中の異なるグループ間のニーズが対立することがあっても、共同体という心理的感覚を破壊しないような方法でその対立を解決しなければならないという感覚、孤独感を薄めるのではなく、むしろ強めるような人間関係のネットワークと構造があるという感覚であった。もしコミュニティ心理学がこのような目的を持たなければ、その誕生を正当化することはできない。”
第3章に書かれていたこと
3. Some Unfortunate Aspects of American Psychology
3.アメリカ心理学の残念な側面
まず大学における心理学を検証し、伝統と実践がコミュニティ心理学の出現にどのような影響を与えたかを発見することから始める。
60年代の終わり、大学変革と外部への働きかけを求める圧力が高まる
⇔
心理学は哲学から独立して生まれた
=人間の本質を自由自在に研究する基礎科学の一つ
・社会科学ではなく生物学
・人間の行動は複雑 自然環境の中で研究すると基本的なプロセスが曖昧になるという恐れ
John Dewey ジョン・デューイの話
心理学者よりも教育学者として知られる
社会変革や実務に興味を持っていた
教育者でもあるが、個人と社会の密接な関係について研究をした人であった
しかし、デューイのこの貢献はあまり注目されていない。
George Herbert Mead ジョージ・ハーバート・ミードの話
デューイの親友、社会心理学者
自己の感覚が対人関係の文脈からどのように生じるかについての理論を展開ミードの影響は、心理学よりも社会学や精神医学の方がはるかに大きい
それはおそらく、彼の理論が思弁的で非定量的志向に思えたからであると同時に、心理学が敬遠し始めた現象学的なものを強調したから
ウィリアム・ジェームズの話
その関心と活動が心理学の実験室からプラグマティズムや宗教現象といった分野に及んだため、デューイと同じような運命をたどった。学問的心理学の立場からすれば、彼もまた哲学者に「なった」
戦前の伝統的な心理学は神話となった
社会改革や制度改革を目的とした行動、あるいは個人的な問題を抱えた個人を助けるための行動は、大学の価値感や機能に背くと考えられた。
科学的であろうと懸命に努力するうちに、学術的な心理学は宗教的になっていた。
つまり、科学のための科学に献身したために科学の天国にいる人々と、「堕落した」、あるいは才能に恵まれなかったり不適切なインスピレーションを受けたりして、実際的な問題を解決しようとする心理学者たちである。心理学者を「救われた者」と「堕落した者」に分けるというこの準宗教的な区分
強調されるべきは、人間と社会の本質をよりよく理解するために「現実世界」で行動することは、異常であると見なされていたということである。
行動主義 → 実験室実験 汚れのない大学の中で研究は行われるべきと考えられていた。
しかし、それでは人間の心理のことはよくわからない。
感想交換
コミュニティ心理学誕生の背景
第2次世界大戦で、大学および心理学は戦争に協力するために、社会との関係や応用を余儀なくされた(そのような願望もあった)。
ロシアなどとの国際問題の中で、アメリカ教育の中にはプレッシャーがあった(国単位でロシアには負けられない)。
日本の戦時中、戦後の「心理学の発展」についても調べてみたい
日本の地域コミュニティ崩壊は1980年代以降という印象(戦時・戦後、日本は全国民が大変な思いをしたから?)
アメリカは、1960年代からコミュニティ崩壊(アメリカ本土は被害を受けておらず、退役軍人が大変な思いをしたから?)
歴代の大統領が関わっていることがアメリカらしい。
環状7号線の地域住民のストレス調査(個人のストレスと、コミュニティのストレスの関係を検証)
※余談 参加者それぞれにとっての他者とは?
会社のコミュニティは、励ましてくれるところ。
会社は、良いものを一緒に作っていく人たち。居場所がある。
他者とは、喜んでほしい存在。
他者から問われる緊張感。「救われた者」と「堕落した者」・・・過激な表現!
「デューイは教育者」という”レッテル”は心理学に現場実践を持ち込ませないためだった・・・!
次回に向けて
「コミュニティ心理学」の立ち位置が、当時のアメリカ社会の時代背景や、心理学コミュニティの構図と共に少し見えてきました。
次回はまた2週間後、第4章・第5章を読みましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
