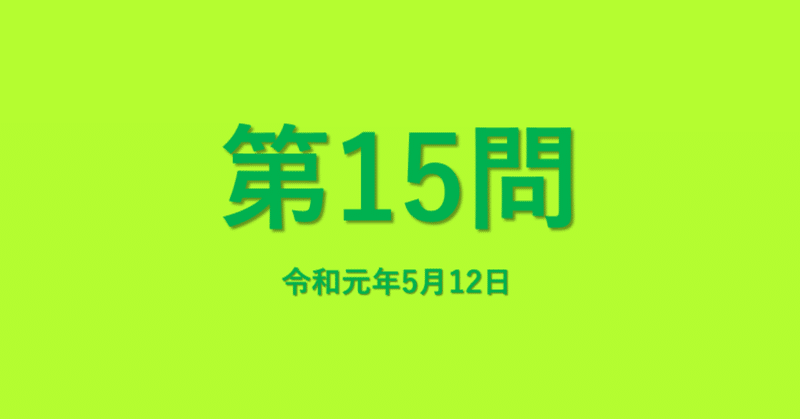
15.コミュニケーション能力を上げたい
はじめに
前回も触れた通り、現代においては社会不安や自己責任がクローズアップされ「自分」と「組織」の関係性をどう認識していくかという課題がより鮮明になってきています。
「プレトーク」前半は「レジリエンス」を意識しつつ、主に「個人の能力」を追求してきました。今日から三日間は、組織や集団の「チーム力」について触れてみたいと思います。そして18、19問で「自信」と「落ち込み」のケア方法を通して再度「自分自身」の課題を見直します。
本日は、「チーム力」の要、人間関係の改善に必要なスキル「コミュニケーション能力」のお話です。
では、早速始めましょう。
内部アプローチ・外部アプローチ
内部アプローチと外部アプローチについては、第2問「ストレス対策」のところで既にお話をしましたが、「自分」の環境設定の基本事項でもあるので、もう一度確認しておきましょう。
内部アプローチとは、
一人ひとりが考え方の癖や感じ方を観察し、よりしなやかな思考で自分を見つめ直すこと。
外部アプローチとは、
一人ひとりが他者を意識し、相互主体的に、自分に何ができるか常に考えていく姿勢。
でした。
言い換えれば、「内部アプローチ」とは内面の自分自身と対話し、自分の性格傾向や気質を明らかにすることです。これを「イントラコミニケーション」といいます。
そして、「外部アプローチ」とは他人とどのように関わるのか、それを自分の立ち位置から判断するものと考えていいでしょう。これを「インターコミュニケーション」といいます。
コミニケーションは基本的に会話のキャッチボールと言われています。その大元になるのは、特に「内部アプローチ」に関連しています。
その向き合い方は、「瞑想」や「座禅」、あるいは前回お話した、「スキ」という感覚を大切に、「自己肯定感」を見出すとこからはじめてもいいでしょう。
もちろん、この「内部アプローチ」の作業と「外部アプローチ」の取り組みは同時進行で行うことが可能です。
簡単な図をお示ししましょう。

非常に単純な図ですが、ここにはある法則があります。それは、「自分」と接している表面(※図中では青と赤の線)しか認識できないことです。
外部は「感覚器」(青線)で接しています。内部は「情動」(赤線)で接しています。
そして、 [からだ]と(こころ)と<あたま>の痛みの多面性もありました。

感覚-識別の[からだ]の痛み
情動-意欲の(こころ)の痛み
認知-評価の<あたま>の痛み
というものでした。
感覚器は[からだ]のセンサー、感情は(こころ)のセンス、そして自分はその調整を行う、<あたま>のセンスィティビティーとお話しました。
この調整を行う<あたま>の働きを専門的に言えば「認知」といいます。
これは概略ですからそれぞれ[からだ](こころ)<あたま>の代表的な働きを簡略化して示しているものです。
そして、様々な変化を来す原因は必ず触れているところで生じるということです。接するところと言ってもいいでしょう。(※つまり境界や線の部分)
そこで、この二つの図を重ねてみましょう。

ここで大切な視点は、「自分」領域は、「内部」、「外部」を分かち、「内部」へは「感情」から、「外部」へは「感覚器」で、その両方にアプローチできる「存在」だということです。
それぞれの領域の説明をお話しておきましょう。
[からだ]の外部:実際の行動活動動作。
[からだ]の自分:皮膚感覚や五感感覚。
[からだ]の内部:内臓組織皮膚の内部。
<あたま>の外部:経験に基づく判断領域。
<あたま>の自分:今の意識。覚醒の領域。
<あたま>の内部:睡眠状態無意識の領域。
(こころ)の外部:文化・慣習の集団心理領域。
(こころ)の自分:組織の帰属心など従属心理。
(こころ)の内部:自分自身の嗜好心理の領域。
ここで、特にコミュニケーション能力に関与するのは、(こころ)の心理的な部分です。
この図は、とてもシステマティックにできていて、これが「こころの立体モデル」の一部です。この六角構造が「マインド」あるいは「自我」といっても良いでしょう。
今回のコミュニケーション能力に関して、ここでは、外部アプローチのお話をするので、内部の自分自身の嗜好性(指向性)や性格傾向などには触れません。
つまり一般的な「内向的」とか「消極的」といわれているような性格傾向は、今までお話した「自己効力感」や「自己肯定感」などが課題になってきます。
基本的な自我構造の中のどの辺にコミュニケーションスキルが関与するかは、この図を見ていただくと分かるように、(こころ)の自分と外部・内部のバランスを保つスキルのお話になってきます。
その中でも今日は、外部へ向けたバランス感覚のお話を続けていきます。
コミュニケーションを阻むのはいつでも感情
世の中でコミュニケーションについて語られる場合、その多くが「何をどのように伝えればいいのか?」というスキル的な話になります。
しかし、このようなスキルに頼ってもチームメンバーが動いてくれないことがありますよね。
このような時、原因は「感情」そのものにあることが多いのです。
「どうせ無理」「しょせんダメ」「やっぱりムダ」といった言葉に代表されるチームやチームメンバーに対するネガティブ感情が、コミュニケーションに対する理解や共感、その先にある行動を阻害してしまうことがあります。
ここに対応するには、相手をまず理解することが大切です。「7つの習慣」の中にも「理解してから理解される」という方程式があるのです。
人間は「自分のことを理解してもらおうとしているうちは相手から理解されず、自分が相手のことを理解しようとしたときに、相手から自分のことも理解される」という考え方です。
以前ご紹介した「THE TEAM」には、相手の「経験」「感覚」「志向」「能力」を「相互理解」することで、伝わる度合いが全く変わってくると解説しています。
弱さを見せあえる組織
「心理的安全」とは
組織やチームのコミュニケーションを飛躍的に改善させるため、最近では様々な組織論があります。先ほどの相互理解も重要ですが、組織やチームそのものに「心理的安全」という「場」の雰囲気があるのとないのでは、チーム自体のモチベーションも全くかわってきてしまうという事実です。
学習発達理論心理学の分野からロバート・キーガンの「なぜ弱さを見せあえる組織が強いのか」にもヒントがありますが、外部アプローチとして課題は、(こころ)の「外部」文化・慣習の集団心理領域と「自分」の帰属心など従属心理領域のギャップです。
前出の「THE TEAM」には、この「ギャップ感」を少なくするために、チームの雰囲気をより活気のある「場」にする「心理的安全」という観点が語られています。

このように最近では、外部そのものの問題、つまり集団・組織の風土や風紀という観点からコミュニケーションが語られるようになってきました。
これらの視点から「改善」を目指そうとしている組織は、おそらく「活気」に満ち「やりがい」のある雰囲気が出てくるはずです。
当然、会社の風土というものは、特に社長やCEOの意識次第で「雰囲気」も変わります。このお話は、第17問集団のモチベーションのところでも触れたいと思います。
コミュニケーションの課題は「人間関係」の要なので、本日のお話が少しでも改善にお役に立てれば幸いです。
明日は、さらに「チームの在り方」「チーム力」についてお話して参ります。
本日も最後までお読みいただき
誠にありがとうございました。
ここのコメントを目にしてくれてるってことは最後まで読んで頂いたってことですよね、きっと。 とっても嬉しいし ありがたいことです!マガジン内のコンテンツに興味のある方はフォローもよろしくお願いします。
