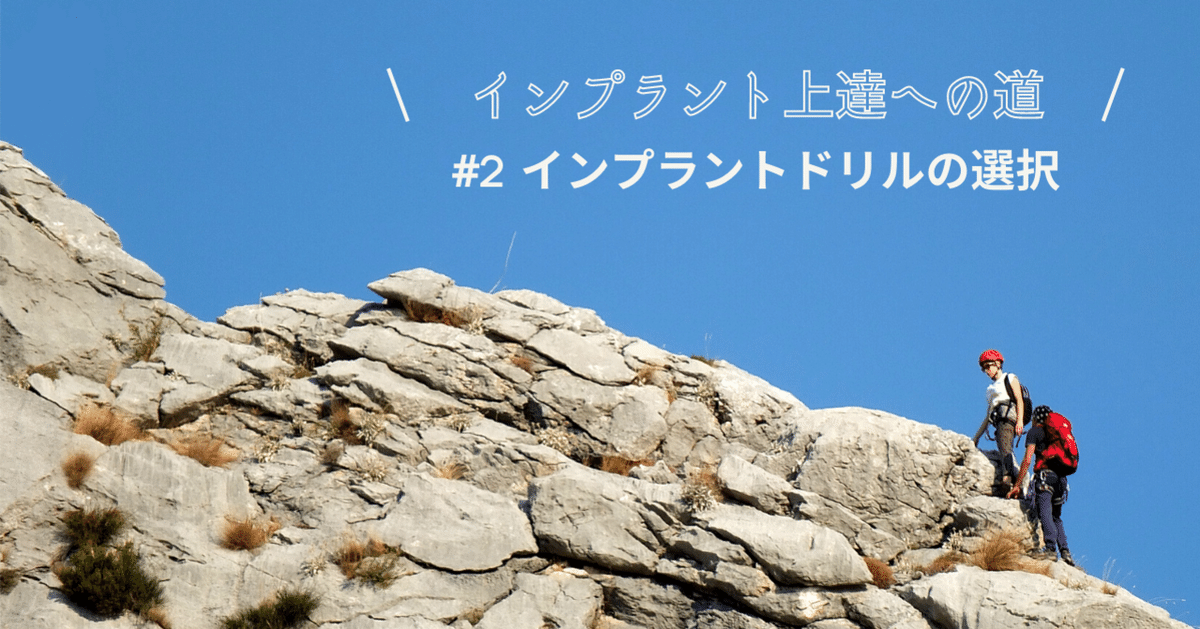
インプラントドリルの選択
シリーズ第2回は、「インプラントドリルの選択」です。今回も、医療法人社団山の丘よつば会理事長の山岡が担当いたします。インプラント治療にとって、なくてはならないもの、それが「ドリル」です!最近では、ピエゾサージェリーと言って、超音波の力で骨を削る方法もあるようですが、基本は、「ドリル」ですね。
インプラントドリルって?
基本的には、各インプラントメーカーがドリルも開発しています。各社のインプラントの形状や表面性状に合わせて、ドリルも進化し続けています。それに合わせて、我々歯科医師も技術や知識を向上させていく必要がありますね。今回は、メーカーごとの方法は伝えられない(よくわからない)ので、当院で扱っているノーベル・バイオケア社、スピーディインプラントのドリルについてお伝えしますね。
ドリルの本数
ドリルの本数は、インプラントの形状や目的によって変わります。一番わかりやすいのは、インプラントの形と同じ埋入窩を形成できるドリルでしょうか。勤務医時代に使用していたインプラントは、スクリューの形状ではなく、寸胴型であったため、最後のドリルまで形成したら、インプラントをマレット(トンカチ)で叩いて埋め込んでいました。
現代の多くのインプラントは、ネジが切ってあり、セルフタッピング(木ネジのように、穴を開けなくても、そのままぐりぐり入っていく)が施されています。細い埋入窩さえあけられれば、インプラントが埋入できるものもあります。おかげで、計画した埋入部位や深さに術者が誘導できるので、精度が高くなりました。

手術はシンプルにしたいので、できれば、ドリルの本数は少ない方がいいと感じますが、精度をあげるためには、細かく数本あった方が確実かなと思います。初めが細いドリルであれば、方向の修正が利きますので、安心です。また、骨の硬さを感じとるには、細いドリルが向いていますし、硬さに合わせて、ドリリングを微妙に変化させていきます。
クローバーデンタルでのやり方をご説明しますね。具体的には、
①φ1.5mmのドリルで、所定の長さまで掘り込みます。最初のドリルですから、慎重に方向を見定めながら、行います。
②φ2.0mmのドリルで、埋入窩を太くしていきます。前のドリルからφ0.5mmだけです。ここで大切なポイントが2点。「方向の修正」と「骨の質」を手で感じながら進めていきます。もちろん、https://note.com/cloverdental/n/n474e29932733に記載したように、超低速回転です。
③φ2.4-2.8ドリルで埋入窩を太くします。このドリルは、2段階に太さが変わり、その後のドリルが入りやすくなります。
④φ3.0mmドリル、⑤φ3.2mmドリル、⑥φ3.4mmドリルまで細かく埋入窩を太くしていきます。
ここで大事なのが、φ1.5mmで決めたインプラントの長さに合う埋入窩の長さを全て同じではなく、骨の質に合わせて、太くなるにつれて浅くしていきます。クローバデンタルで使用しているスピーディインプラントは、先端が細いですが、ほとんどが同じ太さでテーパーが付いていないので、ドリリングで調整していきます。

このドリルが太くなるにつれて、浅く形成していくことで、セルフタッピングのインプラントが骨にしっかり固定されるようになります。専門的には、「初期固定」と言いますが、木ネジのようにインプラントが骨にグググっと入るようにすることが重要です。これをアダプテーションテクニックと呼ぶそうです。これができると「即時荷重インプラント」と言って、埋入した日に仮の歯をつけることができるようになります。
インプラント自体は、3〜6ヶ月経過すれば、骨と結合します。しかし、即時荷重を狙うなら、これだけのドリルの本数が必要となります。
手術は、シンプルに短時間で受けられた方が、楽ですよね。でも、インプラントもしっかり結果が伴った方がいいですね。我々からすると、ドリリングの時間は、長い時間はかからないので、やはり確実な方法を選びたいなと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
