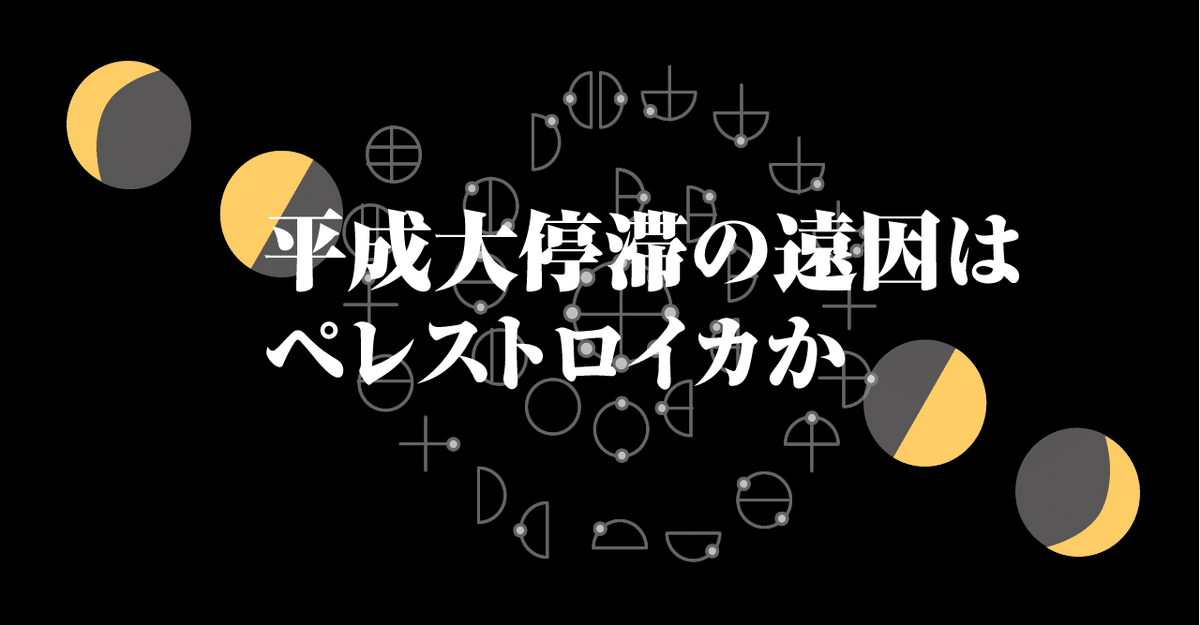
平成大停滞の遠因はペレストロイカか 9/2
〔44〕「平成大停滞」の遠因はペレストロイカか
平成から令和にかけて三〇年余にわたり日本国民がが経験した「日本大停滞」は、平成七年七月七日に財務官榊原英資が行った為替介入に端を発する「ゼロ金利」が主因と私見は考えるが、ここで問題は、財務省で榊原の後を追って昇進してきた黒田東彦が、平成二十五(二〇一三)年三月に日銀総裁に就いて敢行した異次元の金融緩和がもたらした未曽有のカネ余りにも関わらず、物価が騰がらなかったことである。
本稿ではこの問題を短く「黒田緩和の謎」と呼ぶが、その理由の第一としてわたしが挙げるのは、中華人民共和国(シナ)ならびにシナ周辺の諸国から大量に流入した低廉な物資(百円グッズ)が国内製品を駆逐したことである。
これは中華人民共和国(シナ)に対する金融・経済支援を意図的に推進したわが政策がもたらしたもので、政治的原因によるから経済学では説明できないが、これだけで黒田緩和の謎を説明できる筈はあるまい。
よって白頭狸が学力不足を痛感しながらも、探ってみたことを以下に述べてみる。
WWⅡの終戦とともに復活した金本位制がベトナム戦争の終焉を機に行き詰まり金ドル本位制のブレトンウッズ体制が建てられたが、それも束の間に崩壊し昭和四十七(一九七二)年以降の世界は変動為替の時代となった。
これに鑑みた場合、「黒田緩和の謎」は本位財の欠如が原因との見解もあるであろう。しかしながら、この問題を解くためには、貨幣制度の根本から考える必要があると、わたしは思う。
そもそも一九七〇年代前半を特色づけるオイル・ショックと石油価格の暴騰は偶然発生した事件でなく、軍産連合体と連携した国際金融連合によって計画されたもので、目的は石油を「隠れた準本位財」として信用体系に取り込むことにあった。
石油価格の人工的高騰により、各国通貨の強弱は「石油節約技術を織り込んだ工業品の生産性の上昇度」によって決せれられることとなったのである。輸出による外貨獲得力とそれを裏付ける工業生産力が当該国の通貨の強弱を決める変動為替制度の本質は、姿を顕わさない「金・石油複本位制」であった。
産・金・軍連合が企んだこの制度の実現に協力した関係者は、➀産油国の連合たるOPEC、②八百長の中東戦争を敢行したサウジラビアとイスラエル、③産油国として間接的に参加したソ連であった。
プラザ合意が成立したのは昭和六十(一九八五)年十月であるが、半年後の翌年四月、ソ連においてチェルノヴイリ原子力発電所の重大事故が発生したのは、はたして“天意”であったろうか?
それはさておき、現在はウクライナ領となったチェルノヴイリで発生した原発事故に関する報告が、共産党書記長たる自分の元に届くのが遅れたことで、党官僚の秘密主義がもたらした現実に驚愕したゴルバチョフは、硬直した社会体制を立て直す目的のもとに、言論・思想・集会・出版・報道の自由化を図り、厳重な秘密主義のもとで鎖されていた情報の公開を命じた。これが「ペレストロイカ」である。
ペレストロイカはソ連の国家社会を束縛していた社会主義思想の枠を越えて進行し、ブレジネフ時代に抑圧されていた知識人を解放し、報道機関による政府批判も許されるようになった。
その一環をなすグラスノスチ(情報公開)が、共産党の高級幹部がノーメンクラツーラと呼ばれる特権階級を形成して豪奢な生活を楽しむ現実を暴いたことで、国民の反共産党感情が一気に進み、ソ連体制は平成三(一九九一)年に崩壊した。ワルシャワ条約機構を構成していた十五カ国もこれに先立って独立し、なかにはNATOに加盟する国も出て来て、WWⅡ以後四十年余も続いた東西冷戦はこれを以て終焉するが、水面下では新たな対立が進行していた。
いただいたサポートはクリエイター活動の励みになります。
