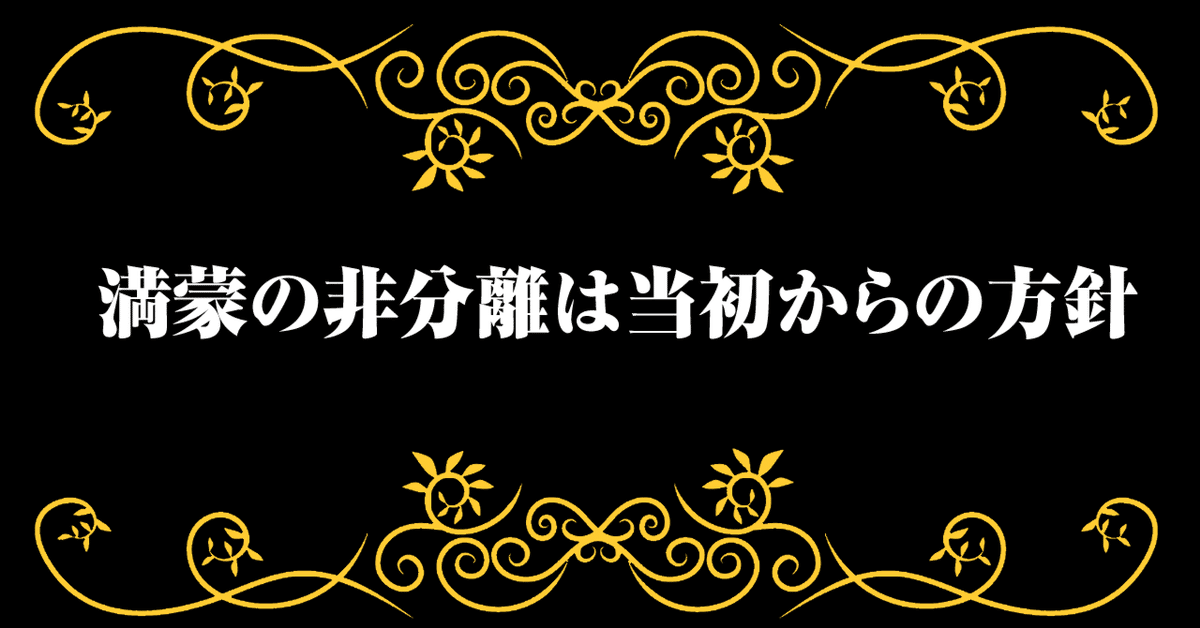
満蒙の非分離は当初からの方針 12/24
〔110〕辛亥革命後の満蒙非分離は國體の方針
前項で述べたように、辛亥革命後の愛新覚羅氏は醇親王と粛親王の両派に分かれたが、前者は「遜帝」と呼ばれ、紫禁城に居住したまま外国君主待遇を受ける宣統皇帝溥儀を名目上の棟梁とし、その父醇親王が北府と呼ばれる邸宅に居住して事実上満洲皇室のトップとなった。
後者のトップは大連に広大な領地を所有する粛親王で、部下は清朝の復興を唱えたため「宗社党」と呼ばれたが、構成員は満族と蒙古族で、辛亥革命に際して分離独立の手続きを取らなかった満蒙の地の中華民国領土からの分離独立を図ったのである。
支那の本部(固有領土・チャイナプロパー)は周知の十八省であるが、乾隆皇帝が征服した東トルキスタンを新疆省とし、また滿洲族発祥の地満洲も東北三省としたので、これに支那本部を加えると二二省となった。
歴史的に蒙古族が満洲族と同盟し通婚もしていたモンゴルは、清朝皇帝に直属する八旗蒙古・内属蒙古と自治権の下の外藩蒙古に分かれていた。西蔵(チベット)は外藩蒙古と同じく清朝の外藩で、この満・蒙・漢・回・蔵五族が構成していた多民族国家が大清帝国だったのである。
辛亥革命が指導理念とした三民主義のうち民族主義とは、支那本部を漢族の土地として、他の四民族を分離独立させることであるが、結局実現することはなく、モンゴル・チベット・ウイグルの自治独立が、今日も中華人民共和国に内在する重大問題となっている。
それでは、大日本帝国は辛亥革命においていかなる行動をしたか。
孫文を支援して辛亥革命を成就せしめたのは日本の民間人で、日本政府はむしろ清国政府の意向を受けて日本在留の革命党員を取り締まる立場を取ったが、やはり表向きであろう。
孫文の支援者として周知の玄洋社を、通俗史学は「大アジア主義の右翼団体」などと称しているが、白頭狸が受けた國體秘事伝授によれば、頭山満を名義人とする玄洋社の実質的創業者は旧熊本藩士安場保和で、実質的社主は孝明天皇の孫堀川辰吉郎を擁した杉山茂丸ということである。
明治三十年頃に玄洋社の招きで来日した孫文に堀川辰吉郎が付き添ったのはもとより偶然でなく、計画的行動であった。
白頭狸がこのほど受けた國體秘事伝授では、博物学者南方熊楠は國體奉公衆で、堀川辰吉郎の実父堀川殿(前皇太子睦仁親王で大室寅助とは別人)によって大英博物館に送りこまれたが、そこで孫文と遭遇したのは偶然でなく堀川殿の計らいによるもので、当時大英博物館の別室に入った堀川殿がそれとなく両人を観察していたという。
さらに言えば、孫文を支援した民間人として知られる久原鉱業社長久原房之介は、今日の学校史学やマスコミ史学では、陸軍大将から政友会総裁となった田中義一の経済幕僚とされているが、「吉薗周蔵手記」によれば、実は久原は上原勇作元帥の秘密の財務担当であったことが明らかである。
上原勇作は帝国軍人というより、ハプスブルク大公隷下の大東社参謀として行動していたから、財務担当の久原はその指令のもとに孫文を経済支援していたのである。
ワンワールド國體は日本皇統とハプスブルク大公に二本柱であるが、もとは同じ血統から出た。その詳細は落合莞爾著『日本皇統が創めたハプスブルク大公家』、『ハプスブルク大公に仕えた帝国陸軍國體参謀』などに詳述したからここでは省く。
國體天皇堀川辰吉郎隷下の玄洋社は、ワンワールド國體ハプスブルク大公隷下の秘密政治結社たる大東社の分身であるから、結局、ワンワールド國體が孫文を支援して辛亥革命を成就させたわけなのだ。
かくて辛亥革命がワンワールド國體の指令のもとに行われたことに疑いを容れる余地がないとすれば、革命が成就したのちに満蒙を中華世界から分離しなかったのは、ワンワールド國體が元々立てていた方針か、あるいは途中で満漢分離を不分離に方針変更したのか、ということになる。
後者とすれば「西太后と孫文が満漢分離を約した」ということに疑問が生じるが、狸としては國體伝授に従うほかないから、ここは「國體は辛亥革命の目的を最初から満蒙の非分離を方針としていた」と観ることにする。
西太后から後事を託された醇親王は、光緒皇帝亡き後の愛新覚羅家のトップとして王室連合に近く、すでに大東社に加わっていたとみられるから満漢非分離の方針に不満はなかったが、粛親王の宗社党はあくまでも満蒙の中華民国編入を喜ばず、醇親王と袂を分かって満蒙独立の兵を挙げたのである。
いただいたサポートはクリエイター活動の励みになります。
