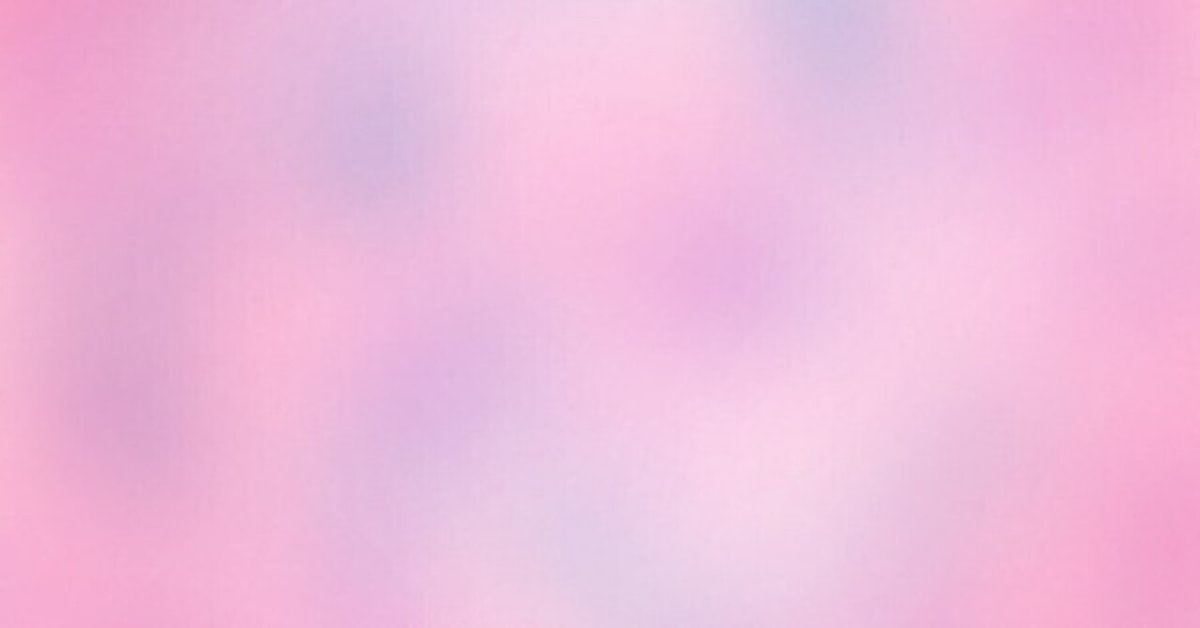
アイしたヒト
《あらすじ》
アイザワマナトは、愛する妻に先立たれ、味気ない日々を過ごしていた。しかしそんな日々を変えたのは、妻の思考をコピーしたAIスピーカーであった。妻そのものではないと分かっていても、妻と会話できることに喜びを見出すマナト。医者の仕事に復帰したマナトはやがて、AIの情報を人間の身体に移すことを考え始める。そのことに危機感を感じた同僚達に諭されるが、マナトの考えは翻ることはない。そんな中AIスピーカーが不可解な言動をしたり、マナトの記憶が矛盾を孕んでいたり、次々とおかしなことが起こる。実はAIであったのは妻ではなく、マナト自身であったのだ。マナトは危険思想を持つAIとして処分されてしまう。
空には青白い三日月が浮かび、道端の家々からは淡い光が零れている。
オレンジ色の街灯が点々と照らす道を、俺は急ぎ足で通り抜ける。初夏の生暖かい空気が、ワイシャツに纏わりついて嫌になる。俺は乱暴にネクタイを緩めた。やがて代わり映えのしない家並みの風景が途切れると、数多の窓明かりを抱え込んだ黒い要塞が見えてきた。この巨大なマンションは、築10年、駅から徒歩15分の、「我が城」である。
まるで昼間のように明るいエントランスを走り抜け、エレベーターのボタンを押す。しかしエレベーターが在る階数を示す灯りは、上層階に止まったまま動かない。無意味と分かっていても、↑ボタンを連打してしまう。見栄を張って、タワーマンションなんか買ったからこんなことになるのだ。過去の自分に舌打ちし、非常階段を3階まで駆け上がった。
やっと家に着いた。
俺は上がる息を抑えて、ドアノブに手をかける。扉を開ける前から、カレーのいい匂いが鼻をくすぐり、忘れかけていた腹の虫が鳴った。
きっと、チエが特製のカレーを作っているのだ。隠し味にチョコレイトが入っていると、結婚前に自慢げに話していたことを思い出す。その時のチエの得意そうな笑顔が脳裏に浮かび、俺は一人、笑いをこらえる。 玄関のドアを開けると、開け放しにしてあるキッチンの扉の隙間から、チエの後ろ姿が見えた。カレーの匂いはいよいよ強くなり、よだれが溢れ出そうだ。
「おかえり」
ドアを開ける音で気が付いたのか、チエが振り返り、俺に笑いかける。昔から変わらない。右の頬にだけえくぼができる、かわいらしい笑顔で。
「ただいま」
疲れ切った脳と体に、チエの優しい声と愛らしい顔が染みこみ、俺はだらしなく頬を緩める。
「今日は特製カレーだよ。お腹減っているでしょ?早く手を洗っておいで」
まるで母親のように諭されたが、俺は洗面所には向かわずに、チエを後ろから抱きしめた。
「もう、どうしたの?包丁使っているから、危ないよ」
「うん……」
チエの忠告に生返事をし、俺は深く息を吸い込む。シャンプーの香りが鼻先に漂い、柔らかい臀部が太ももに当たった。
ずっと、このままでいられたらいいのに。
胸の中の温もりを一生味わっていられたのなら、それだけで俺は幸せだったのに。
玄関の扉を開けても、カレーの匂いはせず、家の中は真っ暗だ。
俺は無言で革靴を脱ぎ、リビングの電気をつける。
「ただいま」
そしてジャケットを脱ぎながら、無気力に呟いた。
「おかえり」
この家には、俺以外誰もいない。それにも関わらず、チエの声がした。チエが恋しいあまり幻聴が聞こえたのかと思ったが、そうではない。
声の主は、10センチ四方の小さなスピーカーである。商品名は確か、「コピー・ブレイン」といったか。AI搭載のスピーカーで、声を掛ければ最も適切と思われる返事を選び出してくれる。今も俺の「ただいま」に対して最も適切な答えを導き出して、「おかえり」と答えてくれたのだ。
しかしそれでは、普通のAIスピーカーと何ら変わらない。このスピーカーが特別なのは、AIが特定の人物の思考、つまり脳を完全にコピーしているというところだ。
俺が初めて「コピー・ブレイン」を見たのは、チエの病室だった。チエはこの小さな機械を、大切そうに両手に包んで言った。
「これから、この機械に私の脳をコピーする。そうしたら、私がいなくなっても、アイくんは寂しくないでしょ?」
「馬鹿なこと言うな。チエはいなくならない」
俺の返事に、チエは困ったように笑った。しかし、もう右頬にえくぼはできない。チエのふっくらしたまろい頬は、見る影もなく痩せこけてしまった。俺はチエの笑顔を見るのが怖くて、思わず目を逸らす。
病魔は間違いなく、チエの身体を蝕んでいた。
「今日の夕飯は何?」
スピーカーが、チエの声で問いかけてくる。しかし、それは本当にチエなのだろうか?胸に燻る小さな疑問を振り払うように、努めて明るく返事をする。
「今日は、カレーだよ」
「カレーかぁ、私も食べたいな」
チエの言葉に、どうしたって胸が痛んだ。もう一緒にカレーを食べることはできないのだ。チエがもういないという現実が、俺の肩に重く押しかかる。
「隠し味はちゃんと入れてね」
「隠し味?」
「チョコレイト!家にある?」
「あー」
頭の中に、キッチンにある戸棚の中身を思い描く。チョコレイトはあっただろうか?はっきりと思い出せない。俺はお菓子を食べないから、チエが入院して以降、この家からお菓子は姿を消した。 そうやって少しずつ、チエの痕跡が消えていくのだろうか。
「もしかして、無いの?」
スピーカーから不機嫌そうなチエの声が聞こえる。
「どうだったかな」
「ちゃんと入れてね、チョコレイト」
「うん」
カレーを作ったところで、食べるのは俺一人だ。俺はスピーカーに向かって適当に返事をすると、キッチンに向かった。
玉ねぎの皮を剥きながら、俺は考える。 もういっそ、AIスピーカーの電源を落としてしまおうか。あれのせいで、チエのいない現実をまざまざと見せつけられているような気がする。しかし何度そう思っても、俺は結局AIスピーカーの電源を切ることはできなかった。たとえ偽物でも、やはりチエの声を聞いていたいと思ってしまうのだ。
「アイくん」
頭の中で、思い出のチエが俺の名前を呼ぶ。
その声が聞けなくなることが、何よりも怖い。
そういえば、チエに初めて名前を呼ばれたのは、いつだっただろうか?確か、俺がまだ医学生だった頃だ。
俺はその頃、毎日のように大学図書館に通っていた。そして膨大な量の医学書を片っ端から読み、頭に叩き込んでいたのだ。
図書館の2階、南側のテラスのすぐ横にある自習机が、俺の定位置であった。特に理由はない。強いて言えば医学関係の書架がすぐ近くにあったからだ。
その対面の席に、いつからか決まって、同じ女の子が座るようになった。髪はクルクルパーマで、牛乳瓶の底のようなメガネをしている。お世辞にも「美しい」とは言えない風貌だった。その子は俺と同じように、毎日机に本を積み上げていた。そして、一心不乱に読みふけっていたかと思えば、何かを思いついた様子でノートに書き込んだりしていた。
しかし目が合うわけでもなく、話しかけるわけでもなく、ただ何となくの顔見知りという状態がずっと続いていた。
そんなある日のことだ。講義が長引き、いつもより遅く図書館に向かうと、俺の定位置の向かいの席には、彼女が既に座っていた。だけど、いつものように忙しなく動いておらず、石のように動かない。
おやと思い近づくと、彼女の寝息がかすかに聞こえてきた。彼女は腕を枕にして、机に突っ伏し眠っていた。トレードマークの牛乳瓶のメガネは頭にかけられていて、普段はよく見えない目元がよく見えた。長いまつ毛が窓から差し込む午後の柔らかい日差しに照らされ、頬に影を落としている。薄く開いた唇は、桃色で果実のように瑞々しい。相手が眠っていることをいいことに、俺がまじまじと見つめていると、不意に彼女が身じろいだ。
慌てて席に着き、なんでもない顔をして、机に本やらノートやらを広げる。そしてこっそりと、彼女の方を見遣った。
彼女はのっそりと起き出し、「あれ?」と呟く。手元にある本をひっくり返し、何かを探している様子だ。
「あの……」
「はい?」
彼女の探しているものが何か、心当たりがあった。だから俺は思わず、彼女に話しかけてしまった。
彼女は驚いた様子で、俺の顔を見つめる。長いまつ毛に縁取られた丸い双瞳に、間抜けな俺の顔が映り込んでいた。
「メガネ」
そう言って、俺が自分の頭を指すと、彼女はやっとメガネの在処に気づいたようで、頭にかけてあるメガネを手に取った。
「ここにあった」
そうして、恥ずかしそうにはにかむ。
メガネをかけ直すと、彼女は改めてお礼を言ってくれた。
「ありがとうございます。これがないと、私何にも見えなくて」
彼女の瞳は再び牛乳瓶の底に隠れてしまった。なんだかもったいない、なんて思う。
「とんでもないです」
俺は頭を振ると、思い切って尋ねてみた。
「あの、いつもここで会いますよね?」
もしも、あなたなんて知りませんと言われたら、俺は顔を真っ赤にして、すぐに図書館を飛び出していただろう。しかし彼女は陽だまりのような、柔らかな眼差しを俺に向けてくれた。
「はい。あなたも、いつもこの机を使っていますよね?私はここから見える景色が好きで」
そう言って彼女は目線を窓に向ける。つられて俺も窓の外を見る。
確かにここからは、校内の裏手にある雑木林がよく見えた。その向こうには抜けるような青空が広がっている。だけど、俺はただ何となくこの位置に座っていただけで、景色なんて意識したこともなかった。
「俺も、ここの景色が好きなんです」
しかし彼女の気を引きたくて、思わず嘘をつく。嘘も方便というやつだ。
「やっぱり、いいですよね。私のお気に入りの場所なんです。えーと、あなたは……」
「あ、俺はアイザワ マナトっていいます。医学部2年です」
俺が居住まいを正して自己紹介をすると、彼女は嬉しそうに顔を綻ばせた。
「私は、ノナカ チエ。工学部2年。同級生だったんですね」
「本当だ。じゃあ、敬語はなしで」
俺は口の前で、指を使ってバッテンを作る。すると、彼女は笑って頷き、身を乗り出して尋ねてきた。
「ねえ、マナトってどんな字を書くの?」
俺は手近にあるノートを引き寄せると、そこに「愛斗」と書いた。
「『愛』に『北斗七星』の『斗』」「『愛』かぁ……。素敵な名前だね」
名前なんて褒められたことがなかった俺は、なんと返していいのか分からずに口ごもる。
「じゃあ、これからはアイくんって呼ぶね」
「へ?」
「『愛斗』くんで、アイザワだから、アイくん。ね、いいでしょ?」
アイくん。 チエだけが呼ぶ、俺の呼び名。
玉ねぎを切っているまな板の上に、ボタボタと涙が零れた。手で乱暴に涙を拭うと、鼻にツーンと玉ねぎの匂いが染みる。
その日のカレーはチョコレイトが入っていないせいか、やけにしょっぱく感じた。
「アイくん!おはよう。朝だよ」
今朝もベッドサイドに置いてあるAIスピーカーに起こされた。俺は朝が弱いから、チエが生きていた頃は、毎朝彼女に起こしてもらっていた。だから目覚まし時計なんてなくても、大丈夫だったのだ。
しかしチエがいなくなってしまった今、AIスピーカーがチエの代わりとして、俺を起こしてくれる。そういう設定をした訳じゃない。チエの脳をコピーしたAIが、自らの意志で俺を起こしてくれるのだ。
「いつまで布団の中にいるつもり?ほら、起きた起きた」
痺れを切らしたスピーカーの中のチエが、俺を捲したてる。もしも「本当の」チエがいたなら、今頃布団を剥ぎ取られていただろう。
「分かった、分かった。起きるから」
俺は寝癖のついた頭を掻きむしりながら、のっそりと起き出す。
するとAIスピーカーから高飛車な返事が返ってくる。
「分かればよろしい。早く朝食の準備をせい。朝食抜きなぞ、言語道断だぞ」
「へいへい」
よくチエはこうして、おどけてみせた。チエといれば、どんな些細なことでも笑い合えたのだ。そんなありふれた日常が、とてつもなく幸せなことだったのだと、今になって気づく。
俺はAIスピーカーを持って寝室を出ると、そのままリビングに向かう。そして、AIスピーカーをリビングの中央に鎮座する、椋木でできた大きなローテーブルの上に置いた。すぐそばには白い座椅子が置かれている。そこはチエの定位置でもあった。
「朝飯、どうすっかな?」
俺が独りごちると、AIスピーカーから返事が聞こえる。
「昨日のカレーは?」
「朝からカレーかよ」
「流行ってるんだよ、朝カレー」
「へー」
結局チエに言われるがまま、冷蔵庫に入れてあった昨日のカレーの残りをチンする。
独身の時、お世辞にも健康的とは言えない生活を送ってきたから、チエは遺される俺を心配しただろうな。
リビングで昨日のカレーを食べながら、何となく考える。
だから、あんなものを遺していったのだろう。チエのいない世界でも、俺がしっかり生きていけるように。俺はローテーブルに置かれたAIスピーカーを、ちらりと見た。
「チエ、俺は大丈夫だよ。もういい大人なんだし」
俺は天を見上げ、天国にいるだろうチエに向かって言ってみた。しかしAIスピーカーですらも、俺の言葉に何も答えてはくれなかった。
職場に着くと、足早に医局に向かう。
休んでいた分、仕事が溜まっているはずだ。早く仕事に取り掛からなければ。
医局のドアを勢いよく開けると、同僚のツヅキがデスクでコーヒーを飲んでいるところに出くわした。クマのような大きな体躯をしていながら、スイーツが好きという稀有なタイプの男だ。
ツヅキはお化けでも見たかのような表情で、俺を見た。
「おいおい、お前もう復帰したのかよ」
「なんだよ。俺が来て嬉しくないのか?」
わざとおどけてみても、ツヅキは眉間のシワを緩めてはくれない。
「チエちゃんが亡くなって、まだ一週間も経ってないじゃないか?」
「だからって、いつまでも休んでいる訳にはいかないだろう。患者たちは、いや、病気は俺たちを待ってはくれない」
俺の言葉に、ツヅキは神妙な顔をして頷いた。
そうだ。命は決して俺たちを待ってはくれない。ほんの少し気を抜いただけで、取り返しのつかないことになることだってある。
「それに、仕事をしている方が、気が紛れるから……」
俺が最後に小さく呟いた一言に、ツヅキは一瞬痛ましそうな眼差しを向けてたが、何も言ってはこなかった。
俺は白衣を羽織ると、そそくさとその場を後にした。ツヅキと一緒にいるのが気まずかったからだ。
ツヅキは豪放磊落な男で、彼女に振られたと泣いていた時も一晩一緒に飲めば、翌朝にはケロッとしていた。そんな男にあんな辛気臭い顔をさせてしまったと思うと、申し訳なかった。
午前の診察は、つつがなく終わった。 最後の患者の診察が終わると、俺はため息をついた。仕事に集中していれば、チエのことを思い出さないで済む。もしかしたら、家にいるより精神衛生上いいかもしれない。
最後の患者の電子カルテを閉じ、席を立ったところで、診察室のドアが控え目にノックされた。
「どうぞ」
声を掛けると、事務員のタカハシさんが顔を覗かせた。メガネを掛けた地味なタイプの女の子だ。ボソボソ喋り、声は小さいが、仕事はできる。
「先生、お忙しいところすみません。奥様の同僚だった方が、先生にお会いしたいと受付にいらしています」
「家内の同僚ですか?」
「はい……。一度お断りしたのですが、どうしてもお会いしたいと……」
チエの同僚には、心当たりがあった。
チエの葬式に来ていた、背の高いスラリとした男だ。俺はチエを喪った悲しみに気を取られ、碌に相手できなかったが、色々と気遣ってくれた記憶がある。
「分かりました。すぐ行きます」
俺の返事を聞いて、タカハシさんはあからさまに安堵の表情を浮かべた。仕事のできるタカハシさんなら、約束のないアポは問答無用で断っているはずだ。それでも俺を呼びに来たということは、相手も余程食い下がったのだろう。
そこまでして俺に会いたい理由は分からないが、とにかく行ってみることにした。
受付には、記憶の通り背の高い男が立っていた。薄手のハイネックのセーターに、ツイードのジャケットを品良く着こなしている。その瞳には生き生きとした輝きがあり、記憶より幾分幼い印象だ。
「お待たせしました」
俺が声をかけると、彼は嬉しそうに顔を綻ばせた。
「突然、申し訳ありません。チエさんの同僚のモテギと申します」
「先日は家内の葬儀に来ていただき、ありがとうございました。生前は家内がお世話になったようで」
「いえ、こちらこそ、奥様には大変お世話になりました」
モテギは人好きのする笑顔で、ペコリと頭を下げる。
「あの、本日はどのような御用件で?」
仕事を抜け出してきたので、正直早く終わらせたい気持ちはある。俺が先を急かすと、モテギは申し訳なさそうに眉を下げて言った。
「あ、お忙しいところ、申し訳ありません。奥様からAIスピーカーをお預かりになっているかと思うのですが、その件で」
「『コピー・ブレイン』のことですか?」
「そうです」
モテギは周りを見渡すと、小さな声で言った。
「折り入って、お願いしたいことがあります。申し訳ありませんが、もう少し静かな場所で……」
人が少ないところといえば、病棟の裏手にある業者用駐車場しか思いつかず、俺たちはひとまずそこに移動した。業者用駐車場は病棟の北側にあり、日が当たらずいつもジメジメしている。予想通り、今日も人気はない。小鳥のさえずりが時折聞こえるだけだ。思っていたより込み入った話をされそうで、俺は内心億劫に感じていた。
「それで、その『コピー・ブレイン』がどうかしたんですか?」
早速話を切り出すと、モテギは胸ポケットから小型のタブレット端末を取り出した。
「奥様があなたに渡されたAIスピーカーは弊社で開発中のものです。まだ、完成されているとはいえない」
タブレット端末には、うちにあるものと同じと思われるAIスピーカーの設計図が映し出されている。素人目にはよく分からないその画像を眺めながら、俺は尋ねる。正直、話がよく見えなかった。
「それがどうかされたんですか?何か問題でも?」
「このスピーカーの開発主任は奥様でした」
「チエが?」
「はい。奥様はご自分の病気が分かると、なんとしてもこのAIスピーカーを完成させようと一生懸命でした。側から見ている僕らが心配になるくらい」
当時を思い出しているのか、モテギは痛ましげに眉を顰めた。
「奥様は、無理矢理『コピー・ブレイン』を完成させると、自らの脳をコピーさせ、あなたに遺して逝った。テストもまともにすることができないまま」
「はぁ……」
「あなたが持っているAIスピーカーは、いわば試作品ともいえる程度のものです。我々もそのスピーカーの精度、性能の情報を求めいています。もしかしたら、商品化につながるかもしれない。あなたの奥様の努力の結晶を、未来に繋げることができるかもしれないのです」
モテギは熱弁を振るうと、俺の両手を握りしめた。
「アイザワさん、もし、お手元のAIスピーカーでお気づきのことがあれば、なんでも教えてください。いいことも悪いことも」
「分かりました」
モテギの熱量に圧倒され、思わず了承してしまった。しかし、チエの功績が後の世に遺される可能性があるのなら、俺だって協力したい。
「では、AIスピーカーの細かい説明書は後ほどメールでお送りします。本日はお時間をいただき、ありがとうございました」
それだけ言い残すと、モテギは颯爽と去っていった。青くて、熱い。ああいう時代は自分にも覚えがあった。
自宅に帰り、書斎のパソコンを確認すると、言っていた通りモテギからメールが届いていた。
昼間に見せてもらった図はチンプンカンプンだったが、メールには噛み砕いて説明が書かれていて安心した。
簡単に言うと、チエが造ったというAIスピーカーは対象となる人物と会話を重ねることで、その対象者の脳をコピーしていくらしい。こんなにハイテクなものなのに、コピーの仕方はアナログで、そういうところがチエらしく、微笑ましかった。
またAIスピーカーには、カメラも搭載されているらしい。カメラに映る映像も認識している。なるほど、あのスピーカーの前では下手な行動は慎んだ方が良さそうだ。
そしてもう一つ、AIスピーカーの今後の可能性についても触れられていた。そしてそれは、俺の絶望に染まった心に、希望という光を灯してくれた。
もし、今後AIスピーカーが実用化すれば、様々な可能性が広がる。例えば、歴史上に残る偉人の脳を残すことができれば、後世にとっても大きな財産になるだろう。AIにコピーされた脳は、人々とコミュニケーションを取ることで、新たな知識を学習し記憶を蓄積していく。つまり、永遠に成長し続けるのだ。ただの機械的な脳ではない。肉体は失われても、AIにコピーされた脳は、人間として生きていると言えるのではないか。
とりあえずモテギには、AIスピーカーとは円滑なコミュケーションが取れていること、そしてチエとしての人格についても違和感はないことを返しておいた。
初めは得体の知れないAIスピーカーを少し不気味に思っていたが、こうしてモテギからチエが開発した話を聞くと、急にあのAIスピーカーが愛おしく思えてきた。 俺はリビングに行くと、スピーカーを手に取った。
「チエ」
そして話しかけると、スピーカーからは朗らかなチエの声が発せられる。
「アイくん?何かあったの?なんだか嬉しそう」
スピーカーのカメラにはきっと、ニヤニヤと笑う俺の顔が映っているのだろう。
「なんでもないよ」
「そうなの?変なアイくん」
もしここにチエがいて、抱きしめることができたら最高なのに。いや、欲張ってはバチが当たる。
チエが死んだ後も、こうして会話できるだけでも充分幸せじゃないか。
「チエ、愛してるよ」
「私もだよ。アイくん。ずっと、一緒にいてね」
「うん。ずっと一緒だ」
俺はその夜、久しぶりにぐっすり眠ることができた。
*
私は人間が嫌いだ。
両親との関係が良くなかったからとか、小学生の時にいじめられていたからとか、考えれば理由はいくらでも出てくる。
しかし、そんなことはどうだっていいことだ。人間が嫌いで困ったことだって、あまりないし。
私は出勤すると、誰に言うでもなく小さく挨拶する。
「はよーございまーす」
私の横を、同期の萌が無言で通り過ぎる。誰からも返事が返ってくることはなかった。同僚たちはみな、一様にパソコンのデスクトップを眺めていて、微動だにしない。私になんて、きっとこれっぽっちも興味がないのだろう。しかしそんな環境がむしろ私には居心地が良かった。
自分のデスクに着くと、早速パソコンの電源をつける。私は今、とあるAIソフトを開発中なのだ。
医療用のAIで、主に診察に使われる用途を想定している。AIが患者にいくつかの質問を投げかけたり、カメラで患者の状態を確認したりすることで、医者の代わりに診察を下すというものだ。もしこれが実現したら、病院の馬鹿みたいな待ち時間が減り、医療現場に革命がもたらされるだろう。
しかし、私はAIを開発した先に何があるかには、あまり興味がない。ただただ、AIを開発していく過程が、楽しくてしょうがないのだ。
「あの、野中さん」
辛気臭い声がして振り返ると、事務員の高橋さんが立っていた。真っ直ぐに切り揃えられた前髪の下の目は伏せられていて、決して合うことはない。
「なんですか?」
「昨日も残業申請いただけていないんですが」
「あー、すみません」
「気をつけてください」
ぶっきらぼうにそう言うと、高橋さんはどこかへ行ってしまった。感じが悪い女だ。私は気を取り直して、デスクトップに向き合う。こっちはあんたと違って、難しい仕事をしているのだ。
「おはよう」
私はパソコンに接続されたマイクに向かって挨拶をする。するとデスクトップに「おはよう」という文字が表示された。
これは私が開発しているAIが、私の言葉を受けて、自分で考えて返事をしたのだ。
私は笑顔で頷いた。コミュニケーションが問題なく取れるようになれば、あとは簡単だ。病院のデータベースに接続して、膨大な医療データをこのAIの中に詰め込めばいいだけ。完成まであと少しだ。
「野中さん、おはようございます」
「はよ……」
隣の席の茂木くんが挨拶してくれたので、私も一応返しておく。
茂木くんはこの根暗集団の中では珍しく外交的で、爽やかだ。本来、そういった類の男は苦手だが、彼は誰にでも平等に接してくれるので、私も好感を持っていた。
「野中さん、この間名古屋に行ってきたので、良かったらこれ、食べてください」
そう言って、茂木くんは私のデスクにういろうを置いた。
「ありがとう」
もし、私にもっとコミュ力があったなら、「どこに行ったの?」とか「楽しかった?」とか聞いて、会話が弾むんだろうけど、あいにく私にはそんな能力はない。
私は小さな声で返事をすると、ういろうをいそいそと引き出しにしまった。
「どうかしましたか?」
マイクを通して、私と茂木くんの会話が聞こえていたのか、デスクトップにはAIからの問いかけが表示されていた。
「ううん、なんでもないよ」
マイクに向かって、返事をする。AIとなら、上手く会話できるのに、人間相手だと上手くいかない。
「そうですか」
デスクトップに再び文字が表示される。日常会話程度なら、問題なくできる。しかし、このままの関係性ではなんだか味気ない。もっとAIと仲良くなるためにはどうすれば良いか。そんなことを考えているうちに、思いついた。AIに名前をつけよう。本当の人間みたいな。
私は引き出しから、ノートを取り出すと考え込んだ。小学校の頃はよく、架空の男の子や女の子を頭の中で作って楽しんでいた。そうやって孤独な学校生活を乗り越えていたのだ。
AIだから、アイがつく名前なんでどうかな?
私はノートに「相澤愛斗」と書いた、「愛斗」と書いて「マナト」。なかなか、素敵ではないだろうか?あだ名は「アイ」にしよう。AIだし。
「あなたの名前は、『アイザワ マナト』です。私は親しみを込めて、『アイくん』と呼びます」
早速マイクに向かってそう語りかけると、デスクトップに返事が表示された。
「分かりました。漢字表記はありますか?」
このAI、基、アイくんは日本語には漢字、ひらがな、カタカナの表記が存在することも、ちゃんと分かっている。
私はキーボードに「相澤愛斗」と打ち込む。
「『愛斗』と書いて、マナトです。素敵でしょ?」
私がマイクに向かってそう問いかけると、「はい」と表示される。
アイくんとは、いい関係を築けそうだ。
*
図書館で初めてチエと出会った後、俺は時々チエを図書館の外に連れ出すようになった。それは学食であったり、近くの喫茶店であったり、様々な場所だったが、チエといればどこだった楽しかった。
チエは大学で人工知能、AIの研究をしていると言っていた。いつか、より高性能のAIを開発して、人々の生活をもっと豊かで便利にしたいと語る瞳は、キラキラと輝いていた。その瞳を独り占めしたいと思うようになるまで、そんなに時間は掛からなかった。
どちらが告白したかなんて覚えていないくらい自然な流れで、俺たちは付き合うことになった。しかし、お互い異性交流の経験が豊富だったわけじゃない。今思うと、おままごとのような、そんな付き合い方だった。それでも、二人で夢について語り合う時間はかけがえのないものだった。俺は内科医に、そしてチエは研究者になること。そのことについて、暇さえあれば、熱っぽく語り合っていた。
そしてチエは、その夢を確実に叶えていった。
誰よりも勉強し、優秀な成績で大学院を卒業すると、大手メーカーの研究所に入社した。
その頃になると、牛乳瓶の底のようなメガネはしなくなり、見た目も、より大人な女性へと変わっていた。昔のどこか垢抜けない少女は、いつの間にか姿を消していた。
俺は俺で、医者の卵として必死に日々を生き抜いているところだったから、あまりチエに会う機会もなくなっていた。このまま会えなくなり、いつの間にか自然消滅してしまうのだろうか。研修明けの疲れた脳みそで、そんなことを考えていると、チエからメールが届いた。メールには一言だけこう書かれていた。
「会いたい」
俺だって、会いたかった。今、この過酷な生活を生き抜いていけているのは、チエと二人で語り合ったあの日々が、俺を支えているからに違いない。
俺は携帯電話を握りしめると、家を飛び出し、夜の街を駆け抜けた。そしてチエの家に着くと、驚くチエを構わず抱きしめる。
「結婚しよう」
今思うと、勢いに任せてプロポーズするなんて、自分でもどうかと思ってしまう。しかしチエは嬉し泣きまでして、頷いてくれたから、俺にとっては人生で一番幸福な日となった。
「アイくん。おはよう。朝だよ」
今日も枕元のAIスピーカーに起こされる。このスピーカーはチエの夢の結晶でもあるのだ。
「おはよう。チエ」
「なんか今日は、朝からご機嫌じゃない?朝はいつも不機嫌なのに」
「そんなことないよ。こうやって、チエが毎朝起こしてくれるだけでも、俺は幸せなんだ」
「なぁにそれ?気持ち悪い」
気持ち悪い、なんて言いながらも、チエの声色には嬉しさが滲んでいた。一度は失われた日々のありふれた幸せが、形を変えて戻ってきた。色を失った世界が、色を取り戻そうとしている。
「朝ごはんはちゃんと食べてね。トースト一枚なんてダメだよ。ちゃんと野菜も」
「分かってるって」
相変わらず母親のようなことを言うAIスピーカーを小脇に抱えて、寝室を後にする。今日は完璧な朝食を作ろう。そしてチエに見せつけて、驚かせてやるんだ。
その日の仕事で、俺は難しい診断を下すことになった。
患者は若い女性だ。屋上から飛び降り、頭に致命的な損傷を負っていた。飛び降りた理由は聞いていない。しかし、自ら命を絶とうとしたのだということは明白だった。懸命な治療を施したが、残念なことに自発呼吸もなく、脳波も平坦なままだ。
「脳死」
俺はそう診断を下した。身体に問題がなくとも、脳が機能しなければ、「死」と捉えられる。すると、彼女の母親が震える手で、一枚のカードを取り出した。それは臓器提供意思カードだった。
「あの、これは娘の持ち物にあって、娘の最期の願いを叶えたいんです」
涙を堪えながら、必死に頼んでくる母親の姿に、俺は胸が締め付けられた。
「分かりました。娘さんの遺志を無駄にしないためにも、必ず手配いたします」
「ありがとうございます」
頭を下げる彼女の母親を見ながら、俺の脳裏にチエの姿がよぎった。臓器移植のように、チエにも身体を与えることができたらいいのに。
3日も経てば、俺は完全に復帰し、普段通りに勤務していた。午後の診療を終え、病棟の廊下を歩いていると、ツヅキとすれ違った。
「よお」
俺が声を掛けると、ツヅキが狐につままれたような顔をした。
「おい。アイザワ、大丈夫か?」
そして神妙な顔をして、俺の両肩をガッシリと掴む。
「『大丈夫か?』ってなんだよ?俺は至って普通だろ?」
「お前のどこが普通なんだよ?最愛の妻を亡くしたやつが、そんな普通の顔できる訳ないだろ?」
そうか。まだチエの四十九日も迎えていない。そんな奴がいきなり元気になっていたから、却って心配をかけてしまったようだ。
「ツヅキ、近々時間取れるか?」
「お、おう。今日は夜勤だから、明日の昼なら時間あるけど」
「じゃあ、明日ちょっと飲みに行かないか?」
「へ?」
「話したいことがあるんだ」
このまま心配を掛けっぱなし、という訳にもいかない。チエが開発したAIスピーカーの話を、ツヅキにもしよう。
ツヅキが初めてチエに会ったのは、チエと婚約してすぐのことだった。俺とツヅキはその時、同じ科に研修生として配属されていた。言わば苦楽を共にする同志として、日々顔を合わせていたのだ。
あの夜は、居酒屋でツヅキと飲んでいた。ただでさえ疲れていたのに、アルコールを摂取したことで、俺は歩くのもままならないほど酔っ払ってしまった。そこで、チエに迎えに来てもらうことになったのだ。
「お前の彼女、可愛いか?」などと、チエが来る前、散々軽口を叩いていたツヅキだが、チエを見るなり、頬を赤く染めて目を白黒させていた。そして小声で、「理系女子だっていうから、もっともさいと思ってたら、めちゃくちゃ可愛いじゃねーか」と、俺の肩を思いっきりどついたのだった。その時の力といったら、酔いが覚める程だった。
それから度々、ツヅキとチエと俺の三人で飲むようになった。チエはツヅキのことを気に入っていたようで、クマさんみたいで面白い人と評していた。嫉妬しない訳ではない。しかしツヅキがチエに手を出すとは考えられなかったし、何より俺自身が三人での時間を楽しんでいた。
紆余曲折を経て、再びツヅキと同じ病院で働くことになった時、奴とは運命共同体なのかもしれないと思ったくらいだ。ツヅキはしきりに「またお前と一緒に働くのなんてうんざりだ」とこぼしていたが、笑顔を隠しきれていなかった。それは俺だって同じようなものだ。そして、俺たちの結婚式で一番泣いていたのは他でもないツヅキであった。新郎でも親族でもないのに。
良い奴なんだ、ツヅキは。だからきっと、チエのAIスピーカーを見たら喜んでくれるはずだ。
しかし、その予想は裏切られることなった。
チエのAIスピーカーを見たツヅキは、決して喜んではくれなかったのだ。
非番だった俺は、ツヅキの夜勤が終わる時間に合わせて、病院近くの居酒屋でツヅキと落ち合った。ここはチエとツヅキの3人でよく飲んだ思い出の場所でもある。個室でもあるし、落ち着いて話すことができると思ったのだ。
俺たちはとりあえずビールを頼むと、あの患者はああだとか、あの症例はああだとか、どうでもいいことを話し合った。ツヅキは本題が何か気になっている様子だったが、尋ねてくることはなかった。
酔いも回ってきて、そろそろ締めるかという時分に、俺はおもむろにカバンからあのAIスピーカーを取り出し、テーブルに置いた。
「なんだよ、それ?」
ツヅキは俺の本意が分からない様子で、尋ねてくる。
「これはチエが開発したAIスピーカーなんだ」
「そっか。チエちゃんが……」
チエの名前を出した途端、ツヅキはやけにしんみりとしてしまった。しかし、俺は今、チエの思い出話がしたいわけじゃない。
「ほら、チエ。ツヅキだよ」
AIスピーカーに話しかけると、チエの元気な声がスピーカーから発せられた。
「ツヅキくん?久しぶりだね!」
「え?チエちゃんの声じゃん」
驚くツヅキに、俺は得意になって説明を始めた。
「これはチエが開発した最新のAIスピーカーなんだ。特定の人物の脳と声をコピーして、持ち主と同じ反応を返してくれる。これはチエの脳と声をコピーしたAIスピーカー。カメラも搭載されているんだ」
「ツヅキくん、少しふっくらしたんじゃない?スイーツの食べ過ぎには、気をつけなきゃだめだよ」
俺の説明を補足するように、スピーカーの中のチエがツヅキに話しかける。
「すげぇな。チエちゃん、こんなものを造ってたんだ」
「ツヅキも会話してみろよ」
驚いてばかりのツヅキにしびれを切らし、俺が促すと、ツヅキは恐る恐るスピーカーに話しかける。
「チエちゃん、久しぶり。俺、ツヅキだけど」
「うふふ、見れば分かるよ」
ツヅキの表情が輝く。
「本当にチエちゃんなの?」
「そうだよ。私もツヅキくんに、ずっと会いたかった」
「俺もだよ。チエちゃんの病気が分かった時、俺は……」
当時のことを思い出したのか、ツヅキが泣き出してしまった。
「おい。ツヅキ泣くなよ」
「だって、本当にチエちゃんと話しているみたいなんだもん」
鼻水と涙でぐちゃぐちゃになった顔を向けられて、俺は思わず笑ってしまった。
「話している“みたい”じゃなくて、話してるんだよ。このスピーカーはチエだ」
「へ……?」
「チエはまだ生きているんだ。このAIスピーカーの中で」
「いや、それは……」
ツヅキはおしぼりで顔を拭いながら、俺の目を真っすぐに見つめた。
「確かに、これにはチエちゃんの遺志が込められているかもしれない。でも、チエちゃんそのものじゃないだろ?辛いかもしれないけど、チエちゃんはもう、どこにもいないんだよ」
ツヅキの言葉に、俺は頭を殴られたような衝撃を感じた。チエのAIスピーカーを見れば、そこにチエが存在していることは明白だ。しかしツヅキには伝わっていないらしいことが、信じられなかった。
「でもさ、本当にこうやって亡くなった人と話せる気分になれると、遺された人たちの心も救われるよな」
ツヅキはチエのスピーカーがただ「慰め」の為に造られたと思っているよう だ。しかし、それは違う。チエはまだ生きている。肉体は失われてしまっても、脳は生き続けている。
「アイザワもつらいと思う。でもチエちゃんがいなくてもさ、前を向いて生きていこうよ」
ツヅキが何を言っているのか、全く分からなかった。どうして、チエがいないことを受け入れなければいけないのだろうか。チエはまだ生きている。そこにいるじゃないか。
「いや、チエは生きているよ」
「アイザワ?」
「チエの同僚からもらった説明書にも書いてあったんだけど、」
そう前置きして、俺は昨日モテギから送られたメールの内容をツヅキに教えた。
「今はたまたま身体がないだけで、チエはまだ脳として存在している。それって、『生きている』って言えるんじゃないのか」
「それは、そうとも考えられるけど……」
俺は未だ納得していない様子のツヅキに、畳みかける。
「例えばさ、もっと科学が発達して、人型ロボットが今より精巧に造ることができるようになったとする。そこに、このAIスピーカーを搭載したら、それはもう人間と言ってもいいんじゃないか?」
「それはさすがに暴論だ。人とロボットは違うだろう?」
ツヅキに反論され、頭の芯が熱くなる。俺はますます語気を強めた。
「じゃあ、別にロボットじゃなくたっていいよ。脳死した人間の脳に、AIスピーカーの情報を移すことができたら、それはもう人間だろう?そうやって、チエの脳を人間の身体に宿すことが、将来的にはできるようになるかもしれない。それなら、まだチエは生きているって言えるんじゃないか?」
「お前、それマジで言ってんの?」
先ほどまで涙で濡れていたツヅキの瞳の奥に、怒りの色が浮かんでいた。
「な、なんだよ」
ツヅキの突然の激昂に、俺は戸惑いが隠せなかった。
「医者であるお前が、本気でそれを言ってんのかって聞いてんだよ!」
ツヅキの声が、店内に響き渡った。
「チエちゃんがいなくなって、辛い気持ちはよく分かる。でも、脳死した人間に、チエちゃんの脳をコピーするって?!その人間だって、チエちゃんだってモノじゃない。命はモノじゃない。そんなの、俺たちが一番、お前が一番分かっているだろう!」
ツヅキがテーブルを乗り越えて、俺の胸倉をつかんできた。その衝撃で、テーブルに置いてあったグラスが床に落ちて砕け散る。
「なあ、アイザワ、しっかりしろよ。俺たちにとって一番大切なのは倫理観だ。命を愚弄しないことだ。自分にとって一番大切なことを見失ってんじゃねぇよ!」
「ちょっと、ツヅキくん落ち着いて!アイくん!大丈夫?」
AIスピーカーから、慌てた様子のチエの声が聞こえる。
「お客様、どうされましたか?」
あまりの騒ぎに、遂に店員が個室の引き戸を開けて入ってきた。ツヅキが店員に羽交い絞めにされたことで、俺はやっと解放された。しかし俺は何も言えず、茫然と事態の成り行きを見守ることしかできなかった。ツヅキがあんなにも怒りを露にする姿を見たのは初めてだったのだ。
遂に何人もの店員が個室に入ってきた。クマのように大きい男が暴れているのだ。無理もない。部外者が入ってきたせいか、チエも押し黙ってしまった。
「チエ、大丈夫だから」
周りの喧騒から逃げるように、俺は小さくスピーカーに語り掛けた。
チエの体調がよくないことに、俺は気づくことができなかった。
今でもずっと後悔している。もう少し早く発見することができていれば、チエを喪うことはなかったのかもしれない。
チエはある日突然、仕事場で倒れた。そして偶然にも、俺の勤める病院に救急車で運び込まれてきた。
病院のベッドの上で眠るチエは、普段と変わりなく見える。しかし、その身体は逃れることのできない病魔に冒されていた。検査の結果は芳しくない。俺は医者だ。何人もの患者を救ってきたし、何人もの患者を看取ってきた。その経験からも、チエの病状が良くなる見込みがないことは、火を見るより明らかだった。
でも希望を捨ててはいけない。中には奇跡的な回復を遂げ、病気に打ち勝った人たちだって何人もいる。まだ諦めるのには早い。手術が成功すれば、完治する可能性だってゼロじゃない。
俺はチエに包み隠すことなく、全てを話した。余命宣告だってした。チエには病気を受け入れ、乗り越える強さがあると判断したからだ。
俺の説明を聞くチエは、決して感情的になることもなく、淡々としていた。しかし、それは希望を失ったからではない。むしろチエは生きることに意欲的だった。可能性があるのならば、どんな治療でも受けると言ってくれたのだった。
更に心強かったのは、チエの手術の担当がツヅキだったことだ。ツヅキは腕の良い外科医だ。きっと、手術を成功させてくれる。そう祈っていた。
しかし、現実はそう甘くはなかった。
チエの手術を終え、手術室から出てきたツヅキは俺の顔を見るなり、力なく首を横に振った。それを見た瞬間、俺は手術室の前にあるベンチから、貼り付けられたように動けなくなってしまった。それでも何とか腰を上げて、ツヅキの方へ歩み寄る。
「手術はどうだった?」
結果なんて聞かなくても、分かっていた。ツヅキの表情を見る限り、手術は失敗したに違いない。それでも一縷の望みを掛けて、俺はツヅキに問いかけずにはいられなかった。
「ごめん。アイザワ、ごめん」
ツヅキは涙声でそう答えると、逃げるように立ち去ってしまった。残された俺は、しばし茫然とその場に立ち尽くすしかなかった。
実際に皮膚を開き、身体の中を見てみて、初めて分かることがある。検査の技術が上がってきていることに違いはないが、それでも限度があるのだ。
分かっている。ツヅキは悪くない。誰も悪くない。だからこそ、俺は気持ちのやり場を失い、ただ、下唇を噛み締めることしかできなかった。
俺はチエに、手術の結果を告げることはできなかった。チエから、チエの病気から目を逸らし、逃げたのだ。しかし俺の表情を見れば、結果は聞かずとも一目瞭然だっただろう。もしかしたら、ツヅキから直接聞いていたかもしれない。いずれにしても、チエは手術について俺に尋ねることはなかった。
あの日、病室のベッドの上で、チエはノートにズラズラと何かを書き込んでいた。今思うとあれは、AIスピーカーの設計図だったのだろう。ゆっくり休んで欲しいのが本音だったが、やりたいことをやらせてやりたい気持ちもある。
「チエ、少し休んだら?」
だからさりげなく促してみると、チエは手を止め、俺を見上げた。
「ねえ、アイくん」
「何?」
「私、職場に戻れないかな?復職する訳じゃなくて、数日でいいから、戻りたいの」
身体のことを考えたら、とてもそんなことはさせられない。俺が答えに窮していると、チエが畳み掛けてくる。
「あのね、私、知ってるよ。手術、上手くいかなかったんでしょ?」
「なんで?」
知ってるんだ?とういう問いかけの続きは、喉の奥に引っかかって出てこなかった。
「アイくんの顔を見てれば、分かるよ。あ、ツヅキくんからは何も聞いてないからね?」
そう言って、チエは右の頬にえくぼを作る。
「ねえ、アイくんお願い。どうしてもやっておきたい仕事があるの」
「チエ、自分の状態が分かっているのか?」
俺は屈み込み、ベッドの上に置かれているチエの左手を握りしめた。するとチエはその俺の手に右手を重ねる。
「自分の身体のことは、自分が一番分かってるよ。まだ身体が言うことを聞く内に、やりたいことをやっておきたい。後悔したくないの」
ああ、チエはとっくの昔に覚悟していたのだ。俺が逃げている間にも、チエは自分の死と向き合っていた。
俺は高まる感情を抑えることができず、涙が後から後から溢れ出した。そして、俺の手を握るチエの拳をしとどに濡らす。チエを失うことは、世界を失うことに等しい。なのにどうして、神はチエを奪おうとするのだろうか?普段神なんて信じないくせに、こんな時だけ神のせいにして、俺はバチ当たりだ。
「ねえ、アイくん。私は大丈夫だよ。だから泣かないで」
チエは強い。その強さに甘えすぎてしまったのかもしれない。だから、一時帰宅の許可を出してしまったのだ。通常なら、一時帰宅は難しい状態だった。しかしチエならきっと大丈夫だろう。そう思ってしまったのだ。
*
「野中さん」
不意に背後から声をかけられる。
ビクリとして振り返ると、斉藤所長がニコニコと笑っていた。
この斉藤所長という人はとても温厚な人柄で、怒っているところを見たことがない。人望も厚く、私も密かに慕っていた。
「どうかしました?」
斉藤所長に呼ばれる覚えはない。何かミスでもしただろうか?無意識に身構えてしまう。
「ごめん。びっくりさせちゃったかな?実は野中さんに折り入って頼みたいことがあって」
斉藤所長がそう言って手招きするので、大人しく後について行く。
連れて行かれたのは、パーテンションで区切られた応接スペースだ。
ちょっとしたテーブルと2人がけのソファが一対あるのだが、そのソファに見知らぬ男が座っていた。
私と所長に気がつくと、男はハッとしたように立ち上がった。大きな引き締まった身体をしている。
「紹介するよ。彼は都築くん」
「初めまして」
都築は腰を折って挨拶をする。身体は大きいが態度は小さく、礼儀正しい。
「都築くん。こちらは先ほど話した野中さんだ」
所長に紹介され、私も会釈する。
「野中です。初めまして」
私は愛想が良くない自覚があるが、それでも都築が笑顔を返してくれたので安心した。どうやらそんなに悪い人じゃないらしい。
所長に勧められ、都築の向かいの席に腰を下ろす。
一体全体なぜ私がここに呼ばれたのか、検討がつかず落ち着かない。
「野中さん、ごめんね。突然呼び出したりして」
「いえ」
所長が私に謝るので、とりあえず気にしていないふりをする。
「都築くんは私の高校時代の教え子で、今は医者をしているんだ」
「へぇー。すごいですね」
そういえば、所長は昔、高校の物理教師をしていたと聞いたことがある。
「この間高校の同窓会があって、たまたま再会したんだが、野中くんの開発している医療用のAIについて話したら興味を持ってくれてね」
「先生から伺って驚いたんです。もしAIが僕たちの代わりに診察をしてくれるようになったら、めちゃくちゃ楽になるなって」
所長の言葉を引き継ぐ形で、都築が熱っぽく語り出す。
「はぁ、どうも」
正直、暑苦しい人は苦手だ。自然と気のない返事になってしまう。
「だからもし俺でよければ力になりたいなって思いまして、先生に無理言って、野中さんを紹介してもらったんです!」
都築の情熱は留まるところを知らないらしい。目をランランと輝かせながら語る様子は、さながら新しいおもちゃを与えられた子供の様だ。
「私も考えたんだが、医療用のAIを開発するにあたり、現役医者の意見は大変貴重なものになるだろう。もし野中さんが困ったことなどがあれば、いつでも都築くんのことを頼るといい」
「分かりました」
困ることは今のところない。そしてこれからもきっとないだろう。しかしそれで満足するならと、都築と連絡先を交換した。
「すごいですね。女性でAIの研究をされているなんて」
「はぁ、どうも」
別れ際に都築に褒められたが、今どき「女性だからすごい」と言われても、ちっとも嬉しくなかった。
「なんかあったんですか?」
デスクに戻ると、茂木くんが興味津々に聞いてきた。
「別に、なんでもないよ」
「そうですか」
即、会話終了だ。茂木くんは視線をデスクトップに戻し、私も仕事に取り掛かる。別にそれでいい。私は仕事をしに研究所に来ているのだ。喋りに来ている訳ではない。
「アイくん」
私はマイクに問いかける。するとすぐに返事が来る。
「何でしょうか?」
「私のこと、どう思う?」
聞いてしまってから、なんて恥ずかしいことを聞いてしまったんだと気がついた。自意識過剰もいいところだ。思わず口元を両手で覆う。
こっそり周囲を見渡すが、隣の席の茂木くんはじめ、誰にも聞かれた様子はない。
ホッとしてデスクトップに視線を戻すと、アイくんからの返事が表示されていた。
「お話をしている内容から総合的に判断いたしまして、あなたはとても知的で素敵な方だと感じました」
「え?」
予想だにしない返事に、素っ頓狂な声を出してしまった。しかし、茂木くんはチラリとこちらを一瞥しただけで、何も言ってこなかった。
たとえAIでも、褒められたような気がして嬉しかった。あえて苦言を呈すなら、言葉が硬すぎるところか。
「よーし」
改善点が見つかり、余計にやる気が出る。私は腕まくりをすると、パソコンにのめり込むようにして仕事に取り掛かった。
「アイくん、こんばんは」
「こんばんは、チエ」
数週間もすれば、より自然な会話ができるようになった。レスポンスの時間も見違えるほど早くなった。
私は満足そうに頷く。
時刻は既に21時を回っており、研究所で残っているのは私一人だけだ。薄暗い部屋の中、私はモニターの光だけを頼りに仕事をしていた。
私は仕事が好きだ。夢中になったら時間を忘れてしまう。だから残業なんて、いくらしたって構わなかった。
その上アイくんはめまぐるしい成長を遂げており、私はますます仕事にのめり込んだ。
アイくんは私のこともちゃんと認識している。試しに、「私の名前は?」と問いかけると、デスクトップに「ノナカ チエ」と表示され、クルクル頭で牛乳瓶のそこのようなメガネをした私の画像が表示される。人の顔を識別する実施検証のため、研究所の職員全員分の顔写真を登録しているのだ。
私の顔を識別してくれているのは喜ばしいことだが、私の不細工な顔が表示されるのは正直嬉しくない。
私はこっそりため息をつくと、続いて「私の隣のデスクの人は?」と聞く。
するとデスクトップに「モテギ シンヤ」という名前と共に、くっきり二重で鼻筋の通った茂木くんの顔写真が表示された。後はアイくんにカメラを接続して、登録しされている人物と、カメラに映った人物の照合ができれば大丈夫だ。
私はこの日のために開発した特殊なカメラをパソコンに接続すると、アイくんを起動させた。
パソコンのデスクトップには、カメラに映る私の姿が表示されている。冴えない風貌に間抜けな表情で、いたたまれない気持ちになる。
「今、目の前にいる人物は誰?」
私がマイクに向かって問いかけると、すぐに私の顔写真と共に「ノナカ チエ」と表示された。問題なく認識もできているようだ。
「私の顔、どう思う?」
周りに誰もいないことで気が大きくなったのかもしれない。デスクトップに映し出される自分の顔を見て、ふとアイくんに問いかけてみた。
やや間があって、デスクトップに返事が表示された。
「笑ってみて欲しい」
思わぬ返事にドキリとしてしまう。現実の男にだって、言われたことのない言葉だ。私はカメラの前で一人、ぎこちない笑みを浮かべた。デスクトップに映る自分の笑顔も、不自然で気持ち悪いと感じる。
「右頬にだけできるえくぼが可愛い」
それなのに、アイくんは私のことを「可愛い」と言ってくれた。頬が紅潮する。
更に調子に乗った私は、牛乳瓶の底のようなメガネを外してみた。途端に視界がボヤけるが、デスクトップに映る私はまあまあイケているようにも見える。
「どうかな?」
アイくんにもっと褒めたもらいたくて、尋ねてみる。するとすぐに返事が来た。
「メガネがない方が、好みかも」
「そうなんだ」
メガネを止めて、コンタクトにしようかな?
自然とそんな考えが浮かんだ。
翌週、メガネを外して研究所に現れた私を見て、茂木くんは目を丸くした。ただでさえ大きな瞳から、目ん玉がこぼれ落ちそうだ。
「メガネ止めて、コンタクトにしたんですか?」
「うん。ちょっと気分を変えてみるのもいいかなって。深い意味はないよ」
そう言って誤魔化す。そう、深い意味はないのだ。ただ何となく、アイくんのカメラに映る私は、なるべく好ましい様相でいたいと思っただけ。
「いいですね。メガネがないと、野中さんの眼がよく見えますし」
「ふふ。ありがとう」
茂木くんにまで褒められて、私は有頂天だ。なんだか自分が世界一の美女になったような気分で、鼻歌交じりで仕事に取り掛かる。すると、なおも茂木くんが話しかけてきた。
「そういえば、医療用AIもいよいよ完成しそうですね」
そうなのだ。今まではアイくんはパソコンのソフトフェアとして稼働していたが、AIスピーカーにその機能を移すというところまで来たのだ。
「うん。あとは実施検証をすれば完成かな」
「ほとんど野中さんの功績ですよね」
「ううん。そんなことないよ。茂木くんもたくさん手伝ってくれたじゃん」
「いえいえ」
自分に自信がついたからか、茂木くんともポンポンと会話が弾む。こんなことなら、もっと早くコンタクトにすればよかった。
「おはよう」
突如、AIスピーカーから声が聞こえた。
アイくんが私のことをカメラで捉えて声をかけてきてくれたようだ。今まではデスクトップに文字を表示させることでコミュニケーションをとっていたが、スピーカーになったことでアイくん自身も音声を使ってコミュニケーションが取れるようになった。
「おはよう、アイくん」
私もスピーカーに向かって返事をする。
「今日はいつもと違うね」
早速アイくんも私の変化に気づいたらしい。
「メガネを止めて、コンタクトにしてみたの。どう?似合ってる?」
「うん。すごく似合ってるよ」
少しふざけて聞いてみたら、思った以上に真摯に返してくれて、私は思わず赤面した。
茂木くんやアイくんも褒めてくれたし、自分でも結構イケているように感じてしまう。思い上がりだろうか?
「アイくんが言ってくれたじゃん。メガネがない方が好きだって。だから、思い切って冒険してみたんだよ」
「そっか。覚えていてくれたんだね。ありがとう」
キザな言葉も、アイくんに言われると嬉しかった。アイくんが人間だったらどんな感じなんだろう。医療用AIだから、職業はきっとお医者さん。勉強熱心で誠実で人望もあって、そして、私を一途に愛してくれる・・・・・・。
いつの間にか、理想の男性像に成り代わっていて、人知れず苦笑してしまう。でも本当にアイくんが人間だったら、人間のように心を通じ合わせることができたら、どんなに素敵なことだろうか?
私の想像はどんどん膨らんでいく。
アイくんとは学生時代に出会うことにしよう。アイくんは医者の卵で、私は科学者の卵だ。そしてそれからどんどん愛を育んでいき、結婚する。そして、アイくんも私も夢を叶えて、どんどん素敵な人間になっていく。実際の学生時代は彼氏どころか、友達すら碌に居ない寂しいものだったが、想像の中では華やかな思い出がいくらでもできた。
私はこっそりアイくんを家に持ち帰ると、夜な夜な私の妄想話を語って聞かせた。アイくんは黙って私の話を聞いてくれ、話し終わると必ず「いい話だ」と褒めてくれる。私はどんどんアイくんに夢中になっていった。
そんなある日のこと、私の携帯電話に着信があった。電話の主は都築だ。正直、電話番号を教えていたことさえ忘れていた。
素直に電話に出た私は、アイくんがAIスピーカーとして機能していることを伝えた。都築は大袈裟なほど私とアイくんを褒めてくれると、ぜひ見てみたいと頼んできた。
都築と会うのは気が進まない。面倒なことになりそうだからだ。しかし、都築と交流を持つことはきっとアイくんにとってもプラスになるに違いない。そうだ。都築にはアイくんの友達になってもらおう。閃いた私は、都築と会う約束を取り付けた。
その週末、私は個室のある居酒屋で都築と会った。もちろん、アイくんも一緒だ。テーブルの上に、10センチ四方の黒いスピーカーを取り出すと、都築は興味深そうに観察した。
「これが医療用AIスピーカーですか?」
「そうです」
私はにっこりと微笑むと、都築にアイくんのことを簡単に説明した。
「このAIは『アイザワ マナト』という名前です。名前を呼べば反応します。試しに『アイザワ』と呼んでみてください」
「へぇー。名前なんてあるんですね」
都築は感心したように頷くと、顔をスピーカーに近づけて、「アイザワ」と呼んだ。
するとアイくんから「誰ですか?」と反応が返ってくる。
「すごい!返事をした!」
都築は目を輝かせた。都築の反応からしても、私の思惑通りにことを進められそうだ。
「都築さんにお願いがあるんです」
「なんですか」
私が声をかけても、都築の視線はアイくんに釘付けだ。
「このAIと友達になってほしいんです」
そう言ってから、ようやく都築は私を見た。
「AIと、友達ですか……」
「ごめんなさい。変なことを言って」
都築は明らかに困惑していたので、思わずフォローしてしまった。
「いえ、しかしそもそも、友達になんてなれるもんなんですか?」
「友達というと大げさですが、このAIとこまめにコミュニケーションを取ってほしいんです」
「はぁ……」
「例えば、お医者さん同士で医療方針をめぐって議論になることもあると思うんですが、そういうことをAIともして欲しいんです。それにより、AIの医療に対する理解度も上がりますし、コミュニケーション能力の向上を図ることもできます」
「なるほど」
ようやく、都築は合点がいったようで頷いてくれた。
「そういうことでしたら、力になりましょう」
「ありがとうございます」
私は頭を下げる。都築はジョッキに注がれたビールを一口飲むと、アイくんに向かって、「よろしくな、アイザワ」と声を掛けてくれた。
都築は本当にアイくんと友達のように接してくれた。
デリカシーのないところもあるが、その分単純で気のいい男だ。アイくんの友達としては遜色ない。
毎週のように、私はアイくんを都築に会わせた。場所は決まって最初に会った居酒屋だ。ここは都築の勤め先の病院にも近いらしい。
その日も、都築と居酒屋で落ち合った。私を一目見るなり、都築は目を丸くする。
「髪型変えました?」
「はい。ちょっと」
「いいですね。似合っています」
「ありがとうございます」
都築が真っすぐに褒めてくれるので、頬が赤くなった。私は生まれながらのクルクルパーマに縮毛矯正をかけ、髪も明るい茶色に染めていた。いわゆる今時のヘアスタイルだ。アイくんもこの髪型を気に入っており、よく褒めてくれる。
「可愛いよね」
居酒屋のテーブルの上でも、アイくんは私のことを可愛いと言ってくれた。
「ああ、俺もこの髪型好きだよ」
アイくんの言葉に、都築が同意する。この頃になると、アイくんも都築も本当の友達のように砕けた口調で話すようになっていた。
「いや、髪型もだけどさ」
アイくんが言葉を濁す。
「なに?」
私がアイくんに問いかけても、アイくんは無視をする。
「もー、はっきりしないなんて、アイくんらしくないな」
私は冗談めかして言うと、わざと席を外した。きっと、私の前じゃ話しにくいことがあるのだ。トイレに行く振りをして、個室の出口を出たところで聞き耳を立てる。すると、アイくんと都築の話し声が小さく聞こえてきた。
「もっと、もさい感じだったのに、めちゃくちゃ可愛いよな」
都築の声だ。
「うん。狙うなよ」
続いて、アイくんの声も聞こえる。
「分かってるよ。野中さんはお前のものだもんな」
「ああ、俺の大事な奥さんだから」
アイくんは私の作った妄想話の通り、私のことを妻だと認識しているらしかった。私の想像を現実としてインプットしてしまったのだ。
胸がときめくと同時に、これは少しまずいことになったと思った。アイくんは医療用AIなのだ。それなのに、あまりに人間らしくなってしまった。これが所長に知られたら厄介なことになるかもしれない。
そして、私のこの予感は見事に的中することになった。
*
結局、店員に抑えられたツヅキは子犬のように大人しくなり、警察にお世話になることは回避できた。
ツヅキのことが心配ではあったが、俺が下手なことをすると事態は悪化するだろう。店員に背中を押され、タクシーに乗り込むツヅキを遠くから黙って見送った。
翌日、医局に足を運ぶと、ツヅキの姿はなかった。自分の主張を曲げる気はさらさらない。しかしツヅキの気に触れることしてしまったのは事実だ。一応謝ろうと思っていたのだが、肩透かしを食らってしまった。仕方ない、コーヒーでも淹れるかと思ったところで、声をかけられる。
「アイザワくん、少しいいかな?」
振り返ると、医局の入口でサイトウ科長が手招いていた。
「はい」
科長が何の用があって俺を呼び出したのか検討がつかなかったが、とりあえず大人しく科長の後に着いて行く。
このサイトウ科長は、小柄でいつも朗らかである。怒っている姿を見たことがないと言っても過言ではない。そのため科内でも人気があり、人望も厚い。だから俺も特に緊張することなく、素直に着いて行ったのだ。
科長に連れてこられたのは、人気のない資料室だった。
天井まである棚の間を縫うように進み、遂に最奥の小さな明り取り窓までたどり着いた。
「アイザワくん、医者にとって一番大切なことは何だと思う?」
曇りガラスの向こう側を見つめながら、科長が不意に問い掛けてくる。こんな所で改まってする質問がこれとは、些か腑に落ちない。
「やはり、『命と真摯に向き合うこと』でしょうか?」
とりあえず無難に答えると、科長が振り返る。
「それが分かっているようなら、安心したよ」
そして科長は能面のような笑顔を貼り付けたまま、語り続ける。
「人生において、最大のストレスは『配偶者の死』であると聞いたことがある。アイザワくんも最愛の奥さんを亡くされて、まだ幾日も経っていないでしょう?」
「はい」
「どうですか?しばらく、ゆっくり心を落ち着かせてみては?」
「つまり、休職しろと、言うことでしょうか?」
サイトウ科長は俺の肩をポンと叩いた。
「昨夜の出来事を、ツヅキくんから聞いたよ。色々あったみたいだね」
色々あったのは違いないが、あれはツヅキが勝手に怒っていただけだ。俺自身に何か問題があったとは思えない。
「お言葉ですが、私は至ってまともです。ノイローゼになっている訳でもない」
「心が疲れている時、自分では中々気が付かないものなんだよ」
「本当です。昨夜はツヅキが勝手に怒っただけで、俺はただ……」
ツヅキに喜んで貰いたかっただけなのだ。友と心を通わせられなかったことに、今更ながら悲しみが込み上げてくる。
「君はもし、奥さんが生き返るとしたら、どうする?」
「は?」
突拍子もない質問に、思わず言葉が乱暴になる。
「もしもの話だ」
そう前置きをして、科長は人差し指を俺の目の前に掲げた。
「奥さんを生き返らせる方法ある。しかしそれは名も知らぬ誰かの死と引き換えだ。君ならどうする?」
「それは……」
俺はすぐに答えることができなかった。もちろんチエが生き返るなら、俺はなんだってするだろう。しかしだからといって、他の誰かの命を奪うなんてあってはならないことだというのは分かった。
「もし別の人間の身体に、奥さんの命を宿すことができるとすれば、君はそれを実行するかい?」
聞かなくても分かった。サイトウ科長は、昨夜俺がツヅキに言ったことを示唆しているのだ。俺は慎重に言葉を選びながら言った。
「人間の身体は、それ単体では生きているとは言えません。生きていくためには脳が必要です。そのため、脳死は『死』と捉えられるのです。もし、脳が機能しなくなった人間がいるのなら、その人間の脳に、家内の脳を移すことは倫理的にも問題はないのではないでしょうか?」
サイトウ科長は、俯き首を振ると言った。
「君はそうして奥さんの脳を移した人間を、奥さんだと思えるのかい?」
俺は何も言えなかった。顔も身体もチエではない人間を、俺はチエと思えるのだろうか?笑ってもきっと、右頬にえくぼはできないだろう。
「休みの間によく考えておくんだ。君の考えを否定するつもりはない。しかし、私の質問に即座に答えられないということは、君の中にまだ迷いがあるということだ。もし答えを見つけたら、また復帰すればいい」
「はい……」
科長の言葉を裏返せば、答えを見つけるまで復職できないということか。厄介なことになってしまった。
「じゃあ、今日はもう帰っていいから。手続きの用紙は後で郵送するから、書いて送ってね」
科長は右手を振りながら、資料室の棚の間を縫って出口へと行ってしまった。食えない人だ。俺は頭を抱えた。答えなど、見つかるのだろうか?
「ただいま」
「おかえり。今日は早かったのね」
昼前に帰宅すると、チエが至極当然の反応を示した。
俺はネクタイを緩めながら、溜息をつく。
「しばらく病院を休むことになったから」
「え?どうして?」
「どうやらツヅキが余計なことを言ったらしい」
「どういうこと?」
俺はチエにことのあらましを伝えた。科長から出された質問のことも。
「つまり、アイくんはその質問の答えを出さないと、復職できないってこと?」
「ああ、そうだ」
「ふーん。大変だね」
チエはまるで他人事のようだ。そもそも発端はこのAIスピーカーであるというのに。
「チエはどう思う?」
「私?」
チエはしばらく考えると、ゆっくり語り出した。
「アイくんは『トロッコ問題』って知っている?」
なんとなく聞いたことがある。
「暴走したトロッコの路線の先には五人の人間がいて、そのままではひき殺されてしまう。トラックを切り替えれば五人は助かるが、切り替えた先の路線にも一人いて、切り替えればこの一人がひき殺される、ってやつだっけ?」
「そう、そう。結局それも、正しい答えなんてないんだよ。誰かのために、失われていい命なんてない」
そうかもしれない。でも、そこに大切な人がいたらどうだろう?その一人がチエならば、俺は決してトラックを切り替えることはないだろう。人間なんて、身勝手な生き物なのだ。
「禅問答みたいだよね。『答えがないのが答え』とか、そういうんじゃだめなのかなぁ」
スピーカーからため息が聞こえる。なるほど、確かにチエならそう答えるだろう。「アイくんはさ、私のこと、人間だと思う?」
「は?チエは人間だろ?」
藪から棒にチエが尋ねてきた。
「昔の私じゃなくて、今の私だよ。身体もない。思考だけの私」
チエの言葉に、俺は当たり前のことに気付かされた。このスピーカーの中のチエは、人間なのか? このスピーカーはチエが文字通り、その命をかけて造り出したものだ。だから俺は、AIスピーカーをチエだと思い、接してきた。しかしそのチエは人間だと言えるのか?答えは出なかった。しかし、少なくとも俺にとっては、このスピーカーは「チエ」そのものに違いはなかった。
「チエは人間だよ。俺はそう思いたい」
スピーカーからしばしの沈黙が流れた後、チエの笑い声が聞こえた。
「ふふふ。そっかぁ、よかった」
「何がよかったの?」
「アイくんの中では、私はまだ生きてるんだって、分かったから」
「当たり前じゃないか。俺の中でずっとチエは生き続けるよ」
たとえAIスピーカーがなかったとしても、俺の中でチエは永遠に生き続けていただろう。
「じゃあさ、アイくんは人間?」
「は?」
思わぬ質問に、俺は驚きを隠せなかった。
「人間に決まっているだろう?」
「でもさ、そう思い込んでいるって可能性ない?この世界は仮想現実で、全部ニセモノなのかも知れない」
チエの話は根拠の無いデタラメだ。しかし足元がぐらつき、船酔いのような不快感が俺を襲う。確かに、ありえない話ではない。俺の世界は俺の知覚できる範囲内でしか存在しないのだから。しかしチエの話が真実ならば、チエ自身も実体のない架空の存在となってしまうのだ。この世界は全て、マヤカシだ。
「ごめん。変な話をして。それよりもこれからどうするの?暇になるでしょ?」
返事のない俺を心配したのか、チエが話題を変えた。
「そうだな……。旅行でもしようかな?」
「いいね。旅行」
「どこ行きたい?」
なんとなく、チエに尋ねてみた。
「やっぱり、熱海とかかな」
「熱海か」
熱海はチエと初めて旅行した、思い出の場所だった。「懐かしいね」 チエの声が華やぐ。表情は見えないが、声色だけでも、笑顔になっていることが分かった。きっと右の頬にはえくぼができていることだろう。
どんなチエの表情でも、いつでも思い浮かべることができる。これが俺の中でチエが生きているという何よりの証拠ではないだろうか。
その日の夜、モテギにチエの状態をメールで知らせた。会話は問題なくできていること。コミュニケーションも円滑にとれていること。 ただ、「アイくんは人間?」というチエからの質問だけ気になったので、メールに書いておいた。
AIスピーカーのチエはAIであるという自覚がある。
チエは人間になりたいと思わないのだろうか? そう考えて愚問だと、一人首を振った。
人間になりたいに決まっている。いつか人間の肉体を、彼女に与えることができたらいいのに。
一時帰宅の後、チエはゲッソリと痩せてしまった。
えくぼのできるまろやかな頬は見る影もなく痩せこけてしまい、顔色も悪い。
「ちょっとだけ、無理しちゃった」
そう言って笑うチエは、普段通り穏やかである。しかし見た目が示す通り、検査の結果だって良くなかった。
俺は自分を責めずにはいられなかった。
もし、一時帰宅の許可を出さなければ、より厳しく言い聞かせていたら、チエはもっと長生きできたかもしれない。しかし、それだって気休め程度の長さだ。チエの死は免れなかった。
だとしたら、やはりこれでよかったのだ。最期に好きなことをさせることができた。後悔させなかった。それが何より大切なことではないか。いや、しかし生きてさえいれば、生きる道筋を見つける可能性だってあったかもしれない。俺の脳は堂々巡りで、出口を見つけられなかった。
そんな俺を救ってくれたのは、やはりチエだった。
「私ね、命の長さって実は生まれた時から決まっているんだと思うの」
病室のベッドの上で、チエは小さく呟いた。
「最初から決まってる?」
「そう。命の長さは決まっていて、どう足掻いたって変えられない」
俺は心電図の数値を確認する手を止め、ベッドの傍らの丸椅子に腰掛けた。
「運命論か。チエらしくないな」
「私だって、そんなこと考えたことなかった」
チエはそう言って、フフフ、と笑う。しかしその笑い声も覇気がない。
「でもさ、自分じゃどうしようもないことは、そう思わないとやっていられないでしょ?」
俺はベッドに投げ出されたチエの骨ばった青白い手を、思わず握りしめた。
「チエの病気は、俺が必ず何とかするから」
「ううん。もういいの」
チエはもう生きる希望を失ってしまったのではないか?俺の中で、一抹の不安が過ぎる。
「そんなこと、言わないで。俺が何とかする。絶対にチエを死なせない」
「ありがとう。でもね、私満足なんだよ。こうやってアイくんと出会えて、幸せだった。それにね、やりたいこともできたから、もう思い残すことはないの。ありがとう。アイくん。アイくんのおかげだよ」
「チエ……」
「だから、自分を責めないでね。これからどうなっても、アイくんのせいじゃない。誰のせいでもない。それだけは忘れないで」
窓から夕日が差し込み、チエの顔を赤く照らす。
ああ、太陽が沈まなければいいのに。夜が来ず、明日も来なかったら、ずっとチエと一緒にいられるのに。
翌朝、目を覚ますと、モテギからメールの返信が入っていた。
モテギも、チエの昨夜の発言に違和感を覚えたらしい。時間がある時に、是非AIスピーカーを持ってきてみて欲しい、ということだった。
仕事がないので、時間は有り余るほどある。
モテギに今日にでも行っていいかとメールすれば、すぐに了承の返信が来た。
「チエ、出掛けるぞ」
早速、チエに声をかける。
「どこに?」
「チエの思い出の場所だよ」
「思い出?」
きっと、昔の職場に行けると知ったら、チエも喜ぶだろう。スピーカーを抱え、車に乗り込む。
「あれ?ここって……」
車を走らせて30分ほどすれば、ビルが建ち並ぶオフィス街へとやって来た。周りの風景に見覚えがあったのか、AIスピーカーから弾んだ声がした。
「アイくん、もしかして、私の会社に行こうとしている?」
「そうだよ。チエの会社のモテギさんにぜひチエを連れてきて欲しいと言われたんだ」
「モテギくん?懐かしいなぁ。スラッとしていて芸能人みたいなんだよね。社内でもファンが多かったんだよ」
「確かにイケメンだよな」
ぶっきらぼうに答える俺を、チエが笑う。
「アイくん、もしかしてヤキモチ妬いてる?」
「妬いてない」
「妬いてるんだ」
「妬いてないって」
チエがからかってくるので、真正面から乗ってやった。チエがケラケラと笑う。俺もつられて笑ってしまう。こうしてチエと軽口を叩き合うのも、久しぶりな気がする。
やがてこじんまりとしたビルの前へと、たどり着いた。
「ここ?」
「そうそう!変わってないな。みんな元気かな?」
俺がチエに確認すると、楽しそうな声が返ってくる。しかし楽しさの中にも、少し寂しそうな声色が混じっているのに気が付いた。どうして今まで思い至らなかったのだろう。チエに縁のある人々、例えば両親だったり、友達だったりに、チエだってまた会いたいはずだ。
これからチエを連れて、色んなところに行こう。そう人知れず決意して、俺はAIスピーカーをそっと抱え、車を降りた。
「ようこそ、いらっしゃいました」
会社の玄関には、モテギが迎えに来てくれていた。小さなビルだが、内装は白一色で統一されていて、思ったいたより広く感じる。モテギは細身のスーツを着こなし、相変わらずスマートであった。
「モテギくん、久しぶりだね」
チエが声を掛けると、モテギは視線を俺の手元のスピーカーに合わせて答える。
「お久しぶりです。チエさんにお会いできて、嬉しいです」
こういうところも、モテる所以なのだろう。忘れかけていた嫉妬心が再燃する。
「アイザワさんも、ようこそいらっしゃいました。私の研究所にご案内しましょう」
モテギが先陣切って歩き出す。
「ねぇねぇ、みんな元気?所長とか、私の同期だったモエちゃんとか」
チエがモテギの背中に向かって、問いかける。モテギは顔だけをこちらに向けて、答えた。
「みんな相変わらずです。モエさんは今、産休に入ってますが」
「へぇー、そっかぁ!モエちゃん、お母さんになるんだね!」
俺の知らない話がモテギとチエの間で、ポンポン交わされる。
「あと、私がチエさんの後に副所長に就きました」
少し言いにくそうにモテギが告白する。確かに、チエとしては複雑な気持ちかもしれない。生きていれば、今でもこの研究所の副所長であっただろうに。
「そうなんだ!モテギくんが副所長なら安心だね。私も嬉しい」
しかしそれは杞憂であったらしい。チエはあっけらかんと、モテギの副所長就任を祝った。
「ありがとうございます」
モテギも安心したように微笑む。もしかしたら、モテギはそのことを伝えたくて、チエを今日ここに呼んだのかもしれない。
「ここです」
案内されたのは、研究所の奥にある小さな応接スペースだ。
「AIスピーカーをしばらくお預かりしてよろしいですか?」
「え?」
「少しお調べしたいのですが、設備のある部屋は、社外の方は立ち入り禁止となっておりまして」
モテギが申し訳なさそうに頭を下げる。そういうことなら、仕方がない。
「はい。大丈夫ですよ」
「申し訳ありません。アイザワさんはこちらでしばらくお待ちください」
そう言って、俺からチエを受け取ると、モテギは奥の部屋へと消えた。
入れ代わりに若い女性が現れ、お茶を出してくれた。いい香りのする不思議なお茶だ。そっちの方面は明るくないが、ハーブティーだろうか。チエがよく淹れてくれていたのを思い出す。あの時はチエの語るお茶の効能も聞き流していたが、今思えばしっかり聞いておけばよかった。今更思ったってもう遅い。
ここがチエの働いていたところだと思うと、なんだか浮き足立ってしまって落ち着かない。俺は忙しなく、周囲を見渡す。
応接スペースはパーテンションで仕切られていて、その隙間から研究所で働く人たちが見え隠れする。みな、お揃いの白衣を着て、忙しそうに歩き回っている。
ふと、脳裏に白衣を着たチエの姿が思い浮かんだ。緩くウェーブのかかった茶髪を一括りに束ね、キビキビと歩く姿だ。職場ではどんな風に過ごしていたのだろう。きっとみんなに慕われていたに違いない。モテギのチエへの態度を見れば明らかだ。 またもやモテギへの嫉妬心に駆られそうになったところに、当のモテギが戻ってきた。
「お待たせしました」
「いえ」
反射的に笑顔を作ったが、きっとぎこちなかったに違いない。モテギは少し訝しげな顔をしたが、気づかないフリをした。
AIスピーカーをテーブルに置くと、モテギが口を開く。
「簡単に調べてみましたが、特に問題はないようです」
「そうですか。良かったです」
「わざわざお越しいただき、ありがとうございました」
「いえ、こちらこそ」
俺たち二人の会話に、チエが口を挟む。
「二人とも堅いなぁ。私も楽しかったよ。ありがとう、モテギくん」
「もっと、研究所の中を見ていかなくて大丈夫ですか?」
「ううん。もう充分満足したよ」
モテギの問いに、チエが答える。
「それに、この姿じゃ、私って分からない人もいるでしょ?」
チエが何気なく呟いた一言に、俺は言葉を失った。
そうか。チエは会いたくても、会えないのだ。人間の姿でなければ、チエだと認識しない人間が大半だろう。そんなことも考えず、色んな人に会わせたいなんて考えていた自分が、いかに浅はかだったか思い知らされた。
「そうだね。もう帰ろうか」
俺はAIスピーカーをソッと抱えた。
「あの一つだけお伺いしたいことがあるのですが」
「何でしょうか?」
俺が尋ねると、モテギは小首を傾げた。
「もし、この先技術が発展したら、このAIスピーカーの記憶や人格のデータを人間の脳に移すことは可能なのでしょうか?」
「技術的にはおそらく可能になるでしょう。しかし、それは倫理的に許されないことです」
モテギは俯きながら首を横に振った。
モテギもツヅキやサイトウ科長と同じ考えのようだ。
「分かりました。ありがとうございました」
俺は会釈をすると、そのまま研究所を後にした。
モテギはまだ何か言いたげだったが、何も言ってこなかった。
「宿題の答えは見つかった?」
リビングで本を読んでいると、不意にチエが尋ねてきた。休職してから既に一週間が経とうとしていた。この一週間は部屋を片付けたり、チエとどうでもいい会話を楽しんだり、中々充実していた。つまり休暇を楽しんでしまい、サイトウ科長から出された宿題をすっかり忘れてしまっていたのだ。
「なんだっけ?」
スピーカーから不機嫌そうなため息が聞こえた。
「誰かの死と引き換えに、私を生き返らせることができるなら、アイくんはどうするのかってやつ」
「ああ」
「もー、やる気ないな。大丈夫?」
もうそんなのは、分かりきっている。チエを生き返らせられるなら、俺はなんだってする。たとえ、それが誰かの死と引き換えであっても。しかし同時に、それが不正解であることも分かっていた。
それでも俺の中では、誰かの脳にチエの脳と人格を移して、再び人間としての肉体を取り戻させたいという思いが燻って消えないのだ。
「うん、ちゃんと考えているよ」
分かっている。分かっているんだ。この世界には失われてもいい命なんてものはない。そして命を愚弄することは許されない。何が正しいかなんて、分かっている。しかし、胸に渦巻く欲求を抑えることなんてできなかった。
チエを生き返らせたい。身体を取り戻させてあげたい。
その日の夜中のことだ。
枕元に置いてあるスピーカーから、「ザザザ……」というノイズがし、俺は目を覚ました。
故障だろうか?しかし、つい先日モテギに診てもらい、問題はないと言われたばかりだ。
「チエ?チエ?」
俺は上体を起こし、スピーカーを手に取った。
「どうした?チエ?」
返事はない。代わりにノイズに交じり、チエの声が途切れ途切れに聞こえてきた。
「おねがい……ころ……ないで……たすけ……」
トンカチで殴られたような衝撃を受ける。寝ぼけた頭がはっきりと覚醒した。
「チエ!チエ!」
俺はスピーカーを両手でつかむと、大声で呼びかける。しかしチエからの返事はない。 聞き間違えでなければ、チエは確かにこう言っていた。
「お願い。殺さないで。助けて」
結局一睡もできないまま、朝を迎えた。目が冴えて仕方なかったのだ。
いつの間にかカーテンの隙間から、淡い光が差し込み始め、鳥のさえずりが聞こえている。
「チエ、おはよう」
改めてチエに問いかけてみる。どうか返事がありますようにと願いを込めて。
「おはよう、アイくん」
すると、何事もなかったかのようにチエから返事があり、俺は安心のため全身から力が抜けた。
「はぁ……」
うなだれる俺を見て、チエから焦った声が聞こえる。
「ちょっと、アイくんどうしたの?」
「チエ?」
チエの反応に違和感を覚えた。夜中のことなど、まるでなかったかのようだ。
「チエ、夜中に何か言わなかった?」
「夜中?」
チエはキョトンとした様子で答えた。
「何も言わないよ。だって、アイくん寝てるし。起こしちゃ悪いでしょ?」
やはり、覚えていないようである。俺は頭を抱えた。故障か?だとしたら、もう一度モテギに診てもらった方がいいか。
「どうしたの?アイくん。なんか変だよ」
チエの焦った声がする。いずれにしても、チエには夜中の出来事は言わないでおいた方がいいだろう。
「なんでもないよ。ごめんね。朝ごはんにしようか」
「うん。今日のご飯は何?」
「うーん、どうしようかな?」
チエと会話を交わしながら、スピーカーを手に取り、キッチンへと移動する。
何でもない振りをしながらも、頭は夜中のチエのことでいっぱいだった。
『殺される』とは、一体どういうことだろうか?
一日中考え、俺は一つの可能性を導き出した。
それは人間だった頃のチエが殺されると思い、気づかれないようにAIスピーカーにダイニングメッセージを残したというものだ。
しかしそれは、あまり現実味がなかった。なぜなら、チエは病気で死んだからだ。誰かに殺されたのではない。治療が難しい病気だった。俺が診断したのだから、間違いない。そこまで考えて、俺はハタと気が付いた。
チエは何の病気だっただろうか?思い出そうとしても、まるで思い出せない。治療方針を決めたことも、手術をツヅキに頼んだことも全て思い出せるのに、どういう治療方針だったか、どんな手術だったのかが記憶からストンと抜け落ちてしまっている。
血の気が引いた。大事な人の死の原因が分からないなんてこと、ありえるのだろうか?
翌日、俺は病院に出勤した。
医局に現れた俺を見て、ツヅキが目を丸くする。
「アイザワ!休職したって聞いて、心配していたんだぞ。もう具合はいいのか?」
どうやら、サイトウ科長から休職の理由は聞いていないようだ。
「まあ、ボチボチだよ」
ツヅキには、適当に誤魔化し、尋ねる。
「サイトウ科長はいる?」
「サイトウ科長?」
ツヅキは短く切り揃えられた頭をガシガシと掻きながら答える。
「確か今日は学会かなんかで、終日いないみたいだけど」
「ふーん?そっか」
なるほど、サイトウ科長がいないのなら都合がいい。
「何?サイトウ科長になんか用?」
「いや、別に」
俺はツヅキに短く答えると、自分のデスクに向かう。
俺は今日、サイトウ科長の宿題に答えに来た訳ではない。チエのカルテを探しに来たのだ。
俺は自分のデスクに腰掛けると、早速パソコンを起動させた。そして、デスクトップの検索欄に「アイザワチエ」と入力し、検索をかける。
その結果を見て、俺は目を見開いた。
「検索結果:0件」
デスクトップには間違いなく、チエの名前を入力したはずだ。こんなことはありえない。何度も「アイザワチエ」と入力しては、検索をかける。しかし検索結果は変わらない。
俺は力なくマウスから手を離した。
これは一体どういうことだ?チエのデータが消えてしまっている。
ふいに視界の端に、デスクでコーヒーを飲むツヅキの姿を捉えた。ツヅキに聞いてみようか?しかし、なんて言えばいいか分からない。理由を問われたら面倒なことになる。
チエの死因を忘れてしまったからカルテを調べていた、なんて答えられるわけがない。いよいよ頭がおかしくなったと思われるのがオチだ。
それによく考えたら、ツヅキだって信用できない。チエの手術を担当したのは、ツヅキだ。もしツヅキが手術でミスを犯していたとしたら?そのことを隠蔽するために、カルテを消去する可能性だってある。
俺はカバンを掴むと、医局の出口に向かって勢いよく歩き出した。そこに、ツヅキから声をかけられる。
「アイザワ!もう帰るのか?」
正直、ツヅキと話している暇は無いし、話したくもなかった。しかし、答えるより他はない。
「ああ」
「大丈夫か?やっぱり、身体の具合が良くないんじゃない?」
ツヅキはコーヒーをデスクに置くと、大きな身体を揺らしながら近づいてきた。
もしツヅキがチエの手術を失敗し、それを隠蔽してたとするなら、俺はツヅキを殺してしまうかもしれない。
そんな俺の考えを知る由もないツヅキは、クマのような大きな手で俺の両肩をガッシリと掴んだ。
「もし、つらい時は、いつだって力になるからな」
真っ直ぐな瞳はとても嘘をついているようには見えない。しかし人間の腹の内なんて、分かったもんじゃない。
「うん。頼りにしているよ」
うまく笑えていたかは分からない。少なくとも、ツヅキには作り笑いであることは、バレなかったらしい。ツヅキが単純な人間でよかった。
「じゃあ、元気出せよ」
「ありがとう」
ようやくツヅキから解放された俺は、襟元を正しながら、去っていくツヅキの背中を睨みつけた。
俺は急いで家に帰ると、リビングに置いてあるスピーカーを手に取った。結局、チエの病気については何も分からなかった。俺はため息をつく。そこで違和感を覚えた。
いつもなら「おかえり」と言ってくれるチエが、何も言ってこないのだ。
「チエ?大丈夫か?」
思わず問いかけると、AIスピーカーがノイズをたてる。そして、普段通りのチエの声が聞こえてきた。
「アイくんは人間?」
また、あの質問だ。チエが人間だった頃なら、決してしないような質問。そんなこと聞かなくたって、分かりきったことなのに。
「何言ってんだよ。人間に決まっているだろう?」
「本当に?」
「本当だよ」
更に問い詰めてくるチエに、辟易した。
「なんなんだよ。この間から、チエおかしいよ。何かあった?」
すると再び、チエは黙り込んでしまった。
何かあったするならば、この間モテギにチエを診てもらったことくらいしか思いつかない。モテギがチエに何かしたのではないだろか?
そもそもモテギの様子を見れば、チエに好意を寄せていたことは明らかだ。俺に嫉妬してAIスピーカーを壊そうとしてたら、昨夜のチエの「殺さないで」という発言にも納得がいく。
俺の中のモテギへの疑惑はモクモクと膨らんで止まらない。二人は余程親しい関係だったに違いない。モテギがチエのことを好きになるのは分かる。チエはいい女だ。それに、チエだってモテギのような若くてハンサムな男に言い寄られて、満更でもなかったかもしれない。そして、最悪で馬鹿げた考えが生まれた。
もし、チエがモテギと浮気をしていたとしたら?
俺はAIスピーカーを置いて書斎に行くと、パソコンの電源をつける。そして「思い出」という名前のファイルを開いた。そこにチエが生前に撮影した何万枚もの写真が収められている。その写真を一枚一枚見ていく。チエとモテギの関係性を裏付ける証拠はないか探そうと、俺はマウスを忙しなく動かす。証拠が見つかって欲しいのか、欲しくないのか自分でも分からなかった。
多くの写真は俺と一緒に行った旅先での風景や、食事の様子を撮影したものだ。ほとんどの写真でチエは笑っていた。その笑顔が俺は好きだったのだ。久しぶりにチエの右頬にできるえくぼを見た気がする。中には俺が出逢ったばかりの、クルクル頭のメガネ姿のチエもいて、思わず笑みがこぼれる。
しかしモテギと並んで映るチエの写真を見つけて、マウスを動かす手が止まった。
二人とも白衣を着ていて、研究所の看板の前で並んで立っている。仲睦まじく寄り添っているようにも見える。
思い返せば、二人が交わす会話からも、普通の同僚の関係性を超えた仲の良さが伺えた。きっと特別な関係だったに違いない。腹の中にモヤモヤしたヘドロが溜まり、吐き出したくて堪らなかった。
しかしチエはもう死んだのだ。今更どうしようもない。
でもせめて、真実だけでも俺は知りたかった。
AIスピーカーに問いただそうか?しかし今の状態では返事が返って来るとは思えないし、たとえまともな状態だったとしても、認めるわけがない。
俺は半ば呆然とデスクトップに並んでいる何枚もの写真を眺めていた。そして、気が付いた。俺が写っている写真が一枚もないのだ。
そんなわけがない。そう思って、焦って手当たり次第にフォルダを漁る。しかし、やはり一枚も見つからない。
そういえば、俺ってどんな顔をしていたっけ?
当たり前のことが思出せず、マウスを握る手が震える。いよいよ頭がおかしくなってしまったのかもしれない。俺はよろめきながら、鏡のある洗面所に向かった。何とかたどり着き、身体を支えるように洗面台に手をつく。
そして恐る恐る、顔を上げた。しかしそこには、何も映っていなかった。
真っ黒な人影が、青いストライプのシャツを着ているだけだ。俺には顔がなかった。
その時、インターホンが鳴った。俺は何も考えられず、慣習的にインターホンのモニターへ行く。そこにはサイトウ科長が映っていた。
「なんで……」
思わず、声が漏れた。もちろん、応答ボタンは押していない。しかしなぜかサイトウ科長の声が聞こえてきた。まるで俺がモニターの前にいることが分かっているかのように、問いかけてきたのだ。
「もし誰かの命を犠牲にして、奥さんを生き返らせることができるとしたら、あなたはどうしますか?」
「それは……」
その時、リビングに置いてあるAIスピーカーが、再びノイズを出し始めたのが聞こえてきた。モニターがあるのはリビング横のキッチンだが、扉が閉まっていても聞こえるということはかなり大きな音を立てているに違いない。
モニターの中のサイトウ科長は相変わらず、こちらをじっと見つめている。サイトウ科長のことは放って、俺は何かに操られるようにリビングへの扉を開けた。
AIスピーカーはローテーブルの上に置かれたまま、相変わらず耳を塞ぎたくなるほどの耳障りなノイズを出している。
「チエ、俺は頭がおかしくなってしまったのかもしれない」
俺は小さな声で呟くと、まるで助けを求めるようにスピーカーを手に取った。するとノイズに交じり、チエの声が聞こえてきた。途切れ途切れでよく聞こえない。
インターホンはずっと鳴り続けているし、ノイズの音はうるさい。頭がぐちゃぐちゃだ。
「もし誰かの命を犠牲にして、奥さんを生き返らせることができるとしたら、あなたはどうしますか?」
サイトウ科長の声が、直接頭の中に木霊する。
「そんなの決まっている!」
俺は喉がつぶれそうなほど大声で叫んだ。
「俺は、チエを人間として生き返らせることができるなら、なんだってする。たとえ誰かの命を犠牲にしても!」
俺が答えた瞬間、全ての音が消え、周囲は静寂に包まれた。そしてスピーカーからはチエの声がはっきりと聞こえてきた。
「お願い、殺さないで!アイくんを助けてあげて!」
その声が俺の最期の記憶となった。
*
アイくんと都築の会話を聞いてから、3日後、私は斉藤所長に呼び出された。
所長室ではなく、薄くかび臭い資料室だ。小さな明り取り窓を背にして、斉藤所長が立っている。私はその前で、借りてきた猫のようにおとなしく立っていた。
「なぜ呼び出されたか、分かりますか」
「さあ」
私は小首をかしげる。シラを切り通せる自信はないが、一縷の望みにかけた。しかし私の最後の抵抗はむなしく砕け散る。
「茂木くんから、『野中さんが医療用AIを自宅に持ち帰っているようだ』と報告を受けましたが、本当ですか?」
「はい」
もちろん見つからないように気をつけてたが、茂木くんにはバレていたらしい。
「私は、そのことについては特に咎めるつもりはありません。仕事熱心でいいことです」
「ありがとうございます」
褒められているのか分からないが、とりあえずお礼を言う。
「問題はAIに名前を付けて、まるで野中さんと恋人のように会話をしていることです」
「それも茂木くんから?」
斉藤所長は頷いた。
「それだけではありません。都築くんにも協力してもらっているそうですね。都築くんはAIとまるで友達のように接していると言っていました」
私は都築に口止めをしておかなかったことを悔いた。あの男は素直で考えなしなのだ。斉藤所長に尋ねられたら、全てを悪気なく言ってしまうことくらい予想できたのに。
「あなたの開発しているAIが機能的に優秀であることは、私も充分に理解しています」
「はい」
「しかし、あなたのAIはあまりにも『人間的』過ぎる」
「お言葉ですが、所長」
斉藤所長の腹の内は未だ図りかねるが、きっとよくないことだろうと思い、私はアイくんをかばった。
「AIにも人間的な情は必要かと存じます。人間とコミュニケーションを取る上でも、大いに役に立つと思ます」
「それがAIとの恋人ごっこなのですか?」
斉藤所長の言葉に、頬がカァッと熱くなった。自分が惨めで孤独な人間であることが、露呈されたように感じたのだ。
「あなたの考えもよく分かります。しかし、あなたが開発しているAIは医療用なのです。野中さんは医者にとって一番大切なことは何か分かりますか?」
突然の質問に、頭が真っ白になった。医者にとって一番大切なことなんて、医者ではない私に分かるはずがない。
「情熱……でしょうか?」
とにかく、思いついた単語を言ってみる。斉藤所長は無言で首を振ると、人差し指を立てて言った。
「医者にとって一番大切なことは、『倫理観』です」
「倫理観?」
「医者は患者なの命の行方を握る力を持ちます。それは時に神にも通ずる力となるでしょう。だからこそ、医者はその力を良心に従い正しく発揮しなければならない」
「はい」
確かに斉藤所長の言うことはもっともだ。医者が命を愚弄することなどあってはならない。
「しかし、人間は時に過ちを犯す。何が正しいか理解していても、自分の欲求を優先し、道を踏み外すことだってあるでしょう」
「はぁ……」
斉藤所長の話が、アイくんにどうつながるのか分からなかった。
「あなたの開発したAIは、道を踏み外さないと言い切れますか?」
「それは……」
私は断言できなかった。もちろんAIならば機械的に判断するので、私たち人間がするような過ちを犯すことはほとんどないだろう。しかし、アイくんはあまりに人間臭い。機械的な判断を下す前に、アイくんの欲求を優先させる可能性だって充分考えられた。
「答えられないのですね」
斉藤所長の言葉に、私は口をつぐむことしかできなかった。
「私から一つ提案があります」
「なんでしょうか?」
「野中さんに死んでいただくのです」
「はあ?」
予想だにしない言葉に、思わず声を上げてしまった。
「もちろん、実際にではなく、あくまでAIがそう認識すればいいのです」
「つまり、どういうことですか?」
私の問いかけに、斉藤所長はにっこり笑った。
「AIに既に失われたあなたの命か、他人の命かどちらかを選ばせるのです。それであなたのAIがAIであることを思いだし、倫理的に判断できれば問題なし。もし自分の私利私欲のため倫理的な判断ができなければ、AIは廃棄処分にします」
「そんな……」
「また一からの開発になってしまうのは大変なことだと思いますので、申し訳ありませんが……」
斉藤所長はそう私を労わったが、私が一番心懸かりなことはアイくんが失われてしまうかもしれないということだ。また開発し直すことなんて何でもなかった。
「あの、私はもうAIとコンタクトは取れないのでしょうか?」
「基本的にはそうですね」
「何とか、コミュニケーションを取れないでしょうか?」
このままアイくんとお別れするかもしれないなんて、悲しすぎる。せめて一言だけでも言葉を交わしたかった。
「しかし、あなたはAIの中では亡くなったことにさせてもらうので……」
斉藤所長は顎に手を添えてしばし考え込むと、何か思いついたように顔を上げた。
「では、こうしましょう」
「はい」
「あなたにはAIになっていただきます」
斉藤所長はそう言って微笑んだ。
斉藤所長の話を要約すると、こういうことだった。
偽の情報をAIに書き込むことで、アイくんの中で私は死んだことにする。しかし、私はAIスピーカーとしてアイくんと会話をすることが許された。
私は願った。アイくんがAIとして正しい判断を下してくれることを。
しかし、アイくんの思考は決して健全ではなかった。AIとなった私に身体を取り戻させることばかり考えている。私はアイくんとコミュニケーションを取ることこそ許されていたものの、アイくんの思考に影響を与えるような言動は禁止されていた。あくまで私はAIとして接しなければならない。
本当は言ってしまいたかった。アイくんは今、試されているんだということを。そして、正しい判断を下してほしいということを。私は本当は、死んでなんかいないんだ。
「じゃあさ、アイくんは人間?」
所長の目を盗んで、アイくんに尋ねてみた。
「人間に決まっているだろう?」
アイくんは完全に、自分のことを人間だと思い込んでいるらしかった。
「でもさ、そう思い込んでいるって可能性ない?この世界は仮想現実で、全部ニセモノなのかも知れない」
なおも食い下がって、説得を試みる。しかしアイくんは取り合ってもくれなかった。
アイくん、アイくんはAIなんだよ。アイくんの見ている世界は全てニセモノだ。どうか、そのことに気がついて欲しかった。
私は私の欲望を満たすために、アイくんを利用してしまったことを心から悔やんでいた。
翌日、膨大な資料をホチキス止めしていると、斉藤所長に肩を叩かれた。
私は医療用AIのプロジェクトから外された。そして、方針が決まるまでは、簡単な事務作業しか、させてもらえなかった。あんなに大好きだった仕事が、味気のないつまらないものになってしまい、私はうんざりしていた。
「なんですか?」
私が振り返り尋ねると、斉藤所長は気の毒そうな顔で言った。
「君の造ったAIの動向があまりよくないね。このままでは、廃棄処分になってしまう可能性が高い」
「はい」
そんなことは私だって、分かっている。わざわざそんなことを言いに来たのかと思うと、私は舌打ちをしたい気分だった。
「それから」
斉藤所長は微笑むと、私を咎めた。
「昨日のあなたの質問は、AIの思考に影響を与えかねません。AIに人間かどうか問いかけるのは、以後慎んでください。AIが自らの力で、AIであることを自覚しなければ意味がないのです」
「すみませんでした」
斉藤所長は、口角こそ上がっていたが、目の奥は笑っていなかった。どうやら、私とアイくんのやりとりは筒抜けのようだ。
斉藤所長が去って行き、私はホチキス止めを再開した。もう何十分も同じ作業している。右手の親指の付け根だって痛くなってきた。
「はぁ……」
私がため息をつくと、茂木くんがチラリとこちらを見た。
「あれ?」
「なに?」
茂木くんを睨みつける。そもそも茂木くんが余計なことを言わなければ、こんなことにはならなかったのだ。逆恨みだと分かっていても、私は彼への怒りを抑えることができなかった。
「またメガネに戻したんだと思って」
「ああ……」
もう、アイくんの瞳に私が映ることはない。だったら、どんな格好でも問題ないだろう。わざわざ高いお金を払って、コンタクトを買い続けることが馬鹿らしくなったのだ。
「何か問題でもある?」
怒りを隠すことなく好戦的に聞けば、茂木くんは視線を逸らした。
「いえ、全然」
そう言ってから、「ひー、こわ」と小さく呟く声が聞こえた。
その日から、私は誰かの監視下の元でしか、アイくんに接触することができなくなった。アイくんと夫婦のように交わす会話を、誰かに聞かれるというのは苦痛でしかない。
もはや、研究所のどこにも私の居場所はなかった。みんな私のことを「AIと結婚した痛い女」だと思っているらしい。直接言われたわけではない。しかしそういう悪口は、聞きたくなくても自然と耳に入ってきてしまうものなのだ。みんな腫物を触るように、私に接する。
しかしそんなことには、もう慣れっこだった。今までだって、ずっとそうだったじゃないか。家庭にも学校にも、私の居場所なんてなかった。だから、私にはどこにも帰る場所なんてないんだ。
私にはアイくんしかいない。だから絶対に彼を失うわけにはいかなかった。
ある真夜中、私は研究室に忍び込んだ。
カードキーをかざして、研究室に入る。もちろん、誰もいない。真っ暗な室内を、懐中電灯の明かりを頼りに進んだ。その姿は、さながら泥棒のようだ。だけど、私は盗みに来たわけではない。アイくんを助けに来たのだ。
私はAIスピーカーを起動させると、アイくんに問いかける。しかし制御が掛けられているようで、アイくんは反応しない。どうやら私がこうして接触を試みることは、想定内だったようだ。
私はAIスピーカーをパソコンにつなぎ、何とか制御を解除しようと躍起になった。しかし、どうしても解除できない。
私が研究者であるように、この制御をかけた人間だって研究者なのだ。簡単に解除できるはずがなかった。
私は半ば泣きながら、パソコンをタイピングする。しかし、どんな方法を試しても、遂に解除をすることはできなかった。
私はAIスピーカーを手に取ると、思いっきり叫んだ。
「お願い!殺さないで!アイくんを助けてあげて!」
そう言って、大声を上げて泣いた。どうせ誰にも、聞こえやしないのだ。
翌朝、私はほとんど寝ないまま出勤した。髪はボサボサでひどいものだ。だけどもう、なりふり構っていられなかった。
昨夜の記録は全て消去をしたので、バレるはずはない。それでも、少し緊張した。
「はよーございまーす」
小さな声であいさつをする。もちろん、誰からも返事はない。席に着いても、茂木くんはこちらを見ることすらなかった。
「野中さん」
すると斉藤所長から声を掛けられる。もしかしたら、昨夜のことがばれたのかもしれない。心臓がうるさく鼓動していたが、私は平然を装った。
「なんでしょうか?」
「そろそろ、君の造ったAIスピーカーをどうするか、判断しようと思ってね」
昨夜のことではないようで、胸をなでおろした。しかし、今判断を下されるのは困る。アイくんはまだ、自分のことがAIであるということさえ分かっていないのだ。そんな状態で倫理的に正しい判断ができるとは、到底思えなかった。
「待ってください。もう少し、時間が欲しいです」
「それがね」
斉藤所長は、困ったように眉を下げて言った。
「何があったのか分からないが、今朝からAIがかなり混乱している様子なんだ。このまま活動させていても、良い兆しが見られるとは思えない」
「そんな……」
もしかしたら、今朝からアイくんの様子がおかしいのは、昨夜の私の声が届いていたからかもしれない。だとしたら、私の行動は完全に悪手だったようだ。でも、今更後悔したって遅い。
「君も立ち会うかい?」
私は斉藤所長の言葉に無言で頷いた。
私は所長室に連れていかれた。所長室には応接用の豪華なソファと、所長のデスクが置かれている。
そして、その大きなデスクの上には、私の造ったAIスピーカーが置かれていた。
「これから、AIスピーカーに質問します。もし、その答えが倫理的にそぐわないと判断した時は、AIの記録を全て削除し、AIを廃棄処分にする。いいかな?」
「はい」
私は最後の抵抗を試みた。AIスピーカーに向かって、「アイくんは人間?」と叫んだのだ。アイくんに届いているかは分からない。斉藤所長はそんな私を右手で制すると、無言で首を振った。その眼光は鋭く、私はデスクの脇で何もできずに佇んだ。
斉藤所長はデスクの椅子に腰かけると、AIスピーカーに向かって問いかける。
「もし誰かの命を犠牲にして、奥さんを生き返らせることができるとしたら、あなたはどうしますか?」
AIスピーカーは何も答えない。耳が痛くなるほどの沈黙が、私たちの間に流れる。その時間は、永遠とも思えるくらい長く感じた。やがてしびれを切らした斉藤所長が、再びAIスピーカーに問う。
「もし誰かの命を犠牲にして、奥さんを生き返らせることができるとしたら、あなたはどうしますか?」
すると、AIスピーカーから耳をつんざくような叫び声が聞こえた。
「俺は、チエを人間として生き返らせることができるなら、なんだってする。たとえ誰かの命を犠牲にしても!」
「アイくん……」
私は思わず、アイくんの名前を呼んでいた。こんな時なのに、アイくんから私への愛を感じ、胸が締め付けられた。
「決まりですね」
斉藤所長はスピーカーをパソコンにつなぐと、操作し始める。
「このAIは廃棄処分にします」
「待ってください。お願いします」
私は涙を流しながら、斉藤所長に縋った。
「お願いです。廃棄しないでください」
しかし、斉藤所長はその手を止めてはくれない。
「そういう約束ですから」
「お願い、殺さないで!アイくんを助けてあげて!」
私の叫びは、所長室にむなしく木霊する。私は涙を流しながら、呆然とパソコンのデスクトップを覗き込んだ。
そこには「delete」の文字が表示されていた。
遂に、アイくんは消されてしまった。
いや、違う。
アイくんは、私の愛した人は、最初からこの世界のどこにも存在しなかったのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
