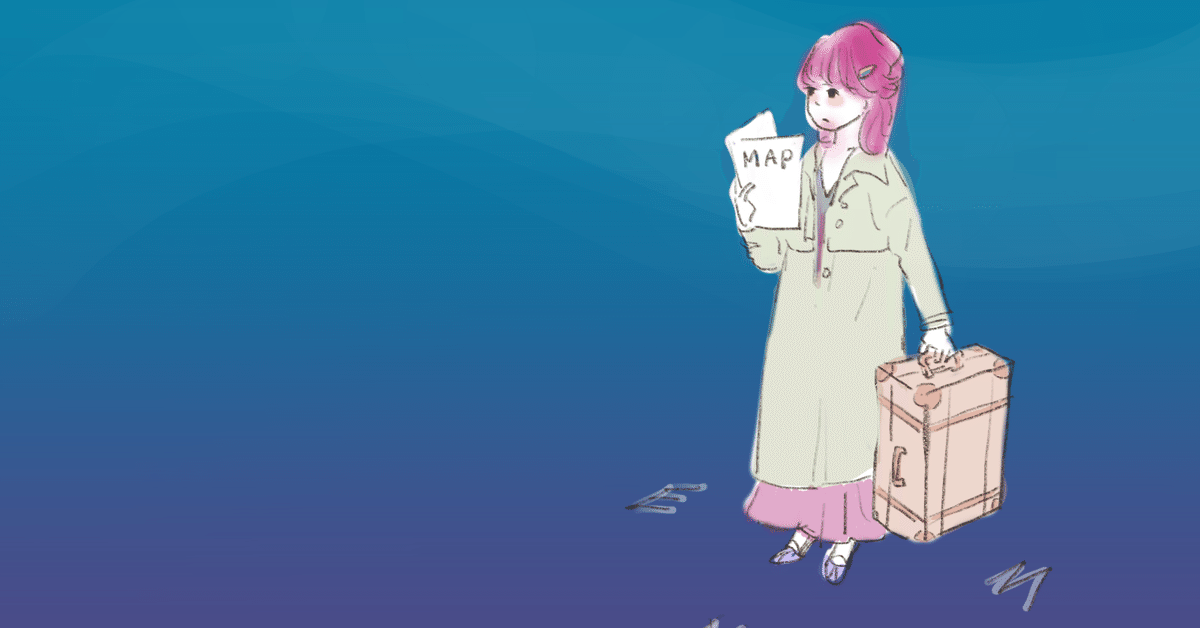
室伏長子(ちょこ)のストーリー
「ひとりひとりの物語りを愛してく」
そんなキャッチコピーがわたしのなかにはあります。
じゃあわたしの物語りも愛することもしよう。
自分では気づけなかったものと
誰かと話すことで出会えるのは実感していて。
わたしと出会うために、皆さんにわたしと出会ってほしくて、
ファンシップ(株)小宮さんにマイストーリーをかいていただきました。
わたしの物語りを小宮さんが紡ぎ直してくださいました。
「誰かが作った正しい答え」から
「自分の中にある誰とも違うワタシというコトバ」へ
脚本・演出 小宮 仁至、原作・監修 室伏長子
のマイストーリーです。どうぞご覧ください。
「わたし」が培われる子ども時代
神奈川県湯河原町。温泉旅館の孫娘として生まれる。
7つ上の兄と4つ上の姉。圧倒的な末っ子として、
また祖父母が営む旅館に入り浸る孫として育つ。
旅館に来るお客さんを含め、常に周囲にあった「大人の目」。
気が付けば、どうやったら大人に褒められるか、
評価を受けるか、を意識しながら、
どうふるまうかを考えていた。
いや、むしろそう考えていることすら自覚がない。
大人に褒められるために行動するのが、
標準装備な幼少期を過ごす。
小学校の教室では、
学級委員や電気を消す係を買って出るだけではなく、
頼まれてもいないのに「静かにして係」までこなす。
総合学習の時間で、川の研究をしようものなら、
クラスメイトの迷惑そうな顔は一切気にせず、異常な情熱を注ぐ。
そのくせ、財布はいろんなところに忘れてくるし、
集合時間には遅れてくる。
計画を立て、やり抜く粘り強さなどは一切持ち合わせいなかった。
小学6年生。
「将来何になるの?」と周囲の大人に問われたら、
「学校の先生になる。」だった。
恩師と出会ったからと言っていたが、
ウケが良い答えだったからだったのか、自分でもわからない。
大人に褒められたい自分と本当の自分との境界線が、
非常に曖昧で、危ういアイデンティティの持ち主だったと振り返って思う。
彼女はゆとり教育の申し子だ。と自称する。その通り高校・大学とゆとり世代の1期生として人生の前半生を歩んで行くことになる。
主観と客観の境界線が非常にあいまいな青春時代だったと思う。そしてそれは自分と他人の違いが分からない。という一種の才能でもあり、欠陥でもある、彼女の最大の特徴を育む土壌となっていく。—脚本・演出 小宮さんより
中学に上がると、オリンピックの影響もあり
大人から後押しされてソフトボール部に入る。
ただし、左投げを教えてくれる人がいなかった。
という理由で、左利きなのに右投げで
3年間プレーを続けるという具合であった。
中学女子特有の、陰湿なイジメの危険性を孕む人間関係とは、
距離を取りつつ、内申点が上がる大人たらしぶりには拍車がかかる。
不登校の子がいると聞けば、プリントを届けたりもした。
本当にその子のことを想ってやっていた行動なのか、
今、自分が思い返してみても怪しい。
それでも、先生方の評価はすこぶるよく、
相対評価ではなく絶対評価に変わったゆとり教育世代1期生として、
本来行けるはずのない進学高校に内申点の大幅な貢献で入学した。
高校では、3年間スーパーのレジアルバイトをした。実家の家計が苦しく、
お気楽に「普通の高校生」をする気になれなかったし、
そういう気持ちが元々なかった。
ただここでも、周囲の大人たちの加点は稼いでいく。
レジの精算は当たり前のように毎日合わない。
それでも、毎日くるお客さんには、無駄に話しかけ、
自分で仕事を探しては品出しの仕事を覚えたり、
最終的には新人さんの研修係にもなっていた。
とにかく、誰かに褒められるのは嬉しい。誰かに褒められている時に、自分はここにいて良い人間なんだと思える。正しい答えがあると信じていたし、常にそれを探していた。
答えは自分で出すものではなく、周囲の誰かが求めること。
ちゃんとしなければならないし、ちゃんとさえすれば、周囲は愛してくれるのだ。そう思い込んでいた。
高校3年生の夏。
はたと気づく。「私、このままでいいんだろうか?」
特に好きなことも熱中することもない。
将来の夢も相変わらず「学校の先生」と言っているが、
それが誰かに望まれた答えなのか自分の願望なのかすら、判断がつかない。
当たり前のようにAO入試で大学に行くつもりだった。
通常の学力で大学に行ける気がしないのである。
そんな時、とある大学の勉強体験合宿に参加した。
「これは!」と思う話をしている教授に出会う。
沖縄大学で「こども文化学科」という新学科が始まるお話をされていた。
教員免許も取れるが、それ以外のカリキュラムや考え方に魅かれた。
初めて自分の意志で、何かを選ぼうと思えた瞬間だった。
「やってみる」ことにした大学時代
急な進路変更に両親ともに反対されたが、ギリギリで説得に成功。
「大学デビュー」とはこのことか、という勢いで沖縄大学での生活を楽しんだ。
と、言っても合コンやビーチパーティーなどではない。
自主企画のイベントを立て続けに開催した。
「沖縄大学は私が変える」という企画に申し込み、
謎の気合で取り組んでいた。
大学の職員さんや学生の間でも、ちょっとした有名人と認識されていた。
相変わらず、働くこと、接客業は好きだった。
デパートの地下1階にあったスムージー屋さんで働いた。
結果的には、卒業後も働くことになるこの場所で、
アルバイトという意識を越えて、
社長とマネージャーに次ぐ重要な位置にいる人物として、
学生アルバイトながら全国の百貨店の物産展にも
出かけていくような働きぶりだった。
人生を変えてくれた出会い
ただ大学時代に一番影響を与えてくれた人は、このバイト先ではなく、
進行性の病でありながら大学に通われていたリサ先輩という人だった。
相変わらず、内申点稼ぎ的思考が取れないままで、
何となく始めたノートテイクサークル。
障害を持ちながら大学に通う学生をサークルとして
サポートするというもの。
耳が聴こえづらい学生に講義等を手書きやパソコンで視覚化して伝えるというものだった。
努力をするのが嫌いな自分でもこれなら、続けられそうだし、
良いことやってそうに見えるし、何となくスキルアップにつながりそうだと軽い気持ちで始めた。
ところが「長子のノートテイクは分かり易くて助かるよ。」と
褒めてもらえた。「次はこういう風にして欲しい。」という
良質なフィードバックも、もらえた。それがリサ先輩だった。
人間として、女性として、この先輩は非の打ちどころがなかった。
大好きな人だった。私なんかよりよっぽど能力も高く、勉強熱心で、
人の接し方はいつも優しかった。
そんな先輩には夢があった。
「同じ障害をもつひとに向けて、いつかは本を出したい。」という夢だった。(これを知るのは時がすぎてからとなる)
ところが、リサ先輩の病は思いのほか、早く進行していき、
結局、卒業式を迎えることも、本を出版することもなかった。
プリンが大好きだったリサ先輩。
「おいしいプリン見つけたから今度行きましょうね~」と
軽い約束をしていたが、そんな約束すら果たせなかった。
もっともっと先輩の言葉を残しておけばよかった。
今日会えている人と明日会えないかもしれない。
そんな命の実感とその人が発するコトバの大切さを教えてくれた人だった。
他人軸で生きた報い
努力をしても報われない人もいれば、努力なんかしていないのに、
私みたいに生きていく人もいる。
何か心に大きな染みを残したまま、
流されるように教員採用試験を地元の神奈川に戻って受けていた。
教員不足が叫ばれ始めた頃。
大学の成績は相変わらず推薦枠が取れるほどの優等生っぷり。
落ちるはずがないと高を括っていたが、ここで人生初の不合格。
「あなたの考えは偏り過ぎている。」それが落選の理由だと聞かされた。
これまで、周囲の正解を自分の答えとして生きていたツケが
一気にまわってきたような気がした。
「沖縄で教員採用試験受けながら働きます。」
親への言い訳のような自分への言い訳のような、
そんなモヤモヤとした気持ちを抱えたまま、
アルバイト先のスムージー屋さんでスタッフとして働く。
店舗での仕事だけではなく、BtoBの開拓営業や配達。
ECサイトの運用や発送業務。
台風の時や早朝いきなり欠勤連絡してくるアルバイトの穴埋め出勤。
誰かに褒められたくて働く。
何にもない空っぽな自分の穴を埋めるように働く。
忙しければ忙しいほど気持ちは落ち着くから、休みたくはない。
そんな気持ちがエスカレートすると、周囲とは軋轢が生まれる。
良かれと思ってやっていたことも、立場や視点が変われば、
憎悪の対象になることもある。
そんなことも気づかずに、自分だけが正しいと思っていた。
自分の頭を後ろから殴られるような出来事があった。
大好きだった仕事に、行くのを体が拒むようになった。
朝起きるのがつらくなり、仕事中に涙がこみあげてくるようになった。
逃げるように退職を願い出た。
「自分」に目を向けた瞬間(とき)
その後、人のご縁で紹介された職場が、
障がい者就労支援事業所での支援員という仕事だった。
それまでの働き方、仕事とはまるで異なる世界だった。
「こんなことを1日中熱中できるんだ!」という人がいたり
「ああ、こんな些細な言動で傷つけてしまうんだな…」という
経験をしたり。
たくさんの言葉と経験をもらう日々だった。
この事業所では約2年間働かせてもらった。
自分ではできもしないキャパオーバーな企画をして、
たくさん迷惑をかけたこともあった。
周囲に褒めてもらいたくて、良かれと思ってやることが裏目に出る働き方は
ここでも繰り返えされた。
人に好かれたくてやった結果、人に「大嫌い」と言わせてもらう自分。
自分は自分を出さない方がいい。
黙って言われたことだけやっていた方が良い人間なんだ。
居心地の悪さも自己嫌悪感も、最高潮に高まり、退職。
ただ救われたのは、上司が退職の前後半年間、月1回のメンタリングを実施してくれたこと。
その結果、出てきた感情。それは
「私は相手のために、こんなにやってあげているのに、なんでわかってくれないの!?」
「環境や組織のせいにして、自分と向き合わない癖」
そういう、見覚えはあるけど、認めたくない自分の欠片たちだった。
『ちょこ』としての一歩は自分を取り戻す作業
それから、特に何か考えがあったわけではないが、
とにかく組織に依存しない生き方をしようとフリーランスで
働いていこうと決めた。
フリーランスと言っても最初はアルバイトの掛け持ちをしているだけの
生活だった。ただ大学時代にリサ先輩が褒めてくれたノートテイク。
これを複数の意見を持つ人が集まる会議やミーティング時に、
模造紙で大きくリアルタイムで、議事録として残す。
「グラフィックレコーディング」として再開してみたところ、
「とっても分かり易い!」と喜んでくれる人が現れ始めた。
誰かのコトではなく、自分のコトを大切にする。
正しい言葉を探すのではなく、その人らしい言葉を探す。
優劣をつけたりせずに、他人との違いをフォーカスする。
そんなことを意識しながら、グラフィックレコーディングを
色んな所でやり続けた。
これで食べていくために、起業塾に通ってみようかとか、
事業計画書の作り方を学んでみようかとか、色々試してみたが、
どれもしっくりこなかった。
うまくいっている人の真似をしてみたり、
背伸びをした翌日に、卑屈になってみたりもした。
昨日「これだ!」と思ったヒントが、
翌日はすぐに「違うかも。」と感じる日々。
ただそれは、これまで自分の正解を他人に委ねてきた自分にとって、
何かを取り戻すような時間だった。
あなたもコトバも大切にそう願う。
あるとき、「もうちゃんとするのは、無理だわ!」と投げ出して、
好きな人の話を聞いて、キャッキャッしながら絵を描いて、
今日の楽しい会話をコトバと絵にして渡したら、
思いのほか喜んでもらえた。
私は私のやり方でいいんだ。
誰かの正解は誰かの正解であって私の正解ではない。
そんなことが、ストンと腹落ちした時に生まれたのが
「コトバグラフィッカー・ちょこ」という生き方・働き方だった。
自分の内側に在るコトバ。
それを誰かに聞いてもらって、言語化し、自分の言葉として発して欲しい。
それは他の誰でもなく自分自身が
ずっと誰かにして欲しかったことなのかもしれない。
誰かに喜んで欲しくて遠回りしたり、人を傷つけたり、自分を否定したり
したけれど、今は自分のコトも他人のコトも受け入れられる。
まだまだ自分の正解はどこにあるのか分からないけど、今の私は自分のコトバを紡いでいる。それが何より心地よい。
———
長いストーリーお読みいただいてありがとうございました。
いかがだったでしょうか?
そんなこんなで今もコトバを探して紡いでいるわたしですが、
どうぞよろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
