
EBTG(Everything But the Girl)1982-1986年(感想)_優しく寄り添ってくれる初期の名盤
EBTG(Everything But the Girl)は、Ben WattとTracey Thornが1980年代前半から活動しているユニット。
2023年4月には24年振りのニュー・アルバム『Fuse』をリリース。正直に言ってこれまであまり注目していなかったのだけど、過去作から遡って聴いてみるといくつか耳に馴染んだので、以下にEBTGとしてリリースされたアルバム/シングルといくつかのソロ作品についての感想などを。
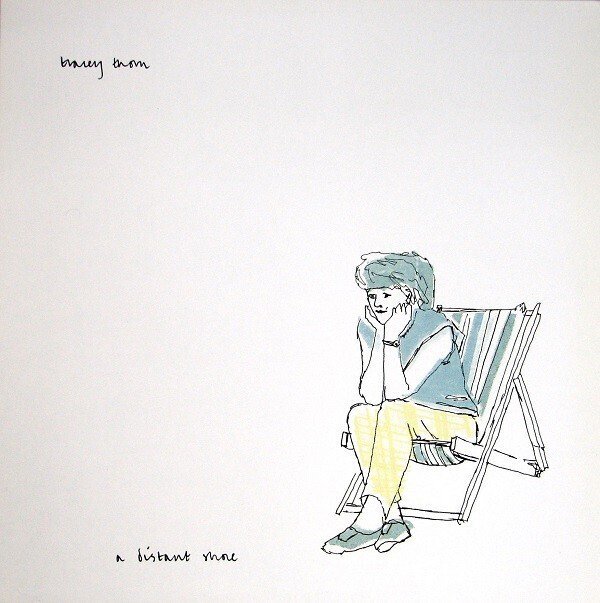
A Distant Shore/Tracey Thorn (1982年)
叙情的なヴォーカルとどこか拙いギターだけのプリミティブなTracey Thornのソロ作品はCherry Redからのリリース。
80年代前半のメインストリームへのカウンターかのような、青臭くて素朴な要素が詰まっていて、寂寥感の漂う8曲はぼんやりとしたい時に聴きたくなる名盤。
アコギのアルペジオが美しい「Dreamy」が特にお気に入り。
残念ながら本作はSpotifyに無さそう。

Night and Day (1982年)
EBTGとしての作品はBilly Holidayのカバー曲をA面に収録した3曲入りのシングルからで、Cherry Redからのリリース。
オリジナルはまったりとしたジャズだが、素朴なアコギの音色が印象的なボサノヴァに仕上がっている。はっきり言って3曲全てが地味なのだが不思議と魅力がある。

North Marine Drive/Ben Watt (1983年)
Cherry RedからのリリースされたBen Wattのソロ作は、ボサノヴァまたはジャズのテイストを含んだネオアコの傑作。
「North Marine Drive」のように心にグッとくるような曲は涼やかで穏やかな時間に浸れて、優しく寄り添ってくれる繊細な感触が心地よい。
再発盤には、元Soft MachineのRobert Wyattと共演したミニアルバム『Summer Into Winter』も追加収録されているのもあり、こちらはアコギの音が控えめで静かに鳴り響くアンビエント・ミュージックのよう。
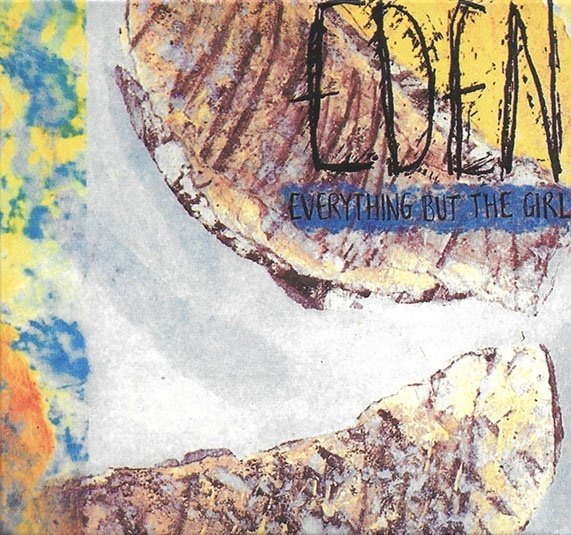
Eden (1984年)
UKアルバムチャート14位。レーベルは本作以降Blanco y Negro Recordsから。
このデビューアルバムを最初に認識したのは、1990年代に渋谷系の文脈でネオアコバンドのひとつとして、本作が紹介されていたから。
憂いのあるTracey Thornのヴォーカルと、ボサノヴァやジャズっぽい涼やかなアコースティックサウンドにはどことなく大人になりたくない青臭さもあって完璧。いかにも渋谷系音楽を好む人達の好物が取り揃えられている。
プロデューサーのRobin MillarはSadeの『Diamond Life』も手掛けており、「I Must Confess」を聴くと、今更ながらなるほどと思う。
渋谷系を好きと思われることへの抵抗感があって、ネオアコブームの頃はピンと来なかったけども、歳を重ねて先入観無しに聴き直してみると素直に素敵な1枚だと思う。
本作のお気に入り曲は2人のデュエットが聴けて、まったりとしたジャズっぽい「Tender Blue」。
2012年にはシングルB面曲を追加した『Eden...Plus』がリリースされており、ギターがキラキラした「Laugh You Out Of The House」とかも好き。「Native Land」にはJohnny Marrがハーモニカで参加している。

Love Not Money (1985年)
2ndアルバムはボサノヴァっぽさが消えて、「When All's Well」「Are You Trying To Be Funny?」のようにギターポップ好きに刺さりそうな曲が増えた印象。
凡庸なギターポップにならないのはいい具合に肩の力が抜けているのと、憂いのあるTracey Thornのヴォーカルが特徴的だから。
プロデューサーは引き続きRobin Millarで、UKアルバムチャート10位。
2012年にリリースされた『Love Not Money... Plus』で追加収録された曲では、音に拡がりがあってキラキラしている「Kid」が好き。

Baby, The Stars Shine Bright (1986年)
Mike Hedgesとの共同プロデュースとなった3rdアルバムで、UKアルバムチャート22位。
収録曲では「Cross My Heart」の盛り上がり方は好き。
この3rdアルバムではシンセやストリングスが多用されており、アレンジもこなれて音の拡がりを感じられる。そのおかげでこれまでリリース作品と比較して音楽がポジティブでポピュラー・ミュージックに寄せた印象があるが、それまでの青臭いインディーズっぽい音楽に良さを見出していたファンにはどうだったのだろう。
カバーデザインがカラフルな色とフォントを組み合わせと、2人のファッションも含めて、いかにも80年代ぽくて懐メロっぽい印象。
長くなってきたので、続きは次回以降。
