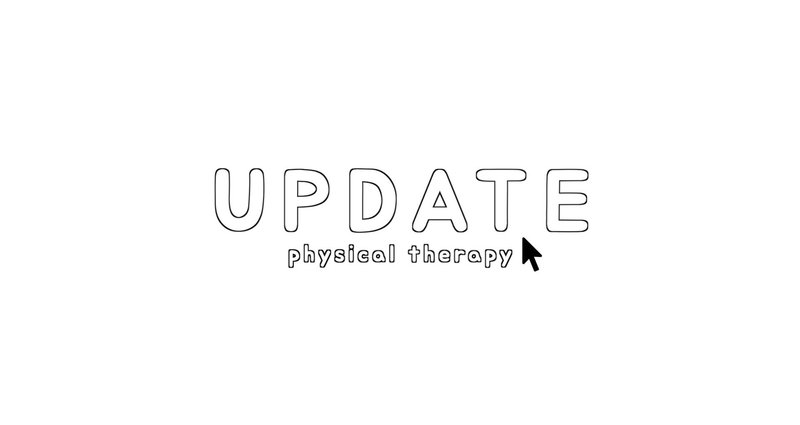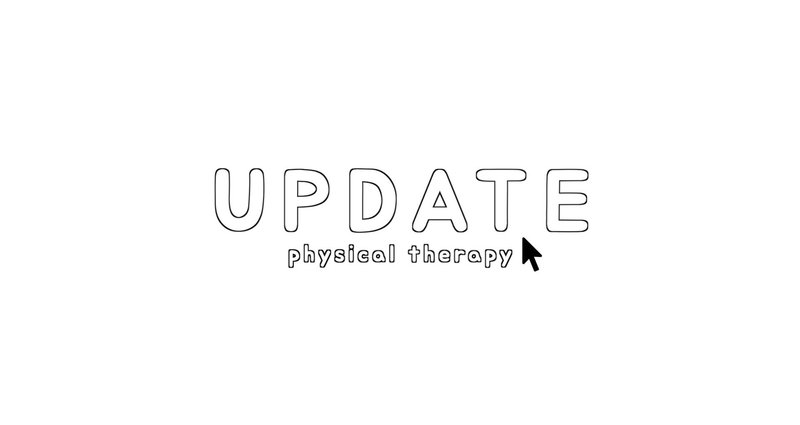「統合と解釈」を制す者は「臨床」を制す
皆さんは「統合と解釈」という言葉をご存知ですか?
私は学生の頃に実習先でこの言葉を知りました。
理学療法評価過程で何が一番大事であるかと問われると、セラピストの多くは統合と解釈であると返答するものが多いと言われているほど。
しかし、統合と解釈についての報告は少なく、分かりやすくまとめているサイトも少ないのが現状です。
また、セラピストによって少し考え方が異なっていたりするので、一概にこれが正解であると言うことは難しいと思います。
統合と解釈について、以下の文献や参考書