
欧州評議会:子ども参加アセスメントツール
先日、欧州評議会の閣僚委員会が2012年に採択した「18歳未満の子ども・若者の参加」に関する勧告(CM/Rec(2012)2)の日本語訳を私のサイトで公開しました。
この勧告は、国連・子どもの権利条約(とくに第12条)、「意見を聴かれる子どもの権利」についての国連・子どもの権利委員会の一般的意見12号(2009年)、そして「子どもの権利の行使に関する欧州条約」(1996年)をはじめとする欧州評議会の関連文書を踏まえ、欧州評議会の加盟国において子ども参加を保障・促進していくために採択されたものです。
勧告は、次のことに関する「確信」を表明したうえで、子ども参加の保障・促進に関わる原則とそのための具体的措置(参加権の保護/参加権に関する意識の促進/参加のための空間の創設)を付属文書で掲げています。ここで表明されている信念は、日本でもおおいに共有されるべきものです。
● 意見を聴かれ、かつ真剣に受けとめられる権利は、すべての子ども・若者の人間の尊厳および健康的な発達にとって基本的重要性を有すること
● 子ども・若者の声に耳を傾け、かつその意見を年齢および成熟度にしたがって正当に重視することは、自己に影響を与えるすべての事柄において子ども・若者の最善の利益が第一次的に考慮される権利ならびに暴力、虐待、ネグレクトおよび不当な取扱いから保護される権利の効果的実施にとって必要であること
● 子ども・若者が有している能力および子ども・若者が行ないうる貢献は、欧州社会における人権、民主主義および社会的結束を強化するためのかけがえのない資源であること
欧州評議会の子どもの権利部と若者局は、加盟国によるこの勧告の実施を支援するため、「子ども参加アセスメントツール」(Child Participation Assessment Tool)を2016年3月に作成しました(訳出済みで、いずれしかるべき形で公開される予定です)。
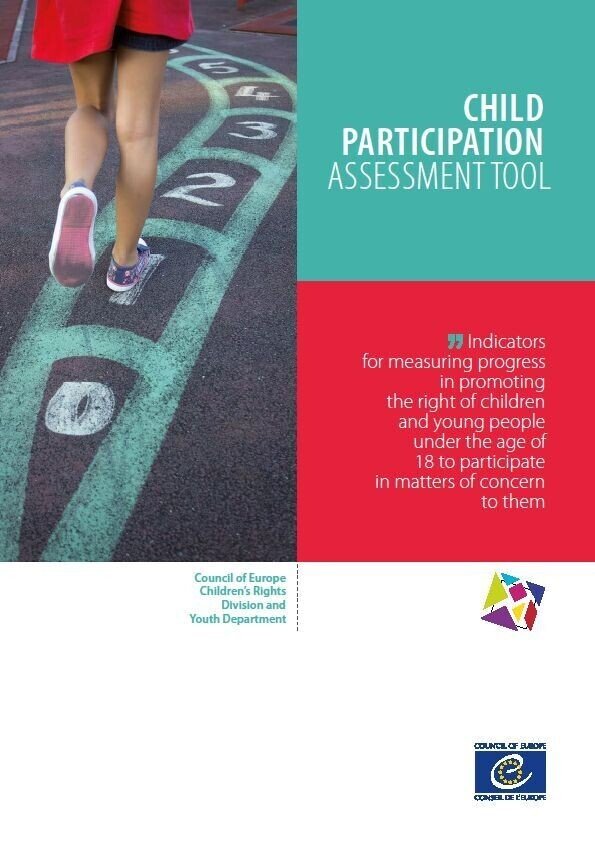
このアセスメントツールは、閣僚委員会勧告を踏まえて以下の10の指標を設定し、それぞれの定義や評価基準を示したうえで、各国がそれぞれの進捗状況を自己評価できるようにしたものです。各指標ごとに、脆弱な状況に置かれている子ども・若者に関してとくに考慮すべき問題も示されています。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
参加権の保護
1.意思決定に参加する子ども・若者の権利の法的保護が国の憲法・法律に反映されている。
2.意思決定に参加する子ども・若者の権利が、子どもの権利を実施するための部門横断型の国家的戦略に明示的に含まれている。
3.独立した子どもの権利機関が設置されており、法律で保護されている。
4.子どもが司法手続・行政手続で参加権を安全に行使できるようにするためのしくみが存在する。
5.子どもにやさしい苦情申立て手続が設けられている。
参加権に関する意識の促進
6.子どもとともにおよび子どものために働く専門家を対象とした着任前養成・研修プログラムに、意思決定に参加する子どもの権利が組みこまれている。
7.子どもたちに対し、子どもの参加権に関する情報が提供されている。
参加のための空間の創設
8.子どもたちが、学校、地方・広域行政圏および国のレベルにおける話し合いの場で代表されている(子どもたち自身の団体の代表によるものを含む)。
9.地方で提供されるサービスに関する、子どもをとくに対象としたフィードバックのしくみが設けられている。
10.子どもたちが、国連・子どもの権利条約(条約に関するシャドウレポートの作成・提出を含む)および欧州評議会の関連文書・条約のモニタリングに参加するための支援を受けている。――――――――――――――――――――――――――――――――――
また、国連・子どもの権利委員会が一般的意見12号で提示した9つの基本的要件(パラ132~134)をより具体的に解説した資料も、付属文書として掲載されています(子ども参加の基本的要件については、「子どもの権利委員会の報告プロセスへの子ども参加に関する作業手法」のパラ7および「一般的討議日への子ども参加に関する作業手法」のパラ7も参照)。
日本では意見表明および参加が子どもの権利であるという考え方自体が十分に浸透していませんが、自治体レベルでは子どもの権利条例を踏まえた制度的な子ども参加の実践も広がりつつあります。欧州におけるこのような取り組みも参考にしつつ、子ども参加を当たり前のこととして定着させていくことが必要です。
noteやホームページでの翻訳は、ほぼすべてボランティアでやっています。有用だと感じていただけたら、お気持ちで結構ですのでサポートしていただけると、嬉しく思います。
