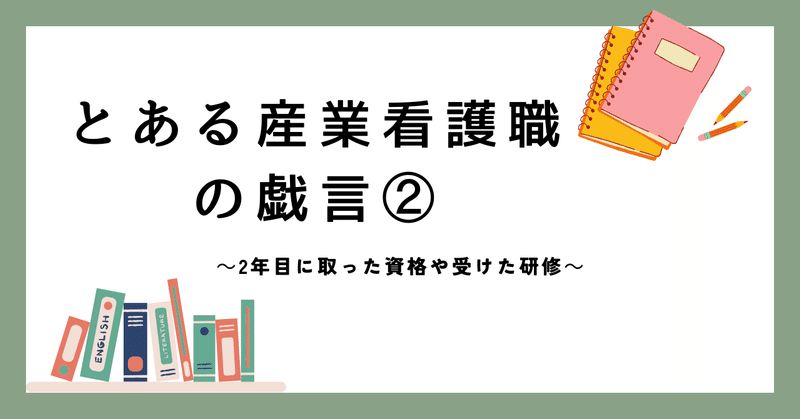
とある産業看護職の戯言②~2年目に取った資格や受けた研修~
こんにちは。
産業看護職として、一人職場で働いています。
一人職場のため、教育制度等はなく、自己研鑽に励んでいます。
2年目に取った資格や受けた研修について、以前の1年目に取った資格に続き、書いてみたいと思います。
どなたかの参考になれば幸いです。
1.産業保健看護専門家制度登録者
この資格については、別記事でさらに記載できそうな感じですね。
日本産業衛生学会により運用されている産業保健看護職の専門制度です。
実は軽い気持ちで受験を決意しましたが、試験勉強は結構大変でした。
ここでは軽く試験勉強について。
公衆衛生、産業保健、学校保健、疫学、保健統計、健康危機管理等、かなり範囲が幅広い。
認定試験要領で出題領域の出題割合が出ているので、割合が高いものを中心に取り組みました。
試験問題は100問のマークシート形式、時間は100分。
「日本産業衛生学会 産業保健看護部会 主催 登録者認定試験準備講座」というものがあり、こちらを受講。
その他、活用した書籍は以下のものです。
ひたすら、保健師国家試験、第1種衛生管理者過去問を解いていました。
衛生管理者の過去問はネットを活用しておりました。
「保健師国家試験問題集」
「保健師国家試験のためのレビューブック」
「国民衛生の動向」
「職場の健康がみえる」
「公衆衛生がみえる」
「労働衛生のしおり」
「第1種衛生管理者 テキスト&問題集」
私は疫学・統計が特に苦手と思っていたので、以下も活用していました。
「看護学生のための疫学・保健統計」
「忙しい人のための公衆衛生」
結果、無事に試験には合格。
試験終了直後は「受かるのだろうか・・・?」と不安を感じてしまうような手ごたえのなさでした。
受かったものの、この試験勉強方法が合っていたのかと言われると「?」と、首をかしげてしまうような感じの試験内容でした。
どういう試験勉強が正解だったのか、今でもわかりません(苦笑)
ただ、改めて保健師の勉強ができたこと、第1種衛生管理者の知識を学べたことはとても良かったと思います。
この試験では、受験までの勉強というプロセスが自分にとっては役立ったなと思いました。
保健師免許をもっていたので、衛生管理者は申請して免許を取りました。
産業保健分野で働くうえで、なくてはならない知識なのに、知らないことばかりで、衛生管理者の勉強ができる機会を得たことは大きかったと思います。
登録者の試験に合格してからがまた大変なのですが、それはまたの機会にでも書けたらいいなと思っています。
2.BLSプロバイダー/ハートセイバー ファーストエイド CPR AEDコース
一人職場で医療職は一人ということで、緊急時の対応を改めて学んでおかなくては思い、期限も切れていたので再度受講。
「BLSプロバイダー」では、実技を通して、質の高いCPRを行うスキルを習得し、コースを修了するとライセンスカードをいただくことができます。
「ハートセイバー ファーストエイドCPR AEDコース」では、BLSでは学ぶことのできないファーストエイドの基本、最も発生しやすい緊急事態、救助方法について学習することができます。何回やっても良いと思いAEDをまた実践できるコースを選択。
私が受講した際は講師の方と1対1だったので、とても丁寧に教えていただきました。
窒息時の対応、なかなか実技が難しく、ポイントを教えていただきました。
今後も緊急時の対応については、アップデートしていかなければいけないなと思います。
3.健康づくり推進スタッフ養成研修
中災防が開催している研修です。
2022年度から新設された研修で、職場の健康づくりに生かすために食生活、身体活動、睡眠、休養、口腔保健に関する基本的な知識を学ぶことができます。
事前の動画学習を受け、2日間の集合研修となります。
事前の動画学習が集合研修の1週間前に5項目あり、仕事をしながらですと、なかなか大変でした。事前レポートもあります。
集合研修では、他企業の取り組みについての講義や参加者の情報交流、グループワークがあり、他の企業の取り組みを知ることができたのは大変参考になりました。
研修を受講すると修了証をいただくことができます。
4.禁煙治療・支援のための指導者トレーニングプログラム
禁煙支援や禁煙治療に必要な知識やスキルを学ぶことができるWEB学習教材で無料で受講することができます。
「禁煙治療コース」、「禁煙治療導入コース」、「禁煙支援コース」があり、自分のニーズに合わせて自分のペースで受講が可能。
動画があり、とても参考になりました。
受講後は修了証も発行されます。
興味がある方は「J-STOP」で検索してみてください。
5.日本産業看護学会 アセスメント研修会
初めて現地参加した学会で開催された研修。
せっかく現地での参加なのでと思い研修会を受講。
「すぐに役立つ産業看護アセスメントツール」を用いて、グループワーク。
事例検討をグループワークを通して、様々な視点から学ぶことができました。
所属する企業に応じて、行っていることも違い、気になるポイントも違ったりして、意見交換が活発に行われて楽しかったです。
他のグループの発表もとても参考になりました。
河野先生もいらして、ご挨拶できたのがとても嬉しかったです。
6.産業保健セミナー
産業保健交流会主催のセミナー。
特に「ビジネスマナー」について、実際に書籍でしか学んでいなかったので、実際にお話を聞くことができて、とても勉強になりました。
挨拶や応対時の言葉遣い、表情など、具体的に学ぶことができました。
「データ活用」について、経営層へのプレゼン資料や魅せる資料の作り方等を学ぶことができたのは、とても良かったです。
学びたかった内容なので、参加して良かったと思ったセミナーでした。

7.グリーフケア公開講座
大学のグリーフケアの公開講座を受講。
グリーフケアについて学びたいな思う事柄がありまして・・・。
様々な視点からの「悲嘆」についてお話を聞くことができ、大変勉強になりました。
改めて「悲嘆」ということについて考える機会となりました。
アーカイブで動画を拝見できたのも、とても良かったです。
8.日本産業看護学会 組織強化委員会主催 産業看護交流会
学会に参加した際に交流会の存在を知り、参加。
まずは、河野先生のお話を聞くことができ、その活躍に改めて「すごい」と思いました。
後半はグループワークでの意見交換。
参加したグループが色々な職業の方が集まっていて、職業が違えば物事をとらえる視点も違い、とても楽しい交流会となりました。
9.日本産業衛生学会東海地方会 2022年度第1回看護部会研修会「産業保健におけるSNS活用法」
地方会だけれども、他の地域からも参加できることを知り、SNSを活用している身としては、とても興味のある内容かつあまりない内容の研修だったので、参加。
SNSを活用して情報収集、ネットワーク形成、言語化を行うことができたりするメリットやSNSを活用するうえでの注意すべきことなど、メリット、デメリットについて改めて考えることができた良い機会となり、とても面白い研修でした。
研修時に講師の先生にご挨拶できたのも嬉しかったです。
10.日本産業衛生学会 産業保健看護専門家制度委員会認定基礎研修
登録者の次のステップが、専門家試験となります。
その受験資格のひとつに
「基礎研修50単位の履修」というものがあります。
地道に研修をうけ、単位を満たすことも可能ですが、これがなかなか大変。
そのため、50単位分の研修を履修できるのが、この研修です。
オンデマンドと実地研修はライブ配信での受講が必要となります。
そこそこのお値段はしますが、地方在住者のため、色々なところへ研修に行くこと交通費等を考慮したら、受講したほうがお得かなと思い、試験直後の知識がまだしっかりとあるうちに受講しました。
私はこの研修で単位を修得できたので、受講して良かったと思っています。
2年目は産業保健看護専門家制度登録者に費やした1年だったなという印象です。登録した後も色々とあるので・・。
1年目は現地開催の研修がとても少なかったのですが、2年目になり徐々に現地開催の研修も増えてきて、少しですが現地開催のものに参加して、色々な方の意見を肌で感じることができたのは貴重でした。
人前での発表などは緊張してしまうため苦手なのですが、なぜか上記の研修で何度か発表者になってしまって皆の前で発表することになったのは、まぁ良い経験になったかなと思います。(うまく話すことができたかは皆無ですが・・・)
オンライン上でしかお会いしていなかった方々と、実際にリアルでお会いする機会に恵まれた1年でもありました。
お会いしたかった念願の方々と直接ご挨拶できたのは、感動でした。
一人職場のため、周囲から教えてもらうことは期待できず、自己研鑽に励まなければいけない環境です。
今後も自分に合ったペースで、研修や興味ある資格取得に励んでいきたいなと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
