
地エネの酒for SDGsプロジェクトの始動【地域デザインの目線#21】
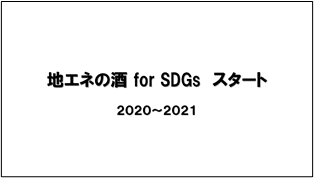
「地エネの酒 for SDGsプロジェクト」は、山田錦の3農家、4蔵元が参加して2020年にスタートしました。人と自然をつなぐ資源循環の要となる消化液の使い方は農家によってさまざまです。

これは、神戸市北区の農家の田んぼで、春、田植え前に稲の肥料として施す「もとごえ」にしようと機械を使って消化液を散布する様子です。

こちらは、8月はじめ、「中干し」といって、一度水を抜いて乾かす期間を終えた田んぼに再び水を張る際に消化液を入れているところです。バルブを回して、流れ出した水といっしょに消化液を流してしまえばいいので、作業は楽です。
この農家は消化液を田んぼの微生物を増やす目的で使っています。微生物が土中の有機物の分解を進め、これから穂を実らせる稲が吸収しやすい栄養が田んぼで常に作り出される状態にしていく狙いです。

地エネの酒for SDGsプロジェクトは、化学肥料とともに農薬を使わないことも目標としています。
人が乗っている赤い機械は田植えの後に生えてきた水田雑草を取り除くための除草機です。土の表面を揺らすようになっていて、まだ根が浅い雑草が土から離れて浮いてきます。

別の農家は、冬から水を張る冬期湛水や米ぬか散布によって、田んぼに雑草が生えにくい環境をつくる方法にも挑戦しました。
それでも生えてくる雑草は手でとることに決めました。雑草だらけになったらどうしようかという不安もありましたが、農薬を使わない除草技術が効果を上げ、田んぼの雑草が少なかったのであまり時間をかけずに済みました。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
