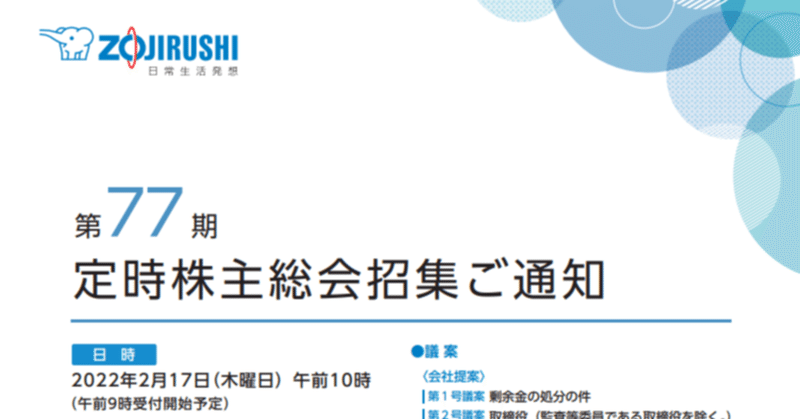
ギャランツと象印の争点についての私見
2022年2月17日午前10時、象印マホービン株式会社(象印)の株主総会が開催される前に、同社と中国企業のギャランツとの間に見られる経営理念の大きな違いが、中日両国メディアの注目を集め、多くの中国語および日本語の記事が新聞紙面やネット上を賑わせた。
日本の世論の理解を勝ち得たギャランツ
日本の資本市場、世論の動向から見ると、ギャランツは多くの理解と支持を得た。
日本経済新聞の報道によると、ギャランツの後ろ盾のおかげで、野村証券は1月16日に象印の目標株価を1200円から2000円に引き上げた。筆者はNewsPicksのサイトでギャランツへの取材とフォローの書き込みの状況を見た。ウェブサイトの記者は同社の責任者に対して長時間にわたる取材を行い、インタビューの実録をネット上に公開した。フォローの書き込み情況から見ると、ほぼ全ての読者は実録を読んだ後、ギャランツの主張は理にかなっているという見解を示している。
象印の経営問題におけるギャランツの観点は日本の世論の理解を比較的に得やすいと言える。その理由として、第一に、ギャランツは象印の全株式の15.5%を保有し、同社創業者の市川典男氏が保有する22%に次ぐ位置につけている。ギャランツは社外取締役の就任を希望しており、日本銀行出身で、弁護士資格を持つ長野聡氏を推薦したが、象印はこの提案を拒否した。象印がにべもなく拒否をしたことは、あまり常識的とは言えない。第二に、ギャランツが有望視しているのは象印の市場空間だが、過去4年間で、象印の売上は悪化の一途を辿っており、利潤も3年連続で下落している。ギャランツの提案と世論が願う日本企業の大きな発展は、図らずも一致している。第三に、今後5年、10年間で、ギャランツは積極的に進取の気性を示したいと考えており、企業経営において従業員の利益をより顧みること(この主張の隠された真意は、このところ株主に対する配当が過度に重視されている一方で、従業員への利益配分がないがしろにされていることにある)を求めるだけでなく、さらに商品開発における推進ペースを加速し、マーケティング分野でもさらに国際市場を開拓することを希望している。このような要求の主張は、経済記者の心に共感を呼び起こすことができる。
象印は中日両国の記者による取材に直接回答していないが、2022年1月11日に外部に対して買収防衛策に関する情報を公開した。象印は、株式市場において当社の株を大量に購入する際には、事前に当社に連絡を入れるべきだが、ギャランツによる当社の株式購入のやり方は、当社としても対抗せざるを得ないものだったという考えを示した。
実のところ、ギャランツが象印の株式の買い増しを始めてすでに5年が経過しているが、これらの年月において、同社の会長は象印の幹部と年間17回も会談する機会があったが、象印は自社の説明において、ギャランツとのコミュニケーションについて一言も述べておらず、全体的な情況をはっきりと説明していないようだった。
問題の核心は市場に対する中日企業の予想の相違にあり
中日メディアによるギャランツと象印の報道を概観すると、両社にとって最大の対立点は市場に対する中日企業の予想の相違にある。ギャランツは1978年に設立された後、市場で進取の気性を示し、今日の世界の電子レンジ王の地位を獲得することができ、電子レンジの研究と生産のみならず、白物家電の分野でも引き続き業務の範囲を広げ、国内外の両市場で同業他社を凌駕している。現在、同社の売上額は300億元であり、5年後の目標額は1000億元だ。これほどの大きな目標は、日本企業も賛同しかねるものだ。
象印は1948年に設立され、一芸一能に秀でた技術で事業を展開し、魔法瓶の分野で70年以上も経験を積み、その歳月の中で製品はほぼ変わっていない。同社はこれまでに炊飯ジャーを開発したが、やはり保温製品を業務の主力としている。国外市場の方面では、欧州市場や米国市場の全面的な開拓にまだ着手していない。製品の入れ替わりも、中国企業の視点からするとかなり遅い。
日本市場だけを見ると、今後業務規模を拡大できる可能性は非常に低いが、世界市場は決してそうではない。象印自体に世界市場を開拓する能力が欠けているかもしれないが、ギャランツのような中国企業も完全に信頼することはできない。ギャランツが会社の拡大を目指していた頃、象印は現在の体制を維持することを望み、経営上のリスクを犯す必要などないと考えていた。
多くの中国企業は市場が急激に伸びた時に大きな発展を遂げ、市場の開拓に対して生来の楽観的な見方を有している。日本企業は何十年、百年以上の歴史を有し、市場の拡大時期を経験したが、その後拡大が振るわず、最終的に失敗した例をよく理解しているため、経営において慎重で保守的になりやすい。今日(2月17日)の株主大会では、象印はふたたびギャランツの人事案を否定した。いっぽう、象印が提出した五項目の提案、中にはギャランツが反対している買収防衛策などは許可された。筆者の日本企業に対する理解からすると、ギャランツと象印の争いは、長期にわたって互いに譲らない状況が続く可能性がある。
文/日本企業(中国)研究院執行院長 陳言
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
